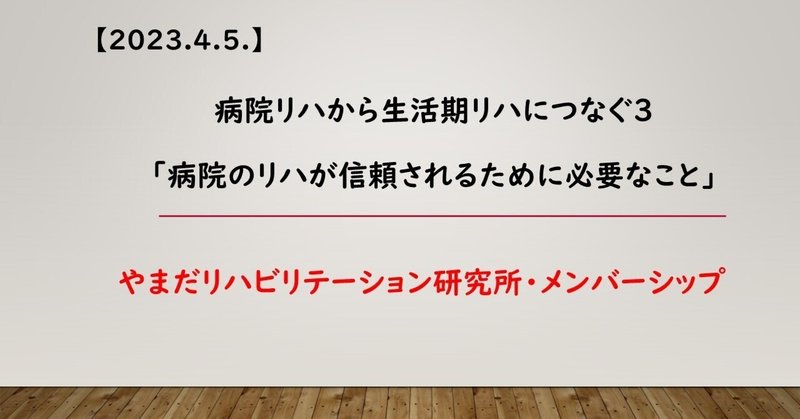
【2023.4.5.】病院リハから生活期リハにつなぐ3「病院のリハが信頼されるために必要なこと」
※今日のコラムはどなたでも全文お読みいただけます。
昨日のコラムで、実は病院のセラピストは患者さんや家族さんから信頼されていないかもしれないということを書きました。
【2023.4.4.】
病院リハから生活期リハにつなぐ2「Home & Awayのこと」
じゃあどうすればいいの?ってことを提案してみます。
しっかりと話を聞くこと
目標設定を適切に行うこと
リハビリテーションのことを伝えること
変化を伝えること
自宅に戻ってからできることを考え病院でも実践すること
退院後の生活のことを知ること
しっかりと話を聞くこと
目標設定を適切に行うこと
この二つについては、シリーズコラムでも書いていますし2023年4月9日開催のオンライン講義でもお伝えします。
◆4月9日開催オンライン講義
「リハビリテーションの目標設定の考え方のこと」
リハビリテーションのことを伝えること
これをしっかりと行っていない病院のセラピストは非常に多いと思います。
リハビリテーションのオリエンテーションとでもいえばいいでしょか?
リハビリテーション、理学療法、作業療法、言語聴覚療法それぞれの中でどのようなことをするのかということの説明をきちんと行っている病院のリハ部門はどれくらいあるのでしょうか?
そうして、入院からの時期のことを考慮して提供するリハビリテーションの中身を変化させている病院もどれくらいあるのかな?
上記の動画でも伝えている内容も少しありますので,、今日のコラムと合わせてごらんください。
リハビリテーションのオリエンテーション
入院中に実施するリハビリテーションのこと
PTやOTのリハビリの違いのこと
退院後の生活とリハビリのこと
そんなことを入院時にきちんとオリエンテーションしている病院ってあるのかな?
患者さんにリハビリテーションのイメージをしっかりと持ってほしいんですよね。
発症からの時期によっても取り組む課題は異なるし、患者さん自身にも主体的にリハビリテーションにかかわってほしい、その先に自主トレとかホームエクササイズとかADLの実践とかがあるんだと思うんですよね。
なにより、リハビリテーションは患者さんが主体的にするものであって、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に「してもらうこと」がリハビリテーションだっていう風に勘違いされることを避けたいんですよね。
そのためには、きちんと病院のリハビリテーションについてのオリエンテーションをしてもらうことが必要だと考えています。
セラピストが関与する時間のこと
セラピストが直接的に関与しない時間のこと
それぞれの時間にどんなことを実践することが必要で、それがリハビリテーションだということを知っておいてもらうことは退院後の生活においてはめちゃくちゃ重要なんですよね。
退院後には毎日マンツーマンで3職種が在宅生活の場でかかわることはありません。
だからそこに向けて、患者さん自身もリハビリテーションに主体的にかかわってもらうことが必要なのです。
あなたの病院では実践できていますか?
◆お問い合わせやご意見はこちらから
やまだリハビリテーション研究所
作業療法士
山田 剛
ここから先は
フリー作業療法士として日々書いております。サポートは励みになっています。サポートなくてもお買い上げいただけますが、あると嬉しい。
