
【小説】冷凍餃子に手招きされた話
「俺さ、冷凍餃子に手招きされたことがあるんだよ。」
中村先輩が、ここ数日バズったワードを使って、また妙なことを言い出した。
この先輩は、俺の職場の先輩であり、直属の上司だ。喋りがものすごく達者で、仕事中の半分は無駄話をしているんじゃないか、と思えるほどの途切れぬトークを得意としている。
ちなみに無駄話をしている以外の時間は、殆ど電話をしているので、つまり一日中、常に喋っている。
「あー、はいはい。手招きされたんですね。すごーい。」
先輩のボケに対しては、スルー対応が鉄板だ。一度反応してしまうと、より調子に乗ってボケてくるので、長くなる。ここは素直にボケを潰しておいた方が、仕事の邪魔にならない。というか、仕事の邪魔をしないで頂きたいです。ほんとに。
「なんや。つれないなー。でもホントに冷凍餃子が喋ったんや。
俺は小さい頃、ひとりで留守番をしてた。すると、冷蔵庫から怪しい紫の光が、ぴっかーん。
勇気を出して、冷蔵庫を開けてみると、その中には、冷凍餃子が・・・」
───長くなりそうなので、たまらず冷静にツッコむ。熱くなっては負けだ。
「んなわけないでしょ。先輩、その話、超作ってますよね。むしろ、なんなら今、創作してますよね。適当ですよね? ホラ、承認終わってない注文書がまだまだ残ってるんですから、現実逃避してないで頑張ってくださいよ。」
「やっとるよー。しかし冷凍餃子が手抜き料理ではなく、手招きする料理であることを、俺はお前に伝えなあかん。」
「い・い・え! 冷凍餃子は手招きしませんし、手抜き料理でもありません。ただ、先輩の今やってることは手抜きですよ。いや、もしかしたら先輩が目の前の注文書を全部、すぐに承認してくれたら、喋りだすかもしれませんが。」
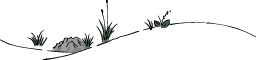
────こんな調子だから、いつまで経っても書類処理が終わらない。
どんなに俺が書いても、それを先輩が承認しないと、俺の仕事は進まないのだ。
「注文書はたしかーに喋らん。でも冷凍餃子は喋るんや。マジで。試しに、そこの冷蔵庫あけてみ?
お前がくるまえに冷凍庫から冷蔵庫に移しておいた冷凍餃子があるから。試しにホラ、そこの冷蔵庫開けてみ。」
まだ言っている。でも今日はやけに食い下がるな…… それならば。
「冷凍餃子は手抜きじゃなくて、ちゃんとした料理ですよ。むしろ冷凍食品ってのは、ものすごい開発努力と冷凍技術が詰まっていると聞きますし、その成果を金で購入しているだけです。日々の食事を準備する手間を嫌わないのなら、お米だって苗を育てて、田植えからスタートするべきだし、なんなら土地を開梱することからスタートです。人の労働はお金がかかるんです。さあさあ、俺たちも働きますよ。今日は定時であがりたいんです。」
先輩と軽口を叩くようになってから、俺も随分と口が回るようになってしまった。最近に至っては、社内で漫才コンビと言われだす始末だ。
さては、また職場の冷蔵庫に冷凍食品を入れたに違いない。同じことをして総務のお局様───通称GODに、つい昨日叱られたばかりだというのに、もうこれだ。また俺も巻き込まれてお説教されてはかなわないので、しぶしぶ重い腰をあげ、フロアの隅にある冷蔵庫のドアを開ける。
「今日もお疲れね~」
冷蔵庫の中から、いい年したおっさんが無理して裏声だしたような声が聞こえてくる。
れ、冷蔵庫がしゃべった……
「何を探しているのかしら」
畳み掛けるように、喋り声が続いている。
────ま、待てよ。冷静になると超怪しいぞ、これ。
絶対これ、冷凍餃子が喋ってるわけではないし、冷蔵庫自身も喋ってない。冷蔵庫の中に置いてある、この怪しげなトーテムみたいなフォルムをした虎人形から声がしている。でも少しかわいいな、これ。
「先輩…… また変なもの冷蔵庫に入れましたね。また総務のGODに叱られちゃいますよ?」
「いいだろ、それ。冷蔵庫用の人形で、扉開けると喋るんや。」
「いいですか。ここは職場で、これは職場の冷蔵庫です。共有資産です。先輩の焼肉弁当を入れてもいいですけど、他の人もヤクルトとか、中途半端に一口だけ呑んだ缶珈琲とも入れっぱなしになってる、職場のみんなのものです。昨日もくさやを入れて、GODにしこたまお説教されたばかりじゃないですか。」
「いやー、あれはマズったよなあ。包装の端が破けてて匂いが漏れてるなんて全然思わへんやったし。総務のおばちゃんのスイーツには、悪いことしたわ。」
不幸にも昨日は、総務のGODが超得意先の訪問に備えて買っておいたケーキが、冷蔵庫に入れてあった。しかしながら紙箱に入ったその高級ケーキは、先輩が入れた袋が破けたくさやの臭気を充分に吸い、とてつもなく残念気味なスイーツに成り下がってしまっていたのだ。総務のGODが激怒したのは言うまでもない。
「とにかく、この怪しげな虎の人形は、冷蔵庫から出しておきますよ。そもそも昨日、ウチの課はしばらく冷蔵庫使用禁止令が出てるじゃないですか。まずいですよ、GODとかにバレたら。」
俺は、まだしきり何かを喋り続ける虎のトーテムを、冷蔵庫から取り出した。その背中を、手の触感でまさぐってみると案の上、背面に電源スイッチがあったので、すかさずOFFにしておく。
「ぎょへー!」
電源OFFで、鳴るような仕組みだったのだろう。
そこそこ静かな職場のフロア中に、気の抜けた叫び声が響き渡る。なんでこの声だけ、こんなにボリュームが高いんだ、このおもちゃ。
フロアからの無数の視線が背中に突き刺さるのを感じる。
とはいえ、先輩と仕事をしていれば、こんなのはいつものことであり、恥ずかしいのにはもう慣れた。先輩が言うに、ウチの課は何故かとても売上が高いので、威張ってていいらしい。いや、でもこれは、威張ってるとかいうのではなくて、ただ周囲に迷惑かけてるだけだと思うが。
しっかし……
今朝方、冷蔵庫でなにかごそごそしてると思ったら、くさやの掃除だけじゃなくて、こんなものを仕込んでたのか……
でもこれ、喋ってるだけで、べつに手招きすらしていないぞ。先輩のいたずらにしては、いつもと比べて随分とネタの仕込みが甘い。
───とんとん。
冷蔵の扉を閉めて、軽くため息をついていると、俺の肩が軽く指先で叩かれているのを感じる。
どうやら冷蔵庫のそばの席の女性社員が、俺の肩を叩いたようだ。なんだろうかと、そちらを振り向くと、彼女は苦笑いしながら、フロアの反対側を指差している。
GODだ。GODが眼を三角にして、総務部の人達がいる一角から、こちらを手招きしている。
どうやら、おもちゃの一連の声で、俺が冷蔵庫で遊んでいると思われたようだ。お、俺じゃないよ?
すぐさま、先輩に助けを乞おうかと席に眼をやると、いつの間にか、どこかと電話をしている。俺が視線を向けているのに気がつくと、こちらを見て親指を立て、にこやかにサムズアップを決めている。
ああっ。絶対あの顔は、確信犯だ! してやられた!!
かくして。
総務島のGODの席に行き、ぐちぐちぐちとお説教されること数分。
苦行。ひたすら苦行であった。
ああ、俺、この人なんか苦手なんだよなあ・・
まだ日も高いというのに、俺の心はすっかり萎み、さながら枯れなめこ気分。
ほうほうの体で開放された俺は、自分の席には戻らず、意識の高いありがちなラーメン屋店主の如く、身体の前に腕を組みながら先輩の席へと向かう。
先輩は爆笑したいのを必死に堪えたドヤ顔で、俺にこういった。
「な? 手招きされたろ?」
俺が小一時間、先輩を説教したのは言うまでもない。

俺はねぇ、饅頭が怖いんだ!俺は本当はねぇ、情けねぇ人間なんだ。みなが好きな饅頭が恐くて、見ただけで心の臓が震えだすんだよ──── ごめんごめん、いま饅頭が喉につっけぇて苦しいんだ。本当は、俺は「一盃のサポート」が怖えぇんだ。
