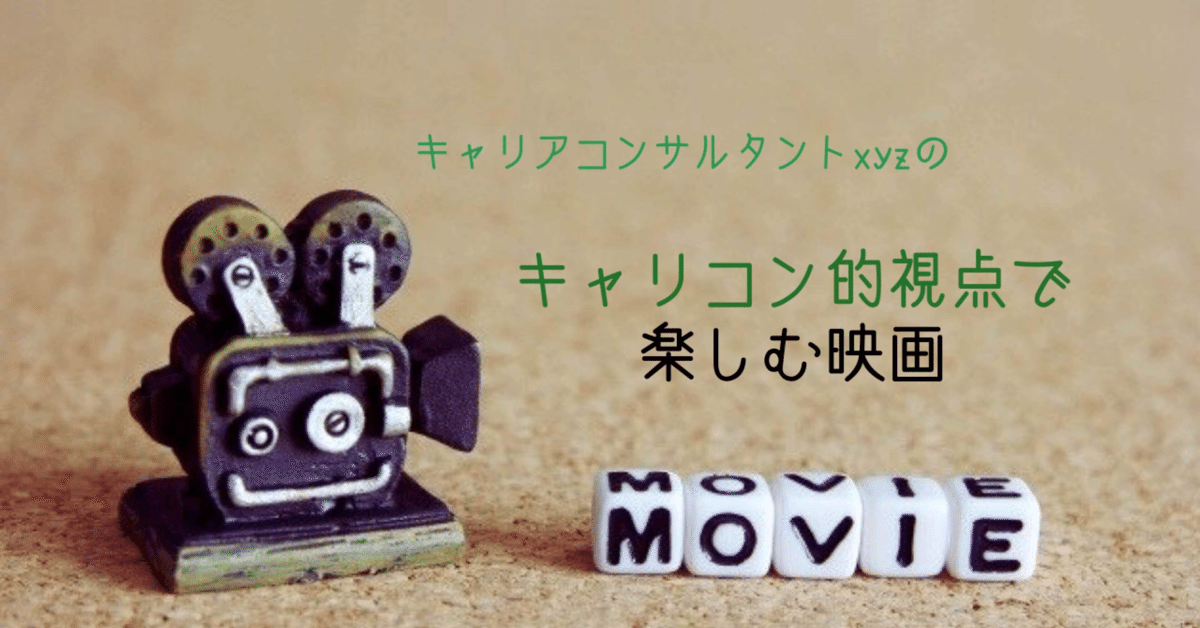
映画『西の魔女が死んだ』から【エリクソンの発達理論】さらに【世界との関わり方】を考えてみる
ドラマ、映画好きなキャリアコンサルタント xyzです。
先日【心理的安全性】を切り口にして書いた記事をupした後で、こんなニュース記事を見かけました。
小中学生の不登校は19万人以上と、過去最多となった(文部科学省調べ)ことを知りました。
不登校の定義は「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席したもののうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」だそうですが、「不登校」の定義にある日数等には当てはまらないけれど「不登校傾向」にあると思われる児童、生徒の実態は統計の数以上になるのではないかと言われています。
(上の記事は2018年のものなので、最近のものではありませんがご参考までに)
学校に「登校」はできても教室に入れない、また一見普通に通学し授業を受けているように見えても、内心学校になじめていないという悩みを抱えている子供たちもいることでしょう。
主人公まいのように学校に行けなくなってしまった原因が友人関係というのは第3位でした。
サード・プレイス
小中学生にとって学校は、家庭(家)に次いで(場合によってはそれ以上に)一日を大半を過ごす場所であり、学校での居場所がないととても辛い状況になりかねません。
しかも、もし家庭でも居場所が見つけられなかったら……行動範囲や生活圏の狭い小中学生は一体どうしたら良いのでしょう。
まいにはおばあちゃんと森の家というサード・プレイスがありましたが、学校の居場所に困っている子供達が皆まいのようにサード・プレイスや頼れる人があるわけでもなく……ひとり悩んだり苦しんだりしている子供やその家族の数を少しでも減らすことはできないのかな、学校以外にサード・プレイスは実際作れるものなのかどうか、キャリアコンサルタントとしてこの問題にどんなふうに取り組んでいけるのか等、日々考えています。
さて今回は、この映画を【エリクソンの発達理論】から更に【世界との関わり方】について考えてみたいと思います。
エリクソンの漸成的発達理論
キャリアコンサルタント試験では避けて通ることのできないエリクソンさんとはこんな方です。
⬇︎
エリクソンの【漸成的発達理論 The Epigenetic Chart in Erikson's Theory】は人間の発達を包括的に捉える理論で、人の生涯を8つの発達段階に分けています。
それぞれの段階で【発達課題(development task)】もしくは【心理社会的危機(psychosocial crisis)】に直面し、それらをクリアしていくことで人間は精神的に成長する、という説です。

表は教育相談情報提供システムHPより抜粋
(先に挙げていた厚労省資料からの表はオリジナルの印刷文字が不鮮明なため差し替えました)
青年期(思春期)
さて、エリクソンの発達段階によれば、中学一年生のまいは「青年期」に該当しますね。
この時期は、思春期(※)とも呼ばれますが、この時期での課題は「自分自身は一体何なのか」という問いへの答えを見つけることです。
(※青年期の様々な変化の中でも「身体的かつ性的な成熟をするとき」を指して「思春期」と呼びます。)
この青年期で獲得するものは【忠誠心】【帰属感】だそうです。
青年期では「自分とは何者なのか」を悩みつつ問い続ける中で【アイデンティティ(自己同一性)】を確立し、自分を受け入れることができるようになると同時に、この問いかけが自分と他者との相違に注目するきっかけとなり、他者との関わりが自己理解の枠を広げる可能性にもつながっていきます。
①自分軸の確立と葛藤
親や友達と異なる自分独自の内面の世界があることに気づき始めるとともに、自意識と客観的事実との違いに悩み、様々な葛藤の中で自らの生き方を模索しはじめる。
➡︎児童期までの自覚されない自己よりも「意識された」自己、つまり自分を客観的に見ることができるようになり「見る自己」「見られる(≒見せる)自己」を考えるようになります。
まいも自分と他者との違いをより意識するようになり、ある種の「生きづらさ」を感じるようになります。
②友人>親や先生などの大人
大人との関係よりも友人関係に強い意味を見いだす。親に対する反抗期を迎えたり、親子のコミュニケーションが不足しがちな時期でもある。
➡︎まいの場合、親への反抗は特に見られませんが、親との強い繋がりもそれほど感じられません。むしろまい母娘の関係はドライにも見えます。
仲間(学校の同級生)同士の評価を強く意識する反面、他者との交流に萎縮し消極的な傾向も見られます。
③自分とは違うものへの恐れ
第二次性徴期にあたり、身体面も大きく変化し、性意識の高まり、異性への興味関心の高まる時期でもある。
➡︎自分の身体の変化へのとまどいだけではなく、異性を意識しすぎる故の潔癖症的な嫌悪、直接的な性表現に拒絶反応も。
まいはゲンジが捨てた(と思われる)エロ本の束を見て、ますますゲンジへの嫌悪を募らせました。
逆にまいの同級生たちにとっては、クォーターであるまいに対して「自分たちとは違うもの」としての(無意識下での)おそれがあったのかな……とも思いました。(小説にも映画にもそのような描写はないので完全にわたしの想像ですが💦)
二方向のアイデンティティ
青年期では、アイデンティティ(自己同一性)の確立には二種類の方向性があります。
「集団行動への適応を前提とした社会への帰属感や忠誠心」と「個人の自立を前提とした社会への適応力や貢献」です。この二つは微妙に方向性が違いますよね。
青年期のアイデンティティを確立する過程では「自己ならざるもの=他者=世界」との関わりが不可欠です。
青年期は自分軸の確立と世界との関わり、自分と世界との折り合いのつけ方を学んでいく時期、とも言えますね。
黒い羊
まいは入学早々、友達作りに躓いてしまいます。
自分らしく友達作りをしていきたいと考えたまいは、女子特有の友達の作り方や排他的な連帯意識に違和感を覚え、あえてその「お約束的な関わり」や「掟」を我関せずのテイでいたところ誰からも相手にされなくなり……今さら誰かと関わろうにもがっちり出来上がったグループからあぶれて孤立してしまいました。
書いているだけで「面倒くさいなぁ」と思ってしまいますね。窮屈というか閉鎖的で……。
そこでわたしが思い出したのは、聖書にも出てくる「黒い羊」という言葉です。一匹の黒い羊が白い羊たちから受け入れてもらえず排除されるという、アレです。
心理学では、集団の成員が、好感を持つ特定の内集団(※英語版)の成員をひいき目に評価し、そこから逸脱した内集団の成員を、外集団の成員よりも低く評価するようになる傾向のことを指して、黒い羊効果 (black sheep effect) と呼称する。
(※ingroup)
Wikipediaより抜粋
その集団の一員でありながら、なじめずにいる者を集団の仲間と認めず、厄介者として扱う、このような傾向を集団心理学において「黒い羊効果」といいます。
集団組織の中に黒い羊が一匹いることで、その他大勢の白い羊たちには連帯感や一体感が生まれて仲間意識が強まります。一方で、集団の中にいる黒い羊は、集団の外にいる黒い羊よりもっと低い評価を受けるという現象が起きるといわれています。
結束の強さはともすると組織の強さと捉えられがちですので、浮いた存在を排除することが、集団としての結束を一層高める手っ取り早い方法として無意識に選択されがちです。
多勢に無勢、という言葉もありますが、異質なもの(往々にして少数派)を「自分たちとは違う」と理由で排除することは数の暴力に他なりません。
こうした結束を、帰属感や忠誠心としてはならないですよね。これでは、世界はとても冷ややかなものになってしまいます。
世界との関わり方
「自己ならざるもの=他者=世界」との関わりは、社会の中で適応していくためのさまざまな能力やスキルを青年期に修得していくために必要なことです。
そこで得られる帰属感や忠誠心について気をつけなければならないのは、ウチ(内集団)とソト(外集団)を過剰に対立させないことではないでしょうか。
排除の論理で内向きな帰属意識を高めるのではなく、ひとりひとりが自分を価値のある存在だと捉え(自尊感情)、そんな価値ある各人がそれぞれの違いを認めた上で受け入れ合う(他者受容)ことで帰属意識を醸成する……それがしあわせな世界との関わり方ではないかな、と思います。
環境を変える≠逃げる
友達関係が思うようにできず辛さを抱えたまいは、おばあちゃんに悩みや思いを打ち明けます。
「サボテンは水の中に生える必要はないし、シロクマがハワイより北極で生きる方を選んだからといって誰がシロクマを責めますか」
そのときどきで考えて決めたらいい、自分が楽に生きられる場所を求めたからといって、後ろめたく思うことはないのだと、おばあちゃんはまいに話します。
学校という、当時のまいには唯一だった共同体で「自分の居場所」が見つけられず、ついには学校に行くことが辛くなってしまったまいにとっては、おばあちゃんの言葉は心にしみたはずです。
集団行動への適応ももちろん大切な成長段階の課題ではありますが、だからといって無理をして心や身体を壊してしまっては本末転倒ですよね。
心を守るために思いきって環境を変えることは逃げではない、とおばあちゃんはまいに伝えたかったのだと思います。
それに集団行動や帰属感、忠誠心を学ぶ場はなにも学校に限定されることはないですしね!
児童や生徒にとって学校は一番身近な「集団」「組織」「共同体」であるとはいえ、サボテンを無理に水で育てるようなことではかえって健全な成長を妨げることになりかねませんし。
居場所というのは単なる物理的な空間ではなくて「自分の存在が確認できる(実存感)」「自分を受け入れてもらえる(受容)」「精神的に安定していられる(安定)」そういう場のことではないかと思います。
つまり、心理的な帰属感を得ることができる特別な空間です。そういう場があって、安心して外の世界に踏み出せるのですから。
自分で考えた結果、新しい土地で新しい中学に通うことを決めたまいは、その後、自分らしくたくましく過ごしていて親友と呼べるような存在(チャムシップ)もできた様子を小説の後日談で知ることができます。
西の魔女の教えはしっかりと東の魔女(まいのことをおばあちゃんはこう呼びました)に根付いたことがわかります。まいは自分なりに世界とのしあわせな関わり方ができつつあることがわかってほっとしました。
最後まで読んでいただきありがとうございました^^
