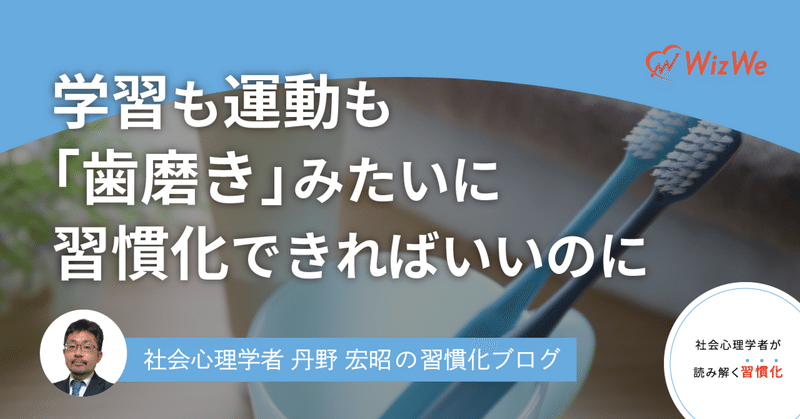
学習も運動も「歯磨き」みたいに習慣化できればいいのに
WizWe総研主任研究員の丹野です。
前回のnoteでは習慣化に関する古典的な心理学研究を紹介し、行動と成果(良い変化)を結びつけることが三日坊主防止のコツであると述べました。
そのため行動開始直後は成果に気づけるかどうかが重要です。
停滞期が次の壁

自分の話で恐縮ですが、私自身が長く続けている習慣としてジムでの筋トレがあります。
筋トレ開始して直後、筋肉量や体脂肪量など体組成計の数値が変化していくのが楽しく、そこからハマっていきました。徐々にマシンやウェイトの重量も上がって「先週までは無理だった重さが上げられる」という効力感が習慣化の後押しになりました。
まさに成果の実感による行動自発頻度増加でした。
ところが多くの人も経験あると思いますが、筋トレもダイエットも、変化がストップする時期があります。
これまで変化し続けていた体組成計の数値が1ヶ月経過しても変わらない。
毎週のようにトレーニング負荷を上げることができていたのに次の負荷に移れない。
いわゆる停滞期(プラトー)と呼ばれる時期です。
停滞期は筋トレやダイエットだけではなく、学習においても生じます。
順調に成績が伸び続けていたのに、急に成績の伸びが頭打ちになることは経験された方も多くいるのではないでしょうか。
しかし運動も勉強も停滞期中に行動を積み重ねることは決して無駄ではありません。ロールプレイングゲームの経験値とレベルの関係のように、次のレベルアップまでに経験を積み重ねることで成果に繋がります。
停滞期を乗り越えれば再び成果を得られるのですが、残念ながらここで行動をやめてしまうケースはよくあります。なぜなら行動の継続には成果(良い経験)の結びつきが重要だからです。
つまり習慣化において三日坊主の次にくる壁は停滞期といえるでしょう。
「飽きる」のは当たり前
習慣化の壁として、馴化という現象があります。
馴化とは、同一の刺激・体験を繰り返すことで徐々に慣れてしまい反応が生じなくなってしまう現象のことです。簡単にいうと「飽きる」ということですね。たとえ自分が大好きな映画や本があったとしても「それを毎日欠かさず鑑賞しろ」となったら、たいていの人はイヤになりますよね。
馴化は変化が乏しい停滞期のときに起きやすく、ここで習慣が消失してしまうことも多々あります。
ではどうやって停滞期と馴化を乗り越えることができるでしょうか。
いくつか方略があります。
①変化を加える
馴化を防ぐためには変化を加えることが有効です。
トレーニングの場合は「シューズやウェアを変える」「種目を変える」など新しい刺激を取り入れることで行動量が回復すると指摘されています。
私自身も停滞期に入ったら、トレーニング種目を変えたり、食事やサプリに変化を加えたり、ジムに行く時間を変えたりなどして自分をごまかしながら続けることが多いです。
②少し休む
馴化は空白時間を設けることで軽減します。
一度飽きてしまった映画や本も久しぶりに読むとまた楽しめるように、時間が経過すると刺激への反応は回復します。
ただし習慣が中断してから再度行動を復活させるためにはエネルギーが必要です。再開時期を明確に決めたり、他の人に宣言するなどして、確実に再開できる工夫をするとよいでしょう。
③別の変化に目を向ける
停滞期に成果を感じられないなら、別の変化に目を向けましょう。
例えばトレーニングの場合、体重に変化がみられなくても、見た目の変化はどうでしょうか。トレーニング強度が上がらなくても、トレーニング後の感覚や気持ちに違いはないでしょうか。トレーニングによってなんらかの変化ないでしょうか。
実際、私も停滞期に入るとジムに行くのが面倒になりますが、身体を動かさない日が続くと不調な感覚があるので(錯覚だとしても)、それをきっかけに運動することがあります。
④「楽しい探し」をする
あとはもう「楽しむ」ことができるかどうかです。
学習や運動自体に楽しみを見出してもよいですし、紐づいた別要因に楽しさがあっても行動は継続されやすくなります。
私が通っているフィットネスジムには高齢者の方も多くいるのですが、トレーニングそっちのけでお友達と談笑している様子をよく見かけます。友達に会いにジムに行くというのは本来の目的とズレているように見えますが、それで結果的に運動が続くならOKでしょう。
以前フィットネス関係の専門家の方から聞いたのですが、最近は入浴やサウナを目的にジム通いをする方も多いそうです。「風呂のついでに運動」となるのであれば良い習慣化の方法だと思います。
歯磨きは変化も楽しさもないのに習慣化できている

ここまで述べてきたように習慣化には変化や楽しさが重要です。
ところが歯磨きはこれに該当しないのですよね。
歯磨きを続けていても特に目新しい変化も起きないし、決して楽しいわけではない。それなのに多くの人の習慣になっています。
(もっとも歯磨きを怠れば虫歯という変化が生じて辛い経験をしますが)
仮に10年間「大好きな同じ本を毎朝欠かさず読む」よりも「たいして面白くもないのに毎朝歯を磨く」ほうが簡単なのは想像できると思います。
これは多くの人が歯磨きを「当たり前の行動」「やらないと気持ち悪い」と捉えているからでしょう。習慣化のゴールはこの状態だといえます。
「成果があるから行う」だと、変化を感じられなくなったら辞めます。
「楽しいから行う」だと、飽きたら辞めます。
「当たり前」として自分の価値観と生活に組み込まれることが永続的な行動継続、つまり習慣化の最終地点でしょう。
もっとも習慣形成の初期はそこまで考える必要ありません。
前回noteでも書きましたが、行動を長期的に継続すると習慣強度が増し、動因の有無に拠らず行動が自発的に発生するようになります。
まずは少しでも行動することが重要です。
「HR情報局 スマハビRadio」にて習慣化シリーズ配信中!
