
自在な「習合」の創造性と生命としての文化−読書メモ:安藤礼二『列島祝祭論』
安藤礼二氏の『列島祝祭論』がおもしろい。
陰と陽、生と死、死と再生、静と動、天と地、海と山、といった対立関係。
そういった対立関係にある両極のあいだで繰り広げられる、両極をひとつに結び合わせる作用や、片方の極を他方の極へと転換する作用。
その作用を、移動、移行、変身といった身体の動きによって、身を持って演じること。
密教、天台、能などへ至る日本列島の「祝祭」の儀礼の中には、そうした対立関係にある両極を媒介するための転換作用を演じる、という明確に意識された動機があるという。
修験道と道教
『日本霊性論』によれば、この活動を実際に担い、列島各地に現在に伝わる数多くの痕跡を残したのは修験者たちである。
役小角に始まるとされる修験道は、大和の葛城山の麓に暮らした渡来人たちのものの考え方にルーツを持っている可能性があり、その渡来人たちのものの考え方というのは他でもない「陰と陽」の対立と転換で世界を説明しようとした道教的なものだった可能性がある。
神話的思考へ
ちなみに、世界を対立関係が織りなすネットワークと捉えるのは道教に固有の考え方ではなく、人類に普遍的な神話的思考の産物である。
レヴィ・ストロースが明らかにしたように、世界を対立する項が織りなす関係として捉え、その起源や、関係を適切な距離に保つ方法をひたすら考える、ということは「人類」が普遍的に行ってきた思考のパターンである。それは大陸を超えて、言語を超えて、時代を超えて、文化を超えて、いつでもどこでもサピエンスが普遍的に行うことである。
おそらく、道教的な思考をする渡来人たちのコミュニティの周囲には、彼らの「渡来」に先行すること数百年以上前に渡来した「弥生」の農耕民の子孫たちが大和の国をつくっていた。
いくつもの弥生といくつもの縄文を通底する神話的思考
弥生の子孫といっても、縄文一色の九州北部に最初に到達した農耕民の直系の子孫ということではなくて、数百年を超える「弥生時代」を通じて、続々と渡来し、列島各地に移住し、互いに争ったり、同盟を結んだり、離合集散を繰り返してきた多数の農耕部族たちが織りなしたネットワークの一部分である。
ルーツの異なる様々な農耕民のコミュニティがあり、その中には縄文以来の狩猟採集文化を色濃く受け継ぐ人々も生きていた可能性がある。
そうした在来の人々もまた、人類に普遍的な神話的思考、世界を対立関係が織りなすネットワークとして捉える思考を行っていたと考えることは、突飛なことではない。
道教が明晰な論理として意識する二項対立とそのあいだの転換という考え方は、在来の様々な部族の人々にとっても、その人類の普遍的な部分に触れる知性だったことだろう。
あるいはその意味も、理由も、よくわからないまま受け継がれてきた儀礼、儀式の意味を、道教的な二元論と媒介の思想は一挙に意識的に説明してくれたのかもしれない。
純粋性ではなく習合こそが進化するシステムの本質
さて、ここからが安藤礼二氏の真骨頂である。
それは文化ということを、純粋性ではなく、徹頭徹尾「習合」として捉えるという考え方である。
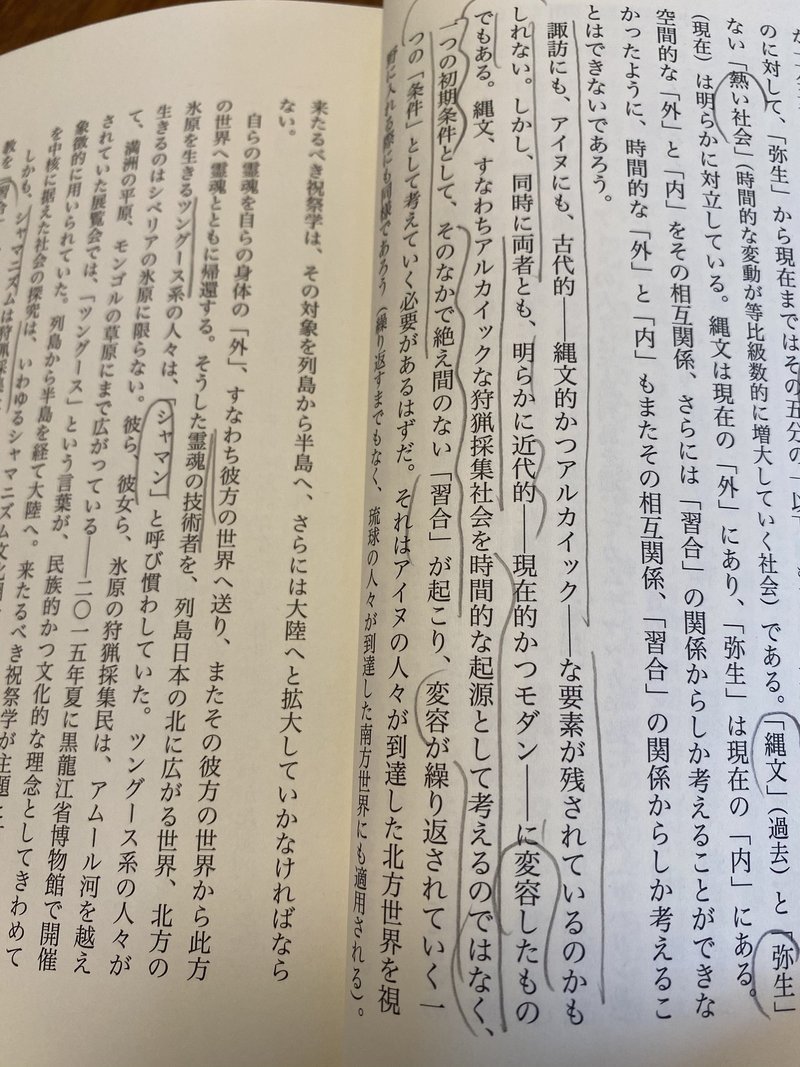
「縄文、すなわちアルカイックな狩猟採集社会を時間的な起源として考えるのではなく、ひとつの初期条件として、その中で絶え間ない「習合」が起こり、変容が繰り返されていく一つの「条件」として考えていく必要があるはずだ。」(安藤礼二『日本霊性論』p.16)
「縄文」というような、なにか単一の純粋な起源を想定し、その起源からの純粋な連続性において後の文化を価値付けるのではない。
そうではなくて、幾つもの異なりながら似たもの、あるいは、そっくりでありながらどこか違ったものが重なり合い「習合」し、変容していくプロセスこそが文化の精髄である。
「縄文」も、「弥生」も、より新しい「渡来人」の文化も、狩猟採集の文化も農耕の文化も、数千年、数百年に渡る時間の中で、場所によって、時期によって、多様な姿に分化しては、対立したり、混じり合ったりしながら姿を変えてきたものである。渡来人の道教的な思考といっても、それは現在に伝わるいずれかの道教の文献と正確に完全一致したアルゴリズムであるはずがない。
世界を対立関係が織りなすネットワークとして分節する
文化というのは進化するシステムである。
文化というシステムがひとつの(そしていくつもの)システムとして、外部の環境から区別されたものになるのは、システムが自らを再生産する処理を繰り返すからである。その反復される処理のアルゴリズムこそが、他ならぬ世界を対立関係が織りなすネットワークとして分節することである。
分節は、まず区別を行い、次に互いに区別される「異なる」極を「置き換え」「変換する」ことによってつないでいく。この二つの側面からなる。区切りながら、同じこととして交換可能にする。
この「異なる。が、同じ」とすることが、人類による意味作用のもっとも根源的なアルゴリズムであり、この上に、壮麗な文化の体系が展開していく。
「対立関係にある両極を媒介する」ことを明確に意識し、その媒介作用の中へと在来の渡来の様々な信仰、図像、記号、言葉、声、そして伝承を引っ張り込み、新たな組み合わせを無数に生み出していく。
列島各地の山中へと分け入っては儀式を行った修験者たちの活動は、それ自体が区別を区切りだしつつ、新たな交換可能関係を開く営みという側面を持っていた。
それは「異なる。が、同じ」で動くアルゴリズムであり、そこから密教へ、天台へ、神道へ、能へ、無数の「習合」のパターンを生み出す進化型システムのジェネレータとなった…。という具合に理解することもできる。
文化、つまり人間にとって意味のある情報の体系もまた進化するシステムであり、ある種の生命である。そういう視座にまで一挙にいざなってくれるのが、この『列島祝祭論』である。
おわりに
文字を生み出して以来、人類は出来合いの区別を機械的に反復し、それによって意味を保存する方向で強実を発揮してきた。
しかし人類は同時に新たな区別を試し、新たな置き換えを試すという、「習合」を新しく始める意味作用の力を持っている。出来合いの意味を反復するときでさえ、この真の創造的意味作用が、切り詰められた形で働いているのである。
「日本的霊性」の特長が、固定的な記号体系を保存するという方向ではなくて、自在に習合を引き起こす創造的な意味作用の方にあるというのはおもしろい。
>続きはこちら
関連note
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
