
【コラム】「タスクマネジメントスキル」(他人のタスク編)
はじめに
前回は、自分自身のタスクについてお話しましたので、今回は他人のタスク編です😁
このコラムを読んでくださっている皆様の多くはマネジメント層だと思いますので、釈迦に説法だと思いますが、自分自身のタスク管理より、他人のタスク管理の方が難易度が高いですよね😨
私は仕事柄、組織やマネジメントの問題をお伺いする機会が多いのですが、その中でも部下のタスクマネジメントでお困りのマネージャーは非常に多いです😨
・タスクを振っても思い通りのクオリティに達しない
・結局全部自分に戻ってくる
・ホウレンソウがないから進捗がわからない
・意図していない方向の処理をする
・筋の悪い仮説を基に業務を遂行する
・時間厳守できない
・全く育たないしやる気も無いように見える
etc...
こういうことはしょっちゅう聞きます😨
根本的な原因を辿っていくと、採用でミスっていることがほとんどですが、今回の記事では「採用は成功している(良い人材を採用できている)」という前提でお話します。
採用で失敗しないようにするためにはどうすればいいのかというお話はまた別途書かせていただこうと思っています。
では、他人のタスクマネジメントについて、最低限押さえておくべきスキルや心得みたいなものを語っていきます😁
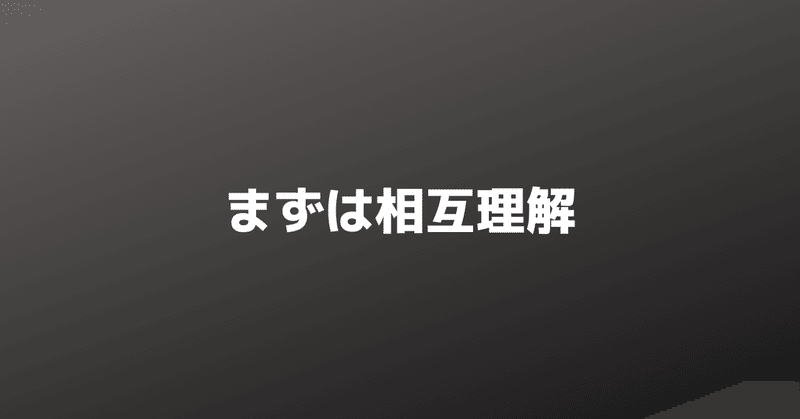
1.まずは相互理解
組織マネジメントが上手く行っていないケースの8割くらいはコミュニケーション不足が原因です。
タスクマネジメントでもこれは同様で、上司と部下のコミュニケーション不足に起因する不具合が最も多いと感じています。
そのため、まずは相互理解を図る必要があります。
しかし、ここで問題が一つ。
それが、マネジメント適性の問題です😨
肩書や役割はマネジメント層なんですが、その人自身の適性がないということがよくあるのです。
そもそも、優秀な人≒タスク処理が早い人であることがほとんどです。
そして、タスク処理が早いということは、集中して物事を処理できるということであり、そういう人は若干コミュ障が多いという現実があります😆
その結果、良いプレイヤーが良い教師(マネージャー)であるとは限らないという現象が起きます。
優秀な人は、自分のタスクに集中することが上手なので、業務時間中の集中時間がかなり長いです。
それゆえにタスク処理も早い。
そして、その集中時間が長ければ長いほど、部下とのコミュニケーションが物理的に減っていきますから、部下は上司が何を考えているのかわからなくなります。
その上、タスク処理が早い上司ほど、部下の処理能力に不満を抱えがちなので、最終的には自分で処理しようとします。
その結果、部下は「自分は信頼されていない」「自分は上司から評価されていない」「自分は必要とされていない」と感じやすい状況が生まれます。
現に、タスク処理の早い上司は、部下を必要としていないことが多いです。
むしろ、完全に見下していて、部下を「無能である」と考えているケースも目立ちます😨
育てる気が元々ないケースも多い……
こういう人はスペシャリスト(マネージャーの対義語とおもってください)として活躍すべき人材です。
自分がスペシャリスト人材であると思う人は、早めにマネージャーから降りましょう。
部下にも自分にもマイナスが大きいので。
仮に、これからもマネージャーとして活躍していきたいと思った方は、以下のことを肝に銘じてください。
マネージャーは、一人一人の貢献量を最大化し、一人では成し得ないようなことを組織として達成するため存在しています😆
したがって、まずは部下の特性を徹底的に把握することからはじめてください。
自分のタスク処理は二の次です。
部下がどのようなことにインセンティブ(動機づけ)を持っているのか、どういう価値観を持っているのか、どういう能力・特技・弱みを持っているのかを理解しないと、マネジメントはできません。
ただ、ここで気をつけないといけないこと(やってはいけないこと)は、部下のことばかり根掘り葉掘り聞くことです。
これは単に危ない上司です😨
相互理解の最初の一歩は、自己開示です。
上司側から、真摯に部下に向き合って、自己開示を行ってください。
その際、チーム内の相互理解を深めることを目的としている点をハッキリと述べてから自己開示を行う方が良いでしょう。
そして、相手に開示を強制しないことも大事です。
相手が話したくないなら話す必要はないという前提をしっかり守ってください。
強制的にプライベートの話をさせられることほど不快なものはないので。
自己開示を続けて、相手も心をひらいてくれた結果、ほぼ兄弟のような状態まで相互理解が完了すれば土台の完成です😁

2.心理的安全性の確保
相互理解がある程度進んだら、心理的安全性を確保しましょう。
心理的安全性とは、元々“psychological safety”という単語で組織論や組織心理学、リーダーシップ論などで用いられてきた言葉です。
誰が最初に言ったかはわかりませんが、私が知る最古の論文は1999年にハーバード大学の教授であるエイミーエドモンドソンが発表した“Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams”という論文の中に出てきています。
この論文では、心理的安全性を以下のように定義しました。
“Team psychological safety is defined as a shared belief that the team is safe for interpersonal risk taking.”
(瀧田訳:チーム内において自分が対人関係上のリスクを冒しても安全だと信じられる共通の信念)
要するに、チーム内のメンバー全員が『チームのことを想っての発言なら何を言っても大丈夫だ!』と思っている状態のことです😁
この言葉が有名になったのは、Googleがチーム内の心理的安全性を重視するという点を外部に発表したからです。
Googleのチーム運営に興味がある方は、以下の書籍を読むといいでしょう!
他人のタスクマネジメントの問題でよく耳にする事象は「部下がホウレンソウをしてくれない」というものです。
ホウレンソウをしない理由は様々ありますが、私が見ている限りでは「心理的安全性の欠如」によってホウレンソウできないという状況が最も多いなと感じています。
何かネガティブなことをいうと上司から怒られる、否定される、非難されるという恐怖があるせいでホウレンソウできないのです😨
この部下の気持ち、私はよくわかります。
私は若い頃、軍隊のような営業組織にいました。
毎日のように怒号が飛び交い、暴力が溢れ、1年目の離職率が50%を超えるような、男ばっかりの組織でした。
こんな組織では、心理的安全性なんて産まれません。
こういう組織での生存方法は2択です。
・従順な犬になる
・喧嘩しつつも結果を出して上に行く
どちらもできなければ、辞めるしかありません。
私の場合は、結果を出して、辞めました😁
あそこで上に上がっても価値がないですし、学ぶことだけ学んだら長くいる場所ではないと思ったので。
この組織では、当時から中間管理職が育たず、人を入れ替え続ける方針を採用していました。
つまり、新卒・中途の大量採用です。
受けに来た人間の8~9割は合格します。
毎年どう見ても売れない新人が大量に入ってきて、大量に辞めていきます。
その結果、私がいた頃は、3年以内の離職率が70%を超えていました。
こういう組織でも、生き残りは可能です。
なぜなら、あれから10年以上経っていますが、まだ生き残っているからです😨
労働基準監督署が何度も来ていましたが、改善は特に無く、そのままの状態で今でも生存しています。
自然淘汰されないということは、そういう組織にも一定の需要があるということだと思います。
しかし、多くのベンチャー企業はそんな組織を作りたいとは思っていないはずです。
もし、マネージャーである皆様が、効率的で、かつ、信頼関係も厚い良いチームを作りたいと思うのであれば、心理的安全性を確保しましょう。
まずは部下と上司で相互理解を深くし、部下の意見をしっかり聞く。
このとき、部下の発言が上手ではないこと、論理展開がおかしいこと、どもることがよくありますが、それは本人のせいじゃないことがほとんどです。
部下が普段は普通に話せているのであれば、その過度な緊張を与えているのは、上司そのものであることが多いです。
それは心理的安全性を確保できていない証拠なので、まずは何を言っても全否定されないという安心が持てる土壌を作りましょう。
そして、部下の意見を全部聞き終わったら、しっかりとお礼を言いましょう。
部下の鋭い視点、新しい意見が未来の組織を形成するのです。
勇気を出して言ってくれたことに敬意を払うのは当然のことです。
できれば、部下の意見で良いと思ったものは即採用し、行動し、部下に結果報告をしてください。
その繰り返しによって心理的安全性が確保されていきます。
この点、WARCの山本さんは心理的安全性を確保するのがすんごく上手いんですよ🤔
しかも、本人は無意識でやっていると思います。
私もいろんな経営者に会っていますが、最高レベルの器のデカさです。
対人関係のスキル(コミュ力)、寛容性がずば抜けて高いんです。
だから、誰もが意見を言いやすい。
自社のため、組織のために、それぞれが言いたいことを言える雰囲気があります。
私が山本さんへの信頼を厚く持っているのは、心理的安全性が確保されているからです。
『この人は凄い。何を言ってもちゃんと聞いてくれる』と心から思っているし、私の主張の論理がしっかり通っていれば、最速で動いてくれるという確信も持っています。
だからこそ、山本さんが動きが遅いときは、他に何かより重要な理由があるか、私の論理構成に何か欠落・不足があるのだという推測が働くのです。
ほぼ100%の確率で山本さんの方が深く思考しているので、私の中で強い信頼が生じています。
その結果、WARCのために何ができるかを安心して思考し続けられるし、動き続けられます。
未だにマネジメントを毎日学ばせていただいていますね🥰
ほんに、良い出会いだったなぁと今でも思います。

3.部下の利益に配慮する
相互理解が深まり、心理的安全性もある程度確保されたとします。
その次にやるべきことは、適性なタスク振りです。
部下にタスクを振る時、自分の視点でタスクを振るのはオススメしません。
それはきっと、マネジメントができなくなります😨
大事な視点は、部下の利益になるかいなかです。
ベンチャーでは、日々大小様々なタスクが発生します。
その中で、新しい経験や知識が得られるタスクも多数発生します。
それらのタスクを一つ一つ分析し、部下の利益・インセンティブを考えましょう。
ここで活きてくるのが相互理解の深さです。
相互理解が深いと、誰がどんな夢を持っていて、将来どういう人物になりたいのかがわかります。
その夢に貢献するようなタスクは、全部部下にやらせてあげましょう!
その際、タスクをポンッ!と振るのではなく、そのタスクから得られる知識や経験を説明し、どのようなメリットがあるかを示した上で「これ、やりたい?」と聞いてください。
本人がやりたいといえば、任せましょう!
ただし、その際、既存のタスクの全体量は確認してください。
部下はまだ自分の限界値を知らないことが多いです。
処理時間の見積もりも甘くなりがちなので、既存タスクの全体量を把握することは必須です。
その結果、振ったタスクを処理できなさそうだなとなったら、既存タスクの内、重要度の低いもの(雑務)をマネージャーが引き取ってください。
部下の成長のために貢献するのがマネージャーの仕事ですから、雑務は本来マネージャーの仕事です。
前記事で、タスクポートフォリオ・マネジメントのお話をしました。

↑これです。
重要度も緊急度も低い仕事はマネージャーがやりましょう。
そして、部下の人生にとって利益が大きなタスクは極力部下に😁
このようなタスクの振り方は、最初のうちは上手にできないかもしれません。
上司自身も部下を信頼できないでしょうし、現にタスクも上手に捌けないことが多いでしょう。
でも、部下にとってメリットのあるタスクは、部下の本来の実力を底上げしてくれます。
また、本人も自分の将来にプラスになることを熟知した上でタスクを引き受けているので、モチベーション高くタスクを処理してくれます。
その結果、処理の質も高くなりますし、自発的に動いてくれます。
その方が仕事も楽しくなるでしょう😁
その繰り返しの結果、タスクマネジメントそのものをしなくてよくなっていきます。
週に1回程度の定例などで進捗確認をしていれば、十分です。
私は今のところ、そういうタスクマネジメントで失敗がほぼ無いので、この方法を採用し続けています。

4.責任は上司が取る
次に、タスクマネジメントで極めて重要な点が、責任の所在です。
最終的に誰が責任を取るのかという論点です。
これは間違いなく上司です。
それ以外はあり得ない😒
マネージャーの主な仕事は責任を取ることだと思うので、責任を取りたくなかったらマネージャーになってはいけません。
タスクマネジメントが上手く行っていない組織では、責任を押し付けられたと感じている部下が、モチベーションを失っていることが多いです。
上司がタスクを振るときに、部下に責任ごと押し付けているパターンです😨
これは部下の立場から見ると何も楽しくない……。
上司から責任を押し付けられたと感じるようなチームは心理的安全性がなくなります。
だからこそ、マネージャーは常に責任を取る姿勢を見せてください😁
私の事例で恐縮ですが、以前、部下にある大事な届出を任せたことがありました。
その子自身、法務として経験を積みたいと考えていましたし、新しいことがどんどんできるようになって行く楽しさも感じていた時期でした。
少し難易度の高い届出でしたが、本人も燃えているし、任せようと判断しました。
その結果、届出当日に、私とその子で行政官庁に出向き、書類を出しました。
出発前に「書類全部再度チェックした方がええよ。大丈夫?」と聞いたら、自信満々で「大丈夫です!何度も見ました!😁」とドヤ顔でいうてたので、そのまま向かいました。
しかーし😨
大事な書類が2枚足りない……。
部下の顔を見るとまさしく「😨」でした🤣
あまりに青ざめていたので思わず笑ってしまいましたが、その場で私が丁重に頭を下げて、すべての書類を一旦持ち帰り、後日再提出させていただくことにしました。
この届出は、行政官庁の担当者との面談と書類チェックが入るタイプの届出だったので、平謝りしました。
でも、そもそも任せたのは私ですし、持っていく前にダブルチェックすべき案件でした。
完全なる私のミスです。
それでも部下は責任を感じたようで、ずっと私に謝っていました。
「気にせんでええよ!おもろかったから全然OK!そんな青ざめんでええて🤣十分よくできとるよ」
と言いましたが、本人はだいぶ落ち込んでいました。
私としては、むしろよくここまで書類を揃えてくれましたなぁと思っていたくらいです。
なお、これがあったおかげで、その部下はその日以降、自分で全部ダブルチェックして、二度と間違わなくなりました。
本当、凄い😨
優秀な部下です。
こういう部下に責任を押し付ける気にはなれないですね。
この話は責任を取る取らないより、私の部下自慢に近いですな😒

5.インセンティブを与える
タスクマネジメントで大事なことは、タスクに関するホウレンソウにインセンティブを与えるという点です。
ホウレンソウする際に、毎回怒られる、注意される、偉そうにマイクロマネジメントされるというケースでは、誰もホウレンソウをしたがらないでしょう😨
でも、意外とそういうマネジメントスタイルの人は多いです。
毎回定例で進捗確認をしながら、怒ったり指摘したりするのです。
これは楽しくない。
私ならそんな定例に出たくないし、ホウレンソウ自体やりたくない(たぶんホウレンソウしなくなる)。
だからこそ、毎回ホウレンソウをもらったら、ピンポイントで褒めましょう!
「この時点で報告してくれて助かった!ありがとう!」
「良い感じに進んどるね!ここで悩むのは当然やけ、むしろ今言うてくれてありがと!」
「ここで悩むとか、着眼点がイイネ!しっかり考えてくれてる証拠だわ」
とか😁
いくらでも褒めるところあると思います。
そもそも、ホウレンソウしてくれている時点で凄まじく優秀じゃないですか😨
今、私が関わっている会社に、部下ではないけど、私を補佐してくれている方がいるんですよ。
この方にパワポの作成を依頼したら、次の日の昼頃にパワポを4案作ってくれて共有してくれました😒
思いましたね。「天才かよ」と。
こういう人を部下に持つと幸せなマネジメントライフを送れるんだろうなぁと常々思います🤣
おわりに
今日も長い文章を書いてしまった😨
上記のようなマネジメントスキルは、すでに皆さんお待ちだと思いますが、いずれの方法を駆使しても上手く行かない人もいます。
そういう人は、そもそも自分に合っていないということだと思うので、早めに異動していただくのが良いかなと思います。
合わない者同士で業務を行うのは、生産性もモチベーションも下がるので、良いことが無いです。
そういう不幸なことが起こらないようにするためにも、採用時のマッチングはしっかり行いたいところですね🤔
では、また次回😁
【お問い合わせ】
WARCで働きたい!WARCで転職支援してほしい!という方は、以下のメールアドレスにメールを送ってください😁
内容に応じて担当者がお返事させていただきます♫
recruit@warc.jp
【WARCで募集中の求人一覧】
【次の記事】
【著者情報】
著者:瀧田 桜司(たきた はるかず)
役職:株式会社WARC 法務兼メディア編集長
専門:法学、経営学、心理学
いつでも気軽に友達申請送ってください😍
Facebook:https://www.facebook.com/harukazutakita
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/harukazutakita/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
