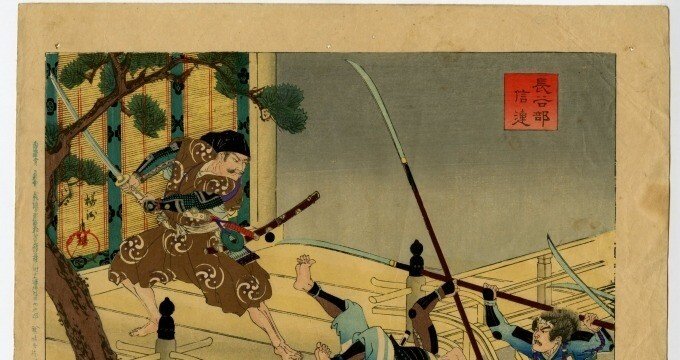
- 運営しているクリエイター
#日本史がすき
■【より道‐115】「尼子の落人」と家訓が残るほどの物語_尼子清定という男
わたしは、小さいころから父に、ご先祖さまは「尼子の落人」だということを言われ続けてきました。父の故郷、岡山県新見市高瀬の家屋跡にある旧墓地には、「尼子の落人」のお墓と伝わるものも存在しています。
ただ、そんなことを言われても、歴史のことはよくわからないですし、しかも、織田でも徳川でも武田や上杉でもない尼子と言われてもよくわかりません。正直、昔は、仏門の尼さんのことだと思ったりもしていましたし、素
■【より道‐112】戦乱の世に至るまでの日本史_時代を超えた因果応報「永正の錯乱」
中世・戦国期の時代がややこしいのは、有力大名のお家騒動に加えて、家格が「下の者」が「上の者」打ち負かす。つまり、下剋上がおきたことになりますが、これまた、あっちこっちで、いろんな問題が起きているのでなかなか頭の整理がつきません。
足利将軍家でも「応仁の乱」や「明応の政変」「船岡山合戦」とよばれるお家騒動がおきていますし、有力武家の六角氏、畠山氏、斯波氏、京極氏などのお家騒動が複雑に絡みあったりも
■【より道‐111】戦乱の世に至るまでの日本史_時代を超えた因果応報_細川政元という男
色んな思惑はあったと思いますが、室町将軍・足利氏のお家騒動、「応仁の乱」が終結すると、幕府の権威が大きく衰退していったそうです。
権威といわれても、ピンときませんが、11年ものあいだ戦が続いていたので、足利一門の兵力が衰退したことは間違いないでしょうし、「応仁の乱」で駆り出された足軽農民たちが、武器を持ち一揆を起こしたり、神仏社や公家の領地を横領しだしたりーー。
最前線の国人が農民たちをまとめ
■【より道‐110】戦乱の世に至るまでの日本史_時代を超えた因果応報_ 六角高頼という男
ふと、思うのですが「応仁の乱」にかかわった、八代将軍・足利義政から、十五代将軍・足利義昭までの間を生き抜いた室町将軍たちのことをじぶんは、よくしりません。
織田信長が活躍した戦国期は、なんども脳裏に刷り込まれているので、なんとなく経緯を理解していますが、どうも歴史のカゲに隠れてしまっている時期が、我が家のファミリーヒストリーにはとても重要のようです。
「応仁の乱」後には、戦国期の突入を決定づけ
■【より道‐107】戦乱の世に至るまでの日本史_時代を超えた因果応報_「応仁の乱(自習):後編」
「応仁の乱」は、政事で対立していた、細川勝元と山名宗全が畠山氏のお家騒動を利用したことで、戦に発展しました。
なぜ、ふたりが対立していたかというと、「嘉吉の乱」で山名氏が討伐した赤松氏の再興を細川勝元が支援したからだと言われていますが、室町幕府に権力が集中して、朝廷のチカラがなくなっていたことも「応仁の乱」に発展した一つの要因だったと思います。
ただし、私たちの日本史は、ペリーが来航したことで
■【より道‐106】戦乱の世に至るまでの日本史_時代を超えた因果応報_「応仁の乱(自習):中編」
人の世のむなしい「応仁の乱」と、語呂合わせがありますが、1467年前後の出来事だけでこの争いの背景を理解するのは、難しいと思います。
これは、なにも「応仁の乱」という、わけのわからない中世の日本史だけではなく、第二次世界大戦にいきつくまでの近代史もそうです。どうしても、目の前のことばかり気にしてしまいますが、時代を超えた理由が必ずあります。
現在起きているロシアとウクライナの戦争もそうですし、















