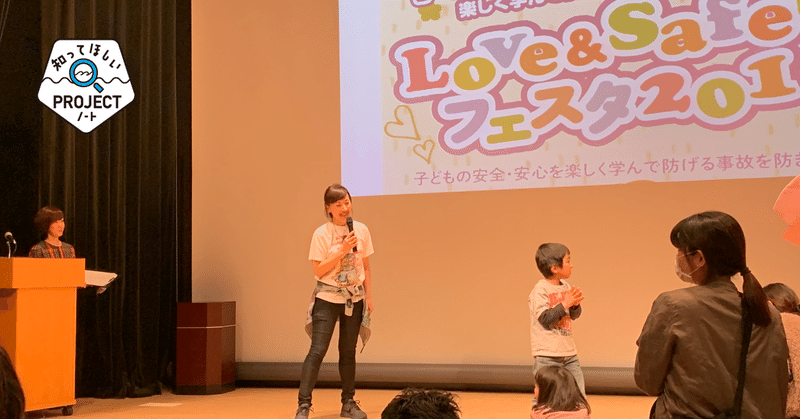
データから原因を検証!地域×医療×教育、大村市一体で取り組む事故防止プロジェクト
子どもを事故から守るプロジェクト「Love&safety おおむら」は、0歳から19歳の子どもの死亡原因の第1位が“不慮の事故”であるという深刻な社会状況を背景に、市内の子どもたちを守るために立ち上げたNPOの事業です。
現在は大村市をはじめ、市内の主要機関である教育委員会、保育園、幼稚園、小・中学校などの教育機関、警察や消防署、さらに産業技術総合研究所などの研究機関が、ネットワークに参加し、地域一体型の社会システム構築を目指して活動を続けています。
今回は、事業を展開するNPO法人Love&Safetyの理事長である出口貴美子さんに、プロジェクトを立ち上げた経緯や活動内容の他、活動の軸である子どもの事故予防の大切さを伝える重要性についてお話を伺いました。

(プロフィール)
認定NPO法人 Love&Safety おおむら 理事長 出口貴美子さん
長崎県大村市で小児科医療を行なう出口小児科医院の院長を務める。2006年より、地域医療に従事しながら、子どもの事故予防活動を開始し、2012年にLove&Safetyおおむらを設立。2012年に内閣総理大臣賞表彰、2017年には地方自治功労者総務大臣表彰を受賞。
小児科医として始めた活動から誕生したプロジェクト
—医師である出口先生が、Love&Safety おおむらを立ち上げた経緯を教えてください。
出口:
2006(平成18)年にアメリカ留学から帰国して、父の医院を継ぎました。それと時を同じくして、子どもの事故予防対策として、院内でおもちゃの安全性に関する取り組みを始めたんですね。
その頃、Safe Kids Japanの理事をされている東京工業大学教授の西田佳史先生と知り合う機会があり、そのご縁から出口小児科医院で、子どもの事故予防セミナーを開始しました。
この活動を数年続けてきた中で、2010年頃から大村市でコミュニティを活用した団体を作ろうという話が持ち上がり、2011年にLove&Safety おおむらを立ち上げることになりました。
私自身が医師会に所属していますので、まずは医師会を中心に事業参加の声かけを行い、そこから警察や消防、学校、幼稚園ともつながりができました。活動の目的が「子どもの安全」だったので、すぐにみなさんの賛同を得ることができたんだと思います。
大村市の人口は約10万人と比較的コンパクトなこともあって、もともと警察や消防、医療機関、教育機関ごとにコミュニティが存在していたんですね。なので、一から立ち上げるというよりは、既存のコミュニティを活用しながらネットワークを構築して、プロジェクトの名称を付けたような感じです。
コンパクトな環境だからこそ地域全体での連携が可能になり、かつ同じ想いを持つ方がつながり、スムーズに設立できたのではないかと思っています。

ネットワークを駆使して、子どもが遭う事故のデータを収集
Love&Safety おおむらの活動の特色の一つに、データの収集と分析による情報発信があります。大村市内で子どもが遭った事故の種類や件数、事故に関連した製品、事故の発生場所をマップ上で示すなどして、予防に必要な情報を伝えています。
—子どもが遭った事故のデータを収集して、その分析や予防に必要な情報を発信されていますが、この取り組みを行うきっかけはなんだったのですか?
出口:
西田先生から「科学的な事故予防を」とアドバイスをいただいたことがきっかけでした。これは、今までにはなかった子どもの事故をデータとして分析して検証する取り組みだったのではないかと思います。
取り組みを始めるにあたり、まずは大村市内の医療機関から医師の診断がついた信頼ある事故データを集めました。そのデータから分かったのは、大村市の子どもの事故の中で、命に関わる重大な事故が“自転車事故”であること。
その結果からネットワークを利用した事故予防の取り組みができ、のちに自転車事故減少へつなげることができました。その後、さらに活動の範囲を広げようと、子どもの保育・教育施設での事故調査を開始したのです。
現在は内閣府からガイドラインが提示されて、事故の報告書を提出することになっていますが、当時はそのような仕組みはまだできていなかったんですよ。
保育園での事故調査は、各園に事故調査票を配布し、保育士の先生方に記載をしていただきました。
事故調査票は、簡単に書き込め、可視化しやすい工夫をしたものでしたが、保育現場の負担にならないかの心配もありました。
しかし実際、始めてみると、みなさんがとても熱心で、ケガをした場所の写真まで添付して送ってくださるようになったんです。それらのデータを分析し、保育園に対して原因と予防策をフィードバックする流れを作っていきましたね。
最初は、私や西田先生から入園時の保護者説明会で、事故調査の結果や予防方法を直接お話をしていましたが、現在は私たちのNPOと大村市が協働で、子どもの事故予防のスペシャリストである「子ども安全管理士」を養成し、大村市から認定を受けた子ども安全管理士が、各保育の現場で、職員や保護者への啓発活動をおこなっています。
このような仕組みの中で、保育園から園児の親御さんに向けたフィードバックを実施するようお願いしました。例えば、「お家でも、こういう予防ができますよ」と伝えていただいたり。
保育の現場での事故予防策は、多くが家庭での事故に応用できます。
特に、未就学の子どもの事故は、多くは家庭内で発生している現状から、保育士が保護者に事故予防の大切さを伝えていくのはとても意味があることだと思っています。
子どもの事故が繰り返される理由のひとつは、子どもの成長とともに発生する事故が多様であるということ。
ご家庭の状況によって、あらゆる事故が起きていて、それぞれの事故の教訓が受け継がれにくいという課題があります。しかし、科学的に検証された有効な予防法を伝えることで、事故予防ができ、小さな命を守ることができると確信しています。

「楽しく!」を大切にしながら、これからも啓発イベントを展開していく
2020年は新型コロナウイルス感染症の感染予防等へ向け、新しい啓発スタイルを模索中とのことですが、Love&Safety おおむらは、データの分析やWEBによる情報発信だけではなく、参加型のイベント「Love&Safety フェスタ」を定期的に開催するなど、Face to Faceの活動にも力を入れています。
そうした出口先生の姿勢は、「予防は楽しく!」という、これまでの啓発活動から生まれたコツだといいます。
出口:
多くの方が感じている“予防の大切さ”を伝えるには、真面目なアプローチだけでは弱いんです。反応する層が限られてしまう。そこで考えたのが、参加体験型のフェスタの開催でした。
フェスタでは、楽しい企画やおいしいものをいろいろ用意して、体験しながら事故予防を学べるようにしました。例えば食の安全なども絡めてお子さんや保護者のみなさんへ伝えています。
事故予防に関しては、法律的な側面と教育的な側面からの2つのアプローチがあると思うのですが、私の立場でできるのは教育なんです。
年齢や育った環境が違う子ども達や保護者にも、教育のチャンスさえあれば、命を守るという観点での子育てや社会活動にきっと役立つと思っています。そのためにわたしたちができるのが、興味を持ってもらえるように工夫をすること。
決まりきったスタイルに固定するのではなく、いろいろな啓発活動の中で、子どもたちに印象付けられるような場面を用意することが大切だと思っています。
子どもたちに新しい外の世界を作っていくような感じで、この活動をこれからも楽しくやっていこうと思います。
***
出口先生、ありがとうございました!
地域に根付いた小児科医院の医師として、またNPO法人Love&Safety おおむらの理事長として、不慮の事故から子どもを救うためのプロジェクトを「楽しく!」続けられていくことでしょう。今後の活動に期待しています。
NPO法人Love&Safety おおむらについてはこちら
https://www.love-safety.jp/about/
