
【ポンポコ製菓顛末記】 #48 全能感
先日リニア新幹線ルートでJR東海とさんざんもめた静岡県知事が任期途中であっさり辞任した。延期させたから役目を果たした、みたいな変なコメントを残した。
世の中、エッ?というような大人が多いものだ。
「お待たせ!」と「お先に!」
ポンポコ製菓の創業家後継者の会長もエッ!というような発言、行動が多かった。前回紹介した理想ばかり追いかけ、現実を見ないなどは序の口。奇妙奇天烈な発言、行動により、会社や部下が随分と振り回された。創業家のお坊ちゃんだからしょうがないなと笑って済ませられる場合と、そうでない場合が多々あった。もちろん後者のほうが圧倒的に多かった。
会長は人生のほとんどがストレートに上がってきたので苦労という苦労を経験していない。
学生時代は三田にある一貫校に小学生から大学まで内進で進学し、受験勉強、入試というものを一度も経験していない。就職も他社で修行などはなく、ポンポコ製菓にそのまま入社した。もちろん入社試験などない。
入社後は帝王学と称してあらゆる部署を経験した。営業、生産、マーケティング、経理、事業部長とそれこそ経営に必要であろう部署はひととおり経験した。しかし文字通り体験しただけで能力を磨いたとはとても思えない。配属された部署の上司、社員も失敗させてはいけないと、それこそ腫物を触るように丁重に扱ったので、仕事の何たるかを経験できなかった。仕事どころか人生経験もできなかったと思われる。
計数感覚、財務リテラシーを磨くべき経理部長の時は、本人の苦手意識もあって仕事はほとんど部下が行った。当の本人は週刊誌を1日中読んで時間を潰した。後日、自身の口からも「あれは酷かった」と述べている始末である。
そんな状態が社外との接触をするとどうなるか。
会長が事業本部長時代に得意先をゴルフ接待することになった。当方が得意先を接待するのだから本部長は当然饗応役である。まず得意先を玄関でお出迎えし、日中は得意先が気持ちよくプレー出来るように気を配り、終わったらつつがなくお送りする。こんなことは新入社員の営業でも察することが出来るだろう。
ところが会長は違った。
まず朝は得意先をお出迎えするどころか、最後に到着した。逆に得意先に玄関で迎えてもらい、「オッ、お待たせ!!」と入ってきた。日中のプレーは気を使うことなく普段通りに気持ちよくプレーし、ニギリも会長が一人勝ちであった。八百長をする必要は無いが多少の気配りをしてしかるべきだろう。そして圧巻は帰りである。あろうことか約束があるからと得意先をおいてサッサと先に帰ってしまった。
同行した副本部長は1日中冷や汗をかきっぱなしであった。最後は平身低頭、平謝りである。得意先は「(創業家の)田沼さんだから・・・・」と笑って済ませてくれた(表面上は)。副本部長は2度とゴルフ接待を企画しなかった。
同様なことがイベントでもあった。
業界では4年に一度、大手、中小含めた各社の見本市を地方都市で開催する。大手企業が持ち回りで幹事会社を務め、その社長が見本市の責任者となる習わしであった。会長が社長時代に丁度当社が幹事となったので、会長が責任者となった。形式とはいえ責任者なので当然見本市を視察し、挨拶もしなければならない。
しかし正直ローカルの見本市なので会長としてもやる気がないのはみえみえであった。しぶしぶ現地に出向き、挨拶もした。役目も終わり現地の事務局長とランチを取ってから午後の飛行機で帰る手はずを秘書がすべて段取りを取っていた。
ところが当日になって、予定があるからと言って、事務局長とのランチをドタキャンし、午後の最も早い便でそそくさと東京に帰ってしまった。
慌てたのは秘書である。平身低頭に事務局長に謝ったそうだ。
この相手かまわずの傍若無人ぶりは海外にも飛び火した。
ポンポコ製菓は2000年以降海外進出を進めた。事業計画は杜撰なため事業そのものはなかなか思うようにいかなかったが、それでも中国、東南アジア、アメリカと展開していった。工場建設や販売会社を創設したので現地での諸準備、手続きには現場は相当の苦労があった。
アメリカ進出の準備が滞りなく終わり、晴れて現地工場建設の運びとなった。目途が立ったので現地子会社社長が市長と会長とのトップ面談、ランチの手はずをとった。ところが、市長の予定に対し会長は先約があるというので日程が合わず、結局面談は流れてしまった。市長との約束を断る会長の予定が何なのか、口ごもるので当初わからなったが後日判明した。なんとゴルフ好きの当社専務との現地名門ゴルフ場の予約をしていたというのだ。自分の趣味を優先するという感覚に現場は唖然としてしまった。
全能感
昨今の若者は自己チュウだと憂える識者、評論家が多い。しかし、それは今に始まったことではなく、昔から一定数いたし、現にポンポコ製菓の会長のようなエッ!という言動、行動をするオトナはゴマンといるものだ。
さてそのようなオトナ、若者の意識、行動は誰かと似ていると読者は思い当たらないだろうか?
そう、赤ちゃん、幼児である。
この辺りを元リクルートで退職後いきなり公立中学の校長となった藤原和博氏が詳しく述べている。
赤ちゃん、幼児は言葉が話せない、自分の意思や希望を理路整然と周りに伝えられない。だから泣いたり、怒ったり、行動や表情で両親や祖父母の保護者に伝える。保護者はほとんど意思を叶えてくれるので全能感を抱くようになる。
全能感とは「自分で何でもできる」「世界は自分を中心に回っている」という感覚のことだそうだ。しかし成長するにつれ全能感は徐々に目減りしていく。「どうも世の中は自分の思い通りにならない」と理解する。そして小学校に上がるころには「世界は自分を中心に回っているわけではない」と気づく。
そしてある時「自分は全能だ」という思い込みが幻想で限界があることを思い知る。幼児の頃は親が傍らにいてくれたからこそ思い通りになったけれど自分一人では何も満足に出来ない。その当たり前に気づき、戸惑い、葛藤し、何とかしようともがく。
しかしその経験をしないまま成人したのではないかという人がかなりいるというのだ。周りの迷惑顧みず、「世界の中心は自分だ」という全能感のままの大人。所謂自立していないオトナである。
ポンポコ製菓の会長そのままである。創業家の長男として生まれた会長は生まれながらにして将来社長を託され、大事に、特に母親に「男は強くなれ」と育てられた。親のすすめられるままに幼稚園に入園してエレベーターに乗り、降りたら大学を卒業していた。そしてまたポンポコ製菓に入社してエレベーターに乗り、降りたらそこは社長のイスであった。そんな感じである。
しかし私はそのような全能感まんまの大人は珍しくないと思う。むしろどちらかというと大勢を占めており、程度の差ではないかと思う。
所謂自己チュウの人、利他より利己、根気よく丁寧により安近短の生き様を信条とし、そのくせ結果は多くを望む、そんな方々だ。
むしろ自立しているオトナのほうが少ないのではないか。割合として6:4か7:3。所謂大衆と言う部類の方々だ。
もちろん彼らには全能感のままだという意識は無い。彼らには彼らのルールがある。何しろ「世界の中心は自分」が基本だから、おかしいのは自分ではなく、周りだ、上司だ、社会だ。『#8 人間関係は“ま”ぬけがいい』で述べた職場の困ったさんにもある意味相通づる方々だ。
ただそういう方々が悪いというわけではない リーダーには向かないだけだ。何故なら周囲に迷惑をかけるから。リーダーでも自分の家族や課長さん、或いは小企業の社長であれば影響は微細だ。ところが何百、何千、何万人の大企業、大組織のリーダーとなるとそうはいかない。従業員の家族まで考えるとその影響は計り知れない。
だからそういうオトナはリーダーになってはいけない。特に全能感が極端な人は。
普通はそういう程度が悪い人、凡人の人はリーダー選抜で淘汰されていく。だがそれが働かない仕組みがある。
そう、世襲だ。
世襲が一概に悪いわけではないが問題視されるのは淘汰が働かないからである。立派な創業者の後継、芸能人の2世、最たる例は政治家の2世、3世。全能感丸出しでエッというような行動や失言を繰り返す。一般の大衆であったら目立たないが、たまたま人の耳目に触れる機会が多い立場だけに目立ってしまうのだ。
ただこの全能感、良い方向に出れば初志貫徹、自信に繋がる。要は時と場合、程度のバランスの問題だ。世の多くの人が悩み、問題となる人間関係のトラブルの元はこの全能感の程度と言っても過言ではないだろう。
次回に続けたい。
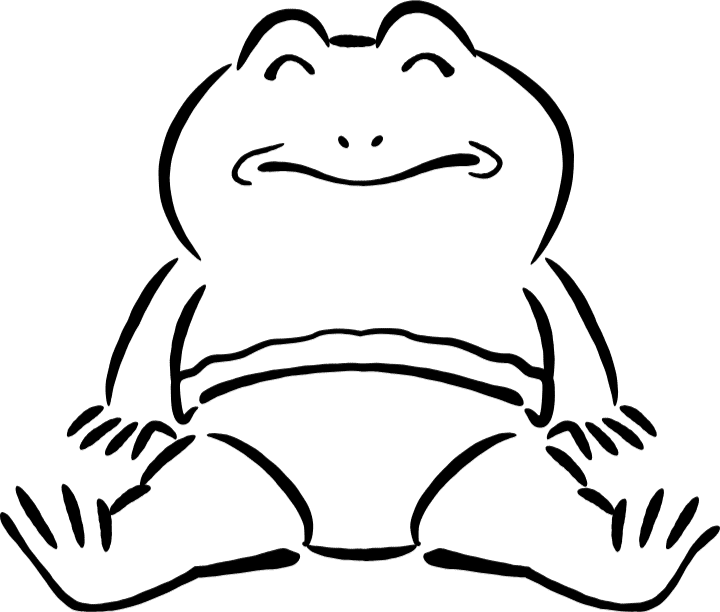
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
