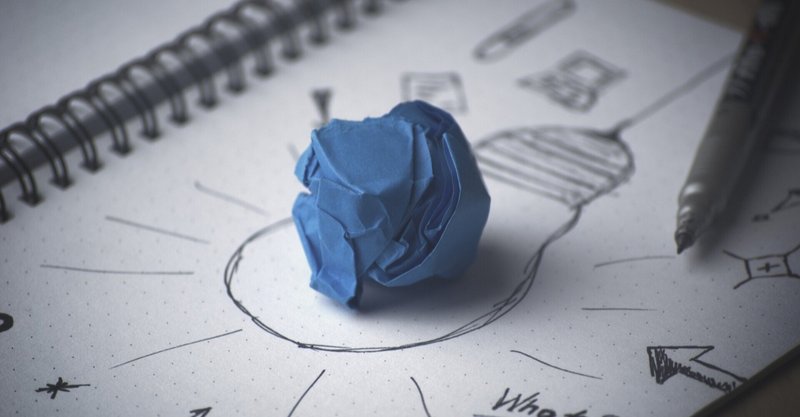
「一貫性がない」という批判への批判
こんにちは。
花粉が飛び始める季節になってしまいましたね。
マスク着用が常態化した生活様式になり、今年くらいは多少、症状も遅れて始まるかと思いきや、
むしろ例年よりも早く出ています。。。
本日のコラムは、
一貫性 × 上下思考
というお話です。
私がこのテーマについて考察したいと思ったのは、
恐らく周りで飛び交っているこの類の批判
「一貫性がない人はいけない」
について、違和感を表明したいと思ったからです。
昨今、世間で多くの批判を受けているのは政府ですね。
コロナ対応についての方針も、手厳しい批判の的となっています。
■主義主張に一貫性がある人、ない人
「一貫性」が、その人への信頼度を測るバロメーターとなっていることは、事実でしょう。
主義主張に一貫性がある人を信頼するのは、実際に私もそうです。
しかし、私がこのテーマについて問題にしたいのは、
一貫性を評価する側の人たち
つまり、「あの人は一貫性がある、ない」と評価する、大多数の人たちの姿勢
についてです。
「うちの上司には一貫性がない」
「政府の方針には一貫性がない」
と言っている人たちは、誰でしょう?
それは、「当事者以外の誰か」になります。
つまり、
まず間違いなくそういう人たちは、
意思決定する側にはいない
ということが言えます。
その人たちにとって「一貫性がない」とは、
「最初に言ってたこと、今言っていることが違う」
ということでしょう。
「うちの子供は、すぐに言うことがコロコロ変わる」
「私のパートナーは、趣味や好みがコロコロ変わる」
と言いたくなる場面が、私生活でもよく起きているはずです。
■なぜあの人は、一貫性にこだわらないのか
一貫性について批判をする人たちは、意思決定をする当事者ではありません。
一見、一貫性を欠いた言動をする人は、ともすると軽薄で、熟慮に欠ける印象を与えます。
なかには実際にそういう人もいるでしょう。
しかしここで、そういった人たちの言動の背景について、想像してみましょう。
もしかしたら、その人たちには、
私たち批判者には見えていないものが見えている
そんな可能性があるとは言えませんか?
私はたちは、その人を表面的に評価できる機会が、2度あります。
1度目は、その人が「主義主張を表明する」とき。
2度目は、その人が「その主義主張と異なる言動をする」とき。
1度目の印象と2度目の印象が違うから、私たちは「ガッカリした」と言うのです。
「あのとき言っていたことと違う」と言うのです。
しまいには、「あの人は信用できない」とレッテルを貼るのです。
■一貫性にに縛られる不自由さ
一貫性に縛られない人が信用を得にくいのは、最初と途中の印象が違っているから、と述べました。
しかし当事者には、その理由が必ずあるはずです。
※もちろんここで取り上げている想定テーマは、主にビジネス上で展開される一般例であり、
人道的、道徳的な観点で「嘘を言っても良い」と言っているのではありません。
先ほども書いたように、
他人に見えないものが、本人には見えている
というのが、その主な理由でしょう。
当然、本人も、その時々のベストな意思決定をしているつもりのはずです。
しかし、昨今の世の中の目まぐるしい状況変化はどうでしょう。
インフォデミックという言葉に代表されるように、多くの人の言動を惑わすほどの、
まことしやかな情報が次々に目の前に現れるのが、今の現実です。
その時々の意思決定は、その時々の情報や状況によって、なされます。
普遍的に正しい意思決定というのは、むしろ難しいでしょう。
つまり、一貫性を欠く言動をする人、あるいは、主義主張を変える人というのは、
言い換えると、
状況を敏感に読み取って、最適な判断にアップデートしている
とも言えます。そして、
その状況変化が、その他大勢には見えていないとき、
「あの人には一貫性がない」と言われてしまうのではないでしょうか?
例えば、自分の会社の社長が、コロナ拡大前となんら変わることのない営業戦略を貫こうとしていたら、かえって不安になりませんか?
ということは、
コロナ拡大前と今とで主張が変わっているのなら、
社長は社長で、その人だけに見えているものがある、と思うのです。
もちろん、なぜ方針を変えたのか、という説明は尽くす責任も、社長にありますが。
私からは、一貫性に縛られる人が不自由に見えます。
みずからが定めた鉄の掟で、みずからを生きにくくしているように見えます。
一貫性にこだわるあまり、
目の前で起きている現実から目を背けたり、
都合の悪い情報をなかったことにしたり。
本人だけの問題であれば、それで良いのですが、
それが例えば経営者の立場だったら、多くの人に迷惑をかけてしまいます。
■「ヨコ思考」と「タテ思考」
「ヨコ思考」と「タテ思考」とは、またまた私が勝手にネーミングした思考センスです。
人の思考のくせは、主に2つに分かれると言われています。
1つは、「各論」に目が行きがち。
時系列的に問題をコツコツと解決していく。
与えられた課題、あるいは目の前の課題を正確にこなすことが得意。
こんなタイプを「ヨコ(左右)思考」と呼んでいます。
つまり、思考が”水平展開”していく人ですね。
もう1つは、「総論」に目が行きがちな人です。目の前の課題よりも、「なぜこうなった?」方が気になる。
時系列でなく、今ある問題を上から俯瞰したり、あるいは
下にもぐって点検したりすることが得意。
こんなタイプを「タテ(上下)思考」と呼んでいます。
つまり、思考が”垂直展開”していく人です。
この二つの思考パターンを同時に持ち合わせる人は少なく、
だいたい、このどちらかに大半の人は属するようです。
■一貫性に縛られない人は、「タテ思考」
少々乱暴な結論づけになるかもしれませんが、
ものごとを俯瞰したり、本質を見出すことのできるリーダーは
「タテ思考」の持ち主のようです。
目の前で繰り広げられる数々の難題や問題に振り回されすぎることなく、
その先に待っている理想やゴールを見通すことができるので、
いわゆる「他の誰にも見えない景色が、見えてしまう」ということになり、
自分だけに見えている”結論”から、”現状”を変えようする傾向にあります。
そのため、周りからすれば、唐突に「また方針を変えられた」と映ってしまうのでしょう。
しかも、そういう「タテ思考」の人にかぎって、
懇切丁寧な説明がヘタ。
という悲しい事実もあります。
「タテ思考」はビジョナリーである分、その表明の仕方によって多くの人を惹きつけるのですが、
丁寧さに欠けるため、勝手に自分のストーリーで進めてしまうのです。
一方で、ビジョナリーに語るのが苦手な「ヨコ思考」は、言われたことに納得して、コツコツものごとをこなす。
しかし、結論や本質から現実を見ることが弱いので、言われたこと、やるべきことにこだわり続けて、変化の機会を見逃す。
いかがでしょうか?
「なぜ部下はわかってくれないんだ?」
「なぜ上司は言うことがコロコロ変わるんだ?」
いまも両者の間に生じる戸惑い、いら立ち、といったハレーションは、
こうした思考センスの違いがから成り立っていると思います。
■組織にとって不幸のはじまり
そして、肝心なのは、
その思考センスが、そのまま適材適所に活かされていない
という事実も、見過ごされてはいけないと思います。
ビジョンを語れないリーダー
実務ができないフォロワー
これは、組織にとっての不幸の始まりです。
しかし、ここを真正面から捉え直すことで、「弱みを補い合えるチーム」が作れるでしょう。
チームビルディングは、まず個性から診断してみてはいかがでしょうか?
ここを理解すれば、コミュニケーションにおけるハレーションもぐっと減ることでしょう。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
◆◇◆ 今週の箴言(しんげん)◆◇◆
(ラ・ロシュフコーより)
ほんとうの雄弁は必要な事は全部しゃべらず、
必要以外は一切しゃべらぬということである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
