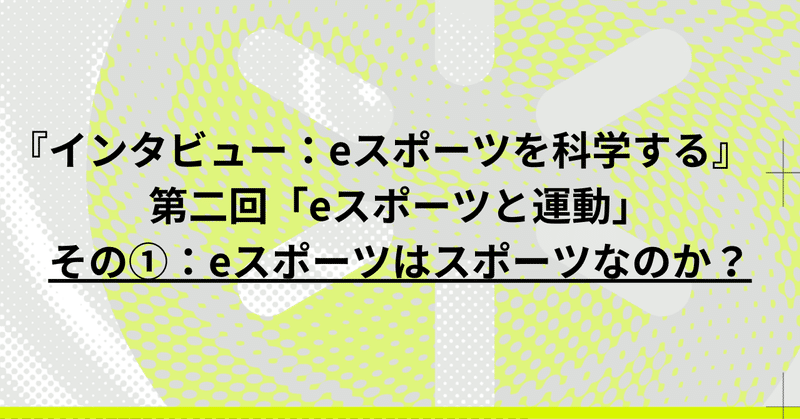
『インタビュー:eスポーツを科学する』 ~第二回~ その①:eスポーツはスポーツなのか?
こんにちは、筑波大学OWLSです!
初めましての方もいらっしゃると思います。
OWLSがどのような活動をしているかは、こちらの記事をご覧ください。
また、今回インタビューを受けていただいた松井崇先生についての詳細は以下のページをご覧ください。
今回は、”第二回”『eスポーツと運動』です。第一回をまだご覧になっていない方は、こちらからご参照ください。
~第二回~
eスポーツと運動
その① eスポーツはスポーツなのか?
運動・栄養・休養・絆について
インタビュアー:
第2回は「eスポーツと運動」に着目してお話を伺っていきたいと思います!その前になぜ「運動」なのか?って思う人もいるかも知れません。実は松井先生は研究のキーワードとして運動・栄養・休養・絆を挙げられています。 なので、第三回以降は「eスポーツと栄養」、「eスポーツと休養」…といったように、順番に触れていきたいと考えています。ではまずその4つのキーワードについて、簡単にご説明をいただいても大丈夫でしょうか。
松井先生:
わかりました。まず日本では20年前に厚労省が主導して「健康日本21」という政策が出来ました。これは「運動・栄養・休養」という三原則が人間の健康やパフォーマンスにとって重要であるということを示したもので、絆以外の三要素はそこで定義されたものなんです。
インタビュアー:
じゃあ「絆」の要素ってどこから来たんですか?
松井先生:
この三原則だけだと、「スポーツ」というものを説明できないんですよ。そもそもスポーツって何なのかというと、身体性・競争性・組織性・遊戯性の四要素で構成されています。わかりやすくいうと、体を使って(=身体性)、競い合うことを(=競技性)、ルールに則って(=組織性)、楽しむ(=遊戯性)っていうのがスポーツです。
では運動・栄養・休養はこの四要素に当てはまるのかということで、もちろん身体性と運動は近いですが、結局は運動・栄養・休養は個人の話になりかねないですよね。

インタビュアー:
運動・栄養・休養だけだと「ランニングして、栄養取って、いっぱい寝る」みたいに一人で完結できちゃいますもんね。それはスポーツじゃないですね(笑)
松井先生:
そうです。その三原則だけでは、競争も組織もルールもなくて、遊びの要素も非常に最低限のものになるんです。「スポーツの良さ」ってそれよりももっと幅広かったりするんじゃないかっていう思いがスポーツ科学者としてはありました。その「幅広さ」が何なのかというと、2人以上で競い合うことをルールに則って楽しむという部分だと思っています。そこで、三原則にどんな言葉を加えればスポーツとして捉えることができるのか。それが「絆」だったってことです。この十年ぐらいで、友だちが多いとか、愛する人がいるとか、そういう社会的な繋がりがある状態も、健康や心身のパフォーマンスに重要であることが分かってきているんです。
インタビュアー:
つまり、従来の三原則では対戦相手とか仲間とか「複数」という視点が欠けてたってことですね。その視点がないとスポーツの競争性、組織性、遊戯性みたいなところが説明できないと。
松井先生:
そうなんです。そこに関してはソフトボール(※第一回参照)もeスポーツも一緒ですよね。そこにこそ「スポーツ性」があるんじゃないかっていうようにも思っています。
インタビュアー:
そうなんですね。そもそも「絆」はスポーツ科学では有名だったんですか?
松井先生:
この言葉は僕が提唱しようとしているんです。この新しい「四原則」をみんなが使っていくような世界にしていきたいと思っているところです。
概念的な話だけど、意味は分かりました?
インタビュアー:
はい! なぜ松井先生が「運動・栄養・休養・絆」のキーワードを提唱しているのか、なんでこの4つが重要なのかが詳しくわかりました。
身体性はどこにあるのか?
インタビュアー:
松井先生の研究では「運動・栄養・休養・絆」という4つのキーワードが重要だということが確認できました。ただ、僕たちはeスポーツの取材をしたいということで(笑)さっきも言いましたがキーワードそれぞれに掛け算をして今後インタビューを進めていこうかなというふうに思っています。今回は「運動」ということで、「eスポーツ×運動」を題材にお話を聞いていきます。
松井先生:
わかりました。
インタビュアー:
先ほどスポーツの四要素として、身体性・競争性・遊戯性・組織性を挙げていたと思います。ではeスポーツの身体性っていったいどこにあるんでしょうか? eスポーツには競争性、組織性、遊戯性っていうのはもちろん見られますよね。ゲームランクとか、チームとか。遊戯性は言わずもがなですが。ただ、身体性っていうのはどこにあるんでしょうか。これは「eスポーツはスポーツなのか」っていう、前回も議論してたことに近いことではあるとは思いますが、、、、
松井先生:
そもそもこの問いは「もうこれが正解だ」っていう答えはないようなものです。世界でも哲学とか生理学とかで大きな議題になっている問いだと思います。そういう意味で非常に良い問いなんです(笑)
「eスポーツの身体性はどこにあるのか」、これは本当に今言ってくれた「eスポーツはスポーツなのか」という問いの置き換えなんですよ。この「eスポーツはスポーツなのか」っていう議論には様々な観点があります。結構論点を絞るのが難しくて、総合的に議論がしにくいし、もししたとしてもズレが生じちゃって終わらないんです。なので私はスポーツの4要素に当てはめて、なるべく検証可能な1つの論点に絞っていこう、置き換えていこう、変えていこう、というふうに考えています。

インタビュアー:
そうだったんですね。では、松井先生は具体的にどういう視点から「身体性」を確認しているんでしょうか。もしかしたら答えはないかもしれませんが(笑)
松井先生:
eスポーツの「身体性」の捉え方については二大派閥があります。まず「画面の中のアバターを動かすという意味の身体性」です。フィジカルスポーツのように大筋運動とか全身のダイナミックな運動がないため、「身体性はない」というふうに捉えられる事が多いです。
もう一つは「身体の内部まで含めた身体性」です。つまり、身体の中身の方でフィジカルスポーツと同じような反応が起きているっていうところまでを身体性と捉える派閥です。これは外見ではなかなか分からない部分ではあります。
私はどちらかというと専門が生化学とか生理学なんで、後者の「見えない部分に関してもその反応は身体である」と捉えている側です。つまり、外見だけでは見えない部分までも含めて、「eスポーツの身体性がどこまであるのか」を検証し、「eスポーツはスポーツなのか」を考えていきましょうというスタンスです。
インタビュアー:
見えない部分まで検証するというのは面白いですね。でもその「見えない部分」ってどうやって確認しているんですか?
松井先生:
そうですね、じゃあ今まで私たちがどんなことをやっていたかについて説明したいと思います。その前に、私の実験に関わるクイズを一つ出します!!体の見えない部分の象徴的なものって何だと思いますか?ヒントは「体と心の象徴」です。
インタビュアー:
、、、、、あ!心臓とかですか?
松井先生:
そう!心臓です!心臓というのは漢字の通り、まさに「心の臓器」です。昔の人たちがそこに心があるんじゃないかと考えて、この名前があてがわれています。その通りで、実際に体と心をつなぐ臓器ですよね。例えば、緊張するとドキドキする。いわゆる身体性の象徴がそこにあるんじゃないかなと私は思うんです。
インタビュアー:
なるほど!松井先生が検証している身体性の「見えない部分」っていうのは「心臓」だったんですね。じゃあ実際の実験では「心臓」のどういった部分を測って身体性を検証しているんですか?
松井先生:
計測している重要な指標の一つは心拍数です。eスポーツで実際に検証している例を出すと、実は一人でプレイするビデオゲームでは心拍数はほとんど動かないんです。ずっと座ってるのとほとんど同じで、全く上がり下がりしません。一方で、対面で二人で対戦してもらうと心拍数が上がったり下がったりし始めるんです!この差が、「eスポーツには身体性がある」と言える証拠の一つではないかというところですね。

インタビュアー:
フィジカルスポーツも一人では特に何も思わないですが、対戦になると途端にドキドキし始めますもんね。確かにeスポーツでも共通ですね!
eスポーツと運動のつながり
インタビュアー:
身体の内部での反応がフィジカルスポーツと同じだったということは面白い発見です。スポーツとeスポーツが見えない部分では一致していることはわかったのですが、スポーツのような外見でわかる実際の運動はeスポーツとなにも関係がないんですか?
松井先生:
もちろん関係ありますよ!では「運動の効果」という視点から、eスポーツのスポーツ科学的な取り組みを紹介したいと思います。ただ、それを説明する前に、まず運動の効果には「一過性の運動の効果」と「長期的な運動の効果」という二つの視点があることを確認させてください。
「一過性の運動の効果」はウォーミングアップ的なもので、今行った運動がその後すぐのプレーを上手くする効果があるのかっていう考え方です。対して「長期的な運動の効果」はそのままの意味なんですけど、日々運動を繰り返すことで、繰り返してなかった頃と比べてプレーが上達するといった効果です。一過性は英語で「アキュートエクササイズ」って表すんですが、一回の刺激に対する「反応」があるかっていうところ、逆に後者は「クロニックエクササイズ」といって、長期的な運動によって「適応」が起こるかに着目しています。
インタビュアー:
運動の効果は2パターンあるんですね。もっと具体的に教えていただきたいです!!
松井先生:
では、「運動・栄養・休養」の三原則から、運動の効果が生み出される流れを説明していきたいと思います。例えば、一回運動をすると、筋肉は疲れとか筋損傷とかですり減ってしまいます。ただ、その後に良い栄養とか休養をとると元のレベルまで、さらにはそれよりも高いレベルにまで回復するんです。これを「超回復」といいます。これは、強い身体を作るための基本原則です。でも、この超回復は一回だけだとすぐ元に戻っちゃうんです。つまり、向上していくためには積み重ねが重要だっていうことです。
インタビュアー:
僕もたまに「運動して、栄養あるもの食べて、よく寝て」っていうことを意識する事はあるんですが、何回三日坊主でやめたことか(笑)やっぱり継続が重要なんですね。逆に「運動せずに、体に悪いものばかり食べて、夜更かしして」って生活だとどうなっちゃうんですか。
松井先生:
質の悪い運動・栄養・休養を積み重ねちゃうと、やっぱり逆効果になっちゃいますね。そのためにも最適な組み合わせっていうのを考えて、心身ともに、さらに社会的にも元気な、老若男女の「ハイパフォーマンス」をどうやって引き出すかっていうところがスポーツ界の究極的な目的としてあります。今までの話をまとめた画像がこれです。

インタビュアー:
この画像、とてもわかりやすいですね。でもここにeスポーツはどのように絡んでくるんでしょうか?
松井先生:
ではこの画像を参考にeスポーツとの関わりについて説明していきますね。この視点からeスポーツをスポーツ科学的に考えていくと、二つの方向性が見えてきます。一つ目は、超回復の繰り返しによって引き出された「ハイパフォーマンス」という部分を、「eスポーツのハイパフォーマンス」として当てはめてみるという考え方です。これは「eスポーツのハイパフォーマンス」を引き出すための運動・栄養・休養には、どのようなものが有効なのかということを考えることに繋がります。

松井先生:
もう一つが「ハイパフォーマンス」ではなく「適度な身体運動」部分にeスポーツを当てはめてみるという考え方です。これは運動やスポーツの代わりとしてeスポーツがどう置き換わることができるのかを考えることに繋がります。

インタビュアー
運動してパフォーマンスが高まったり、eスポーツが身体運動の代わりになるということは、そこに身体性があるとも言えますね。
松井先生
そうなんです。
第二回その②へ続く
【お知らせ】
筑波大学OWLSはnoteの他にYouTubeとX(旧Twitter)をやっています。
様々な情報を発信していく予定ですので、ぜひフォローしてください!!
YouTube
X(旧Twitter)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
