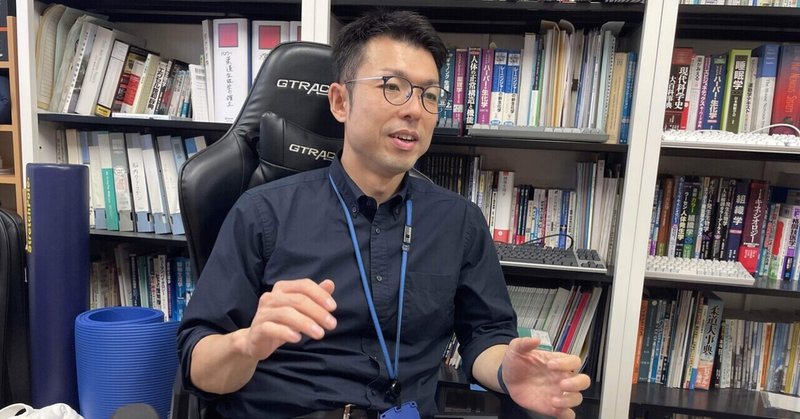
『インタビュー:eスポーツを科学する』 ~第一回~ その①:eスポーツ科学研究の第一人者、松井崇先生とは
こんにちは、筑波大学OWLSです!
初めましての方もいらっしゃると思います。
OWLSがどのような活動をしているかは、こちらの記事をご覧ください。
今回、筑波大学が取り組んでいるeスポーツプロジェクトについて、そして上記の記事には書ききれなかった、eスポーツ研究について、もっと深掘したいと思い、松井 崇先生にインタビューを行いました。
松井 崇先生についての詳細は以下のページをご覧ください。
インタビューは全六回の予定です。そして第一回のテーマは『eスポーツと学問』!!!
第1回のインタビューがとても白熱し、その内容を余すことなくお伝えしたいため、その①〜③のように分割して投稿させていただきます。
ぜひ最後までご覧ください。
~第一回~
eスポーツと学問
その① eスポーツ科学研究の第一人者、松井崇先生とは

筑波大学 体育系 助教(運動生化学・スポーツ神経生物学)/ 筑波大学 スポーツイノベーション開発研究センター スポーツIT分野長 / 筑波大学 健幸ライフスタイル開発研究センター 副センター長 / 全日本柔道連盟 科学研究部 基礎研究部門長
インタビュアー (motti & eneman):
自己紹介をお願いします
松井先生:
39歳です。
インタビュアー:
年齢から(笑)
松井先生:
柔道を5歳からやっていて、元々はもう柔道一直線というか、大学もスポーツ推薦に入ったので、振り返るとまさか自分がeスポーツの研究をやるとはという感じですけど、、、

その① 表彰式
なんで柔道一直線なのに今研究者をしているのかというところに関しては、大体柔道の試合で負ける時というのは、疲れて、今まで耐えたり、対応したりできていた相手の技に対して対応ができなくなる。それで投げられたりとか、抑え込まれたりして負けてしまうということが多々あります。その仕組みをまず理解して、どうすれば克服できるのかということにまず興味を持ったところから、今の私の専門である運動生理学とか運動生化学という領域ですけど、それを志したという感じですね。
インタビュアー:
はい

その② 疲労して投げられる
松井先生:
それで学生時代から、運動による脳の疲労の仕組みとその予防策に関して動物実験もやりながら、研究してきました。
そのなかで、脳内の糖質エネルギー貯蔵であるグリコーゲンというのが、長時間運動によって減ってしまう。それによって脳内の乳酸がとても増えてくる。それが実は脳を守りながら、運動を止めていくという仕組みがあるんだということを明らかにしました。
それはどういうことかというと、運動による疲労をどう克服するかっていうことが研究の動機だったと申しましたけど、結局、疲労って何のためにあるかって言ったら、運動のしすぎを防ぐため。疲れてちょうどいいところでやめさせるためということなんですよね。
運動しすぎちゃうと、下手すると死んじゃうんですよ。
インタビュアー:
ん?
松井先生:
疲労を感じず、運動を止めずにずっと続ければ、死ぬまで運動できちゃうということです。
インタビュアー:
あー、なるほど。
松井先生:
例えば、ドーピングをして、自転車のレース中に選手が亡くなったという事例があるのですけど、あれは疲労の仕組みを壊して、運動を継続しようとしているという風に理解できるということで。
インタビュアー:
へえ
松井先生:
では、「何が私たちの体を過活動から守ってくれてるのか?」っていうところが、脳のグリコーゲン、そして、そこから生まれてくる乳酸というのが実はエネルギーとして脳の活動を支えながら、ブレーキにもなっているみたいなことを明らかにしてきました。
インタビュアー:
なるほど
松井先生:
もうあれだよ、俺話長いから、研究の話だとガンガン進んじゃうからね(笑)
インタビュアー:
全然OKですよ!!どんどん話してほしいです(笑)
松井先生:
で、あとはそれをずっと、今も昔もやってるという感じですが、元々柔道だということを言いましたけれども、柔道出身でこういう生理学・生化学をやってる人は結構少なくて。
全日本柔道連盟の科学研究部ってのがあって、ハイパフォーマンスを支援するのはもちろんですが、柔道というのは競技であるだけではなくて「人間教育の道である」ということで、それがどういうことなのか。絆形成から共感性を育む効果によってそれが具現化されるんじゃないかとか。そういうことを柔道を題材にやってきたということです。
それが、2020年2月頃から、コロナでできなくなったんですよ。
その前年の2019年、茨城県で開催された国体で、eスポーツが実施されたんですね。

「いよいよスポーツ科学でもeスポーツを本気で対象にしないとな」っていうなことを考えているところに、上記のようなコロナ対策も相まって、本格的にeスポーツ科学を進めることになりました。その際には、私の今までの研究の、ちょっと長々と説明した通り、キーワードは「疲労」と「絆」なので。
インタビュアー:
うんうん
松井先生:
それらをeスポーツに当てはめるとどうなるのかっていうことを進めてますっていうのが、自己紹介でしょうか?
研究者としての自己紹介としては、こんな感じでしょうかね。
インタビュアー:
ちょっと気になったところがあるんですけど、元々柔道とか疲労とかを専攻されてたたじゃないすか。でもeスポーツってちょっと離れてるよなって。
まあ完全に離れてるってわけじゃないと思いますけど(笑)
松井先生:
離れてるよね(笑)
インタビュアー:
何か意識して見てないと、気付けないというか。ではeスポーツっていう存在に何か気づいたきっかけみたいなのってあったんですか。
松井先生:
そうですね、私が元々ゲーセン世代なんですね。僕の実家が東京の中野なんですよ。中野ブロードウェイとか近くて。
結構今、コアな文化が秋葉原から流れてきてっていうようなところなんだけど、知ってる?中野ブロードウェイとか?
インタビュアー:
いや、ちょっとわかんない、、、、中野サンプラザしか、、
松井先生:
中野サンプラザの隣なんだよ。ちょうどこの前中野サンプラザ閉館しちゃったけど。で、中野サンプラザとか中野ブロードウェイっていうのは俺の少年時代の遊び場で。そこは1階にいわゆる子供向けのゲーセンがあって、2階にガチ勢がいるゲーセンがあったの(笑)
インタビュアー:
へー(笑)

参考:https://nakano-broadway.com/aboutus/
松井先生:
俺は幼少期から柔道やってたけど、柔道だけやってるわけじゃないし、ゲームももちろんやってて。俺ファミコン世代だからね。幼稚園の頃にファミコン、小学校の1〜2年生の頃にスーパーファミコンを買ってもらって。スーファミで初めて買ってもらったソフトは『ストリートファイター2』。それで、ゲーセンでガチでやるっていう文化があるんだっていうことを中野という環境で知って。
最初は入門編でさ。1階でやってて。でも、「上になんかガチの人いるな」って。なんか怖いけど行ってみたいとかっていうのもあって、たまに行ってボコボコにされるみたいな話だけど(笑)
その1階から2階に行くときの感覚っていうのが、いわゆる柔道でいう出稽古?つまり、いつも練習してる道場じゃなくて、敵チームのところに行ったりするんだけど、その感覚に凄く似ているなと。
インタビュアー:
ほう。
松井先生:
それで、国体とかでeスポーツやっているのを見ながら、自分のeスポーツ経験みたいなものを振り返って行くと、そういうふうな記憶に思い当たって。
ただ、そのときにゲーム一緒にやってたような仲間って、意外と部活の仲間と似たようなノリだったり感覚がある。まあ、今めちゃくちゃ交流があるわけじゃないけど、例えばSNSでその人たちの活躍とか近況を見ると、何か刺激を受けて頑張ろうと思えるような、いわゆる「絆」みたいな。部活の仲間ってそういうところがあるじゃん?
インタビュアー:
はい。
松井先生:
それが、意外と同じような感覚があるなっていうのもあって、「eスポーツで絆形成」できるんじゃないかな、みたいなことをまず考えたっていうとこですかね。

インタビュアー:
なるほど。
松井先生:
まあ、なぜかと言われるとそんな感じですかね。
元々結構好きで、かつ、研究対象にしようとしたときに、意外と「絆を形成する効果」みたいなのは柔道と、、、、
インタビュアー:
同じところがあるんじゃないかと。
松井先生:
そうです。ありそうだなと。とういうのも、eスポーツの定義というのは1人でゲームをすることではないので。
そのゲームを通じて対戦することがeスポーツであるという定義がされます。実は、ゲームの効果ってのは結構研究されてるんですよ。20年ぐらい前から。
インタビュアー:
ほう
松井先生:
ですけど、対戦によって生じる「上乗せ効果」というのは、全然研究されていないところがあって。実はそれってスポーツ科学でも同じで、今までのスポーツ科学は、1人でやる運動の効果を明らかにしてきました。英語で言うと、いわゆるエクササイズだね。1人で自転車を漕いだり、ジムにあるようにトレッドミルの上で走ったりする。ああいうものの効果で、例えば痩せるとか認知機能が高まるとか、個人の心身への有益な効果があることがわかってるわけだよね。
だけど、実際スポーツって、2人以上で競い合い、ルールに則って楽しむことであるという定義があって。運動以外の要素の効果があるんじゃないかと。そう考えたときに、運動要素を含むフィジカルスポーツをすると、運動以外のスポーツの効果が見えにくくなる。つまり、運動の効果なのか、対戦や協力の効果なのかがわからない。
インタビュアー:
そっか、そこは別で捉える必要があるということなんですね
松井先生:
生命科学系で言うとさ、ノックアウトマウス(※1)みたいな感じで、スポーツから運動要素を取り除くと、その機能を可視化したり、それ以外の機能をあぶり出して検証したりできるじゃん。
※1
ノックアウトマウス(Knock-out mouse)とは遺伝子操作により1つ以上の遺伝子を欠損(無効化)させたマウスのことです。遺伝子の塩基配列は決定しているものの、その遺伝子産物の機能が不明な場合にその機能を推定するための重要なモデル動物です
https://www.wdb.com/kenq/dictionary/knockout-mouse
それが、スポーツ科学でいうところのeスポーツの存在意義のひとつなんだっていうことがあって。
科学者目線で説明するそんな感じかな。
インタビュアー:
なるほど。
松井先生:
回答になってるかわかりませんが(笑)
インタビュアー:
大丈夫です!!!
第一回 その②はこちら
【お知らせ】
筑波大学OWLSはnoteの他にYouTubeとX(旧Twitter)をやっています。
様々な情報を発信していく予定ですので、ぜひフォローしてください!!
YouTube
X(旧Twitter)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
