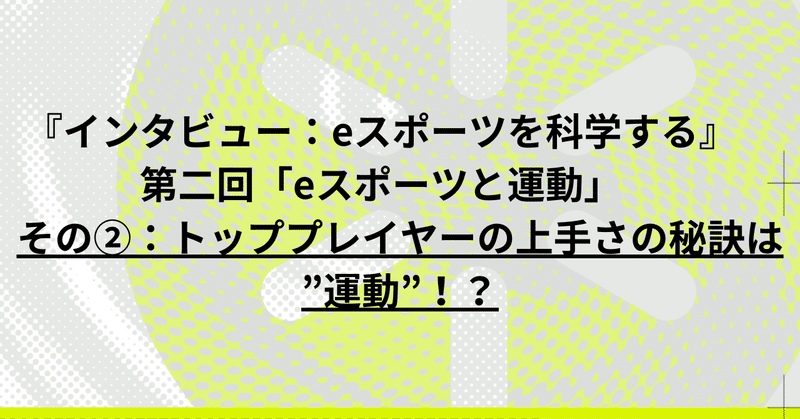
『インタビュー:eスポーツを科学する』 ~第二回~ その②:トッププレイヤーの上手さの秘訣は”運動”!?
こんにちは、筑波大学OWLSです!
初めましての方もいらっしゃると思います。
OWLSがどのような活動をしているかは、こちらの記事をご覧ください。
また、今回インタビューを受けていただいた松井崇先生についての詳細は以下のページをご覧ください。
今回は、第二回『eスポーツと運動』の”その②”です。その①をまだご覧になっていない方は、こちらからご参照ください。
第二回「eスポーツと運動」
その② トッププレイヤーの上手さの秘訣は”運動”!?
eスポーツと運動の研究、トッププレイヤーの話
インタビュアー:
実際のeスポーツ×運動の研究ってどんなものがあるんでしょうか?
松井先生:
これはアメリカスポーツ医学会の雑誌に掲載されたものなのですが、一回の運動をするとその後20分間の『LOL』プレイ中にパフォーマンスが上がるっていう研究があります。この運動っていうのは、「高強度インターバル運動」っていうもので、時間効率がよくて脳も心肺機能も筋肉も活性化できるっていう流行りの運動の仕方です。だからOWLSのみんなには活動前にちょっと息が上がるような運動をしてもらってるんですけどね(笑)
インタビュアー:
去年からVALORANTの練習を行う前にとてもきつい運動をさせられていた理由はこれだったんですね(動画参照)。
松井先生:
OWLSのコンセプトに「強くなる」と「健康になる」ってあったと思いますが、プレー前にやってもらった運動はこの両方を満たすものなんです。もしこのwin-winさが広まれば、長期的にはeスポーツに連想されがちな「不健康さ」っていうイメージが払拭される可能性だってあります。というのも、やっぱりeスポーツプレイヤーってみんなゲームが上手くなりたいので、ずっとゲーム”のみ”に取り組みますよね。だからその人たちに「不健康だから運動しましょう」って言ってもやる気が出ない。だけど、「ゲームが上手くなるトレーニングの一環として運動を取り入れないか」っていうと響くでしょう。ゲームのために運動する。そうするとハイパフォーマンスが引き出されて、それが結果的に不健康さの払拭につながるんです。
インタビュアー:
じゃあ実際ゲームが上手い人って健康なんですか?
松井先生:
FPSのトッププレイヤーの身体活動量とか運動の状況を調べた研究もあって、ランクのトップ10%の人たちは、それ以下の人に比べて日々の身体活動量が多い事がわかっています。他にはその人たちの健康的な感覚も調べています。ただ実際の健康診断とかはできてないので、アンケートで健康状態を確認したんですけど、そうするとやっぱり運動してる人のほうが健康であるという感覚が高いことがわかったんです。
インタビュアー:
感覚って、自分は健康だと思う、みたいな感じですか?
松井先生:
そうです。あとは「こういう症状ありますか?」みたいな質問には大体「ありません」って答えています。その他にも、肥満傾向(BMI)が低いというようなことも知られています。こういった調査はもっと世の中に啓発して行く必要があるんですけど、実際の因果関係がどっちなのかっていうのは横断的研究だから分からないんです。つまり、上手くなったから身体活動量が上がったのか、元々身体活動量が多いからが上手くなったのかわからないということです。
インタビュアー:
ただ相関はあるってことですね。
相関関係と因果関係の違いとは
相関関係とは、「二つの値の間に関連性がある関係」のことです。つまり、一つの値が変化すると、もう一つの値も変化することを指します。
因果関係とは、「原因とそれによって生じる結果との関係」のことで、一つの値を原因として、もう一つの値である結果が変化することを指します。
「ライターの所持」と「肺がんに罹るリスク」、「タバコの喫煙」と「肺がんに罹るリスク」は、両方とも一つの値が変化すると、もう一つの値が変化します。つまり両方とも相関関係があります。しかし前者は、「ライターの所持」が「肺がんに罹る」原因とは考えられないので、後者のように因果関係があるとは言えません。つまり、因果関係がある場合には相関関係もあるが、相関関係がある場合は必ずしも因果関係があるわけではない、ということになります。
松井先生:
そう、相関がある。そして健康面にも相関があるっていうことは既に知られています。実はこういう傾向というのはバーチャルフットボールのプレイヤーたちの方がより顕著であるっていう事も知られています。バーチャルフットボール自体はフィジカルスポーツを題材にしてますし、リアルのサッカーをやってた人たちがeスポーツプレイヤーに移行するってことも結構あるタイトルですよね。そういうリアルとの行き来があるゲームの方がその傾向が顕著なんです。


インタビュアー:
そうなんですね。逆にeスポーツだけやってきた人が、そのタイトルの題材となった現実のスポーツに参加してインスピレーションを受けるとかもありそうですね
松井先生:
そういう例はあります。例えば「ストリートファイター」で有名なときど選手っていますよね。東京大学を出て大学院まで行って、世界チャンピオンにもなってるすごい人ですけど(笑)
ときど選手、実は「ストリートファイター」だからってことで空手道場にも通っているらしいんですよ。リアルの空手道場で打撃のインスピレーションを得た上で、それをサイバー空間に表現してるということですね。
インタビュアー:
本当にすごいですね(笑)
松井先生:
彼は体も鍛えているんです。これはときど選手がスポーツ雑誌の「Number」で、筑波大学OBでラグビー元日本代表の福岡選手と対談した回に書いてあるんですが、もともと「みっともない身体で人前に立つのが嫌」と思って鍛え始めたそうなんです。でも、筋肉がつくと集中力が持続できるようになったことに気がついて、それ以来ずっと続けてるそうです。
また、「大舞台でどうメンタルを保つか」、「試合前のルーティンはあるのか」といった話になった際に、ときど選手が「試合前には舞台袖でダッシュをして、一度心拍数を上げてから試合に入るようにしてます」っていう答えをしていたんです。界隈では「ときどダッシュ」っていう名前がついてるくらい有名な行動らしいんですけど、ときど選手のようなトップ選手は一回の運動の効果とそれを繰り返すことの利益を経験的に自覚して、現場で駆使しながら戦っているんじゃないかっていうようなことが言えるんじゃないかと思っています。

インタビュアー:
そういえば昔の「情熱大陸」で、「ストリートファイター」のウメハラ選手がジムに通うシーンがあったことを思い出しました。
松井先生:
そうですね。だからこういったトッププレイヤーに「ゲームだけをするのは実は逆効果で、運動やリアルなスポーツを取り入れることがゲーム自体にもいい効果を与える」という運動観やスポーツ観を多くのeスポーツプレイヤーの人たちにも広げてもらいたいんです。それがゲーム界隈の不健康なイメージを払拭して、勉強とかその他の活動も含めてより充実した健全な生活を送ることを可能にするんじゃないかと思っています。
OWLSの実験結果について
インタビュアー:
実際にOWLSでは毎回の練習前に運動を取り入れてますが、昨年度の結果とかは出たのでしょうか?

松井先生:
実は結果はまだ未公表なので、今回は予備的なところをお伝えします。昨年度はOWLSの活動が始まったときに、エイムや脳活動、体力とかを測らせてもらいましたね。そして比較するために「運動するグループ」と「運動しないグループ」にわかれてもらったと思います。その二群で3ヶ月後のエイムのパフォーマンスを比較したんですが、実は”差”が出たんですよ!!今までの話の流れを踏まえると、もうどっちがどっちというのは想像できますよね(笑)
インタビュアー:
もちろん、運動をした方のグループに良い結果がでたんですよね(笑)
松井先生:
そうです。運動をしたほうが的を早く撃ち終わるという結果が出ました。しかし「最大酸素摂取量」という酸素を取り込む能力を表したスタミナの指標はあまり変わっていませんでした。つまり運動していたからといって、体力がめちゃくちゃ上がってるのかというと、実はそんなに変わっていなかったということです。ただ、バイクを漕ぎ続けるテストでは漕げる最大の重さはちょっとだけ高かったんです。なので、劇的にスタミナに効果が出ない運動でも、脳を十分に活性化して「eスポーツのパフォーマンス」を発揮しやすいような状況をつくりだせるのだろうということや、eスポーツのトレーニング効果を促進するような運動というものがあるんだろうということがOWLSの皆さんのご協力によって分かってきています。今はちゃんと公表できるように上手くまとめようと思っているところです!
インタビュアー:
面白い結果が出てよかったです(笑)今年度も7月頃にバイクを死ぬほど漕いだ記憶があるんですが、何を調べようとしているんですか?

松井先生:
今年度に関しては、まだデータを明確にお示しできるような状況ではないんですが、何をやりたいと思ってるかは伝えたいと思います。まずは、「体力レベルが高い方がeスポーツが上手いのか、もしくは上手くなりやすいのか」というところを調べようと思っています。
インタビュアー:
それは去年とどう違うんですか?
松井先生:
去年のOWLSの結果では、運動はしたけど、スタミナの指標から、体力はとても上昇したとは言えなかった。ただ充分脳には良い効果が出てたし、eスポーツのパフォーマンス能力も上昇していたことがわかったというのは先程も言いましたね。一方で、昨年度の結果とは逆に「スタミナに関係する体力」が高い方が認知機能が高かったり、子供の場合は国語とか数学の成績と関連するってことも言われています。
インタビュアー:
じゃあ「運動の効果」というよりは「個人の運動能力」に焦点を当てて調べているのが今年なんですね。子供の勉強にも関わっているのは驚きです。子供を対象とした実験で検証した「体力」もOWLSで測ったものと同じなんですか?

松井先生:
ここでいう「スタミナに関係する体力」はいわゆる「有酸素性の体力」です。さっき言ったVO2max(最大酸素摂取量)や、あとはVT(換気性作業閾値)という「どの辺がピークで運動がキツくなり始めるか」っていう指標も含んでいます。その値が高い方が「体力がある」っていうことだし、「なかなかきつくなりにくい」という意味でもあります。
インタビュアー:
なるほど。文武両道じゃないですけど、勉強とスポーツも関係があるんですね。
松井先生:
少し違いますね。いわゆる「スポーツ競技力」という意味ではなく、単に体力が高い方が脳の能力も高いみたいなことです。だからeスポーツも体力が高い人のほうが脳の能力も高いはずだし、上手くなりやすいんじゃないかとか、もともと上手かったりするんじゃないかとか、そういったことが考えられるわけです。
インタビュアー:
それでいうと、OWLSで学生コーチをやっているfumisukeは、コーチなだけあってチームで1番VALORANTがうまいんです。なんですけど、実は彼は高校まで熱心に野球をやっていたらしいんです。やっぱり運動できる人は脳の能力が高いんですかね?

松井先生:
なるほど。データを見ると、彼はOWLSの中で3つ実施した認知課題の正答率が一位ですね。
認知課題・・・認知機能を測定する課題のこと。課題に対する正答率や反応時間を測定し、分析を行う。
インタビュアー:
そうなんですね!確かに彼は普段からエイム力がずば抜けてますね、、。
松井先生:
彼は3つの課題すべての正答率がとても高いです。つまり判断力の正確性がもともととても高いのだろうと思われます。あとはtadano(カナタ)とかRaiseとか、その辺りが好成績ですね。体力やエイムとかの関係についてはまだ分析中ですのでまたいつかお話できればと思います。
インタビュアー:
じゃあこのテストの点数が高い人をレギュラーに育て上げれば、最強のチームになりますね。
松井先生:
ただ、スポーツ倫理的に選手選考としてフィードバックするといった使い方はあまりしない方が良いと思います。どう公開するかというのは、結構難しい問題です。
インタビュアー:
「レギュラーは無理です。なぜなら生まれつきのものなので」っていうのは理不尽ですもんね。努力で鍛えることもできたりするでしょうし、今後どのようにこのデータが用いられるか注目ですね。
ゲームタイトルによって実験の値が違うことについて
インタビュアー:
個人の運動能力だったり認知能力がゲームに直結することがわかったんですが、もしかして「この能力が高いから、このゲームタイトルに向いている」ってこともわかったりするんですか?例えばVALORANTがうまいfumisukeは判断の正確性が高かったですよね。
松井先生:
実はその通りで、ゲームによって必要な能力って違うんです。それがどういうことかっていうと、例えばVALORANTは予想もできないところからいきなり敵が出てくることは日常茶飯事ですよね。でも、バーチャルフットボールってそんなことないじゃないですか。
インタビュアー:
画面に見えていることが全てですもんね。
松井先生:
ゲーム性も、常に画面上のボールと味方と相手を見ながら、方向選択を連続して入力し続けるものですよね。
インタビュアー:
僕もeFootballはよくやってますけど、自分と相手の選手の動きを把握しないといけないので結構見るところが多くて忙しいイメージがあります。ということは空間視野とかそういった能力が重要になるんですね。
松井先生:
そうです。逆に、FPSは予想できないことにもなるべく速く反応する事が必要だということです。こういった課題の特性がそれぞれそのゲームにやっぱり出てきますよね。
インタビュアー:
じゃあfumisukeってやっぱりVALORANT向きなんですか?
松井先生:
そうだと思います。ただVALORANTにとってどの能力が正解なのかはまだよく分かっていないんです。実際、fumisuke選手は正確性がトップクラスに高いですが、反応時間はそんなに早くないというのもありますし、今後も検証していきたいと思っています。そういえば、現時点で1番面白い結果が出ているのは「ストリートファイター」なんです!
インタビュアー:
本当ですか!!OWLS内でも流行っているのでとても気になりますね!
松井先生:
上手い人にストリートファイターをやらせると、さっきの3つの認知課題の一つである「ストループ(色について答える認知課題)」、つまり言語性の部分の出来が良いんです。
ストループ課題
「文字の色ではなく、意味を答えてください」というように、一方の情報(刺激)を気にせず、片方の情報(刺激)にのみ、選択的に注意を向けさせる課題。

写真を見ると「あか」と書いてあるのに文字が緑色のものがある。
松井先生:
僕なりの考察としては、コマンド入力が関係しているんじゃないかと思っています。格闘ゲームって他のゲームとは違って必殺技とかで↑↓ABとか入力したり、コンボを繋いでいますよね。コマンド入力を組み合わせていくというところはとても言語的だと言えるんじゃないでしょうか。
インタビュアー:
これを見た人の多くがプレイヤーが言語性の部分を鍛え始めそうですね(笑)じゃあ別ジャンルのゲームではこの能力って発揮されるんでしょうか。
松井先生:
言語性の課題に影響が出てくるタイトルは今のところストリートファイターだけです。もちろん矢印の向きを答える認知課題とも関係はあったんですけどね。

インタビュアー:
課題の正確率も反応速度と関係しているんですか?
松井先生:
それももちろん関係していて、そこにも上手い人とそうでない人の違いが出ているんです。ストリートファイターのカジュアルプレイヤーたちは、疲れてくると正確性を落とさないために反応時間を落とすっていう方向性になるんです。一方上手い人たちは逆に、反応時間を維持するために正確性を犠牲にするっていう傾向があるんです。
インタビュアー:
それって上手い人は無意識に行っているんですか?
松井先生:
課題を行ってもらったときに特に何も言われてないので無意識だと思います。でも終わった後のインタビューで聞いてみると「プレイ時間が長くなっている時は、何か反応したほうがゲームが成り立ちやすいってこともあって、もしかしたらそういうトレーニングみたいになってるかもしれないですね。」みたいなことを言っていましたね。特に格闘技とかって「動かないより動く」みたいに反射的なことが重要なので、そういった部分との関連もあるのかもしれないですね。
インタビュアー:
ここでも、現実のスポーツと関わってくる可能性が考えられるんですね。今日一日でeスポーツと運動の関わりについて詳しくなりました。第二回を終了します。ありがとうございました。
松井先生:
ありがとうございました。
第3回「eスポーツと栄養」に続く…
【お知らせ】
筑波大学OWLSはnoteの他にYouTubeとX(旧Twitter)をやっています。
様々な情報を発信していく予定ですので、ぜひフォローしてください!!
YouTube
X(旧Twitter)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
