
吹奏楽アカデミー専攻トロンボーン科 with トランペット科 学外演奏会レポート
2月12日(月祝)、めぐろパーシモンホール 小ホールにて、東京音楽大学吹奏楽アカデミー専攻トロンボーン科 with トランペット科 学外演奏会を開催致しました。ご来場くださいました皆様、ありがとうございました。

東京音楽大学に吹奏楽アカデミー専攻が開設してまだ5年。器楽科のような長い歴史もなければ、各パートの人数も極めて少ない状態で、そんな中、トロンボーンパートはすでに今回が3回目(3年目)の学外公演!素晴らしいです。講師の渡邉先生のお力があってこそ。
今回の演奏会は開催までいろいろあって、急遽トランペット科を誘ってもらう形で実現しました。さらに、僕がお手伝いすることになったのはもっと後になってから。

ペガスス
今回のコンサートでの注目作品は、吹奏楽アカデミー専攻特任教授で作曲家の星出尚志先生の作品「ペガスス(トロンボーン四重奏)」の世界初演。この演奏会のために作曲をお願いしていたこの作品、ニューサウンズ・イン・ブラスなどのポピュラー作品の編曲も数多く手がける星出先生ならではの美しいメロディとリズミカルな場面の織りなす素敵な作品でした。
今後どのように楽譜が扱われるかわかりませんが、再演はもちろんのこと、様々なところで演奏されてほしいです。
ちなみに星出先生いわく「ペガサス」は架空の空飛ぶ馬、天馬のことで、「ペガスス」になると星座になるのだそうです。なのでこの作品は後者がテーマになっているとのこと。ということは聖闘士星矢の必殺技は「ペガスス流星拳」になるのですね。

他にもトランペットの学生による4重奏の演奏もありまして、後半は合同ステージ。
選曲が難しい
トランペットとトロンボーンの編成で書かれた楽譜というのはとても少なく、ガブリエリというJ.S.バッハより古い作曲家の作品(の編曲)とか、そういうのがほとんどです。そうした作品ばかりでプログラムを組むのは今回のコンサートでは少し避けたく、学生も選曲に悩んでいたので、僕がだいぶ前に書いた金管8重奏や10重奏の楽譜を使って、ホルンパートをフリューゲルホルンが担当したり、テューバパートをバストロンボーンに演奏してもらったりと調整して演奏してもらいました。
アンコールで演奏した「ロンドンデリーの歌」や、渡邉先生が素晴らしいソロを演奏してくださったプッチーニ作曲「トゥーランドット」より「誰も寝てはならぬ」も僕が以前書いた楽譜でした。ありがとうございました。

自主公演をしなければ体験できないこと
吹奏楽アカデミー専攻は各パートの人数も器楽科に比べたらはるかに少なく、技術面でもまだまだ頑張らなければならないところもありますが、ひとつの演奏会を完成させることがいかに大変なことか、それを学生の時点で体験できただけでも貴重なものだったと思います。こうした経験があると、ひとつひとつの演奏会にどれだけの人が関わり、そして随分前から準備をされているのかを知ることができ、スタッフさんに感謝の気持ちを持つことができます。これ本当に大切なこと。
と、いつものブログだったらここで終わらせられたのですが、今回はそうもいきません。
MC
最大の反省点はMC。ご来場くださいました皆様、本当に申し訳ありませんでした。あと、ステージ内での演奏以外の進行、ステージマナー、星出先生をステージ上にお呼びするときの流れなど、こうしたものは、やはりどれだけ生のコンサートに足を運んでいるかが重要です。プロの奏者や指揮者の立ち振る舞いや動きなど、これは音源ではまったくわかりませんし、映像ではカットされるために開演から終演までを一連の流れとして見ることがほとんどできません。見たことなければどう動けばいいのかわからないのは当然。それが露呈していました。
そして日本語、特に丁寧語の使い方なども日頃から意識していなければ絶対出てこないわけで、その辺りは大反省点です。
演奏会に限らず司会者さんがどのような喋り方をするのか、立ち姿勢、表情、原稿を読みつつも客席に目を向けるタイミングや時間なども、それを実際に意識的に見る経験がなければわからないと思います。
そうして、それらを練習しなければできるはずもありません。演奏会をするというのは、演奏だけがしっかりできれば良いわけではないのです。

重要なのは客観的視点
コンサートを企画するにあたって、どのような雰囲気、コンセプトで会場を作るかを最初に決めておく必要があります。格式高い、いわゆるクラシック音楽のコンサートにするのか、リラックスして楽しめるコンサートにするか
、それによって選曲(曲順)もMCも(言葉遣いも)変わります。衣装や会場設営、フライヤーやプログラムなども変わるかもしれません。
そのために最も重要なのは客観的視点です。お客様の立場になってみること、スタッフの立場になってみること、そうした演奏以外の視点で物事を考えられるようになれば、もう少し演奏会として形になったのではないか、と思います。
とは言え、先ほども書いたように演奏以外でも学ぶことの多い学外公演を実行できたからこそ得られた反省点ですから、今後に期待したいですし、僕もそうした側面での学生への配慮をしていきたいと思います。
今回僕は急遽参加することになったので大してお手伝いできませんでしたが、学生からステージでお花をいただきました。ありがとうございました。
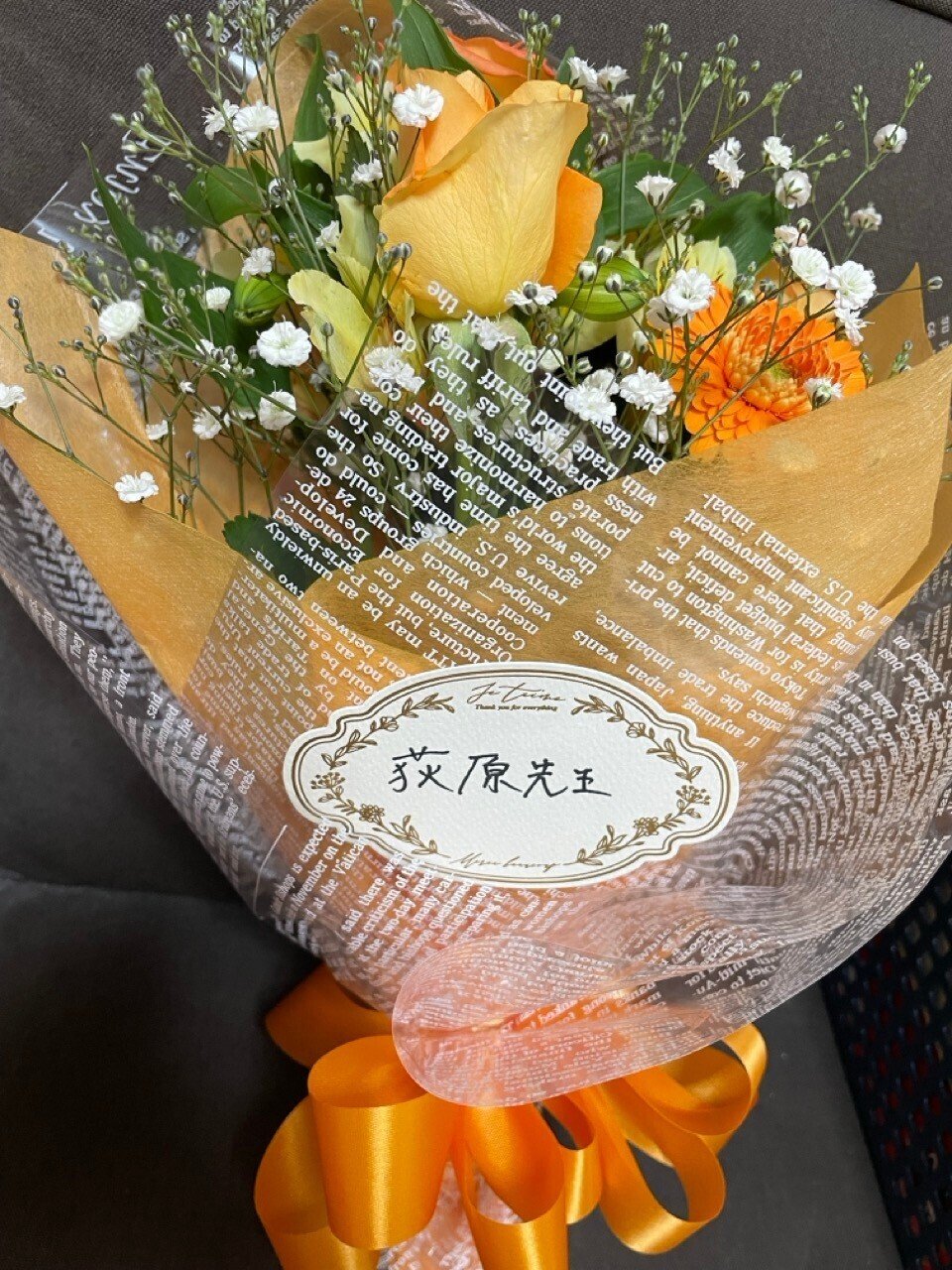
ステージマネージャーを務めてくれた吹奏楽アカデミーのフルートの学生のご実家がお花屋さんだそうで、とっても可愛らしい花束をいただきました。オレンジ大好きなので嬉しいです。ありがとう。一週間経ちましたがまだかなり元気に咲いてます。
しかし…またMCの話になっちゃいますが「お花をお渡ししたいと思います。先生方、『前へ』」には驚きました。思わず敬礼しそうになりました(笑)
丁寧語、難しいですね。
荻原明(おぎわらあきら)
荻原明(おぎわらあきら)です。記事をご覧いただきありがとうございます。 いただいたサポートは、音楽活動の資金に充てさせていただきます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
