
短編小説『空のうつわ』
縦読みと横読みのバージョンがあります。
読みやすい方で読んでください。
縦読みバージョン

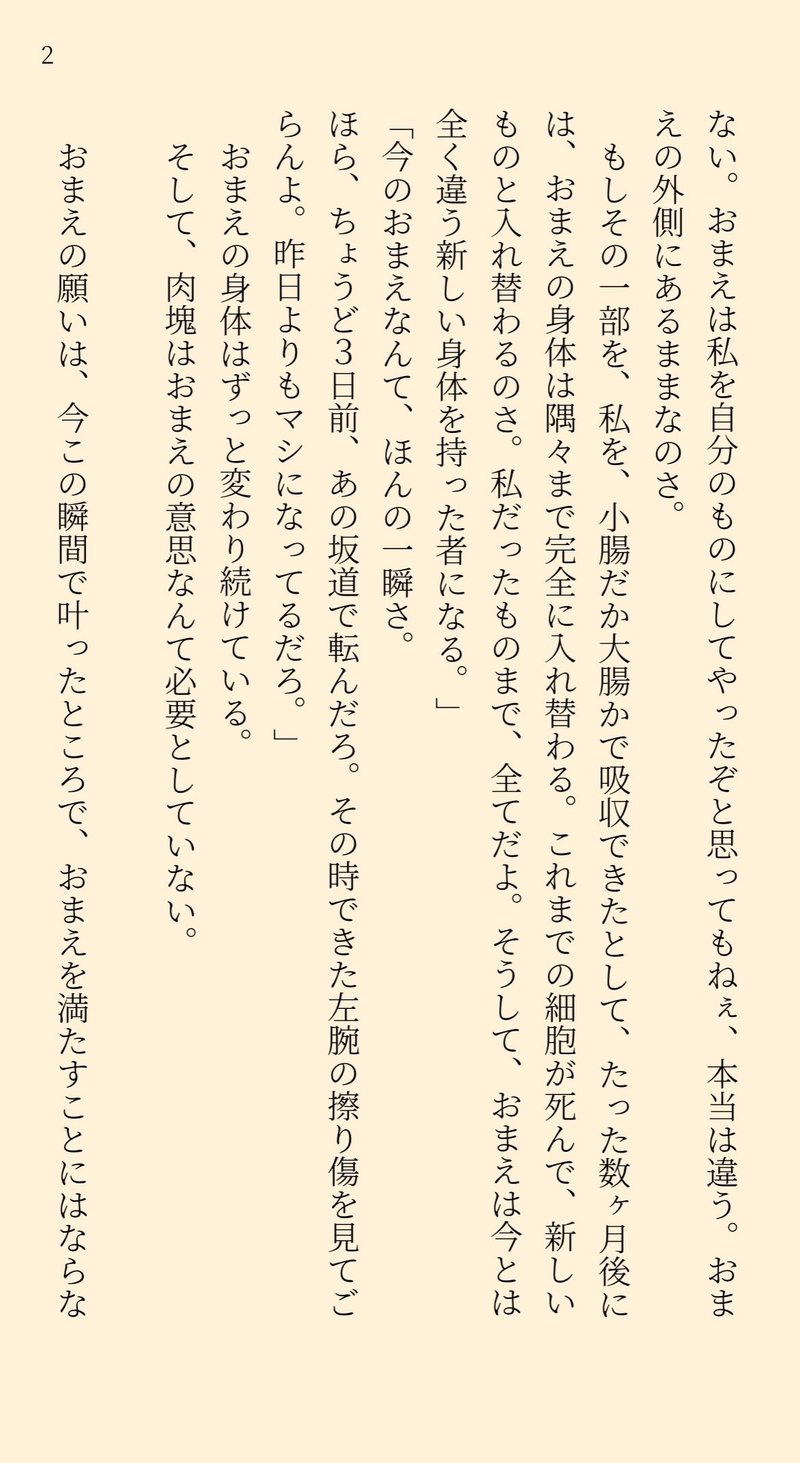












お読みいただきありがとうございました。
横読みバージョン
空のうつわ
「私を食べるなんてよしなさいな」
Dの笑い声はとても軽やかに響いた。
ちょうど夕食どきだからか、ファミリーレストランの店内は子どもたちの声が混じる喧騒に包まれていた。Dはアイスココアを注文していた。スラリと長く骨ばった指でストローをつまみ、中身をクルクルとかき混ぜている。
わたしはあんたを食べたい、と伝えたら、Dはいたずらっ子のような顔をした。
わたしはとても真面目な顔をして言ったのに。Dは、わたしがどれほどそれを切実に願っているかを知っているのに。
「私をおまえの胃の中に放り込んだところで、それはおまえの中にある外側でしかない。おまえは私を自分のものにしてやったぞと思ってもねぇ、本当は違う。おまえの外側にあるままなのさ。
もしその一部を、私を、小腸だか大腸かで吸収できたとして、たった数ヶ月後には、おまえの身体は隅々まで完全に入れ替わる。これまでの細胞が死んで、新しいものと入れ替わるのさ。私だったものまで、全てだよ。そうして、おまえは今とは全く違う新しい身体を持った者になる。」
「今のおまえなんて、ほんの一瞬さ。
ほら、ちょうど3日前、あの坂道で転んだろ。その時できた左腕の擦り傷を見てごらんよ。昨日よりもマシになってるだろ。」
おまえの身体はずっと変わり続けている。
そして、肉塊はおまえの意思なんて必要としていない。
おまえの願いは、今この瞬間で叶ったところで、おまえを満たすことにはならない。
それとも腹が満たせれば満足かい、とイタズラな笑みを深くしてDは言った。
そんなわけないじゃ無いか、と声にはならなかった。
代わりに、Dにお勧めされたハンバーグプレートに目を落とした。湯気に乗った香ばしい匂いが鼻を刺激する。
まだ、ナイフを握ったまま一口も進んでいない。
その、動かない自分の腕を見つめる。この身体は、自分の意思とは違うものでつくられたものなのだ。ばらばらと動く指たちや、持ち主の知らないところで勝手に働き続けている内臓どもは、できる限り長くこの世の環境に合わせて生きられるように、誰かがひとつひとつ考えて作りあげた。けれどそれは、人が、互いの目にも映るように、わかりやすいように、目には見えない己の霊魂を今ここに留めておくための、ただの器でしかないと、Dは言っている。
そっと、片腕で自分の身体を抱きしめた。
この動く肉塊が、急に自分の所有物から切り離された存在のように思えた。
熱を発する、土偶。
隅から隅まであらゆる細胞、神経が絡み合った、生き生きと己の生命力を放ち続けていたものが、本当は脆く、今にも簡単にバラバラと剥がれ落ちてしまう泥の寄せ集めのような、土人形の一つであったのか。
わたしは土偶の所有者だったか。
ドクン ドクン ドクン
心臓の音が聞こえだした。音はだんだん大きくなる。
わたしの意思が鳴らしているものではない。
ドクン ドクン ドクン
鳴り止めと命令したところで、止まってはくれない。止めてはいけない。だがいつか止まる時が来る。
それを回避する術も、わたしが知ることは、無い。
器の中に留まっている霊魂が、出口はないかと探し始めたみたいに、ブルリと身体が震えた。
聞こえる心臓の音は、このリズムは、この身体はわたしのものだ。わたしだ。
そう信じて疑わなかったのは、なぜだ?
昨日のわたしだったものに問うてみた。返事はない。
自分を抱いていた右手の先が、鈍い痛みにあたる。
さっきDが見ていた、わたしの左腕の擦り傷。坂道で転んだ3日前、皮膚が砂利と擦れ合って破け、血が滲み、今はそこに膨らんだどす黒い瘡蓋ができている。
わたしは人差し指の爪で瘡蓋を剥がした。先ほどよりも鋭い痛みが走った。
瘡蓋は土人形から離れ、音もせず落ちた。
もうわたしではないものを、小さなカケラを、しばらく見ていた。
その行為が続くのを、ジンジンとわたしに危険信号を送る傷跡の痛みが邪魔をした。血が滲んでいた。
もう、カケラは見つけられなかった。
初めからそこには何もなかったみたいに。
再び目の前の人物を見た。
自分とはまったく違う人生を生きてきた、不完全な人。
わたしと違って、相手を真っ直ぐ見つめる、美しい人。
Dを食べたい。
Dの頬を、瞳を、右手の中指を、血を、背骨を肝臓を。すっかり食べてしまえたなら、わたしはDと一体になれる。
2つの欠けた生き物たちが溶け合って、ひとつになれる。
それは、不完全なものが新たに完全なものへと変わるための必要行為であり、わたしは、完全な存在になりたかった。
とても素晴らしいことのように思えた。
わたしは不完全なんだということは、数年前から気づいていた。いくら完璧なオリジナルを目指したところで、わたしはそのやり方さえ思いつけない。引き出しを全て開けたところで、物を入れていなければ何も発見することができないように。
わたしの中には、何もない。
空っぽならば、そこに新たな物を入れる必要がある。
わたしではないナニカを。
それは魅力的でなければならない。
目に見える物は、しまっておける。
美しいものは、わたしを美しくさせる。
全て、わたしの中に。
ひとり黙って思考をかき混ぜていたわたしの表情は如何様だったのか、わたしを横目に見たDは口を開いた。
「私を食べたって美味しくないと言っているのさ。」
わたしを揶揄っているのか、真面目に言っているのか、わからない。
いまDが何を考えてるのか、鋭い視線の先で(わたしはこの目が好きだ)、何を見ているのかわからなかった。
わたしには見えないナニカを見つめて、Dは薄くて血色の良い唇を動かす。独り言のように、わたしに向けて。
「私をあんたの中に入れたいなら、私の言葉を、声を、記憶を聞きなさいな。あんたの記憶のピースとして、私を入れるんだよ。」
そしたら、いつか肉塊が朽ちて、あんたが今のあんたじゃなくなった時、つまり霊魂だけのあんたになっても、多少は長い時間溶け合えるだろうよ。
それも永遠なんかじゃあないだろうけどね。
期待しないことだ。
Dは、わたしから少し視線を外して呟いた。まるで自分に言い聞かせるように。その表情は、笑っているようでも、何かに失望しているようにも見えた。
左の口の端が、やや上がっている。
Dが考えながら喋る時の癖だ。
わたしは、Dの仕草を知っていた。
わたしは記憶の石を持っていた。きらきらと光るDの石を。
Dは、この石を、わたしが肉塊を持たない者になっても持っていて良いと言ってくれた。その中に、もっとDを閉じ込めても良いと言ってくれた。
「Dは、わたしとひとつになることを許してくれる?」
Dの口元をじっと見た。
薄い唇が上下に開かれる様子を見ていた。
「人は、結局はひとつでしか存在し得ない。この世に生きていようがいまいがね。
孤独は、別に悲しくも嬉しいものでもない。ただ、そうであるだけさ。
肉体なんかわかりやすい、目に見えてくさっていくからね。お前とわたしが違うものであることを、はっきりわからせられているのさ。」
Dは吠えた。わかりやすいのは好きさ。考えなくても視える。
いくらか時間が過ぎて、わたしはDとひとつになった。
Dは死を受け入れたけれど、わたしは耐えられなかった。
ただの土偶だとしても、この身体はわたしの熱を知っている。
けれど、わたしにも手放すときが来た。
自分から手を離すのではない。勝手にぷつんと糸が切られてしまうように、わたしの身体はわたしではないナニカとして離された。
いや、はたから見たら、わたしが、さっきまでとは違うナニカになったのだ。
この世の誰にも見えないナニカに。
空中にぽわんと放たれたシャボン玉の気分だ。いつか完全に消えてなくなる、ようにみえるのだ、わたしの存在は。
わたしたちは肉塊を持たないから、完全なひとつになれた。器に入っていた、わたしの霊魂と光るDの石がひとつになった。
ひとつの光になった。
どの部分がDで、どの感情がわたしのものか、わからないくらいに。
それを願った。
永遠を。
けれども、Dだった光は、笑い声のような、軽い音を立てながらわたしからはなれた。わたしの光はやや弱くなる。いや、わたしがそう感じるだけだ。
ひとつの光は、揶揄うようにくるりとわたしの周りを一周し、一瞬のうちに遥か遠くに飛んでいった。
音は、今や耳のないわたしでは、記憶の中のものでさえ残らないらしい。もう、Dの声は思い出せない。
わたしは光になってここに漂った。
Dとも、以前のわたしとも違うわたしで。
瞬く間に時間が過ぎていった。わたしはまだ、ここから動けないでいた。
ここ、が、ついさっきまでのここ、かどうかは、わたしには判断がつかなかった。あたりを見回しても(眼球はないけれど、ぐるりと見たんだ)、どこも穏やかなものに包まれている気がした。
だって、心地いいんだ。今のわたしが、そう感じている。
永遠が漂っていた。
わたしがいる場所だ。
たまに自分と違う光とぶつかって、その度にひとつになった。Dの光の時とは違い、お互いのカラダをつつき合ったり擦りあったりして、遊ぶように混ざり合った。
大抵は遊びに満足したら、どちらともなく離れていって、相容れない相手とは、触れた瞬間パチパチと電気が走り弾け飛んだ。
心地よかった。
ある時、遠くに光るナニカが見えたけれど、それは相手ではなくて、新しい器に入るための入り口だった。
わたしはまだここに漂っていたいと願ったが、光のカラダは言うことを聞かず、どんどん入り口に近づいて行った。
なにかの苦しむ声が聞こえる。
音が聞こえるのは随分久しぶりの感覚だ。
また、自分が不自由な器を持つことになるのがわかった。
また、期待と失望を繰り返す生が始まるのだろうか。
けれどそんなことよりも、いまだ絶えず聞こえてくる声の持ち主の顔が見たくなった。
これまでの長い孤独に比べたら、たった少しの間じゃないか。
不完全に生まれ、最後まで望むものは手に入ることはないけれど、良いだろう。そこへ行こう。
あの人にまた会えたら。
(終)
お読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
