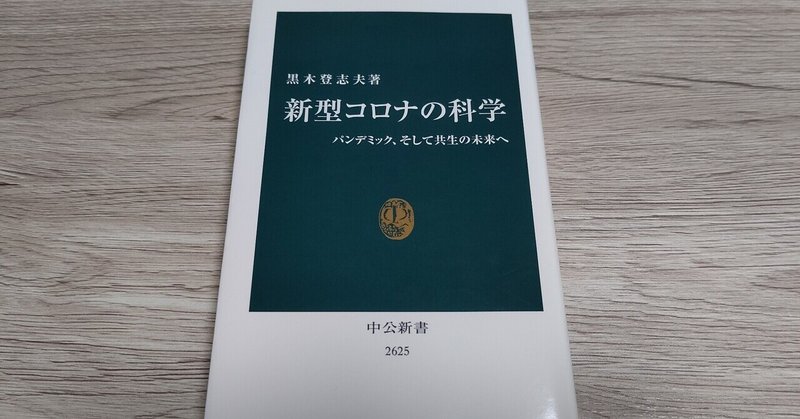
【読書感想】新型コロナの科学 パンデミック、そして共生の未来へ
がん研究者で、サイエンスライターでもある黒木登志夫さんが武漢で初めて新型コロナウイルスが発見されてから本書が出版される2020年10月末までの新型コロナウイルスの世界の動向やそもそもの感染症の歴史、ウィルスや感染方法、共生までを書いた本です。
新型コロナウイルスとの生活が日常化してしまっていたのですが、この本で「あー!最初はこんな感じだったな」と世の中の動きが思い出せるとともに、「え?PCR検査が全然進まなかった裏に厚労省噛んでたの?」とかコロナ対策の裏側まで知ることができました。
最初は、感染症の歴史から始まるのですが、これはとても興味深くて昔も今も大学休講やロックダウンをして、感染症への対策をしていたみたいで、大学が休講して田舎で暮らしを強いられたニュートンはそこで万有引力の法則を発見したとか。このエピソードを知って、外出自粛とか言っても本読んだり、知識や考えを深めることができると改めて思ったので、個の期間だからこそしっかり本を読んだり、オンラインイベントで様々な人の話を引き続き聴いて、自分の考えを深めていこうと思いました。
後、第一次世界大戦はスペイン風邪によって、勝敗が決したとも言われ、アメリカがドイツなどの同盟国に送り込んだ最強の兵器とも称されています。しかし、問題だったのが穏健派だったアメリカのウィルソン大統領がスペイン風邪にかかってしまい、ドイツに対する賠償金の話し合いに参加できず、ベルサイユ条約が結ばれて、巨額の賠償金を背負ってしまったドイツにナチスが台頭してしまったとのこと。1つのウィルスで世界のパワーバランスがここまで変わってしまうとは・・・。
新型コロナウイルスへの対応も記述されていたのですが、まあWHOもどの国もコロナを甘く見て対策が遅れてしまった(WHOのパンデミック宣言が遅れたことによって、各国の対応が遅れるなど)とよく分かる内容で、鬼滅の刃の鱗滝さんから「判断が遅い!」と平手どころか往復ビンタされる人が多数出てきそうです。ただその中でも、台湾は中国の圧力でWHOにオブザーバー参加すらできていなかったので、WHOや中国の情報を鵜呑みにせずに自分たちで考えて行動して、感染の封じ込めを頑張ってきたことがよく分かりました。
このエピソードは、個人に置き換えても上司や周りから何も言われなければ動かない思考停止した働き方をしているとコロナのような有事の際に全く動けなくなると改めて思い知らされるもので、そうした個人が多くなってしまった結果がコロナの感染拡大を招いた最大の要因なのかなと思ったりしました。
コロナ対応で感染者が少ない国であるニュージーランド、台湾、ドイツは女性がトップを務めていて、権威主義的でポピュリストの男性がトップを務めている国は感染者が多くなっているという考察もとても面白かったです。
ジェンダー的な観点で誤解を招くかもしれませんが、たしかに男性のリーダーは見栄っ張りで「俺についてこい!」と自分中心に考える人が多いなという印象があるので、自分の意にそぐわない意見は排除しがちかもと思いました。一方で、本の中でも言及されていたのですが、女性リーダーたちは専門家の話を聴き、国民に分かりやすいメッセージを伝えていたのが功を奏したのかなと思います。この話は、これからのリーダーシップを考える上でもとても重要な話で、女性参画が少ない日本にとってはまさに今、考えないといけないです。
という感じで、この他にもPCR検査の有用性や集団免疫、そもそもウィルスの話まで書かれている本でした。著者の黒木さんはこの本を書いている昨年の10月末時点で変異株の可能性に言及されていて、実際問題デルタ株が市中蔓延した経過もあったので、これまでの経緯はしっかり振り返ってどの政策が良かったかを確認していきたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
