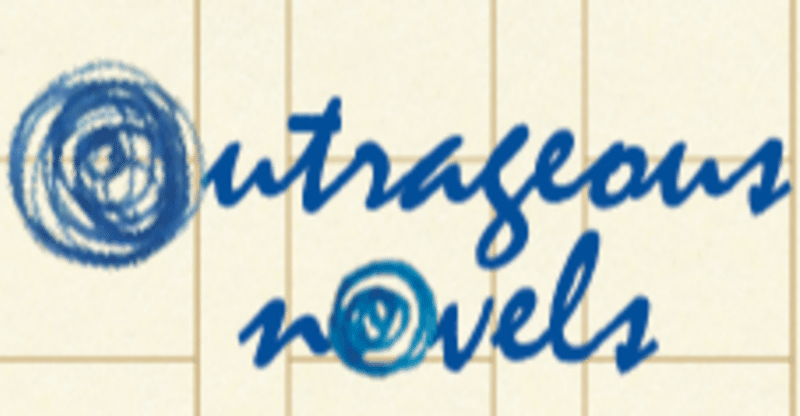
慶應ボーイ・ミーツ・慶應ガール(再掲)
◆姉妹編「毒親育ちが転生しそこなって普通に進学したら絶望しかなかった」、現在連載中。ともに半自伝的な内容ですが、「慶應ボーイ~」が大学編(ライトコメディ、2013年作)、「毒親育ち~」が高校編(ダークコメディ、2017年作)となってます。
それは富田林寛(慶應義塾大学・経済学部四年)が通算四度目となる失恋を経験した直後のことだった。寛は坂下みな実(桜美林大学・環境情報学部四年・休学中)に献身的に尽くした挙句、「あんたなんか大嫌い!」と言われてふられたのだった。
波乱に満ちた恋愛が終止符を打つと、彼の心はすっかり磨り減ってもはや何も感じられなくなっていた。いや、そうではなかった。彼には感傷が残されていた。寛は一人で地元小田原の海岸に行くと、感傷的な気分に浸った。習慣とすべき行為ではなかった。
二月の海は寒かった。寛は、砂浜に落ちていたくたびれたビニール袋を何気なく拾いあげた。ビニール袋ではなかった。季節外れのクラゲだった。まだ生きており、おまけに強い毒があった。彼は手を刺されて強烈な痛みに悶絶した。
そこへ、制服姿の四人の男子高校生(小田原高校二年)がやってきた。寛が卒業した高校の後輩だった。彼らは鬱屈を溜めこんだ、やさぐれた目つきでこちらを見ていた。寛はあわてて目をそらした。
遅かった。彼は四人に取り囲まれ、ピンボールの玉のようにどつき回された。財布を出せと迫られると、寛は人の道を説く代わりに言う通りにした。ところが、財布から学生証が出てきて彼が慶應大学の学生だと分かると、四人の顔は不快さに歪んだ。彼らがどうあがいたところで手の届かない学歴だったのだ。寛は尻を蹴られ、横っ面に肘打ちを決められた。腰骨に膝蹴りを食らい、腹を殴られた。
「おれは、きみらの高校の先輩だぞ」砂浜に突っ伏した寛は、あえぐように言った。
すると、尚更ひどい目に合わされた。
レンズがひび割れ、フレームが曲がったメガネを何とか引っかけて、寛は駅へ戻る道をよろよろと歩いた。ふいに脇道から自転車が飛び出してきた。避けきれなかった。寛は倒れざまに路肩にあった干物屋の看板に頭をぶつけて額を切り、足を側溝に突っ込んで足首を折った。自転車は振り返ることもなく去って行った。
寛が入院すると、大学の同期たちが続々と見舞いに訪れた。
彼らは、寛に訪れた一連の不幸を自分の目で確かめるために、我先に病室に押しかけてくるのだった。そして、寛が本当に不幸な目にあったのだと分かると、これ以上面白いものはないというように遠慮なく声をあげて笑った。
ドアを開けて颯爽と現れたのは、世良(慶應義塾大学・経済学部四年)だった。自信家で快活なこの男は、ソウルで開かれていた学会からわざわざこのために一時帰国したのだ。
「最近スカイダイビングに凝ってるから」開口一番、彼は言った。「飛行機から飛び降りて、窓から登場しようと思ったんだけどな。他の患者に迷惑だからやめておいた」
世良は大学院への進学が決まっていたが、学部生のうちからすでに学会のエースと目されていた。世界中の学会を飛び回っては新しい論文を発表し、それをまとめた本も出版していた。これは学術書としては異例の三万部というヒットを記録していた。
世良は昨年受験生向けの大学受験対策本も出版していた。この本はまたたく間に重版を重ね、その印税は最終的には平均的なサラリーマンの生涯賃金に達すると予測されていた。世良は、大学院生のうちに教授の座につくだろうと噂されていた。
女性看護師たちの嬌声から逃れるようにして病室に入ってきたのは、岸和田(慶應義塾大学・法学部法律学科四年)と安達(慶應義塾大学・商学部四年)だった。
岸和田は、ある有名アイドルグループの元メンバーで、日本で最もイケメン揃いと言われたそのグループの中でも一人群を抜いてイケメンだった。ということは、日本で最もイケメンだといっても過言ではなかった。三田祭のミスター慶應コンテストでは、彼が参加すると勝負にならないという理由で出場登録を禁じられていた。
岸和田は、病室にたどり着くまでの間に七人の女性看護師の連絡先をゲットしていた。そのうち五つは一方的に渡されたものだった。
「次は看護師と合コンだな。制服で来てもらうか」
岸和田が、眩しさに思わず目を細めてしまう自慢の白い歯を輝かせて言った。彼にあっては自慢は歯だけではなかった。全身のすべてのパーツが自慢だった。
「おれはそれに参加するだろう」安達が未来を予言するように言った。
安達は、口数が少なく何を考えているか分からないところがあったが、どこか危険な匂いのする男だった。彼の父親は世界的に名を知られた実業界の大物だと言われていた。一方では、裏社会を牛耳る闇の帝王なのだという噂もあった。事実はその両方なのかもしれなかった。安達自身は、決して親の職業を明かそうとしなかった。
安達は、卒業後は国立の経済研究所で働くことが決まっていたが、その一方で世良とともに起業する計画もあった。二人は、安達個人が所有している瀬戸内海のある島を、老人のユートピア――もしくはディストピア――にしようと目論んでいるのだった。超高齢化社会に備えて、次世代の社会システムのあり方を模索するのがテーマらしい。
「ちなみに今日はモデルと合コンだ」岸和田が軽やかに言って笑顔を決めた。自慢の歯がきらりと光り、暗く沈みがちな病室の光量が増した。
岸和田はアイドルグループを脱退した現在、ソロでアルバムを出したり映画に出演したりしており、その人気は今やアジア全域に及んでいた。にもかかわらず、卒業後はIT系のトップ企業に就職が確定しており、芸能活動のかたわら一社会人として働くというのだ。アイドルである前に人であることを忘れたくないというのが本人の言だった。
「おれはそれに参加するだろう」今度はソウルにとんぼ返りする予定だった世良が言った。
「学会は?」ベッドの上で劣等感に苛まれていた寛は、余計なおせっかいを口にした。
「まず合コンに出る。それからソウルに戻る」世良がスケジュールを整理しながら言った。
「おれも、モデルとの合コンに参加するだろう」寛は痛みを堪え、むっくりと起き上がりながら言った。
「ダメだ」
「無理だ」
「足手まといになる」世良と岸和田と安達はすげなく言った。
そのとき、廊下から「ぬあーっはっはっはっはーっ!」と病棟を揺るがすような笑い声が響いてきた。常盤に違いなかった。誰がおかしいことを言ったわけでもないのに一人で大笑いしながら登場するのが、計り知れないスケールを持つ常盤という男だった。
「おい、世界で初めて空飛ぶ車を実用化するのはおれだぞ」病室に入ってくるなり、常盤(慶應義塾大学・法学部政治学科四年)は宣言した。
「何の話だ」寛は、何となく悔しくなって言った。
「うちの大学の研究チームを組織して、ある発明家と手を組んで空飛ぶ車の開発にとりかかった。五年、いや、三年で何とかなると思う。岸和田、完成したらCMに出ろよ」
「いいよ」岸和田は簡単に請け負った。
常盤は、春から官僚としてエリートコースを歩むことが決まっていた。何かというと新しいチームを組織したり、既成の組織を改革したりすることが好きな男で、そのカリスマ性でリーダーシップを取るのだった。彼の優れた弁舌はTVの討論番組でもいかんなく発揮されていた。常盤には人に命令を下す稀有の才能があった。
「おれは」常盤はあっさり言ってのけた。「そう遠くない将来、世界を手に入れるだろう」
「半分くれ」寛はすねた子供のように口を尖らせて言った。
「ダメだ」常盤は即座に却下した。「そして、大学にはおれの名を冠した奨学金が設立されるだろう」
世良、岸和田、安達、常盤の四人の経歴は完璧で、卒業後の進路も約束されていた。彼らには成功に至る道が開かれていた。何にも邪魔されない、目的地まで高架で一直線にすっ飛ばせる道だった。しかも、その道の両側にはモデル級のルックスの女たちがずらりと並び、スカートの裾をつまみ上げて太ももをちらちら見せながら立っているのだ。
寛はといえば、その道の路肩に木箱を置いて靴磨きをやるのがせいぜいといったところだった。彼は坂下みな実とのすったもんだの恋愛の末、就職活動を途中で放棄してしまっていたし、卒論も期限に間に合わせることができなかった。
卒論は全体の四分の三まで書いたものの、残りは目次だけという状態で提出したのだった。担当の沼尾教授は「何とかしてみよう」と言ったが、その口ぶりからするとあてにはできなかった。
この分では卒業は危うかった。そうなればもちろん卒業旅行に行くこともできない。卒業旅行はそれぞれ別のルートで世界一周するという話になっていた。途中、日本の裏側に当たるブラジルのポルト・アレグレという港湾都市で落ち合って、「陽気な港」を意味する町の名前通り、陽気に飲んで騒ぐ計画だった。
寛もそれに参加したいと思っていた。そのためにこっそり金も溜めていた。しかし、仮に卒業できたところで、この怪我では海外旅行など無理だった。寛は今、ろくにベッドから出ることもできなかった。世良たちとの差は、あまりにも歴然としていた。
「どうやったらふられて骨折できるんだ」常盤は、彼にだけできるやり方でいきなり核心に触れた。
「まずふられた。そのあと骨折したんだ、自転車に轢かれて。その前には高校生にリンチにあってる。ふられて、リンチにあって、自転車に轢かれた」安達がなるべく正確を期して説明した。
「高校生というのは富田林が卒業した地元の学校の後輩だ」ルービックキューブの最年少記録を持っている世良が、機転を利かせて付け足した。
「ちょっとじゃれあっただけだ」寛は弁解した。
「それからクラゲにも刺された」岸和田も情報を添えた。「カツオノエボシ。猛毒がある。普通はGW頃に現れるんだが、この異常気象だからな」彼は海洋生物の生態にも詳しかった。
「おれはクラゲに刺されたことなどないぞ」常盤が聞いてもいないのに言った。
この連中と一緒にいると、寛はいつも自分が何の取柄もない田舎者であるかのように感じられたが、今ほど惨めな気持ちになったことはなかった。何もかも手にしているように見える同級生たち。それに引き換え、何ひとつ持っていない自分。寛の父親は地元小田原市の公園管理事務所で働いており、母親は主婦だった。
かつて、寛の家柄や出自を聞いたとき、岸和田は率直な驚きを表明したものだった。
「そんなことが可能なのか? おれはまた、世帯収入が少なくとも三千万以上あるか、三親等以内に医者や弁護士や経営者や国家公務員といった人物が五人以上いるかしなければ入学できないんだと思ってた」
ここが寛の地元であり、今いるのがまさに彼が生まれ出でた病院(小田原市立病院)でもあったことから、岸和田が懐かしむようにその話を持ち出した。世良も安達も常盤も、かつての岸和田と同じように率直な驚きを表明した。
「それでもおれは入学した。現役で、偏差値の一番高い学部に、独力で」
寛は虚ろな眼差しで言った。そんなことはこの連中にとって何ほどのものでもないと痛いほどよく分かっていた。それでも言わずにいられなかった。それだけが寛の心の拠り所だったのだ。
「そんな細かいこと、誰も気にしてないぞ」岸和田は愉快そうに笑った。
寛は、心の傷も身体の傷もしばらく癒えそうにない気がした。
「卒業できないかもしれない」寛は弱音を吐いた。
「できるさ」世良が言った。
「就職も決まっていない」
「決まるさ」
「なぜそう断言できる」
「学則第二十二条がある」
「学則第二十二条?」
そんな学則は聞いたことがなかった。他の三人を見ると、安達も岸和田も常盤も口々に「学則第二十二条」と言うのだった。寛だけが知らなかったことらしい。
「入学にふさわしくない者は」世良が説明した。「我が校への入学を許可しない。ひとたび入学した者は、我が校の学生としてふさわしいふるまいをしなければならない。中途退学は我が校の学生にふさわしいふるまいではない」
「どういうことだ」寛は要点を掴みかねた。
「万が一卒業しそこなったら、お前は卒業しなければならないだろう。万が一就職しそこなったら、お前は就職しなければならないだろう」世良はポイントを解説した。
寛は、その冷徹で非の打ちどころのない凄まじい論理に舌を巻いた。
「逃げ道なし、か」寛は、流しに溜まった洗い物を見るときのような憂鬱な目つきで、己の足首を固定しているギプスを見て言った。
「前から不思議だったんだが」安達が文字通り不思議そうに言った。「お前という奴は一体将来何がしたいんだ。おれにはそれが分からない」
まさにそれこそ、寛が自分について分からないでいることだった。一体、自分は将来何がしたいのか。それが分からないがために、現在やっていることもどこかピント外れになるのだった。
「おれはまだ二十一歳の学生なんだ」寛は言い訳がましく言った。彼の誕生日は三月で、早生まれだった。二十二歳まではあとちょっとだけ間があった。
「お前は色彩を持たない奴か」岸和田がある小説の題名を引用して突っ込んだ。
「おれも二十一歳の学生だ」同じく早生まれの世良が言った。「だが、おれは二十五までに教授職を射止めるだろう。それから一足飛びに学部長になるつもりだ。四十歳までには最年少の学長になると思う。そして、四十五歳で引退する。それがおれの人生設計さ。すでに全工程の三分の一が終わろうとしてるんだが、これは予定よりもずいぶん早い。もっと早く引退するか、あるいは四十五歳までもっと仕事をするか、どっちかだろうな」
「ずいぶんなスピードで駆け抜けるな」寛は、世良がまだこの場にいることを確かめるように、頭からつま先へと視線を走らせた。
「そこが連中とおれたちの違いなのさ」世良はまだその場にいた。
「連中?」
「我々以外の連中」
「我々以外」
「連中は大学三年も終盤になってからのろのろと就活を開始する。ところが、おれたちは入学したそのときから就活をしているようなものだ。いいや、違うな。正しくは入学すること、つまり受験が就活に相当するのであって、入学はすなわち入社。おれたちは学生であると同時に、社会人として働いているようなものなのさ。まぁ、学生のふりをしたければそうもできるが」
それを聞いて、寛は大学入学以来抱き続けていたすべての疑問が氷解したような気がした。しかし、一瞬ののちには、その答えは再び闇の中に姿をくらませてしまった。
「ということは、おれは小学校のときから働いていることになる」慶應幼稚舎出身の安達が言った。
「おれは高校から」慶應高校出身の岸和田が言った。
「おれもだ」同じく慶應高校出身の常盤が言った。
「世の中もその事実を知っている。世の中がその事実を知っているということを、おれたちも知っている。そこで我々は連携をとって社会で働く」
「我々」寛はうなった。
「個々の能力を社会に還元してこその仕事だ。我々はそれを最大限に活用する。我々はスモール・サークル・オブ・フレンズなのさ」世良は説明を完了した。
「おれはどうしたらいい」率直に言って、寛は話についていけなかった。
「新しい女を見つけろ。何なら紹介してやる」岸和田が言った。
それが今の話に関係があるかどうか分からなかったが、寛にはひどく説得力があるように聞こえた。
「そうしてやってくれ。こいつが三田キャンパスのパンチラスポットで何時間も一人で座ってるのを見ると、おれは涙が出そうになるんだ」安達が同情心を起こして言った。
「モデルでも看護師でもいい」寛はすがりついた。本当に紹介してほしかた。
「いや、やっぱりやめておこう」気分屋の岸和田は簡単に前言を撤回した。「その代わり、お前には差し入れを用意しておいた」
「何を」寛は何でもいいからほしかった。
「すぐに分かる」岸和田は思わせぶりに言った。それから寛の耳元で囁いた。「この四年間は祭りみたいなもんさ。楽しめなかったらバカだぜ」
その深夜、病室に突如として四人のベリーダンサーが現れた。
彼女たちは寛のベッドを囲むと、官能的に腰をくねらせて踊りはじめた。それこそ岸和田が用意した差し入れだった。ベリーダンサーは非常に面積の小さい布切れを二枚身に付けているだけだった。我慢しきれずに触ろうとすると、寛は手をぺしっと叩かれた。
「見るだけよ」ベリーダンサーはウィンクして言った。
寛は見るだけでも大いに楽しんだ。
この四年間という意味では、寛はまったく楽しめていなかった。しかも、退院してみると大学から留年決定の通知が届いていた。彼は二十二歳になっていた。
寛は自分が何をしたいのか分からないでいたが、それを知るために何をしたらいいのかもまた分からなかった。とりあえず就職活動を再開してみたものの、何をしたいのか分からないということが意識されると、それは去年にもまして苦痛なものとなった。
エントリーシートを書くことからしてひどく難しかった。少しでも気を緩めると、企業を批判してしまうのだ。そうでなくても曖昧な物言いばかりが並んだ。例えば「もし通信サービスというものが機能しなくなったら、社会はどれほどの混乱に陥ることでしょう」などというように。
寛は、未完成だからということとは別に、卒論のタイトルも明かさない方が賢明なのではないかと考えた。それは「商業主義の終焉、すべての主義の終焉、そして依然として世の中は金」といった。反発を招くだけになりそうだった。
そうなると面接での会話も弾まなかった。彼を面接したある企業の人事部員は、「実を言うと、富田林さんがうちで働きたがっているようには見えないのです」とやんわり非難した。否定できなかった。
「聞いた話によると、きみは昨年いくつかの企業の面接を連絡も入れずにすっぽかしているね」沼尾教授(慶應義塾大学・経済学部教授)は慇懃に言った。
寛は、就職のことをこの教授に相談したのは間違いだったと感じながら言い訳した。
「プライベートで色々ありまして」
「大学の評判を落とす行為だ」沼尾教授は、耳を貸す素振りも見せず、忌々しげに口元を歪ませた。「そしてもちろん、私の業績にも響いてくる。きみが私の学生だということを忘れてもらっては困る」
「は」寛は恐縮した。
「他の学生たちはもう全員内定をもらっている。きみは一体何をしているのだ」
「は」寛は恐縮した。
「この話はもういい。来週のゼミなんだが、プリンストン大の教授を招いて御茶ノ水の経済研究センターでやることになったから、間違いのないように」
「は」寛は恐縮した。
翌週、寛は御茶ノ水の経済研究センターを訪れたが、そこでは沼尾教授のゼミなど開かれていなかった。プリンストン大の教授もいなかった。それ以前に、経済研究センターなどという建物自体が存在しないのだった。
「昨日、御茶ノ水に行きました」その翌日、寛は教授に抗議した。
「なぜ」沼尾教授は取りかかっていた書類から目を上げて、疎ましげに彼を見た。
「経済研究センターでゼミをやると仰ったので」
「御茶ノ水にそんなものはない!」教授は一喝した。
「では、どこに」寛は狼狽して言った。
「知らんね」教授はそっけなく言うと書類仕事に戻った。
寛は納得が行かないまま、その場に立ち尽くした。
就職がうまくいかなかったら、引き延ばし策として大学院に進学するという手もあった。しかし、とりわけ成績優秀でもない彼が大学院に進むためには、担当である沼尾教授の推薦が不可欠だった。寛は、そうなったときにこの教授は推薦状を書いてくれるだろうかといぶかしんだ。
三分後、沼尾教授は再び目を上げた。「のわっ!」教授は寛がまだそこに立っていたことに驚き、熱狂的に万歳するかのように両手を上にあげて仰け反った。
「は」寛は不信を押し隠して言った。
「仕事は決まったのかね」教授はすばやく動揺を鎮め、乱れた髪を整えながら高みからものを言った。
「いいえ」
「ハローワークに行ってみるといい」教授はまるでその方角にハローワークがあるとでもいうように、人差し指で一方を指さした。その方角にあるのはドアだった。
「よろしいでしょうか」寛は出て行く前に是非とも訊きたいことがあった。
教授は何も言わず、ただ睨むように彼を見た。
「いったい、あなたはどういった業績が認められて教授の地位に就かれたのですか」
大学教授になる道はひどく険しい。特に、この大学の教授になる道はひときわ険しい。世良から聞いたところによれば、沼尾教授はこれまでろくに論文を発表したことがなく、発表した数少ない論文でも話題になったものは一つもないということだった。この男には目立った業績は一つもなく、その一方でもっと優秀な人材はいくらでもいた。それなのに、なぜこの男が教授なのか。
「私は何もしていないよ」それが沼尾教授のよこした返事だった。
寛は、ある大手銀行のセンタービルに大学のOBを訪ねた。その銀行は、慶應義塾大学出身の職員が多いことで知られていた。
面会を快諾してくれた宮田(慶應義塾大学・商学部卒)は、弱冠二十六歳にして幹部となった出世頭だった。
「見てくれ」宮田はビル内を案内しながら惜しげもなく言った。「好きなだけ見てくれ」
寛の目の前を、現金をたんまり積んだ網かご台車が横切った。まさしく札束の山だった。これほどの量の現金を生で見たことがなかったので、寛は圧倒されて言葉を失った。
「八億ある」宮田は得意満面になって言った。「厚みでいくらか分かるようになる。もちろん、重さでも分かるようになる」
寛は、八億円の札束を乗せた網かご台車を物欲しげな目つきで見送った。見るからに屈強そうな警備員が二名同行し、鍵も厳重にかけられていた。とても近づける雰囲気ではなかった。
「今、法に抵触するようなことを考えたね?」宮田がからかうように言った。
「いえ、滅相もありません」寛はあわてて否定した。
しかし、図星だった。床に紙幣を敷き詰めて、げらげら笑いながら裸で転げまわり、群がる女たちの頬を札束で張るという夢想をしたのだ。
「毎日毎日、三十億から四十億の金が動いている」宮田は言った。「我々の金さ」
「わ、我々の金」寛は、使ってみたい言葉だったので、自分でも言ってみた。そうしながらも、若干の疑問がわくのを抑えることはできなかった。
「しかし、それは預金者の金では」
「はっはっは」宮田は軽快に笑ってその考えをいなした。「あるいはそうとも言えるだろう。しかし、そう厳密になる必要はない」
「そうなんですか」寛は合いの手のつもりで言った。
だが、それは宮田には反抗的な態度に映ったようだった。
「きみは、どうも素直じゃないところがあるな」宮田は寛を横目に見て、不信感をにじませて言った。「本当にぼくの後輩なんだろうね」
「もちろんです。よろしければ学生証を」寛はあわてて財布を取り出した。
「よしたまえ!」宮田はそれを制して言った。
「は」寛は恐縮し、媚びへつらうように言った。「しかし、間違っても早稲田の学生などではありませんので」
「なに?」宮田が眉根を寄せ、険しい顔になって言った。「今、なんて?」
「え?」寛は、何かまずいことを言ったかとまごついた。「いや、あの、早稲田の学生などでは……」
「おーーーっと、っと、っと、っと、っと、っと、っと、っと、っと、っと!」
宮田は一つひとつの「っと」にやたら力を込めて、大袈裟につまずいて言った。これが冗談などではないということは、それに続く口調から明らかだった。
「言ってはいけない言葉を言ったな」
「は」寛はとにもかくにも恐縮し、しどろもどろになった。「しかし、一体何が……」
「きみは、今、言ってはいけない言葉を言った」宮田はもう一度厳しく指摘した。
「早稲……」寛には何が起きたのか分からなかった。全然分からなかった。
「ハッ!」宮田は、手のひらをばっと突き出し、寛が愚かにも再び口にしかけた言葉を気合で封じた。
寛は出かかった言葉を無理やり飲み込まされ、涙目になって口をつぐんだ。
「そんなものは存在しない。きみが言おうとしている言葉は、この世に存在しない。言葉自体も、それが指し示す対象も存在しない。つまり、まったく存在しない」
宮田が殺気に満ちた目つきで言った。
「そ、そうでした」寛はわけが分からないながらもすくみあがって同意した。
宮田が右手の人差し指をぴんと伸ばし、目玉をくりぬこうとするかのように突きつけてきた。
寛は思わず後ずさりした。心臓が激しく脈打っていた。
「知っているだろう」宮田は言った。「その言葉を言った者にはペナルティが課せられる」
「ペ、ペナルティ」
「一万」
「いいい、一万」
「ちょうどうまい具合に、きみの財布には万札が一枚入っている」宮田は残虐非道になって言った。「人相を見て分かるようになる」
宮田の見立てが完全に正確だったので、寛は身震いした。
「きみは二十二条を知らないのか」宮田が続けて言った。
「二十二条!」寛はどきりとして、床から三センチ飛び上がった。
「ある者が我々の一員であるなら、彼もしくは彼女はそれらしく振る舞わなければならない。それらしく振る舞えないのなら、その者は我々の一員ではない。我々のように振る舞い、我々が知っていることを知っているなら、それは我々の一員であり、我々である」
「そ、そうでした。ぼくとしたことが」
寛はもごもごと口ごもった。それから、学生証を出そうとして手に持ったままだった財布からなけなしの一万円を取り出し、両端を指でつまんで恭しく差し出した。
「気をつけることだな」宮田は何のためらいもなく札を掴むと、目にも止まらぬ速さで上着の内ポケットにしまった。「実際、これについてはどれだけ注意してもしすぎるということはない」
「は」寛は、両手を身体の脇にぴたりとつけて、気をつけの姿勢になって恐縮した。
「これは我々の金さ」宮田は仕切り直して言った。
「左様でございます」寛は追従した。
「そうだとも」宮田は心地よさそうに言った。
しかし、今度は別の疑問が寛をとらえたのだった。彼は、言ってしまった直後に言わなければよかったと激しく後悔することになる疑問を口にした。
「我々とは誰のことなのですか?」
「なんだって?」宮田はぎょろりと目を剥いた。
「いや、あの……」寛は居たたまれない気持ちになって、身体をもぞもぞ動かした。
「今なんて言った」宮田は容赦なく追及した。
「我々というのが、誰のことなのか分からないのです」寛は度重なる失敗に恥じ入りながら小声で言った。今すぐこの場から消えてしまいたかった。
宮田はもはや疑問に答えてくれなかった。
慶應義塾大学では基本的に一、二年生は横浜の日吉キャンパスで学び、三、四年生は港区の三田キャンパスで学ぶことになっていた。
寛は四年生だったが、週に一日だけ日吉キャンパスに通っていた。足りない単位を取得するためと、一年のときから通っている学生相談室のカウンセリングのためだった。
寛は、幼少の頃よりずっと自分には何か問題があるような気がしていた。しかし、それが一体何なのか、自分でもはっきり分からなかった。それでカウンセリングに通いはじめたのだが、その具体的な成果があるかどうかもまた分からないのだった。
カウンセラーの鈴木さん(慶應義塾大学・文学部卒)は、寛が大学においてほとんど唯一くつろいだ気持ちで話せる相手であったが、それでも彼が抱える問題を理解しているわけではなかった。それどころか、彼女は「私が相談を受けている学生の中でも、富田林さんはもっとも恵まれています」と言い渡したことさえあった。
鈴木さんは、寛が話している途中で寝てしまうこともしばしばだった。彼が不服を申し立てると、彼女は落ち着き払って「ただ目を閉じていただけですから」と言うのだった。
「自分が何をしたいのか分かりません」
寛はカウンセリングルームの座り慣れた椅子に座って窮状を訴えた。就職したいわけではなかった。進学したいわけでもなかった。だからといって、他に何かやりたいことがあるわけでもなかった。
しばらく間を置いて鈴木さんは言った。
「それで富田林さんはここにいるというわけです」
考えてみればまったくその通りだった。少しの沈黙のあと、鈴木さんは続けた。
「では、今まで何をしてきたかは分かりますか」
寛ははっとなった。驚くべきことに、この先何をしたいのか分からないのと同様に、今まで何をしてきたのかも分からないのだった。四年間の学生生活と、四年間のカウンセリング。すべてがおぼろげだった。積み重ねられたものが何一つないようだった。
「分かりません」寛は自分でも受け入れがたい思いで言った。
「今日は時間です。ではまた来週」鈴木さんは無情にも言った。
日吉キャンパスには多くの野良猫がいたが、寛は食べ物を分け与えることによって彼らを手なずけていた。今もまた、彼は心を慰めるべく、生協でフィッシュフライサンドを買い求めて餌やりスポットに向かった。
しかし、今やこの猫たちまで彼につらく当たった。フライを千切ってやっても、猫たちは示し合わせたようにそっぽを向いた。猫なで声で涙ぐましいアピールをすると、ようやく一匹だけ近寄ってきた。寛は、手の平に餌を乗せてそっと差し出してやった。ところが、その猫は彼の腕を思い切り引っ掻いて、一目散に逃げていったのだった。
寛は、まるでつげ義春漫画の主人公のように、ひりひりと痛む傷口を押さえながら、悲しみに暮れて学生会館に入っていった。
学生会館の地下には、音楽系サークルの部室兼練習室が並んでいた。一、二年のときに出入りしていた音楽サークルに、誰か話し相手になってくれる者がいるかもしれない。寛はぬくもりを求めて辺りをうろついた。
ふいに、どこかからピアノの旋律がもれ聞こえてきた。クラシックらしかった。寛は耳を澄ませて音の出所を探り当てると、ドアについた丸窓から室内を覗き込んだ。
壁際に置かれたアップライトピアノに向かって、女子学生がピアノを弾いていた。弾き慣れた曲のようで、指は滑らかに動いていた。ショートカットの小柄な子だった。
寛は吸い寄せられるようにして彼女の横顔を見つめた。控えめながら意志の強さを秘めた眼差し。かすかに赤みがさした頬のふくらみ。寛は思わず胸が高鳴った。
「あの」
遠慮がちな声に振り返ると、三人の女子学生が中に入ろうとして声をかけてきたのだった。そこはピアノサークルの部室だった。寛はあわててドアの前からどくと、ごまかし笑いをして足早に立ち去った。
寛は、週に一度だけ来る日吉で講義を三コマ履修していた。いずれも単位がとりやすいと評判の授業だった。三田で履修している数コマと合わせて、その中からわずか八単位あれば卒業には足りるのだった。あとは書きかけの卒論を完成させれば問題なかった。
大学の講義で寛の知的好奇心を真に刺激したものは、ただの一つもなかった。高校で、あるいは中学で、あるいは小学校で、どんな授業があろうとどうでもよかったのと同じだけ、大学でどんな授業があろうとどうでもいいことだった。
だから、「和歌と短歌と日本史」というお題目の文学部系の講義も、ほとんどと言っていいほど内容に興味はなかった。担当の教授が使い古した講義ノートを見ながら訥々と喋るだけの講義は、実際何の面白みもなく、定員二百人の大教室に出席者は毎回四、五十名ほどだった。しかも、午後最初の授業ということもあって、出席者の半数近くが催眠にかかったように眠ってしまうのだ。
後方に一人で座っていた寛は、いつもと違って眠るどころではなかった。頭の中はピアノを弾いていた女の子のことでいっぱいだった。彼女が弾いていた旋律がいつまでも耳に残っていた。彼は、このときばかりは例外的に、自分の身に何が起きたのか分かった。一目惚れをしたのだ。
そのときだった。寛は、教壇に向かって緩やかに下っていく広い教室の前方の席に、彼女の姿を発見した。ピアノを弾いていた彼女だ。まったくの偶然だった。同じ講義を取っていたのだ。
寛は、ベートーヴェンがなぜ「ソソソ・ミ♭、ファファファ・レ」と作曲したのか、その内的動機を心の底から理解することができた。寛の心臓は、運命にノックされたように激しく打ちつけた。
寛は、今こそ、自分が何をしたいのか理解した。
何をしたいのか理解することと、実際それができるかどうかはもちろん別の話だった。
寛は、何とかして彼女と知り合いたかったが、講義で一緒になっても後姿を遠目に眺めることしかできなかった。彼にできたのは、毎日ひたすら彼女を想い続けるということだけだった。
「ドリア、注文入ってるよ!」
尾尻(高校中退、フリーター)がやや切れ気味に言った。
寛は白昼夢から覚めると、あわててドリアの皿をオーブンに入れた。
それも束の間、またしても尾尻が「なんだこりゃ!」と悲鳴をあげた。フライヤーに放り込まれたまま忘れられ、すっかり黒焦げになったポテトを引き上げたのだ。
「おれだ」寛は真っ青になってミスを申告した。
彼は二時間分の給料を引かれた。地元小田原でのファミレスのアルバイトは、時給八五〇円だった。
「お前、飯田成美って知ってる?」
客足が引いて暇になると、尾尻が前置きもなく言った。
尾尻は寛と同じ小中学校に通った同級生だった。高校は中退したとのことだったが、詳しい事情は寛も知らなかった。勤続三年の尾尻はシフトリーダーだったが、深夜勤務が多かったため二人が顔を合わせる機会はあまりなかった。寛としては、その方がありがたかった。
寛は、尾尻の口から彼が知るはずもない飯田成美の名前が出たので驚いた。飯田成美は寛の高校の同級生であり、元恋人でもあった。
「知ってるけど、なんで知ってるの?」寛は動揺して問い返した。
「世間は狭い」尾尻は詳しい説明はしなかった。
「あぁそう」
「高校のとき付き合ってたな」尾尻は事実を確かめるように言った。
「まぁ、そうかな」
飯田成美は、寛が初めて付き合った相手だった。色々な初めてを彼女と経験した。いい思い出もあれば、そうでないものもあった。
「彼女はそんな事実はないと言ってる」尾尻はどこか面白がるようにして言った。
寛は最初その言葉の意味するところが分からなかった。それから、意味を理解して、驚きに目を丸くして言った。
「なんで?」
「さぁ」
「どうして?」
「知らんな」
「直接聞いたのか」寛は質問の方向を変えた。
「いいや。友達の友達の友達の、そのまた友達が、その彼女と友達でね」
尾尻を追求しても埒が明かないようだった。
「彼女は、お前がアスペだとも言ってるらしい」尾尻はさらに言った。
「なんだって?」寛は耳を疑った。
「アスペルガー」尾尻は今度は略さずに言った。
アスペルガー症候群のことは寛も知っていた。発達障害の一つで、社会性、コミュニケーション、想像力に障害のある病気だった。人の輪の中で浮いてしまったり、暗黙の了解が理解できなかったり、分かりにくい話し方をするなどの症状があった。
「なんで?」寛は思わず強い口調になった。
「知らねぇよ」
尾尻はそう言うと、肩を震わせていっひっひと笑った。
寛は、小学五年生のとき、板書している担任の女性教師の太ももを食い入るように見つめていたところを、尾尻に大声で指摘されたことを突如思い出した。おかげでクラス中が彼のいやらしい行為を知ることとなり、大恥をかかされたのだった。
なぜ飯田成美がそんなことを言うのか、まったく見当がつかなかった。寛は、自分の女運の悪さを呪った。彼の多いわけでも少ないわけでもない標準的な女性遍歴は、そのまま心の傷の歴史だった。
大学に進学して間もない頃に付き合ったのは、百瀬桃子(フェリス女学院・音楽学部)だった。音楽サークルの交流を通して知り合ったのだ。
もともと見栄っ張りなところのあった桃子は、彼氏が慶應生ということが何よりの自慢で、フェリスの友人たちにも寛のことをあれこれ触れ回っていた。ただし、彼女には物事を自分のいいように誇張したり脚色したりする悪癖があり、寛はいかにもそれらしい人物として描写された。
彼は、IQ140の頭脳を持ち、自由が丘の高級マンションで独り暮らしをしていることにされたのだった。芸能人の友達が大勢いて、俳優や歌手を部屋に招いてはパーティに明け暮れているというのだ。父親は国際線のパイロットだということにされた。母親は元客室乗務員で、職場結婚という設定だった。
桃子は、寛に対して友人たちの前に絶対に姿を現さないよう要求した。ボロが出ないようにするためだったが、寛は否応なく従わされた。そのうち、彼女は自分が友人たちに伝えている話と寛の実像とがあまりにもかけ離れていることに耐えられなくなっていった。
思い込みの強い性格である桃子は、しまいには寛に対してまで自分のすてきな慶應生の彼氏のことを自慢するのだった。もはや寛にさえ、その幻の男と自分との共通点を見出すことができなかった。
交際から半年ほどで寛はふられた。その際にも、彼女の友人たちの同情を買うために、彼は死んだことにされたのだった。恋人のよしみで、寛は死に方を選ばせてもらうことができた。寛が選んだ死に方は、雷が直撃したことによる感電死だった。
「そしてぼくは稲妻を自在に操るダークヒーローとして復活する」寛は言ったが、その提案はあっさり却下された。
湯川るり子(神奈川大学・人間科学部)とは、大学二年の秋から付き合いはじめた。二日間だけの試験監督のアルバイトで知り合ったのだった。
湯川るり子は、百瀬桃子とは打って変わって、まったくおとなしい性格だった。おとなしすぎて、寛が話しかけてもうんともすんとも反応が返ってこないことも度々だった。電話で話しているときなど、ときどき彼女がちゃんとそこにいるのか不安になって、寛は「もしもし? 聞いてる?」と問いかけずにはいられなかった。不安を掻き立てる短い沈黙のあと、彼女はか細い声で「えっ?」と返事をするのだった。
当然のこととして、デートは気詰まりになることが多かった。彼女にはどこそこへ行きたいとか、何が食べたいといった望みもなく、寛は何も話さなくて済むようによく映画に誘った。
ストーリー展開にのめりこんだときなど、場内が明るくなってふと隣に目をやるとそこに彼女がいて、思わず声をあげて驚いたこともあった。映画に夢中になるあまり、存在を忘れてしまったのだった。
普段はおとなしいるり子だったが、二人で会っているときに携帯に電話がかかってくると、断りもせずに出るのだった。寛が話している最中でもお構いなしだった。るり子は、彼を放置したまま平然と長話に興じた。そういうときの彼女は、ぺちゃくちゃ喋り、けらけら笑い、普段とはまったく違っていた。
彼女が電話を切ると、寛は相手が誰なのか問いたださないわけにはいかなかった。しかし、彼女はいつも「別に。大学の子」程度にしか教えてくれないのだった。
三年生に進級したばかりの頃、寛は大学帰りの横浜駅で偶然るり子を見かけた。彼女はどこかの知らない男と腕を組み、見たこともないような笑顔で歩いていた。寛は大きなショックを受け、それから二度と彼女に連絡しなかった。彼女の方からも何一つ連絡はなかった。
そのあとが坂下みな実だった。
彼女との出会いは就職活動の場だった。坂下みな実はある売れない大所帯のアイドルグループに所属していたのだが、卒業後もアイドルを続けるか、それとも就職をするかで迷っていた。
ルックスは十人並みだったが、昨今のアイドル事情においてはそれでも十分通用した。しかし、就職活動においてはそれではまったく通用しなかった。ルックスどころか、歌や踊りも彼女より達者な素人がいくらでもいた。
坂下みな実は、将来に強い不安を覚えて精神の安定を失った。そうしたところへ、グループ内でいじめられるという事態が起きた。それまではどちらかと言えばいじめる側だったのだが、ついに順番が回ってきたのだ。
きっかけは、彼女が控え室でスナック菓子を貪り食べていたことだった。みな実にしてみれば、面接を控えた製菓会社の商品を試食していただけだったのだが、ダイエット中の他のメンバーがこれを無神経な振る舞いとして不愉快に思ったのだ。
いじめに怯え、精神安定剤を乱用したみな実は、混乱した行動を見せるようになった。会社説明会では他の就活生たちに「いつも応援ありがとうございます!」と言って握手して回り、ファンとの撮影会では唐突に就職の志望動機を喋りだした。マネージャーも事務所も何もしてくれなかった。
彼女は次第にアイドル稼業がいやになりはじめた。いったんそう感じはじめると、すぐにそれが大嫌いになった。グループのメンバーも大嫌いなら、業界も大嫌い、自分たちに与えられた歌も踊りも大嫌い、おまけにファンも大嫌いになった。
寛だけが彼女を見捨てなかった。彼は辛抱強く彼女の話に耳を傾け、愚痴や不安に理解を示した。しかし、それでも十分ではなかった。
みな実が「死んでやる」と言って展望台から飛び降りようとすると、寛は腰にしがみついてさせなかった。みな実が「死んでやる」と言って睡眠薬を大量に飲むと、寛は彼女の両脚を掴んで逆さに振ってすべて吐き出させた。みな実が「死んでやる」と言って車道に飛び出すと、寛は交通整理をはじめて事故を防いだ。
その挙句、「あんたなんか大嫌い!」と言われてふられたのだった。
結局、みな実は大学を休学した。寛は、ご存知の通り、度重なる不幸に見舞われて入院したのだった。
バイトのあとに立ち寄った市立図書館で、寛は飯田成美(東海大学卒・練り物屋の事務員)にばったり出くわした。
「なんでおれがアスペルガーなんだよ」寛は食ってかかるように言った。
「よしてよ、こんなところで」飯田成美は人目をはばかるようにして彼を表に連れ出した。
「噂を流しているのは本当にお前か」寛は昔の恋人を改めて問いただした。
「誰から聞いたの」
「バイト仲間の、友達の友達の友達の、そのまた友達が、お前から聞いたと言ってる」寛は、そう口に出してみると、自分の言ってることがひどく根拠薄弱に思えて弱気になった。
「私はそんなこと言ってません」成美はきっぱりと否定した。
「じゃあどうしてそんな噂が立つ」
「私って現実主義者なの」成美は、まるでそう言えば何をしても正当化されるとでもいうように、己の主義を標榜した。
高校時代に彼女と一年近く付き合った寛だったが、それでも彼女が現実主義者だったかどうか思い出せなかった。彼女ばかりでなく、同級生の誰も、どんな主義も持っていなかったような気がした。いずれにしろ、寛自身にはどんな主義もなかった。彼は何も信じられなかった。そのことは最近になって発見したわけではなかった。物心ついて以来、寛には信じられることなど何一つなかった。
「どうしてこんなこそこそ話さなきゃいけない」寛はバカげてると思って言った。人目をはばからなければいけない理由など何もなかった。
「大きな声出さないで!」
成美は鋭い語気で咎め、怯えたように周囲を見回した。まるで、こんなところを見つかったが最期、もうこれまで通りには生きていけないとでも言いたげだった。
「私が今何してるか知ってるの?」彼女は責め立てるように言った。
「いや」寛は少なくともこの一年、彼女を思い出したこともなかった。
「働いてるの」
成美は、大学卒業と同時に地元でよく知られた練り物屋に就職し、事務員として働いていた。彼女は、学生時代も今も実家に暮らしていた。現在交際中の恋人も、やはり地元に暮らし地元で働く二歳年上の会社員なのだという。
「邪魔されたくないの。分かるでしょ」
彼女の生活の基盤はここ小田原にあるということが言いたいようだった。
しかし、寛には分からなかった。彼もまた地元で暮らしていた。まだ身分こそ学生だったが、小田原市の住民だった。彼女の言い分はまったくの自分本位にしか聞こえなかった。それに、邪魔するも何も、今更彼女に何かしようなどと考えたこともなかった。
寛にとって、飯田成美は思い出の一つでしかなかった。だが、この女は二人が付き合っていたという事実自体がなかったと触れ回っているのだ。否定しているが、噂を流しているのはやはり彼女自身に違いないと寛は確信した。
「あなた、留年したんでしょ」成美は冷たく言った。
「どうして知ってる」寛は思いがけない反撃にあって動揺した。
「みんな知ってるわよ」成美は、なぜそこまでというほど、よそよそしく言った。
「どうして。誰から聞いた」
「友達の友達の友達の、そのまた友達から」
先ほどと同じ質問と同じ答えが、話者を入れ替えて発せられた。寛の劣勢だけが変わらなかった。
「おれに一体どうしてほしいんだ」寛は苛立って言った。
邪魔者扱いされなければならない謂れなど、どこにもないはずだった。どこかで話が食い違ってしまったに違いない。寛は原因を究明したかった。
「あなたって、基本的に私たちをバカにしてるのよね」成美は、昔のよしみなど微塵も感じられない、何とも疎ましげな目つきで寛を見た。
「何の話だ」
「留年までして、まだ大学生でいたいわけ。慶應義塾大学の」
彼女の口調は今や百万本の針のように尖っていた。高校時代に別れ話をしたときでさえ、こんなものの言い方をされた覚えはなかった。
「卒業できなかったんだ!」寛は成美の皮肉をはねつけた。「それに就職だって決まってなかった」妥協して、その事実も付け加えた。
「慶應義塾大学。画数の多い漢字ばっかり!」成美は攻撃の手を休めなかった。
「いいかげんにしてくれ!」寛はあからさまな当てこすりに我慢できなかった。
「言わせてもらうが、だいたい、大学なんて行きたくて行ってるわけじゃない。お前だってそうだろ。普通そうだろうが。大学に限らず、高校でも何でも。会社だって同じだろ。行きたくて行くわけじゃないだろ」寛は常日頃から感じていた不満を述べ立てた。
「そりゃ私が行った大学なんて行きたくないでしょうね、誰だって」成美は自分の好きなように解釈した。「東海大学。小田急線の東海大学前駅にあるのよ。駅から歩いて十五分。ずっと上り坂」
彼女はその道のりを四年間通った過去を思い出し、猛烈に頭に来たようだった。東海大学が小高い山の上にあることは寛も知っていたが、それは間違っても彼のせいではなかった。しかし、成美はそれさえ彼のせいにしそうな勢いだった。
「そういうことじゃなくて」寛は彼女の曲解を正そうとした。
「あなたの行ってる大学なら、誰だって行きたがると思ってるんでしょ」
「そんなこと言ってないだろ」寛は否定した。
「やっぱり。まるで自分の学校が優秀だみたいな口ぶり」成美は寛の発言を捏造した。
「だからおれはそんなこと言ってない!」寛は思わず声を荒げた。
「言いました」成美は確信に満ち満ちて言うのだった。
「なんて言いがかりだ」寛は、うっかり攻撃すると分裂して増殖するRPGのモンスターを相手にしているような気分になった。
「言っときますけど、そんなの思い上がりもいいところよ。私たちをバカにしないで」
何を言っても無駄だった。話せば話すほどすれ違い、憎み合っていくようだった。そのとき、寛はふいにまったく別の疑問にとらわれた。
「その私たちというのは誰のことだ」
「は?」
「私たち、と言った。私たちをバカにしないで」
「私たちは私たちよ」
寛は、つい最近どこかでその「私たち」という言葉と似た言葉を耳にしたような気がした。すぐに思い出した。それは「我々」という言葉だった。
「それは、我々ということか」
「は?」
「私たちというのは、我々のことか」寛は、自分がとんちんかんな疑問を口にしていることに気がつく余裕もなかった。
「同じことでしょ。どっちにしろ、あなたはそこに入ってないけど」成美は皮肉たっぷりに言った。
「なぜ」寛は歯軋りしながら言った。
「なぜでも」成美は間髪入れずに答えた。
「入れてくれと頼んだら?」寛はそのサークルの正体が掴めないまま、仲間に入りたいと熱望していた。
「無理」成美はあっさりはねのけた。
「なぜ」
「なぜでも」
寛の脳裏を、もう一つの恐ろしい言葉がかすめた。
「まさか、二十二条か」彼はたじろぎながら言った。
「二十二条?」成美は一瞬怪訝な表情を浮かべた。
「違うのか?」寛は一縷の望みを持って彼女を見た。
「いいえ」成美はやはり否定した。「違わない。二十二条よ」
寛は絶望の淵に立たされたような気持ちになった。
「あなたにはあなたの仲間がいるでしょ」成美は冷たく突き放して言った。
「いいや」寛は熟考してから答えた。「いないと思う」
「そんなことありえない」成美はそう言って去っていった。
富田林茂(小田原市内の公園管理事務所勤務)と素子(主婦)の夫婦は、寛の両親であった。
「自分だけ特別だみたいな顔をするな!」父親はだらしのない息子を叱り飛ばした。
寛がこれまで経験したあらゆる苦痛と苦悩は、父親から「そんなもの悩みのうちにも入らん!」と一蹴されるのが常だった。
「悩みがあるのはみんな同じ。他の連中の方がよっぽど悩んでいる。お前は何も分かってない!」茂はそう怒鳴りつけては息子の訴えを封じ込めた。
そもそも、寛は己の悩みをわざわざ報告するつもりなどなかった。ところが、茂が「悩みがあるなら言ってみろ」としつこく迫るので、仕方なしに、就職が思うに任せないことや人付き合いがうまくいかないことを打ち明けたのだった。罠にはめられたようなものだった。
不条理だとは分かっていても、寛はこの暴君と面と向かうと繰り返し電気ショックを与えられたモルモットのように萎縮して、何も口答えできなくなるのだった。
茂は、説教をして悦に浸るたびに「お前は間違っとる!」と宣告した。客観的に判断すると、だいたいいつも寛の方が正しかったが、そうすると子供が親よりも正しいということ自体が間違いだとされるのだった。
母親の素子は「お父さんの言うことが正しいよ」と言うばかりで何の助けにもならなかった。それどころか、彼女は幼少期から現在に至るまでの寛の失敗を面白がって近所中に話して回り、息子に大恥をかかせていた。
息子に対するひたすらの否定を重ねることを、富田林家では教育と称していた。寛が将来何をしたいのか未だに分からないでいるのも、この教育と無縁のことではなかった。
息子に偏差値の高い大学へ進学することを望んだのはまさにこの両親であったにもかかわらず、いざ寛が本当に偏差値の高い大学へ進学すると、彼らは途端に息子を敵視しはじめたのだった。しかも、留年した今となっては、寛はこの家で文字通りの冷や飯を食わされていた。
「お前がこれまでにやった一番の親孝行が何か知ってるか」父親は言った。
「いいえ」寛は、何も分かっていない能無しという割り当てられた役回りを演じて、言葉少なに答えた。
「お前の行ってるその何とか大学の学費が、他と比べて少しだけ安かったことさ」父親は嫌味たっぷりに言った。「私立にしてはな」
寛は天を仰いだ。こうして天を仰ぐたび、それが数センチずつ降下してきているのを彼は察知していた。やがて落ちてくる天に押し潰される日も、そう遠くなさそうだった。
絲山遼子(慶應義塾大学・文学部一年)というのが彼女の名前だった。
寛は、文学の講義で教壇にばらばらに提出される出席カードの整理を買って出て、彼女の名前と学部を突き止めたのだった。
彼は、糸が二つ並んだその漢字にえもいわれぬ魅力を感じた。苗字と名前は、画数の多い漢字と少ない漢字の組み合わせから成っており、その配列は横書きにしても縦書きにしても見事なバランスで見映えがした。知性を感じさせ、力強くて品があり、どこか謎めいていた。思わず口に出して呟いてみたくなる名前だった。
寛は、こっそりあとをつけ回すという古来から伝わる方法によって、自分が日吉に来る水曜日の絲山遼子のスケジュールを調べ上げた。一限が語学、二限が近代思想、お昼はピアノサークルの仲間たちと一緒に部室で過ごす。三限が寛と一緒の文学、四限が心理学。
絲山遼子はいずれの授業にもきちんと出席し、たいていは友人たちと一緒だった。なかなか隙がなかったが、四限が終わるとようやく彼女が一人になるチャンスが訪れた。心理学に一緒に出席した友人らと別れ、大学図書館で自習をするのだ。
翌週の水曜の午後、寛は学生会館の物陰に隠れて絲山遼子を待ち伏せた。彼女が図書館に向かうところを捕まえるつもりだった。
四限が終わり、絲山遼子が校舎から出てきた。寛は、彼女の姿を確認すると、食堂棟を回り込んでいったん日吉駅に向かって走った。逆方向から来たように見せかけて、図書館前で偶然を装って出くわそうという魂胆だった。
このときのために、寛は日本の古典文学に関する本を数冊借りて読んでいた。それらの本を返却するという口実にもなり、同じ講義を取っている彼女と話題にするにも自然だという計算だった。
寛は、平安貴族を気取って、彼女に贈るべく和歌も書いてみた。昔の貴族はそうやって女性を口説いたという話を講義で聞いたのだ。しかし、イマジネーションに欠ける彼にはまるで歯の健康週間の標語のようなものしか作れず、この案は却下となった。
図書館の前にある大学創設者の銅像の前で、寛は計算通りのタイミングで絲山遼子と出くわした。入口のところで、お先にどうぞと互いに譲りあう格好になった。
「あの」寛は、内心どきどきしながら声をかけた。「文学の講義で一緒だよね。三限の」
小柄な絲山遼子は、見上げるようにして寛の顔を確かめた。すぐに彼のことが分かったような表情になった。
「あぁ、そうですね。三限の」
寛は脈ありだと直感した。
「図書館?」寛は、聞くまでもないことだと知りながら、行く先を確認した。
「はい」絲山遼子は少し口元を緩ませた。
「おれも」寛はそう言って先を譲った。
入館ゲートを抜けながら鞄から本を取り出すと、寛はさりげなく彼女に題名が見えるようにした。「これを返さなくちゃ」
寛の言動は、何から何まで全然さりげなくなかった。
「文学にはちょっと興味があって」寛は格好つけて言った。「特に日本の古典文学にはね。自分たちがどんな言葉を使ってきたのか、その歴史を知ることは大事だと思うんだ。それに、物事を考えるときには、何でもルーツまで遡って考えないとね」
拾い読みした本のどこかに書かれていたフレーズの借用だった。
「私もそう思います」絲山遼子はおかしそうに笑いながら言った。
「自分と同じように考えている人がいるなんて嬉しいな」寛は、彼女が富田林寛という男に抗いがたい魅力を感じていると手前勝手に思い込んで言った。彼は、自意識過剰であるばかりか、調子に乗りやすい男でもあった。
「そういえば」寛は彼女にもう一歩近づく口実をひねり出した。「今日の講義だけど、レジュメをコピーさせてもらえないかな。欠席してしまったので」
「確か、出席されてたと思いましたけど」絲山遼子はすぐにこれがウソだと分かったが、礼儀を欠くようなことはなかった。
その日の文学の講義がはじまる前に、二人は一度目が合っていたのだ。寛が絲山遼子を探して小鳥のようにきょろきょろしているところへ、ちょうど彼女が近くのドアから入ってきたのである。寛はさりげなく目を逸らし、さりげなく授業の準備をするふりをしたのだったが、そのときの彼の行動もやはり全然さりげなくなかった。
「そう。そうそうそう。そうだった」寛自身もそのことを思い出し、慌てて辻褄を合わせようとした。「出席したんだけど、だからつまり、なんと言うか……」
「なくしちゃったんですか?」
「そう。それ。まったくその通り」
コピー機のある談話室で、寛は絲山遼子と十五分の会話をする機会に恵まれた。
絲山遼子は和歌山県出身の十八歳。地元の女子高を卒業した彼女は、大学進学のために単身上京したのだった。実家は老舗の和菓子屋で、六つ離れた兄がいるという。彼女の品のよさや落ち着いた雰囲気は、そうした環境で育まれたものだった。
祐天寺のマンションで一人暮らしをしている彼女は、授業が忙しくてアルバイトをする暇もなかった。語学が得意で、将来海外で働くことを希望しており、大学の勉強とは別にそのための勉強も進めているということだった。
まだ一年生の彼女がすでに将来を見据えているということに少なからず焦りを感じた寛は、思わず自分は週に一度日吉に来て学生相談室でカウンセリングを受けているのだと告白した。
「自分でも何が問題なのかはっきり分からないんだけど、問題があることは確かなんだ」
「きっと根が深いってことなんですね」
絲山遼子は寛の告白に真剣に耳を傾けて言った。寛には思いがけない言葉だった。
「そう思う?」
「はい」
「そうなんだ」寛は我が意を得たりと勢い込んで言った。「おれもそう思ってた」
未だかつて、自分には何か問題があるという己の考えにこれほど自信を持ったことはなかった。絲山遼子の優しさと率直さは、過去の女たちから受けた心の傷をすべて払拭してくれそうなほどだった。
「自分でもそう思ってたことは何となく知ってた気がするけど、今はっきりと分かった、自分がどう思っていたのか。どう思っていたか分かって、はじめて自分がおぼろげに思っていたことが何だったのか、はっきり理解できた。つまり、自分の中でもやもやしていたものをうまいこと対象化できたというか」寛は自分の身に起きたことを懸命に説明した。「ぼくには根の深い問題がある」
絲山遼子は、こらえきれない様子で、それでも控えめに笑った。
「ごめんなさい。笑っちゃいけないんですけど、でも、富田林さんって面白い人ですね」
「そうかな」寛は、自分ではよく分からずに言った。
「私、自分が真面目で面白くないので、すごいと思います」
「そうかな」寛は、なんとなくよく思われているように感じて気をよくした。「あの、よかったらまた話したいな」
「はい。是非」絲山遼子はそう言ってにっこり笑った。
カウンセリング四年間分よりも効果のある十五分の会話だった。寛は、小田原までの一時間半の道のりを、絲山遼子との会話を何度も反芻しながら帰った。
絲山遼子とゆっくり話す機会を持てないまま、すぐに前期試験の時期になった。
単位を落とすわけにはいかない寛だったが、彼女の姿を一目拝みたいがために、わざわざ講義のない日に日吉キャンパスに出かけた。前の週の水曜は、企業の面接が入ってしまって文学の講義に出席できなかった。その前の週の水曜は、教授の都合で講義が休みになっていた。二週続けて彼女に会えなかったのだ。
日吉に来たところで彼女に会える確証はなかったが、寛は何かに突き動かされるようにしてキャンパスを探し歩いた。思いが通じたのか、混み合う大学図書館を見て回っているとき、寛は三階の隅の席で勉強する絲山遼子を見つけることができた。
ところが、いざとなってみると声をかける勇気が出なかった。書架の間を行ったり来たりするばかりで行動を起こせないでいると、絲山遼子がふと顔をあげた。寛はついに思い切って手を振ってみた。彼女はにっこり笑って手を振り返してくれた。
それだけで天にも昇る気持ちになった。
夏休みに入ってまもなく、寛は京都に来ていた。
「和歌と短歌と日本史」の講義で、勉強会をかねた京都旅行が計画されたのだ。主催は担当教授の高山(慶應義塾大学・文学部教授)だった。もちろん絲山遼子も参加していた。彼女が参加すると知ったため、寛も参加することにしたのだ。
実を言うと、絲山遼子から聞かされるまで彼はこの企画自体を知らなかった。試験がすべて終わり、ねぎらいのメールを送るついでに夏の予定を訊いてみたところ、彼女がこの旅行のことに触れたのだ。講義の中で何度となく説明があったらしいが、寛は完全に聞き逃していた。
彼はすぐさま高山教授に連絡した。申し込みはとっくに締め切られていたが、そこを何とかと拝み倒して参加を許可してもらった。一泊二日の旅だった。二日間ともファミレスのバイトが入っていたが、それも尾尻に頼み込んで代わってもらった。
参加者は高山教授を含めて十四名だった。京都に現地集合ということで、多くの者は新幹線で来ていた。飛行機という者もいた。寛だけが、安上がりな青春十八切符で来たのだった。
講義で扱った和歌や短歌と縁のある名所旧跡を訪ね歩くのが、勉強会の目的だった。堅物の教授は、観光しながら授業のときと同じように話をし、学生たちに京都に来てまで講義を受けているような気分を味あわせた。
絲山遼子と二人きりになる機会に恵まれないまま、夜になった。
ホテルにチェックインすると、教授の部屋に集まって飲もうという話になった。寛は気乗りしなかったが、絲山遼子が参加するとなれば行かないわけにはいかなかった。
一同は車座になって座り、そこでもまた古典文学の話をするのだった。それだけではなかった。国家間の紛争について、福祉制度について、古代文明から学ぶべきことについて、これからのエネルギー資源について、税金の使い方について、二十一世紀の芸術について、ありとあらゆるトピックについて議論が交わされたのだった。今度は学生たちも活発に発言した。まるで国連総会だった。
寛は一度、ユーロ諸国の財政状態についてどう思うか、経済学部に在籍するものとして専門的な意見を求められた。しかし、彼はどうやって絲山遼子と二人きりになるかばかり考えていて、ろくに話を聞いていなかった。そもそも、彼はリボ払いというものがどういう仕組みなのかさえ理解できない経済学部の学生だった。
寛がうまく答えられないでいると、一同は彼に話を振ったことなどなかったかのように議論を続けた。やがて、夜も更けると会はお開きとなった。取り上げられた問題のいずれが解決したわけでもなく、世の中が一ミリでもよい方向に動いたわけでもなかったが、各自がそれなりに満足を得たようだった。
寛はパンクしたタイヤのようにぺしゃんこな気分だった。それでもへこたれず、ちょっと外の空気を吸いに行かないかと絲山遼子を散歩に誘った。彼女は少し疲れた顔をしていたが了承してくれた。
「夜の、京都だね」
寛は言った。確かに夜の京都だった。二人きりになったらああしてこうしてと、何百万通りものシミュレーションをして備えていたはずだった。しかし、そういいように事を運ぶことはできなかった。
「私、留学するんです」絲山遼子が思いがけず言った。
寛は、突然もたらされたこの情報によって思考停止に陥った。彼は、必死に手繰り寄せた命綱が途中で切断されていたのを発見したかのように、ショックに言葉を失った。夜の京都は、まるでこの世の終りだった。
「留学?」
「はい」
「誰が?」
「私です」
「いつから?」
「八月半ばには発つ予定です」
「す、すぐじゃないか!」
「すぐです」
「どこに?」
「カナダのマギル大学というところに」
「マギル大学」寛は恨みがましい口調でうなるように言った。「レナード・コーエン、バート・バカラック、ジノ・ヴァネリ、ウィリアム・シャトナー」
いずれも寛が知っている著名なマギル大学卒業生の名前だった。芸能関係に偏ってはいたが、そのリストを見るだけで優秀な人材を輩出する大学だということが分かった。だが、そんなことは彼にはどうでもよかった。
「いつまで?」
「最低でも一年」
「一年!」寛の声はリアクション芸人のように裏返った。
「もしかしたら、二年」
目の前が暗くなった。寛は、彼女を乗せた旅客機が音速を超えるスピードで遠ざかっていくイメージに襲われ、目眩に倒れそうになった。音速とは秒速約340メートルで、そうすると飛行機が飛び去る音を目で見るよりあとに聞くことになるのだ。
「あぁカナダ」
寛は、ジョニ・ミッチェルの歌にあるように口の中で呟いた。
カナダはとてつもなく遠かった。英語とフランス語が公用語で、森林地帯が多く、アイスホッケーが盛んだ。そして何より、寛にはまるきり縁のない国だった。
「おれはみんなに嫌われている」寛は沈痛な面持ちで言った。
何もかもが手をすり抜けていくようだった。どこに行っても仲間はずれにされ、いつも彼だけが蚊帳の外なのだ。さっきの国連総会かと思うような宴会の席でもそうだった。
寛は、この旅の参加者たちを「いやになるほど精神のまともな連中」と感じていた。それだけではなかった。彼を取り巻くすべての人々が「いやになるほど精神のまともな連中」なのだった。そして、みんなが寛を仲間はずれにするのだ。
寛はこれらすべての人々を忌み嫌った。声をあげて泣きたいくらいだった。カナダという言葉が彼の頭の中でこだました。カナダ、カナダ、カナダ、カナダ、カナダ……。カナダという言葉をこんなに連発したことは、かつて一度だってなかった。彼は、猛烈にメイプルリーフクッキーが食べたくなった。もうどうにでもなれだ。
「どうしてそんなこと言うんですか」絲山遼子は悲しげに言った。
「それが事実だから」寛はやけくそだった。
「私には、富田林さんが嫌われていると言うより、富田林さんが他の人のことを嫌っているように見えます」
寛ははっとなって絲山遼子を見た。しかし、彼にはまっすぐ訴えかけてくる彼女の目を直視することができなかった。
「こっちが嫌いだから」寛は弁解した。「みんなから嫌われてるように感じるのか。あるいは、みんなから嫌われてるように感じるからこっちも嫌いになるのか。どちらが先か分からない。卵が先か鶏が先かの関係なんだ」
「としたら」絲山遼子は努めて理性的に言った。「好きになれば、好かれてると思えるようになるんじゃないでしょうか」
寛には返す言葉がなかった。
旅の二日目は、絲山遼子と口を聞くこともなく終わった。
一行は京都駅で解散した。絲山遼子はこのあと和歌山の実家に立ち寄るということだった。他の学生たちもこのまま別のところへ旅行に行くなどする者がほとんどだった。
寛は、またしても一人で、青春十八切符で、小田原まで帰った。
一年は長すぎた。二年ともなれば、ほとんど永遠だった。
寛は絲山遼子のことを忘れようと、延び延びになっていた卒論の完成に集中した。すでに書いてあった分も大幅に書き直し、さらに予定していたよりも倍近くの分量を書き足してそれは完成した。これほど何かに打ち込んだことは久しくなかった。
夏休みがあけて最初のゼミで、寛は沼尾教授が数年ぶりに発表したという論文を目にすることになった。一読して愕然となった。教授の論文は、寛が昨年度にいったん未完成で提出していた論文から論旨やフレーズをいくつも借用していたのだ。
「どういうことですか」寛は、沼尾教授の研究室に乗り込むと怒りを滲ませて問いただした。
「なんだね」沼尾教授はしらばっくれて言った。
「これはぼくの論文だ」寛は論文が掲載された研究誌を机の上に叩きつけた。
「違うな」沼尾教授は顎を撫でさすりながら一考して言った。「これは私の論文だ」
「おれの卒論からパクりまくってる!」寛は思わず声を荒げた。
彼は盗用された文章を蛍光ペンでマーキングしていた。まったく同じフレーズを用いているところだけでも、その数は三十以上に及んだ。段落ごとそっくりそのままコピーされている箇所もいくつかあった。
「そういうことを気安く言うもんじゃない」教授は眉一つ動かさずにぬけぬけと言った。「ところで、きみの新しい卒論に目を通させてもらったが、このままでは私の論文の盗用と考えざるをえないだろう。改稿して再提出してもらう必要がありそうだ。いっそ、別のテーマに変えた方がいいかもしれないな」
寛は完成した論文をすでに提出していたのだった。一度ならず二度までも致命的なミスを犯していたことに、今更気がついた。
「あんたがおれの論文を盗んだんだ」寛は糾弾した。
「私の論文は完成し、発表されている。苦労の甲斐あって好評を博しているよ」教授は厚かましくも言った。
「きみの論文はそれよりあとに完成したものだ。発表もされていない。これをどう説明するかね。もっとも、優れた教師の教えがまだ論理的思考力のない学生に大きな影響を与え、似たようなことを考えるに至るという例はいくらでもあるが」
何を言っても手遅れだった。汚い真似をする人間は用意周到にするのだ。寛は自分が敗北を運命づけられた男であることを改めて思い知った。シャドーボクシングでさえ負ける男、それが富田林寛だった。
「訴えてやる」寛は歯ぎしりしながら言った。
「つまらない真似はよしたまえ」教授は笑っていなした。
「富田林くん、私がきみの指導教授だ。きみの問題は私が処理する。私の権限でいかようにもできるのだよ。もし、それ相応の振る舞いをするなら、大学院に口をきいてやらないでもない。きみはまだ進路が決まっていない。違ったかね? 学問はいいものだよ。きみもやってみたらどうだ」
寛は、最も握られたくない人物に己の運命を握られているのだった。絶望というより他なかった。
「それ相応の振る舞いとはなんだ」寛は言った。この薄汚い男は、あまりにもあからさまに不誠実な取引を要求しているように思われた。
「それ相応の振る舞いとは、それ相応の振る舞いだ」教授は答えた。
「まさか」寛は突如恐ろしい考えに襲われた。「二十二条か」
「二十二条?」沼尾教授は一瞬眉をひそめた。それから何か心得たような表情になって、薄気味悪い笑みを浮かべて言った。「もちろん二十二条だ」
寛は、またしても現れた正体不明で理解不能の学則を前に、どんな抵抗も無力と化してゆくのを感じた。
「あんたは自分のしていることが分かってない」寛は最後の力を振り絞って言った。
「私は何もしていないよ」教授はいつもの返答をよこした。
寛はその足で学生課に向かった。
対応した職員に事情を話すと、ふいに相手が「しかし、学則二十二条がありますので」と言葉を濁した。寛の顔からさっと血の気が引いた。どこに行っても二十二条が現れるのだった。彼はよろよろと後ずさるようにして逃げ出した。
「富田林くんだろ?」
ある企業の面接の待合室で、寛は一人の就活生から声をかけられた。見覚えのある顔だった。
「大木だよ」男は言った。
寛と小学校で同級だった大木(明治学院大学・国際学部四年)だった。
「こんなところで会うとはね。小学校卒業以来じゃないか? おれは一浪したんだけど、富田林くんは留年したんだって? 地元の友達から聞いたよ。同じ会社を受けるなんて偶然だね。おれなんか落ちまくりだよ。もうすぐ百社。不採用不採用不採用。どこ受けてもダメ。何がいけないんだと思う? 先輩とかに聞くと数撃ちゃ当たるって方法しかないって。でも百社だよ、百社。富田林くんはどうなの? きみが通ってるような大学だとやっぱり違うわけ? おれは明治学院なんだけど、時代がどうのって言ってもやっぱり大学名がでかいと思うんだよな。ていうか、結局それが決め手っていうか。ま、お互い正々堂々やろうよ」
大木は一人で喋り続けた。彼がこんな男だったかどうか、小学校三、四年辺りまでしか付き合いのなかった寛には思い出せなかった。
グループ面接で、寛は奇遇にも大木と同じグループに振り分けられた。内定まであと一息というところまで来ていた。
「この男はいじめっ子です!」
大木が突然立ち上がって、寛を指さして高らかに宣言した。
「小学生のとき、ぼくをいじめました!」
三人の面接官は眉をひそめ、それから手元にある二人の履歴書を見比べた。そこに同じ小学校名が記されていることは間違いなかった。
寛はいきなりの展開にうろたえた。そう言われてみると、大木を木製の三十センチ物差しで叩いて泣かせた記憶がかすかにあった。しかし、一度きりだったはずだし、いじめというほどのものとは思えなかった。
面接官たちは見定めるような目で寛を見ていた。そればかりか、他の就活生たちも同じような目で彼を見ていた。その途端、寛は自分が試されているのだと気がついた。
「ち、違います、違いますよ!」寛は顔の前でぶんぶん手を振りながら言った。
「何が違うんだね」面接官の一人が慇懃に言った。
「この男はいじめっ子です!」大木がよく通る声でもう一度訴えた。
大木は過去のつらい記憶を思い出したかのように目を潤ませ、唇を噛みしめていた。正々堂々やろうと言った者が取る言動とは到底思えなかった。
「とにかく違うんです」寛は落ちつかなげに足をぱたぱた動かした。
「証明してみてくれませんか」別の面接官が言った。
「証明?」
その場の全員が寛に注目した。彼は潔白を証明しなければならない立場に追い込まれた。しかし、いじめていないということを一体どうやったら証明できるのか、いくら考えてみても分からなかった。
「この男はいじめっ子であります!」大木が追い打ちをかけた。「私は明治学院大学、国際学部の大木と申します! 過去のいじめ体験にもめげず、御社で身を粉にして働きたいと考えております!」
居合わせた者たちが拍手で称えた。寛はもはや挽回のしようがなかった。
これでは去年の失敗の繰り返しだった。
未だ就職が決まらず、卒論は白紙に戻り、そしてまたしても恋に破れたのだった。このままではどうにもならないと分かってはいたが、どうしたらいいか考えてみたところで何も思いつかなかった。
富田林寛を歓迎してくれる場所はどこにもないということが、今や明らかとなった。もがけばもがくほど深みにはまる底なし沼に落ちたような気分だった。
「尾尻って、どうして学校やめたの」
寛はふと気になって、若鶏の甘酢炒めの定食セットを盛り付けながら訊いた。
「くだらないから」尾尻は巧みなヘラ捌きで二枚の厚切りステーキを焼きながら言った。
「くだらない」寛はおうむ返しに言った。
「くだらねぇよ」
「そう思うか」寛ははっとなった。
「そう思うかとは何だよ」
「いや、おれも最近同じようなことを考えてたもんで」寛は思いがけないところで友を見つけたような気持ちだった。
「へぇ」尾尻は、しかし、小馬鹿にしたように笑った。「でも、お前はそんなことしない方がいいぞ」
「どうして」寛は不服そうに言った。
「お前は一人じゃ何もできないからさ」尾尻は声をあげて笑った。
「分かってるのか? 今までここに入ったバイトで、皿の洗い方さえろくに知らなかったのはお前だけだぞ。高校一年のバイトにさえ、お前は使えないお坊ちゃんだと思われてるんだ。最初なんか火の付け方さえ知らなかっただろうが」
寛は思わず頬を赤らめた。それは本当のことだった。しかし、今では皿の洗い方も火の付け方もちゃんと分かっていた。青春十八切符を使って一人で京都に行くことだってできた。失恋したあとでも迷わず帰ってくることもできた。そんじょそこらのお坊ちゃんには、こんな真似はできまい。
「富田林! フロアの片付け行って!」
寛の動きが悪いので、店長の高橋(駒澤大学・経営学部卒)は指示を出した。
高橋は、昨年寛に対して「もしその気があるなら、うちで社員登用できないこともない」と話を持ちかけたところを、たいして考慮もされずに断られて以来、彼に冷たい態度を見せるようになっていた。そこにきて、寛が七月に無理やりシフトを代わって旅行に行ったのに土産の一つも買ってこなかったことから、その冷たさには拍車がかかっていた。
ランチタイムの混雑はピークを迎えていた。会計が済んだテーブル席をあわてて片付けはじめた寛は、小鉢を取り落として割ってしまった。小さい食器だったが、割れる音だけは惜しげもなく大きかった。
「失礼いたしました!」
寛は、客というよりもむしろスタッフに向けて言ったが、店長の苛立ちの視線が背中に突き刺さったのを感じないわけにはいかなかった。もうすぐ四十になる店長の高橋はまだ独身で、この五年というものは恋人さえいなかった。
そこへフロア担当の女子高生バイトの柴田(私立相洋高校二年)が、状況をさらに悪化させる報告を持って厨房に戻ってきた。
「クレームつけられました」柴田は、自分のせいではないことで客に頭を下げなければならなかったときに裏でいつも見せる不快さに歪んだ顔で言った。やや舌足らずな喋り方をする女の子だった。機嫌がいいときには、その喋り方はとてもかわいらしかった。
「何?」店長の高橋は、相手が若い女の子だからといって少しの愛想を見せることもなく訊き返した。彼は柴田を見もしなかった。
「クリームつけられたって言ってます」柴田が、堂々とふて腐れて説明した。
「だから何」店長が、せかせかとご飯を盛りつけながら、再び彼女の方を見もしないで言った。
「クリームつけられたって」柴田は、洗浄機にがちゃがちゃと食器を突っ込みながら、うんざりして繰り返した。
「だから、何て」店長は語気を強めて問いただした。
柴田の説明は店長には通じていなかった。彼女はクリームをつけられたというクレームをつけられたのだ。だが、飛び交う雑音と彼女の舌足らずな喋り方のせいで、高橋にはクレームとクリームを聞き分けることができなかったのである。
「クレームです」柴田は、もはや明らかな敵意を見せながら声を張った。
「だから、どんな!」店長もまた苛立ちをあらわにして声を荒げた。
柴田の舌足らずで若者じみた平坦な発音にも問題がないわけではなかったし、店長の己の仕事に対するほとんど憎悪と言ってもいい感情ゆえのスタッフへの思いやりを欠いた態度にも問題がないわけではなかったが、厨房のあわただしさと店内の喧騒の中で、話は混乱の一途を辿った。
「クリームつけられたんですよ!」柴田は悲鳴をあげるように叫んだ。
「だからどんなクレームかって訊いてんだよ!」店長がフロアにも聞こえるほどの声で怒鳴り返した。彼は女子高生が嫌いだった。特に、学校の制服姿でないときの女子高生が大嫌いだった。
「クリームつけられたって!」柴田も負けてはいなかった。彼女の声は興奮で甲高くなり、ますます何を言ってるのか分からなくなった。
「何言ってんだよ!」店長はもどかしげに叫んだ。
「クレームだっつってんだろ!」柴田は育ちの悪さを丸出しにして言った。
「だからどういう内容なんだよ!」店長は怒鳴り返した。
「だから! クリーム!」傍で聞いている者にも、もはやクリームともクレームとも、どちらとも聞きたいように聞こえた。
「あぁもう!」店長は両手で宙を無茶苦茶にかき乱し、話にならないと投げ出した。
「デザート皿に残ってたやつ! 多分プリン・ア・ラ・モード!」柴田は少しも引き下がる様子を見せず、詳しい内容に踏み込んで言った。
これを聞いた寛は、さっと血の気が引いた。身に覚えがあったのだ。先ほど食器を下げたとき、クリームの少し残ったデザート皿を乗せていたのだ。おまけに客とも接触していた。すれ違いざまにわずかにかすっただけだったが、そのときにクリームをつけてしまったに違いなかった。
「は?」店長は眉間に深いしわ作った。
「だから、そのクリームつけられたって客が怒ってんだよ!」柴田が金切り声を上げた。
「クリームつけられたのか!」店長はようやく事態を理解した。
「最初からそう言ってんだろうが!」
「いつ? どこに?」店長は今や怒りの矛先を変えつつあった。
「多分、富田林がさっき食器下げたとき! 客のスーツに!」寛は女子高生に呼び捨てにされた。
「スーーーーーーーツ!」店長の頭に「クリーニング代として一万円」という言葉が急浮上した。「とんだばやしーーーっっ!」店長は声の限りに叫んだ。
寛は思わずフロアに逃げ出していた。
ところが、彼は店の真ん中で突如呪いにかかったように立ちすくんでしまった。この世のものとは思えない恐ろしい光景が、彼を取り囲んでいたのだ。
店内は彼の顔見知りで溢れかえっていた。
寛の恥ずかしい過去を知っている小学校の同級生がいた。中学校の部活で先輩だった意地の悪い男がいた。理不尽に叱られてから一度も口をきいていなかった数学の教師がいた。近所に住む不良姉妹がいた。この姉妹は、その昔田んぼの真ん中で寛の服を無理やり脱がせて裸にしたことがあった。所属していたリトルリーグのコーチがいた。このコーチはどんな負け試合であろうと決して寛を起用しようとしなかった。昔ちょっと好きだったファーストフード店の店員が恋人らしき男と来ていた。勉強が忙しいとウソをついて一月足らずでバイトをやめた雑貨屋のオーナーがいた。飯田成美もまた恋人らしい男と来ていた。親戚の伯父夫婦までいた。
いずれも寛が会いたくない人々だった。全員が彼を指さし、腹を抱えてその失敗を笑っていた。まるで地獄だった。寛の視界がぐるぐると回った。とどめに、店内の有線で「ゴッドファーザー 愛のテーマ」が流れ出した。
寛は、突然下腹部に刺すような鋭い痛みを感じた。このような事態に陥って、彼はどう振る舞うべきか分かっていた。
寛は気を失って、その場に倒れた。
「こいつは仮病を使っとるだけです」
偶然ファミレスに居合わせた兄夫婦から連絡を受けた富田林茂と素子の夫婦は、あわてて病院に駆けつけた。しかし、息子のどこにも外傷がないことを見てとると、この父親は医者に食ってかかったのだった。
「急性虫垂炎かと思いましたが、そうではないようです」医者は所見を告げた。寛は救急車で運び込まれたのだった。今回もまた小田原市立病院だった。
「だから仮病だと言ってる」父親は言い張った。
「おそらくストレスや過労から来るものでしょう」
「過労!」茂は叫んだ。「働いてもいないのに!」
寛には、父親が自分に恥をかかせるためにわざと大声を出しているとしか思えなかった。時代錯誤なこの父親にとって、アルバイト労働など仕事のうちに入らないのだった。
「それにストレスときた!」この暴君は、常日頃から精神という掴みどころがないものの存在を認めようとしなかった。「こいつは甘ったれとるだけですわい!」
寛は、慣れ親しんだ虚無感が今また霧のように立ち込め、自分をすっぽり包み込むのを感じた。
無抵抗主義者と化した彼は、父親によってされるがままにベッドから引きずり出されそうになったが、医者と看護師がなんとか食い止めてくれた。両親があきらめて帰っていくと、寛は脇腹の痛みがいくらか和らぐのを感じた。
「あの教授がそういうことをしかねない人間であることは確かだ」
見舞いに訪れた世良は言った。ケンブリッジ大学で開かれていた学会からカイロ大学で開かれる学会への移動中に、回り道をして小田原の病院に立ち寄ったのだ。
「しかし、そんなことはしないと思う」世良は公平を期すかのように付け足した。
「今お前が言ったことを合わせて考えると、わけがわからなくなる」寛は気だるげにまばたきをしながら言った。
「彼自身はなんて言ってる?」
「私は、何もしていない」寛は教授の言い草を思い出して憂鬱になった。
「やはりな」
「でも、したんだ」
「あるいはそうかもしれない。でも、してないんだ。あの教授は次期学部長になるという噂だ」
「何?」
「まぁ、すぐにおれがその座を奪うことになるわけだが」
「論文のことはもういい」
寛は賢明にもその話題に深入りすることを避けた。この一件もストレスの大きな原因になっていたため、無理に考えたくなかったのだ。
「それより、おれには考えていることが……」寛は身体を起こしながら言った。
「ぬあっはっはっはっはーっ!」
そのとき、病棟の彼方から低くてよく響く、まるで黄金バットのような笑い声が聞こえてきた。
「おれは世界最軽量のブリーフケースを作ることになるだろう」常盤が喋りながら現れた。
「本当のところ、こいつはブリーフケースじゃない。ロボットなんだ。必要が生じたらボタン一つで変形し、主人であるサラリーマンと合体してスーパーロボリーマンに変身だ。会話機能も搭載して商談のパートナーになれるようにしたい。世界中のありとあらゆる言語に対応できるものになるだろう。世良、その辺のことでちょっと協力しろよ。ところで、おれは今ハンスト中で忙しい。だがこいつがうまくいけば、おれが作った法案が議会に通る可能性が高い。都内の地下鉄をすべて高架にするという法律だ。実現したらすごいことになるぜ。おれは地面の下が好きじゃないんだ。モグラみたいな気分になるからな。はっはっは。富田林、元気そうで何よりだ。それじゃあまたな。安達と岸和田にもよろしく言ってくれ」
常盤は来たときと同じように笑いながら去っていった。
安達と岸和田はすでに見舞いに来て帰っていた。二人は、安達の所有する瀬戸内海の島から女の子同伴でヘリコプターでやって来て、帰るときにはまた別の女の子を連れて帰っていったのだった。
「それでだな」寛は切り出しかけていた話を続けた。
「おれは大学をやめようと思う」
寛は言ってしまうと心が楽になるのを感じた。
「どういう意味だ、大学をやめるというのは」世良の顔に当惑が浮かんだ。
「やめる。退学するんだよ」
「そんなことはできないぞ。二十二条を忘れたのか」
「二十二条」寛は険しい目つきで中空を見据えて言った。「それが一体何なのか、誰もはっきりと知らない。調べてみたんだ。だが、学則二十二条なんてものはどこにも書かれていなかった。それは存在しないんじゃないか?」
「するさ」世良は顔を強張らせた。「誰でも知ってる。知ってるからこそ我々なんだ」
「その我々もだ!」寛は叫んだ。「おれにはそれも分からない。我々とは何なんだ?」
「富田林、質問が間違っている。我々がまさしく我々である限り、我々のことを客観的に定義することはできない。我々は我々の外にはいない。我々はその中にいるんだ」
「世良、お前はうまくやってるのか。そこで。その中で」
「おそらくそういうことになるだろう」
「そうするとどうなる? その中でうまくやり続けるとどうなるんだ?」寛はその先を知りたくてたまらなかった。
「どうなる? ただうまくやり続けるだけさ」
「どうにもならないのか?」
「どうもこうもない。やれるだけやり続ける。それだけだ」
「我々とは、宇宙人か何かなのか?」寛は半ば真剣な気持ちで訊ねた。
「そんなことを訊いてはならない」世良もまた真剣な気持ちで答えた。
「とにかく、おれはどんな我々の一員でもない。おれの方から御免蒙るよ」
「そんなことは不可能だ」
「やってみるさ。おれはおれの道を行くことにする」
「どの道?」今度は世良が寛を質問攻めにする番だった。
「おれの」
「どんな?」
「分からん」
「そいつはよした方がいい」
「でも、それしかなさそうだ」
「よく調べてみたのか」
「調べるも何も、おれにはこれしかない」
「その道にはどんな保証がある?」
「分からん」
「その道を進むとどこに出る?」
「分からん」
「おれの知ってる限りじゃ、どんなギャンブルにだって攻略法はある。絶対にだ」
「おれの道にはないんだ」
「そんなまさか」論文が三万部売れても動じなかった男が、心底驚いた様子で言った。
「そのまさかだよ」
「お前、死ぬ気か」
「そんなひどいことにはならないと思う」
実のところ、寛が学校をやめると言い出したのは、これが初めてではなかった。はるか昔、まだ小学一年生のときに彼は宣言したことがあった。
「学校に行きたくない」
両親の返答は、この時点からすでに華麗なる論理のすり替えを特徴としていた。
「大学に行くのが当たり前」
寛は小学校のすべての学年において、中学校のすべての学年において、高校のすべての学年において、同じ要望を言ったのだった。しかし、そのたびに同じ返答によって希望を打ち砕かれていた。
大学にはもう行った。そこには何もなかった。小中高大、十六年間の学校教育。何もなし。十六年もの長い間、冤罪で牢獄に放り込まれていたようなものだった。これよりひどい話があるなら聞きたいくらいだった。
寛は、自分が何をしたいのか、今ようやく理解したのだった。
自分をだまして生きることはできなかった。それが問題の核心だった。
この八方塞がりの状況にけりをつけ、一人になって最初からやり直すこと。それこそ彼に必要なことだった。
「やめます」
寛は三田キャンパスの学生事務局のカウンターで言った。
対応した職員は「今なんと?」「確かですか?」「本当に?」と何度も意思を確認した。寛はどの質問にも迷いなく「やめます」と答えた。
異例の事態に、事務局が騒然となった。しかし、彼の決意が断固としたものであると見てとると、事務局側はついに手続きを取ることを承諾した。
退学届けを提出するには、寛が在籍する経済学部の学部長と面談し、承認印をもらうことが必要だった。
寛は職員の案内で学部長室に通された。教員棟の五階、長い廊下を抜けた先にその部屋はあった。
ドアノブに手をかけたとき、ふと嫌な予感がした。予感は的中した。正面にある横幅が三メートルくらいありそうな重厚な書斎机に座っていたのは、沼尾教授だったのだ。
「あんたは学部長じゃない」寛はすばやく警戒態勢になって言った。
「学部長は多忙で不在にしている」沼尾教授は、時代劇の悪役さえ善人に思えるほど根性のひねくれた笑みを浮かべて言った。「私が留守を預かってるんだ。次期学部長の私が」
「判子がほしい」寛は余計なことは言わず、机の上に退学届けを差し出した。
「そんなものはただの紙切れだ」沼尾教授は鼻にもかけない調子で言った。
「なら勝手に押させてもらう」
寛は机の端にあった学部長印に手を伸ばした。すると、沼尾教授は「おっと」と言ってすばやくそれを手繰り寄せた。寛の手は空を切った。
「あんたはおれの邪魔ばかりする」寛は相手を睨みつけて言った。「なぜだ?」
沼尾教授の陰険な目がぎらりと光った。
「知りたいのなら教えてやる。貴様は一年のとき、私の経済学の講義を履修した。講義には出席していた。しかし寝てばかりだった。毎回欠かさずだ。しかもかなり前列で。いやなら出席しなければいい。寝るなら後ろの方に座ればいい。そのくせ試験となるとやたら高得点を取る。貴様は私を一体なんだと思ってるんだ。私の講義と、私の研究を」
「よく知らない」寛は持ち前の正直さで答えた。
寛の正直さは、時と場合をわきまえずに発揮されることがあり、しばしば災いの種となることがあった。実際のところ、一年のときに受けた沼尾教授の講義の内容など、彼は何一つ覚えていなかった。
沼尾教授は怒りに顔を紅潮させ、鼻息を荒くした。その鼻息で退学届けがひらひらと宙を舞った。
「判など押さんぞ!」沼尾教授は両手で机を叩き、飛び上がるようにして立ち上がった。「ついでに言っておいてやる。貴様の名前は変な名前だ。とんだばやし! ひろし! くそっ、韻でも踏んでるつもりか!」
「それはおれのせいじゃない」寛は場違いな指摘に頬を赤らめた。子供の頃から気にしていたことだった。
「いいや、貴様のせいさ。何もかも、悪いことがあったときは貴様のせいに決まってる」
「ならおれも言わせてもらう」寛はやられっぱなしになるつもりはなかった。
「あんたは本当はこの大学の出身じゃない」
「なんだと?」
「調べたんだ。あんたが卒業したのは専修大だ。慶應出身であるようなふりはしているがな。あんたは仲間になるのに必死なんだ。我々とやらの仲間に」
沼尾教授(実は専修大卒)は、顔面蒼白になって全身を硬直させた。喉の奥からしゅーしゅーと奇怪な呼吸音が洩れ、指先が激しく震えていた。血走った眼はもはや焦点が合っていなかった。見るからに危険な状態だった。
寛はすきをついて判子を奪い取ると、すばやく退学届けに判を押した。そして、これ以上相手を刺激しないよう、背を向けてすみやかに出口を目指した。
ところが、部屋を出ようとしたところで、沼尾教授が横から音もなくすーっと現れてドアの前に立ちはだかった。教授は、糸で吊られた操り人形のように首だけがっくりとうなだれて、手足を奇妙に脱力させて立っていた。
どこからともなく一陣の風が吹き、教授がおもむろに顔をあげた。生気を失った顔にみすぼらしく伸びた髪が乱れかかったその姿は、落ち武者の亡霊を彷彿とさせた。寛は生唾を飲み込んだ。
「きみは知りすぎてしまったらしい」
沼尾教授は放心したように呟くと、突然ペーパーナイフを片手に襲いかかってきた。
寛はさっと身を翻し、間一髪で刃先をかわした。
教授は勢い余って書斎机に突っ伏した。
寛は慌ててドアから飛び出した。長い廊下を猛ダッシュで駆け抜けた。振り返っている余裕はなかった。
ところが、いつの間にか前方に回りこんだ沼尾教授が、ホラー映画のモンスターのように柱の陰からぬっと現れて行く手を塞いだのだった。
「通さんぞ!」
教授は、またしてもペーパーナイフで猛然と突きかかってきた。
寛は覚悟を決めて正面から突っ込んでいった。彼は絶妙のタイミングで足を踏み切ると、高々とジャンプして相手をかわし、背中を踏みつけにして先を急いだ。
階段を駆け下りた。四階、三階、二階。あと少しでこの忌まわしい建物から脱出することができた。
ところが、またしてもどこからともなく先回りして現れた沼尾教授が、地上階で狂気のオーラを撒き散らしながら待ち受けていた。彼の周囲の空気はどす黒く歪んでいた。
「逃がさんぞ!」
教授は、魔界から召喚された魔物のように地を震わすような吠え声をあげると、鉤爪の生えた両手を荒々しく広げ、寛めがけて飛び上がってきた。
捕まったら八つ裂きにされることは間違いなかった。寛は巧みなフットワークでこれをかわすと、手すりを尻で滑り降りた。
学生事務局に駆け込んだ。息を切らしてカウンターに退学届けを差し出すと、いきなり手首を掴まれた。事務職員のふりをした沼尾教授だった。
教授は悪魔のように不気味に笑うと、頭上にナイフを振りかざした。刃が天井の蛍光灯を反射してぎらりと光った。寛はとっさにカウンターにあった消毒用アルコールを掴み、相手に吹きつけた。
教授はぐわっと悲鳴をあげて目を押さえた。そして、苦し紛れにナイフをめちゃくちゃに振り回した。寛は上体を反らせて刃をかわし、隙をついて反撃に出た。
「これでも食らえ!」
寛は、教授のおでこに退学届けを叩きつけた。
その瞬間、退学届けがまばゆい光を放った。
「ぐぎゃー!」
断末魔の叫びとともに、教授の体はみるみる崩れ去り、腐臭を放つどろどろの液体へと溶けていった。
最後まで見届ける必要もなかった。
寛は、長い間彼を縛りつけていた不毛の世界から、すたこらさっさと逃げ出した。
了
いただいたサポートは子供の療育費に充てさせていただきます。あとチェス盤も欲しいので、余裕ができたらそれも買いたいです。
