
映画感想 鬼滅の刃は語りづらい
『鬼滅の刃』テレビシリーズの特別編集版が地上波放送!!
というわけで、全部録画しましたとも! すべてCMカットしてからまとめて視聴! CMなどという余計なものはいらん! あんなものがあるから集中力をなくすのだ!
CMカットしてから視聴……と一見すると一手間のような気がするけど、レグザはCMのだいたいの位置をチャプター分けしてくれている。本当はもっと正確にCM位置を把握してチャプター分けできるはずなのだけど、それができないのは「大人の都合」。あらかじめだいたいの位置でチャプター分けしてくれるので、もうちょっと微調整してカットすれば、すぐに作業が終わる。うっかり内容見ちゃってネタバレ……なんとこともほぼ起こらない。かかる時間は数分。対してCMは2時間番組で25~30分。一手間のように思えて、実はCMはカットしてから観た方が時間短縮になる。
というわけで、CMがほぼない快適な状態で一挙視聴!
特別編集版……とはいっても、以前放送した内容からオープニングとエンディングをカットして、だいたい2時間くらいずーっと見れるようにした……というだけ。「OP・EDなし一挙放送」が実態。
こういった編集版にありがちなことといえば、テレビ版のいろんなエッセンスを削りすぎて、ただのダイジェストになっちゃった総集編……『進撃の巨人』ですらそうだったのだけど、ほぼカットシーンなしの「OP・EDなしの一挙放送版」が作成されたのは、『鬼滅の刃』人気ゆえ。テレビ業界で働いている人間はアニメなんて格下と見なしているから、そのテレビ業界人の「見下し」を跳ね返す『鬼滅の刃』人気がいかに凄いかわかる。
さてさて、本編を観ていきましょう。
第1部 兄妹の絆
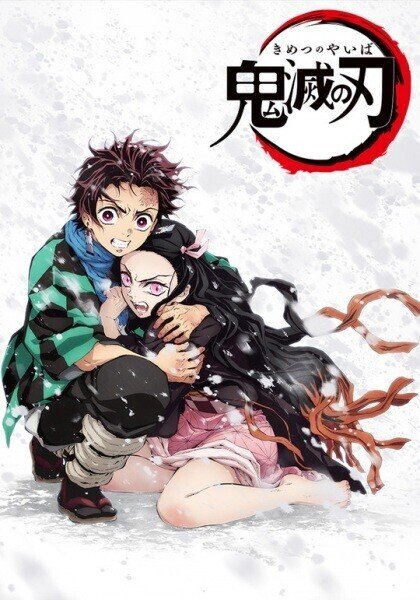
第1部の内容は、炭治郎の旅立ちと育ての鱗滝左近次との出会い、最終選別の戦いまでを描く。
個人的に気になっていたのは……炭治郎の額のアザ。あれ途中から変わったけどいつからだったっけ? 答えは最終選別(手鬼戦)の後。正確には第1部ではまだ変化はなく、包帯が外れる第2部になってからアザの形が変わる。いやぁ、忘れてるもんだね。見返して良かった。
もう一つ気になっていたのは禰豆子。あの子って、どんな話し方してたっけ? 第1話で1ワード喋ったきりだから、もう覚えてない。以降はずっと「んー」としか喋らないし、ゲーム版のプロモーションですら「んー」しか喋らないから。
でも今回一挙視聴して確かめてみると、シリーズ全体で数ワード喋ってたんだね。それでも数ワードだけど。
あと、最終選別で生き残っていたやたらと目つきの悪いにーちゃん。……あれ? あんな奴いたっけ?? あんな奴って、後で確認したらオープニングにもバッチリ登場してる。あー、そっかそっか。「アイツ誰だっけ?」ってずっと思っていたけど、そうか最終選別の時にいた奴だった。その後、ずーっと出番がないから完全に忘れていた。
第1部は炭治郎が家を出ることになった惨劇が描かれ、次に修業時代の真菰と錆兎とのやりとり、最後には手鬼が登場する流れになっている。
第1部はまだ「少年バトル漫画」的な色彩は弱く、心情に迫るエピソードが強めになっている。
第1話は竈門一家に起きる悲劇と、鬼となってしまう禰豆子を描くエピソード。こちらは以前ブログに書いたとおり、「完璧な第1話」。禰豆子はまだ「漫画のキャラクター」として成立しておらず、古色蒼然とした幽霊画的な怖さと美しさが同居する見せ方をしている。禰豆子をそういった描き方をしているのはこの冒頭の部分のみだが、非常に印象深い。竈門炭治郎の身に起きた悲劇を力強く描いているからこそ、後々のエピソードに対する重しとなっている。
(これ以降は、禰豆子は「キャラクター」になってしまって、可愛く描こうとしているところがちょっと鼻につくというか……。鬼本来の悍ましさと美しさを描いた第1話の姿が私は好きだった)
続いて、真菰と錆兎のエピソード。この二人は炭治郎が巨大な岩を切るという修行のエピソードをいかに面白く、ドラマチックに見せるか……ということで導入されたキャラクター。また後々手鬼戦に向けた伏線にもなっているので、一石二鳥のキャラクターだ。
炭治郎自身は真菰と錆兎と交流していると錯覚しているが、実はそれは幻に過ぎず、単に巨石を切るまでの出来事を物語化したもの。人の体験話というのは「物語化」するものであって、例えば後進国の人々が先進国に出稼ぎに行って帰ってくるお話は、語られる段階に入ると「お宝探しの冒険物語」に変化させられる。物語と呼ばれるものが、昔ながらの「語り物」と連なっているということがわかって興味深い。
第1部はそういった人物の心情に迫るエピソードが多いのだが、どうしてこのように語れるかというと、「話術」。「話芸」という言い方もある。
例えば第1話、炭を売って山へ帰ろうとする途中、炭治郎は三郎という男の家に泊まる。あそこで一度物語のトーンが一度落ち着く。三郎は炭治郎と一度も目を合わせず、炭治郎の質問にも曖昧にして、ただただ「鬼が出るぞ」と語る。その翌日、自宅に戻ると惨劇が起きていた……という展開が語られる。これが「話術」的な物語の作り方。
真菰と錆兎のエピソードもそうだし、手鬼の過去話にしても、よくよく見ると展開が強引。かなり強引に視点がコロコロ変わる。しかし、話術の巧さがあるから、強引な展開でもうまく引き込んで、素晴らしいエピソードに仕上げている。第1部はそういった意味での「話術」や「話芸」に長けたエピソードの作り方をしている。
もう一つ、個人的に確かめたかったのはアクションの作り。
錆兎との打ち込みのシーン、コマ送りで確かめてみたが、やはり中割が入ってなかった。炭治郎の動きには中割が数コマ入っているが、錆兎には中割がまったくなく、いきなり木刀を振り切った絵を次々と入れている。
その代わりに木刀を振りきった瞬間のコマを3コマ止めて、止めた瞬間に画面揺れとエフェクトの発生を描いている。中割を抜いているが、しかし細かな画面揺れとエフェクトを入れているので、一振り一振りの重さが表現されている。また止める瞬間があるから、動きの軌道をしっかりと目で確認できる。動き続けるより、むしろ止め絵を入れる方が重さが表現できる。おそろしく細かい職人技だ。
全てのシーンでそんなアクションの描き方をしているわけではないが、どうやらufotableにはピーキーなアクションを得意としているアニメーターがいるらしい。
アクションを得意としているアニメ会社と言えばボンズがあるが、ボンズはとにかく徹底した立体的な立ち回り。尋常ではない空間把握能力によって描かれた絵。京都アニメーションの場合は流麗なアニメーション。会社ごとに得意としているアクションが違っている。
ufltabieはそういったものと違って思いきりのいいコマの使い方。力のためなしでいきなりすっ飛ばす、止め絵をうまく使って重さを表現する。こういう表現がジャンプバトル漫画的な表現とうまく合致していたのかも知れない。
話芸的なうまさと、力強いアクションがうまく噛み合って、第1部はプロローグとして文句なしの作り。導入部としてもやはり「完璧な第1話」だった。
第2部 浅草編

めでたく鬼殺隊に入れた炭治郎は、その任務を受けて、異能の鬼と対峙する。ジャンプ流「バトル漫画」になっていくのは、ここから。1匹目の土に潜る鬼は、その以前のエピソードとこれからのエピソードとしての繋ぎ役としてちょうどいい存在感。古色蒼然とした語り物の匂いを持った第1部が、じわじわ「バトル漫画」に変貌していく過程のキャラクターとなっている。
土鬼を撃退して、続いて浅草へ。ここでいきなり鬼舞辻無惨と遭遇する。物語の導入部で「ラスボス」を提示するのはいい案。
初代『ドラゴンクエスト1』が良かったのは、最初の城を出た後、すぐに打倒すべき竜王の城がそこに見えること。最終目標を見せていた方が、何に向かう物語なのか明確になる。それは漫画においても同じ。『美味しんぼ』でも最初から「海原雄山」という究極乗ラスボスが提示されているから、お話の方向が明確になる。
ところで鬼舞辻無惨って、ちょっと『ジョジョ』のDIOっぽい。立ち振る舞いもどことなく似ているし、作中に出てくる鬼が全て鬼舞辻無惨一人が生み出している設定も似ている。家族持ちの設定は吉良吉影だけど。
鬼舞辻無惨と遭遇した後は、「逃れ者の鬼」である珠世と出会う。鬼退治の物語で水増しせず、一歩一歩物語が前進している感覚があってよい。
第3部 鼓屋敷編

問題なのが「鼓屋敷編」。ここで構成がガタガタに崩れる。
特に鼓鬼を撃退し、屋敷を出た後。エピソードの順列も滅茶苦茶だし、同じシーンが繰り返されたりする。尺調整的なスロー演出も連発する。
いったいどうした?
ufotableは高い制作力を持ったアニメ会社のはずなので、なにかしら足並みを乱すゴタゴタが内部的にあったのかな……? と推測するが。
理由はわからないが、とにかくエピソード全体から見ても、引っ掛かりを残す一編。
制作現場の足並みが乱れる理由は……↓
第4部 那田蜘蛛山編

続いく「那田蜘蛛山編」は傑作エピソード。やはりこちらがufotable本来のポテンシャルであるはずなので、「鼓屋敷編」は何かあったのかも知れない。
那田蜘蛛山編では炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助の3人が揃っての正式な討伐依頼となる。が、炭治郎達はここで決定的な挫折をする。とにかくも鬼が強力すぎて倒せない。これまでの向き合っていた雑魚鬼たちは、対策さえわかってしまえば対処できたが、那田蜘蛛山の鬼達は、対策がわかった後でも決定的な力差があってどうにもならない。
結局のところ、炭治郎達が討伐できた鬼の数は2匹のみ(炭治郎1、善逸1、伊之助0)。あれだけ苦戦して撃破不能と思えた鬼でも、富岡義勇が瞬殺。圧倒的な力差を見せつけられてしまう。
炭治郎達は那田蜘蛛山の戦いで決定的な敗北を経験し、己の未熟さを知る。
強力すぎる敵、圧倒的な力さを持った先輩の登場……こういうのもやはりジャンプ流「バトル漫画」らしいキャラクター配置。『ドラゴンボール』なんかでさんざん試みられたパターンがここでも使われている。それだけ、ジャンプ流「バトル漫画」の見せ方が時代を経ても人を魅了させる力を持っているということでもある。
那田蜘蛛山は2時間半。全体を見てもここが一番ボリュームの大きなエピソードだけど、ぜんぜん見飽きないし、それどころか加速度的に面白くなっていく。圧倒的な敵と向き合って死力を尽くし、限界を越えた力を発揮しつつ、それでも挫折していくエピソードが力強く描かれている。
注目すべきは下弦の五である累との戦い。炭治郎が「火の呼吸」の力を発動し、累を追い詰めるシーンは、『鬼滅の刃』全体を通して見ても最高のワンシーン。シーンの作りも完璧だし、アニメーションも完璧。手放しで「最高だ」と言える名シーンだ。
第5部 柱合会議・蝶屋敷編

那田蜘蛛山のエピソードを終えて、またしても満身創痍になった炭治郎達は、柱合会議に連れ出される。
柱達についてだが……とにかくまともに話ができる奴がいない。一人はえんえん空を見ているし、一人はえんえん泣いているし、一人はえんえん「まあ素敵」という独白ばっかりだし、残りは「とりあえず鬼殺す」しか言わないしで、対話の余地がまったくない。
「天才」はだいたいにおいて人格的な欠陥を抱えるものだけど、それをきちんと表現している。現実世界の「天才」も、まともに対話できないやつらばっかりだよ……作品は素晴らしいけど。
それがお館様の一言で、一気に話が反転していく。
……ほうほう、ということはお館様の正体は……。
しかもその後の、鬼舞辻無惨のシーンと呼応する作りになっている。
……私はあえて原作を読んでいない。この辺りの答え合わせはアニメシリーズを追いかけて確かめるとしよう。
柱合会議を終えて、炭治郎たちは蝶屋敷での療養と同時に、鍛錬を始める。
蝶屋敷で出会うのが栗花落カナヲ。今回最初から見直して、最終選別で生き残っていた一人だと気付いた。あーぜんぜん覚えてなかった。私の記憶力は鳥レベルだ。
もう一人、蝶屋敷ですれ違うのが不死川玄弥。同じく最終選別での同期生だが、もう完全に忘れてた。いや、最終選別以来の再登場だから、忘れてるのもしょうがない気もするけど。
無限列車編では、いつも泣いている柱と一緒だったから、どうやらその人の門下生(継子)らしいのはわかったけど……未だにどういうキャラクターなのかわからない。
第6部 無限列車編
日本映画史上に偉大なる記録を残した大ヒット映画がついにテレビ放送! 私も今回が初見。
しかし、この放送ではあまりにもCMが多いとクレームが上がる。
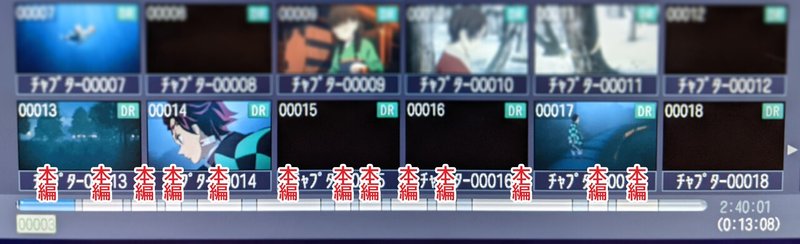
実際どれくらいCMがあったのかというと、2時間40分の放送中、45分がCM。普通、2時間番組でのCM分数は25分前後。第1部から第5部までの『鬼滅の刃』もだいたいどれもCM分数は25分だった。その倍の45分だから「多く感じる」という体感に間違いはない。1回のCM分数が本編とほぼ同じくらいあったケースもあり、CMは「多い」うえに「長い」とも感じられたはずだ。
どうして劇場版『鬼滅の刃』のCMがこんなに長くなってしまったのか……たぶん「儲かる」と思って群がってきた連中が一杯いたからだろうね。大ヒット映画だからこその現象だ。どいつもこいつも楽して儲かろうとしやがる。
私はそういう金の亡者が嫌いなので、CMはサクッとカットしてから視聴する。リアルタイム視聴はほぼしない。
これからの『鬼滅の刃』にはフジテレビが絡んでくるけど、作品に問題が起きるとしたらフジテレビ。テレビ制作者は自分たちのセンスが50年くらい遅れてることに気付いていない(『アナと雪の女王』のエンディングに子供たちの歌が流れたとき、昭和に引き戻される感じがあった)。裸の王様だ。裸の王様だが、自分が王様だと思って、企画に口だししてくるだろう。テレビ関係者には、とにかくも「余計なことはするな」と言いたい。今回の多すぎるCMも、早くも1つ「やらかした」と言える。
これ以上フジテレビは何もするなよ……と願いたい。素材を受け取ってテレビ放送するだけでいい。何もしなければ『鬼滅の刃』はどうあがいても成功する作品なのだから。

では本編。
無限列車編では夢を操る鬼・魘夢と戦うことになる。
映画が始まって10分ほどで夢の世界に落ちて、以降30分ほど彷徨うことになる。
「夢を操る敵」といえば『ジョジョの奇妙な冒険』第3部におけるデスサーティンを連想させる。夢の世界では、夢を見ている本人にはどうにもならない世界だからこそ、その世界でいかに立ち回り、脱出するかという過程にエンタメ性が現れる題材だ。かつて漫画柱の手塚治虫は「夢落ち」を禁じ手としたが、むしろ夢世界だからこそ強力なエンタメ性が現れるということを証明している。
夢の中で竈門炭治郎は、「もしも家族が生きていたら」という夢を見る。もしも鬼殺隊になることもなく、家族と平穏に暮らせていたら……。このように描くことで炭治郎が旅に出ることになった元々の切っ掛けに立ち戻りることができるし、果たして炭治郎は、その幸せな状況を撥ね付けてでも修羅の世界に戻れるのか。そこで主人公としての決意の強さを表現できる瞬間となる。少年漫画らしい「燃える展開」とドラマが同時に表現できる仕掛けになっている。
もう一つ、興味深いのはそれぞれの「内面世界」を描いたこと。これで、作者がそれぞれのキャラクターをどのように捉えているか……がわかる。炭治郎の場合は、どこまでも続く美しい凪の世界。作者が炭治郎をどういう人物として捉えているのか、どういう人物であって欲しいという理想が込められているのか、あそこで見えてくる。
我妻善逸の内面世界は真っ暗闇の世界として表現され、伊之助は延々続く洞窟として表現されている。漫画の上では善逸も伊之助もずいぶん愉快なキャラクターとして表現されるが、作者の視点では、二人が暗澹たる世界でもがいている様子が想定されているようだ。二人のひねくれた性格がどこから来ているのか、あそこでわかってくる。
そこから唯一外れているのが煉獄さん。煉獄さんだけが「内面の表現」ではなく、キャラクターの解説になっている。煉獄さんだけがまだ登場したばかりのキャラクターであるので、ここぞと「キャラクターを掘り下げる」フェーズとして利用している。
魘夢戦で一つ惜しいな……と感じたのが、夢世界の描写が「鬼滅の刃を初めて見る人」に向けた説明になっていないことだ。作品自体があくまでも、テレビシリーズがあり、その延長として、テレビシリーズを見たお客さんのみを想定して作られた“劇場版”になっている。夢の世界は改めて「鬼滅の刃とは?」を初めて見るお客さんに説明するチャンスだったのに、そのように作っていなかったことが惜しい。
ではどうしてそのように作られなかったのか? つまり、広く大衆に向けた作品になっていないのか? それはテレビシリーズが終わり、劇場版をスタートするまでのプロモーションの過程で、まさかここまで大きなコンテンツになるなんて、制作者もプロデューサーも誰も想像していなかったからだ。あくまでも深夜放送テレビシリーズの劇場版映画。もっと小さい規模での劇場公開を想定していたからだ。
この辺りは、「誰も想定し得なかった情勢」が絡んでくるので、仕方ないと言えば仕方ない。後でこんな話をしても後出しの話でしかない。
それでも、劇場版がスタートするまでの短期間で、あっという間にあらゆる世代に拡散していき、劇場版が始まる頃にはみんなテレビシリーズのストーリーを知っている状態になっていた……この流れが作れてしまったことは凄い。情勢が娯楽に飢えていた……という(こちらもやはり)特殊事情があった上……というのはあるが、それでもここまで一気に広がり、もはや「定番の作品」にまで成長した『鬼滅の刃』のコンテンツとしての強さは凄い。
開始40分ほどでようやく夢世界から脱出して、以降は魘夢とのバトルシーンに入る。この魘夢とのバトルシーンに決着が付くのは1時間20分ほど。
さて、魘夢戦が終わった。列車が停止してそこに現れたのは上限の参の鬼・猗窩座だ。
猗窩座は……回復スピードがチートすぎて……。ほとんど毎ターン全回復状態。あれがなければ煉獄さんが勝ってたはずなのになぁ……。
という話はさておき。
猗窩座戦の最中にも、かなり無理矢理なやり方で煉獄さんの回想シーンが挿入される。これが本当に強引な演出なのだけど、しかし成立しているように見える。この辺りが、「話術」の巧さ。作品全体に流れる「話術」の巧さが、こういうところで現れてきている。
結局は煉獄さんが敗れて、炭治郎達が悲嘆に暮れる。ここで炭治郎達が悲しむのは、煉獄さんとの関係性ではない。だって、煉獄さんと炭治郎はそこまでの関係性を築いていない。善逸や伊之助になるとさらに関係は薄い。炭治郎達は、その場の気分で泣いていたわけではない。
ではどうして善逸や伊之助まで煉獄さんの死に泣いたのかというと、無力感から。目の前で戦っていたのに、なにひとつ手出しできなかった。殺されるまで、ほとんどただ見ているだけだった。その後ろめたさと、煉獄への謝罪。弱い自分への後ろめたさもある。
あれだけ修行して、強くなった実感があったのに、さらに上を突きつけられた絶望。それを物語の最後に持ってくる。こういう見せ方は『アベンジャーズ』ですらやらなかった。凄いところにドラマの核を持ってくる。
荒木飛呂彦先生の著作『荒木飛呂彦の漫画術』の中に「プラスの法則」というものが出てくる。主人公の立場や能力は常にプラスに向かっていかなければならない。実際、炭治郎達は常にプラスプラスで真っ直ぐに成長してきた。なのにさらに上がいるということの絶望。少年ジャンプ的な「強敵が出現した瞬間にありがちな絶望感」の表現だが、その絶望感をドラマにしちゃった。これは今までのジャンプ作品の中でも新しい局面かも知れない。そういうところで凄さを感じた。
さて、映画として『無限列車編』を見ると、正直なところ、1本の劇場作品として観るとバランスを欠いている。お話が途中から始まって途中で終わるし、列車での一つの事件を追いかけただけで、展開が乏しく、奥行き感もない。あくまでも「テレビシリーズの劇場版」という映画の作りだ。ただ、それはもともと「そういうものだ」と見なければならないのだが。
実際、深夜放送アニメの劇場版として作った作品だったものが、かなり特殊な事情が絡んできて話題性が爆発し、最終的に邦画歴代興行収入1位を獲得するまでになってしまった。
そんなことも起こりうる……。そういう、不思議な前例を作ったしまった。映画史的にちょっと奇妙な点となる作品となってしまった。
これが、もしかしたら「特異点」に変化する可能性を残している。つまり、コンテンツが「テレビだけ」「劇場だけ」の作りではなく、全てが大きなメタバースの一つとして作られ、展開していく……そういうコンテンツ作りの前例になるかも知れない。ハリウッドではすでにそういう流れのコンテンツを作り始めているので、『鬼滅の刃』はそれを意識したわけではないが、結果的にそれに追従する流れの映画になった。色んな意味で展開が面白くなりそうなので、これからも見守っていきたい作品だ。

ところで、鼓屋敷編に出ていた女の子が出ていたような気がしたけれど……。
鬼滅の刃は語りづらい
語りづらいというか、語りづらい作品になっちゃった。
私の肌感覚では、『鬼滅の刃』は最初のテレビシリーズの時は、そこまで爆発的な大ヒット作ではなかった。『Fate』で高いクオリティを誇示してきたufotable作品で、しかも週刊少年ジャンプ発作品のアニメ化で、アニメ自体良質な1本なので注目されていた作品には間違いないが、それでも話題は「深夜放送アニメを見ているユーザー」という枠組みから出ることはなかったように感じている。
『鬼滅の刃』がここまでの一大コンテンツに発展したのは、その後。劇場公開に向けたプロモーションの過程で起きたことだったと感じている。この時に、『鬼滅の刃』は何かしらの「特異点」を通過し、あっという間にコミュニティのスケールが大きくなっていった。そのうちにも街を歩いたらどこにでも『鬼滅の刃』にぶつかるようになり、店に入ったらどの棚を見ても炭治郎がこちらに向かって微笑みかけてくる。(せめて禰豆子であってくれ)
もっと詳しい人なら、『鬼滅の刃』ムーブメントがどのように形成されていったか、正確に語ることができるだろう。私が感じている「肌感覚の話」とは違う話が出てくることだろう。だが私はそもそも「世の中の出来事に興味がない」ので(興味があるのは作品だけ)、「特異点」が正確にいつのどの時点だったのか把握していない。
私はこの状況を見ながら……困ったなぁという気になっていた。
もともと私は『鬼滅の刃』が好きで、ストーリーを追いかけてきたのに、私みたいな気軽に「作品が好きだ」と言っていた人間が、巨大すぎるムーブメントの外側に追いやられてしまったような……そんな感慨があった。
こういう状況になってしまうと、私みたいなごくカジュアルにアニメを見ている層は『鬼滅の刃』について語りづらい雰囲気になってしまう。まず、「最近の鬼滅の刃人気に群がってきた奴」と見なされる可能性があるからだ。「どうせ鬼滅の刃の何もわかってないくせに」と。「といあえず「鬼滅の刃好き」とか言っとけばいいと思っている奴」と見なされる恐れもある。
私は最初のテレビシリーズが放送されたときに、リアルタイムで視聴していたし、ブログに感想文を書き残している。でも「鬼滅の刃を軽々に語るな!」と言ってくる人々が、私がその以前に書いていた……ということまで確認したりはしないだろう。誰がそんな面倒なことをしたがるのか。
ブームが巨大化し、過熱化していくと、しばしばコミュニティの内部で奇怪な現象が起きる。作品の「崇拝者」が現れるのだ。
作品は「崇拝」の対象であるから、作品を語る時には「狂信者」となって、何かに浮かされているように熱を込め……それこそ鬼舞辻無惨圧迫面接の時の魘夢のような調子になって語らねばならない。内容が問題なのではない。語る人が狂信者になっているかどうか、「同志」として認められるかどうか以外、狂信化していくコミュニティを納得させるすべはできない。
例えば『ワンピース』がそういう作品になってしまった。
私は『ワンピース』がジャンプで連載が始まった第1回から読んできた。その後、引っ越しがあったので、その時にバタバタして数週逃してしまい、それで読むことはなくなった。あの時は、「まあ完結したときにまとめて読みましょうか」と悠長に考えていたのだが、まさかそこから十数年連載が続くとは夢にも思わなかったし、もはや「後で読みましょうか」と気軽に言える分量ですらなくなってしまった……。
(私が読んでいたのはブルックが登場しかけたところなので、46巻くらい。ここから100巻まで続くなんて、想像もしない。初期のストーリーも忘れているので、今から100冊も読むとなると……いや、本当どうしよう)
途中挫折があったとはいえ、私は『ワンピース』を連載第1回から読んできた。『ワンピース』についてはそれなりに知っているものもあるし、思うところもあるが、ブログではほとんど語っていない。なぜなら『ワンピース』は不用意に語れない作品になってしまったからだ。
『ワンピース』について語ろうとすると、「どうせ世間で話題になったから便乗して語っているだけなんだろ」と言ってくる厄介な連中が集まってくる。取り上げている用語に少しでも間違いがあると、これみよがしに糾弾の種にする。書いていることが難しくて、わからなかったら、それはそれで怒りの対象になる。『ワンピース』も大ヒットしていく過程で、作品を崇拝する熱狂者達を大量に生み出してしまった。「ワンピース原理主義者」のような人々があっちこっちにいるから、だから語りづらい作品になってしまった。
(押井守が、『エヴァンゲリオン』を「奇怪な複合物」と評して、ネットで炎上した。しかし、これこそ的を射た表現だった。しかしこれを理解できない人々が、なんだかわからないまま「とりあえずの反応」として怒りだし、「炎上」という現象が起きていた)
ネットの世界だけではない。道を歩きながら、一緒に歩いている人と雑談のノリで「ワンピースのあそこのシーンどうなんだろう?」なんて会話なんかしたら、すれ違った人にいきなり「ワンピースを非難するんじゃねぇ!」と絡まれるかも知れない。というか、そういう実例は本当にあったようだ。
現実の世界では、そういう絡み方をしてくるのは、ちょっとヤンチャをしているタイプと決まっているが、ネットの世界ではその真逆。現実の世界では何も言えない人達が、「顔が見えないこと」を盾に絡んでくる。
『ワンピース』も社会を動かすレベルで大ヒットしてしまったから、その中に「面倒くさい」人達を大量に産むという現象もまた作り出してしまった。もはや名前を出している状態で、「ワンピースのあの描き方はどうなんだろう?」なんて懸念一つでも示すことはできない。これをやったら、「それ!」と言わんばかりに集中砲火を喰らう。作品が崇拝の対象になってしまったから、欠点一つ挙げて指摘することすら許されないのだ。
そういう状況を前にして……「ワンピース語るのめんどくせー……」と感じたから、『ワンピース』についてはもう語らない、と決めた。
こんなふうに作品が崇拝の対象になっていくのは、一つには日本人自身の宗教観が曖昧であることから来ている。
私は何度かこのブログの中で話をしているが、人間は独力で精神的に自立していくことはほぼできない。できているという人は、社会的に成功している人だけだ。そんな幸運に恵まれる人なんて現実的には一握りなので、社会的な自立に成功していない多数派の人々は、「自立に失敗している」ことをごまかすために、何かしら宗教的なものを求める。ただ、その当人にそれが宗教的な崇拝であるという認識がない。
日本人は独自の宗教観を持たないがゆえに、それに準ずるものを現代的な虚構に求める傾向がある。特定の作品だったり、アイドルアニメだったり。若い人は「推し」という言葉を使うが、この言葉の実態は「信仰」であることは間違いない。アイドルイベントは現代人にとって宗教的行為、ある種の「参拝」となっている。
ただ、本人達にその自覚はまったくない。
私はこういう行動を「悪」だとは言わない。人間、結局は宗教なしでは生きられないものだからだ。それこそが人間の本質だと思っているから、その実態をとりあげて糾弾しようなどとは一切思わない。
ほとんどの人は自覚無しに、自分の周囲を「物語化」して捉えている。ある人を仮想敵にしたり、ある人を崇拝者にしたり……。こうした心理の構造は、物語の構造と完璧に符合する。人間の精神自体、そういうプリミティブな意識が隠れている。ただそういった感覚は、現代的な洗練された文化という見せかけのものにごまかされていて、ほとんどの人が気付いていない。
こういった現象は日本特有の話ではない。キリスト教意識が根強い欧米にでもよく起きている現象だ。というのも、古くから根付いてきている宗教観なんて、若い世代にしてみればただ古くさいだけ。神様なんてそんなのいるの? 胡散臭い! ……そう考えるのが若者世代にありがちな心理だ。
(神様がいないのは当たり前の話で、なんだったらアニメキャラクターだって実際に存在するわけではない)
だから宗教に代わる、「自分の精神を支えてくれる崇拝の対象」を別に求めてくる。こちらの場合も、若者達は「古くさい宗教の代わりにアイドルに夢中になっている」なんて自覚はまったくない。もっと洗練された刺激的で新しいものを追いかけているつもりでいる。でもよくよく検証してみると、当事者の内的なところで起きているものは、昔ながらの宗教的なものと変わっていない。
私だって人に言えないヘンなモノを崇拝したりしている。それがなんなのか言わないけど。
結局はそういうものをどこかしらに入れ込まないと、人間は正気でいることなんてできないのだ。
こうした心理の中に、「熱狂者」や「狂信者」が生まれてくる。そうなっていくのは、ごく当たり前の話だった。ただ、本人はただの「漫画好き」のつもりであるから、自身が「狂信者」になっているとは想像もしない。
もう10年も前の話だが、私はちょっとした被害に遭った。
『魔法少女まどか☆マギカ』の感想文を書いたとき、2ちゃんねるでボロカスに叩かれた。誰かがスレッドを立ち上げて、1行1行丁寧に非難してきたのだ。
一応断っておくが、私は『魔法少女まどか☆マギカ』を非難したつもりは全くない。むしろ大絶賛だった。だが狂信者たちは私の書き方一つ一つが許せないらしく、「こいつはわかってない!」「アニメの素人だ!」と非難してきたのだ。どうやらあの時2ちゃんねるを書いていた狂信者達は、私の文章が大絶賛だったことを読み取れなかったようだ。
私はそういう反応をエゴサーチで探していたわけではない。普段使っているデスクトップPCとは別の、ノートパソコンを使う機会があったので、それで自分のブログを探そうとしたところ、検索第1位にその2ちゃんねるスレッドの、おだやかではないタイトルが出てきたのだ。わざわざ検索1位になるようにして、私のブログより多くの人に目に付くようにしていたのだ。
それ以来、新しいデバイスを手に入れたとき、面倒くさくとも私はURLを入力して自分のブログを探すようにしている。
私のようなネットの片隅で、ぽつぽつ書いているような人でさえ、このように非難される事例はあるのだ。
『鬼滅の刃』は途方もない大ヒットコンテンツになってしまった。すると「鬼滅の刃崇拝者」や「鬼滅の刃原理主義者」たちも現れるはずで、私の知らないどこかで暴れ回っていることだろう。きっと彼らは、自分たちのしていることは『鬼滅の刃』という作品が絶対的であることを守るため「鬼殺隊」のつもりで戦っているのだろう……むしろ「鬼」のほうだと気付かず。社会現象級大ヒットコンテンツになると、どうしてもそういう「輩」もまた生まれるのだ。
すでに私の書いたものはどこかのネット掲示板でスレッドとして立ち上げられ、「あいつは『鬼滅の刃』を否定した! 許せない! みんなで叩くぞ!」と行動を始めているのかも知れない。
そういう状況になると、私のような書き手はどうしなければならないのか。「鬼殺隊」になるのではない。「鬼」になるのだ。すでに書いたが、鬼舞辻無惨に対する魘夢のように、陶酔的に作品を語り、作品そのものではなく、「作品の狂信者である」ということを証明しなければならない(最近のアニメの語り手の中には、「作品そのもの」ではなく、「作品の狂信者となっている自分」を中心に語る人が増えている感もある)。その証明が認められたとき、「鼓屋敷編はちょっと構成おかしいよね」という指摘が許される。
社会現象級メガヒット作品が生まれると、どうしてもその中に厄介な「輩」も生まれてくる。この輩連中は、「作品をどう感じたか」ということにも自治を求めてくる。他人の感受性をコントロールしたがる。「鬼滅の刃に欠点は何一つない」ということを広めようとする。すると、作品に対して気軽に語れない空気が作られてしまう。
これから『鬼滅の刃』シリーズ後半がはじまる。もちろん私は見るつもりだ。普通のいちユーザーとして非常に楽しみにしている。あえて原作は読んでいないし、『鬼滅の刃』関連情報は一切調べていないし、目に付きそうになったら慎重に避けている。この先、何が起きるか全く知らない。それだけ楽しみにしているからだ。私は普通に『鬼滅の刃』を楽しみにしているし、楽しんで見るつもりだ。
放送が終わったらいつものように感想文を書くつもりだし、引っ掛かるポイントがあったらそれを書くつもりでいる。
その私が「問題点」として一つでも挙げているのを見て、「とらつぐみは何もわかっていない! 許せない!」と憤慨し、またどこかの掲示板でスレッドを立ち上げて非難する人達は現れるかも知れない。「猗窩座の“あ”を書き間違えている! あいつはにわかだ! 許せない! みんなで叩くぞ!」……そういう反応をする連中も出るかも知れない。
今のうちに宣言しておこう。私はそういう連中と向き合うつもりは全くない。なぜなら私は忙しいからだ。漫画も描いているし、小説も書いている。今の私は、ネット上で起きていることに何一つ興味がない。どこかで炎上が起きていても、興味がないので一切見ていない。だから私に関することをどこかでバッシングを始めたところで、私は「知らん」で通すつもりだ。
私は勝手に『鬼滅の刃』を楽しんで見る。普通に楽しんで、普通に感想文を書く。狂信者が「とらつぐみは何もわかってないから見るな!」と言ってきても、私は相手をしない。
とらつぐみのnoteはすべて無料で公開しています。 しかし活動を続けていくためには皆様の支援が必要です。どうか支援をお願いします。
