
海外MBA入学審査官式、語学の最適な習得法
語学の専門家でもないのに、語学習得法を語るのは気が引ける部分もあるのですが、キャッチーさを求めてタイトルがこうなりました 笑
語学習得の基本は、自分が到達すべきレベルとそれに必要な内容を適切に見極めた上で、「1. 日々の地道な鍛錬」、「2. 読む・聞く・書く・話すのバランスが取れた学習」、を遂行することに尽きるのではないでしょうか。
私の場合、英語は日々の仕事で公用語として使っています。
確かに、この仕事を始めた初期には、専属トレーナーについてもらってプレゼンの訓練をしたりするなどしていました。
最近は発音の部分的なものを除いて、英語については特段の訓練をしていないので、大変恐縮ですが、読者の皆様の参考になりにくいです。
また、昔、どう勉強していたかあまり覚えておりませんし、色々回り道もした気がしますし、金融庁国際室出向中あたりからとにかく場数(一部修羅場)を踏んでその中で伸ばしてきた記憶の方がやや強いです。
英語が完璧であるとかそれに近いとか奢っているわけでは一切なく、仕事に必要があるとは言えない分野で英語をこれ以上身につけるよりも、他のことに時間を割いた方が有意義と考えているだけです。
もちろん時々色んな振り返りをすることはありますが、日々継続しているというほどではありません。
私自身がどのレベルを英語で求めるべきかについて自分なりの明確な解はありますが、人によって解釈が分かれそうなので、あえて言及することを控えます。
パネルディスカッション等において大勢の前で喋る場面は多いにせよ、少なくとも英語自体が仕事と言える通訳や翻訳のそれとは明確に異なるはずです。
それに対して、必ずしも毎日仕事で使うとは限らない状況下で私がスペイン語で日々実践している内容は、言語の差はあれど、示唆となる部分を一層含むものと思われます。
ということで、前置きが長くなりましたが、以下で示すのは、英語ではなくスペイン語の事例となります。
IESE(イエセ)MBA在学中、ほぼフル活用していた、週3回×各2時間のBusiness Spanish Program(任意参加)以外の内容です。
私の語学勉強法
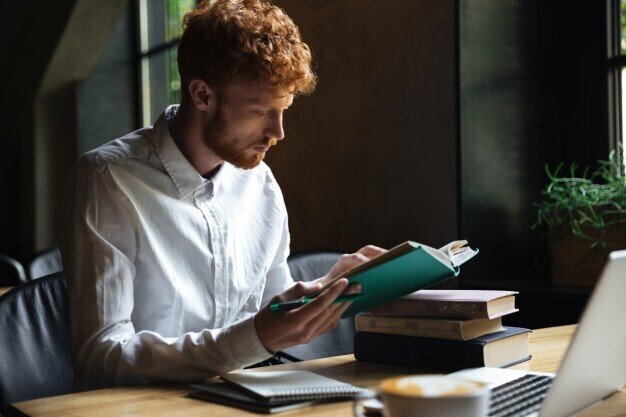
まず、目標レベルを大まかに定めることが大事と書きました。
私の場合、雑に括ると、仕事でスペイン語をストレスをほぼ感じることなく使えることが到達レベルです。
ニュアンスが伝わりにくいと思いますが、今もそれなりに使えるのに対し、今後は「ストレスをほぼ感じることなく」まで昇華したいというイメージです。
まず、携帯電話の言語設定など、可能な範囲でスペイン語に囲まれる環境を作り出しています。
そして、「読む」と「聞く」については、EURONEWSのスペイン語版が最近の専らの教材です。
これのメリットは、音声と文面に微妙な乖離があるものの、スクリプトがあることです。
どの程度見るかはともかく、ただの聞き流しではなく、やはりスクリプトが不可欠です。
わからなかった単語を確認したり、音読用にも使えるので、用途は多岐に渡ります。
テレビゲームをスペイン語設定でやることも試したことはありますが、都度止めたりしなければならず、ゲームに集中できないのと、仕事で使う上ではあまり役立たない語彙が多いと判断し、やめました(ゲームの選び方によるかもしれませんが)。
海外出張が頻繁だった際は、機内で字幕と音声を英語とスペイン語にしたりとかしていることもありましたが、観る映画に依っては、こちらの方がゲームよりも多少有益でした。
他方、EURONEWSのようなニュース素材は、一定期間ある程度似通ったものが多くなるので、いくつか触れているうちに自然と単語が記憶されていくというメリットがあります。

例えば、最近は、上記のような新型コロナウィルス関連(今冬の欧州のスキー事情)に加え、アゼルバイジャンとアルメニアによるナゴルノ・カラバフ係争に関連したニュースが非常に多かったので、関連する単語が自然と習得できました。
ニュースに関連しない単語・熟語帳も必要に応じて語彙習得に使っていますが、文脈がなかったり、文脈を変えて再度その単語に出会う機会が限られている点で、やはり習得率は下がると感じます。
有用性が下がると述べた聞き流しからも得られるものが多少なりともあるのは事実です。
したがって、公共交通機関での移動中などは、音楽ではなく、可能であれば既に聞いたことのあるスペイン語の素材(集中して聞く重要性が下がる素材)をひたすら流すようにしています。
デスクワーク中もスペイン語を垂れ流すと更に良いのかもしれませんが、この場合いよいよ垂れ流しの効果が相当限定的になると考えます。
ですので、垂れ流しを時にしつつも、集中力を下げても大丈夫なように、また気分転換を兼ねて、テレビゲームの音楽を垂れ流すことが多いです。
「話す」については、これまで色々やってきました。
スパニッシモ(オンラインスペイン語会話)でグアテマラの先生と1 on 1で会話をしたこともあります。
また、IESEの福利厚生で活用できるSpeexxにおいて1 on 1もしくはグループセッションを受けたり、冬休みを利用してニカラグアやグアテマラの現地の語学学校で1 on 1の短期集中型特訓をしたり...
それぞれのやり方にメリット・デメリットがあります。
スパニッシモの1 on 1セッションは、教材の充実度ゆえに文法を漏れなく体系的に学びつつそれを同時にアウトプットする機会を十分得ることができます。
Speexxのグループセッションは、他の学生のスペイン語表現から気づきを得ることができたり、議論する能力を高めることができたり、純粋に彼らの考え方を学ぶことができます。
Speexxの1 on 1セッションは、スペイン語が平易なグアテマラの先生が教えるスパニッシモのそれとは違いもう少し難易度の高い別のスペイン語に触れることができます。
ニカラグアやグアテマラの現地の語学学校では、スペイン語以外に何も考えない環境を作り出してそれに集中することができたり、現地の生活や文化にも触れることができたりします。
大事なことはどのやり方も中途半端にせず、一定の小目標を達成するまでしっかりやりきることかと思います。

4技能どの項目にも関連し得る「単語」については、わからなかったものと少しでも確信が持てなかったものを、上の写真のように、アプリの「SpanishDict」に地道に記録し、クイズ形式でも振り返ることができるようにしています。
なお、スペイン語は、英語と比べて発音が負担になりにくいので、その点はあまり考慮していません。
ただ、最近は、思うところがあり、「聞く」と「読む」に少し比重を移して日々勉強しています。
「書く」については、最近やや怠けていますが、これは私の目標に鑑みると4技能の中で最も重要度が低いです。
仕事で使えるレベルで、とはいえ、他の3技能と比べて、最も使用可能性が低く、且つ、そもそも「話す」ができれば、ある程度補完可能です。
勇者を目指す旅路

いずれにせよ、「1. 日々の地道な鍛錬」については、何もしなければ少しずつ能力が落ちていくという意味合いも含めて、下りエスカレーターを上るのが語学取得の旅路という使い古された表現が適切かと思います。
「2. 読む・聞く・書く・話すのバランスが取れた学習」については、ドラゴンクエスト的に言うと、語学習得は勇者を目指す旅路に近いでしょう。
ドラゴンクエストにおける勇者は、一技能に秀でた戦士や僧侶といった他の職業とは異なり、打撃も防御も回復も呪文も、いずれもバランス良く強化しつつ強くなっていきます。
攻撃面については、打撃が効きにくい敵もいるので、ギガデインのような強力な魔法を習得することが不可欠です。
防御・回復面については、いくら防御力を強化しても、どうしてもダメージは蓄積されていきますので、やはりベホマのような強力な回復魔法を習得することが不可欠です。
一般的な日本人は「読む」に強く、他の3技能は弱い、というアンバランスなケースが他国籍の人と比べても強いことが多いので、海外MBA受験生は、特にこのバランスを保つことを意識すると良いかもしれません。
特に、「話す」が弱いと、面接でそれが露呈され、他の努力が台無しになるリスクさえありますし、「話す」は一番一朝一夕で鍛えづらい技能である気もします(「聞く」がその前提になりますね)。
語学習得のためには現地在住経験が必要か

語学習得のためには、現地在住経験が必要でしょうか。
現地でしか身につかない、触れられない要素も確かにそれなりにありますが、それを言語能力として昇華できるかはかなり個人差があります。
英語について、帰国子女といっても、現地の日本人学校に行っているか否か、海外在住時の年齢がどうだったか、等によって、英語力は大きく変わってきます。
私自身、特に帰国子女というわけではありません。
日本在住でも、努力次第では結構なレベルまで英語を伸ばすことはできます(が、限界もあります)。
先日、日本人ではない某アジア人を面接させて頂いた際に、大学卒業まではバックパッカーとして海外を旅行した程度で、公用語が英語ではない、アジア・オセアニアの某2カ国で数年働いた経験のみながら、大変流暢で美しい英語をお話されていました。
改めて、語学は努力で後発的に身につけることが一定レベルまでは十分可能であるということを再認識させられた事例でした。
ちなみに、全く同じ英語力を持つ2名の受験者がいた場合、英語力については、IESEの入学審査プロセスでは、国際経験が多い人よりも国際経験がない方を一層好意的に見る傾向があります。
国際的な機会に恵まれなくともそのレベルまで英語力を高めたという事実が、今後の潜在可能性を示す要因として光るからです。
但し、これは、あくまで英語力についての話であり、国際的な環境でのリーダーシップの発揮については全く別の話です。
社会人になるまでに留学できるかについては、育った家庭環境などに少なからず依存するものであり、自分でコントロールできる領域を十分超え得るものです。
過去は変えられなくても未来は変えられる、そう思って突き進めるかどうかが語学習得に必要な心持ちであり、その心持ちは海外MBA受験成功の鍵の1つでもあると言えるのではないでしょうか。
そういったこともあり、私は、社会人になってから、つまり自分の人生に一層主体性を持てるようなタイミング以降、明確な目的意識と覚悟を以て語学の修練に日々励む方のことを、その方のレベルに関係なく、応援・尊敬しております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
