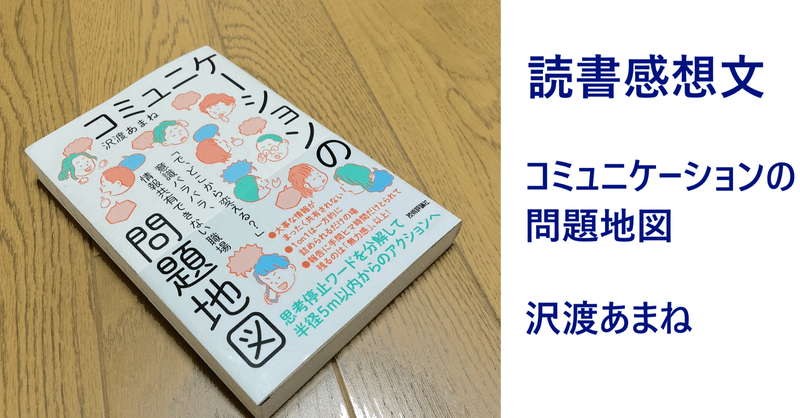
沢渡あまねさん「コミュニケーションの問題地図」。社内の仕事のやり方が一気に変わりそうな予感しかない
沢渡あまねさんの「問題地図シリーズ」の最新作を読んだ感想を綴ります。沢渡あまねさんの本ですが、世の中の企業の痛ーいところ(本質)を、絶妙のタイミングで、確実に突っこんでおられます。各所で注目を集めるのも当然でしょう。また執筆活動と並行して企業の顧問や、「組織変革Lab」をはじめとした組織変革や地域開発などの独自プログラムを主催されるなど、幅広く活躍されています。
本書のテーマは「コミュニケーション」。一見何の問題もなさそうなポジティブ・ワードに見えるコミュニケーションという言葉が意外にも「思考停止ワードである」という問題提議から始まります。
はじめに
本書を開けると一番最初に「コミュニケーションの問題地図 全体マップ」なる巻物風のが紙が出現します。コミュニケーションの問題を俯瞰図にしたもので、本書の構成を1枚に分かりやすくまとめてあります(この内容をここで書いてしまうとほとんどネタバレになってしまうので書きません)。
企業や部門毎にコミュニケーションの問題は様々なので、この全体マップを見ながら、「うちの部門はこれが問題だよねー」的につまみ食いするような使い方もできるのが良いと思いました。今回は、自分がついやってしまいがちな問題発言や行動、会社でよくあるイケてないコミュニケーションの事例を紹介しながら、感想を書かせてもらいました。
1.「コミュニケーションを良くしよう!」って結局なに?
例えば、急な退職者や組織異動で人が減った!そんなときマネージャー(課長とか係長とかの中間管理職)がこんな行動をとるのを見た経験はありませんか?
業務がひっ迫すると「部門長がやみくもに対面での会話を増やそうとする。忙しいメンバーはますます忙殺される」
マネージャーは、いつも通り経験の浅いメンバーに対して事細かに手順や仕事のやり方を教え、既存メンバーに対しても業務過多を回避すべく細かく指示出しをし始めたのです。実はその時、
「でも、なんかおかしくない?」メンバーたちはモヤモヤしていたのです。
「あの部門、また会議室に籠ってますよ」
情シスのメンバーがそっと耳打ちしてくれました。彼はその部門で使っているTeams(マイクロソフトのチャットツール)のやり取りが全く使われていないを以前から気にしていました。
コミュニケーションの密度を増やす事
=会議を開いて確認やチェックを増やす事?
確かにこれは大切。でもこの勘違いがメンバーの貴重な時間を奪ってしまっていたようです。メンバーは気づいていました「この会議って必要?今日も長かったなあ…」と。
本書の冒頭で、コミュニケーションを良くするためには、5つの要素に着目する必要があると書かれています。
環境(話しやすい雰囲気か?)
プロセス(オンライン、オフラインなどやり方の選択肢があるか?)
関係性(その組織が理想とする人と人との関係性はどういったものか?)
スキル(対話力、傾聴力などのスキルは身についているか?)
カルチャー(その組織はどんなコミュニケーションのを理想とするか)
事例の部門は、管理職がすべて指示を出し、メンバーはそれに従って業務を行い、上司のいう事が絶対に従う、というスタイルでした。コミュニケーションは常に上から下への一方通行。チャットは担当同士の雑談と愚痴のツールになっていました。しかし、人が減ってそのスタイルが限界にきている事に気づくことなく、やり方を変えずに進めてしまったために、メンバーのモヤモヤが爆発しまったのです。
これは単に一部門の仕事の仕方だけの問題ではなく、組織全体のカルチャーのお話しです。要は、その組織が変わりたいのか、変わりたくないのか?変わらなくて良いという組織のマネージャは、メンバー全員が今までのやり方でやり切れるという自信があるのか? という事なのだだと思います。
・主体的に行動しろと言われも…やったことないからできません
・管理職はとにかくやれ!としか言わないでしょ
・ミスをしたらそこでお終いだから新しいことなんか挑戦できません
メンバーやまわりからこんな声が上がったら、もう今までのやり方は綺麗さっぱり捨てる時ですよ、マネージャの皆さん。
2. 情報共有できない情シス部門
「その場にいる人にしか情報が伝達されない(情報共有の概念がない)」
「井戸端会議で重要な意思決定」「教えて欲しければ聞きに来い」
数年前のうちの部門のお話をします。どこの会社でも良くあることですが、うちの部門も例にもれず「一人親方の集合体」でした。仕事の依頼や指示はすべて口頭。だれがいつやったかはその時の会話に加わっていないと知る由もない。そんな状態でした。上手くいかなくても周りに相談せず(しにくい雰囲気)一人で解決しようとする。そんな感じでした。
分かりやすい例で言うと、部門からの問い合わせや依頼は「100%担当個人宛の電話やメール」でした。依頼されたAさんは「俺って頼られてるよなあ」とその仕事を最優先にしてしまい、離そうとしません。一方で他のメンバーは「あの人は忙しそうだけど何やってるか良くわからない」と全く興味なし。
ところがいつしかAさんが休暇を取ったり、忙しくなると事情が一変したのです。部門からは「なんで忘れるんだ!」とクレームになり、他メンバーは「だって俺たちやり方教えてもらってないし」と他人事。
いやはや、チームとして機能しない状態でした。情報共有がなされないことで情シスの顧客である部門に対するサービス品質が低下していたのです。
さすがにこの時は全員で考えました。まずは、Baclogという共有ツール(現在はTeamsとRedmineに移行)に問い合わせと依頼事項を共有して、ヘルプデスクチームを中心に、全員が助け合いながら、誰でも同じ品質で対応できるように仕事の仕方を変えてみることから始めました。
情報共有は誰の、何のためにするの?
情報共有すると何がどう良くなるの?
この「何のための情報共有?」という視点が抜け落ちると、情報共有自体が目的化されてしまい「無駄な情報共有会の開催」が常態化してしまいまうので注意が必要ですね。
3. その日報本当に必要?
管理職がメンバーの業務をチェックするためだけの作文のような長い日報は意味がないと思いませんか?
例えば営業職。営業日報が必須と思われがちですが、実際は見積もり作成や顧客との商談、社内調整、事務処理など、多種多様な業務を抱えています。社外に出ることもある営業にとって本当に営業日報は必要でしょうか?営業がその時にリアルタイムで共有&蓄積されていれば、わざわざ1日の最後に「日報と言う作文を書く作業」は不要なはずです。
今日の予定:スケジューラ
顧客訪問の時間と内容:CRM(顧客管理システム)
社内調整や申し送り事項:グループウエア(Teams、チャットツール)
我が情シスチームは、色々な仕事が並行で走る小規模なチームでは「日報は、自分自身で計画を立てて毎日振り返りをする目的で書く。形式は今日の予定と目標、結果を箇条書きでTeamsに投稿するだけ」と言うシンプルなルールで運用しています。

著者である沢渡あまねさんも、noteで日報の運用の仕方について述べています。日報を儀式のように「書かされている」人、「書かせてしまっている人」は以下の記事をぜひ読んで下さい。
4. ピラミッド型組織に根付く忖度文化
役職者や社歴の長い人、年長者のいう事は絶対
彼らの心地いいやりかたに合わせろ
自分は今の会社の情シス部門に中途入社して4年が経ちますが、最初の頃はこの言葉を言われて何度も心が折れそうになりました。確かに自分の知識不足や経験不足が表に出てしまったからではありますが、ここで言いたいのは「組織文化に紐づいたコミュニケーションの問題」についてです。
伝統を重んじ、上位の役職の方を敬う。これは全然否定しません。特に製造業では、堅実さ、安全性、高い品質を実現したからこそ、顧客からの信頼を勝ち取って成長してきた歴史があるからです。
しかし一方で、「組織を変革しなければ厳しい競争に打ち勝てない、変わるんだ!」とトップが大号令をかけたとしたらどうでしょう。伝統の裏に隠れた「忖度主義」が変革の妨げになることがあると思いませんか?
恐ろしいことに、会社全体の忖度文化はやがて組織内の「コソコソ主義」へと発展するのです。
部長や課長にお願いや説明をするために資料を作り始める
部長や課長の意見を部下が代わりに無理やりすり合わせようとし始める
部長や課長がいないところでメンバーがワチャワチャ議論し始める
結果、本来メンバーがやるべき業務が何も進まなく、無駄なコミュニケーションのコストだけが垂れ流されていきます。
本書では、この忖度文化を解消するための7つの解決策が書かれていますので、是非、購入して読んでみてください。
おわりに(マネジメント層の方へ)
世の中の企業、特にマネジメント層の方々は、この言葉をポジティブにこう表現しがちです。
「うちの部はコミュニケーションが円滑でいいぞ!」
「コミュニケーションこそが組織運営で重要なんだ!」
みなさんもどこかで聞いたことありませんか?朝礼とか、年度初めの決起集会とかで。ちょっと立ち止まって考えてみてください。「うちの会社や組織が理想とするコミュニケーションって何だろう?」「昔ながらのやり方でこの先も上手くやっていけるのか?」
同じ情シス仲間の原田篤史さんは、本書の感想でこう述べています。
フラットな組織を望むか、望まないのかは経営戦略によるものだから、社員が勝手に進めていくものではない…という前提の元、
一番重要なのは「経営方針として何を望むか?」だと思うんです。
それに反発して「俺はフラットな組織がいいんだ!」といったところで、「それってあなたの感想ですよね?」で終わってしまう事でしょう。
なので、その組織がどういうことを望み、どの様なコミュニケーションを推奨するかは、よく対話する事が必要だと思うんです。
(中略)
会社として、巨大戦艦大和のように、全体像はわからないけど、乗組員が持ち場の仕事をしっかりこなす様な経営方針なのか?それとも戦闘機のように個々人が操縦して、大まかな指示や連絡はあるものの、いざ戦闘になったときは、その場の状況に合わせて各自判断するのか?
私も原田さんの意見に賛成で、トップ含めて社員全員がピラミッド型の組織文化や意思決定を望むなら、正直この手の本や考え方は不要です。しかし、そうは言っても先進的な考えを取り入れる事が必要な部門(研究開発、事業開発、経営企画、人事、情シスなど)が存在するわけで、彼らは、こういったコミュニケーションの問題に立ち向かっていかなければいけない時が、そう遠くない将来に訪れるに違いないと思うわけであります。
さあ、みんなで景色を変えていきましょう!

(おわり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
