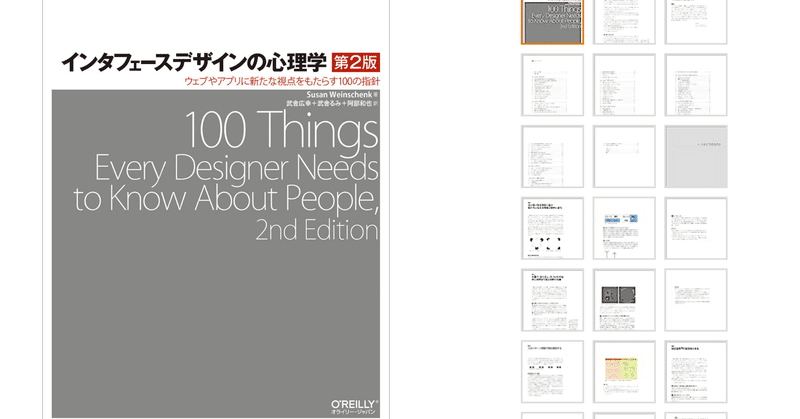
ワーキングメモリー/ 一度に覚えられる個数は4つ/ 情報を覚えとくためには使う/ 情報は認知させる/ 記憶は疲れる/ 証言は信じない/ 忘れることは普通/ 鮮明な記憶でも間違っていることが多くある
6/26 インターフェースデザインの心理学 (人はどう記憶するのか)
ワークングメモリ
ワーキングメモリとは、一時的に人が記憶することができるメモリーのこと
・画面が変わってもユーザーが情報を覚えれていると期待してはならない。
あるページで読んだ文字や数字を別のページで入力させることをしてはならない。 ユーザーはイライラする。
・ワーキングメモリにあることを忘れてほしくない場合は、ワーキングメモリを使って課題が完了するまで、他のことをさせないようにする。
例えば、パスワードを覚えさせていろいろな情報をおいた後に、入力させることなどはイライラさせる
一度に覚えられるのは4つのみ
・相手に提示する情報を4つに限定できるならそうするべき、
無理でも情報をいくつかのチャンクに分けれられるなら、情報は最も多くても大丈夫
例えば、、、、
私の自己紹介(適当です)
私が好きな食べ物は、アイスとラーメンと、ビールと、チョコと、エスニック料理、コーヒーと辛いものです。学生時代は、チアリーダー、ピアノ、ダンスをしていました。好きなことは、映画鑑賞とデザインとカフェ巡りです。
という文章を分けると。
好きな食べ物
アイス、ラーメン、チョコ、エスニック料理
好きな飲み物
ビール、コーヒー
学生時代の経験
チアリーダー、ピアノ、ダンス、
好きなこと
映画鑑賞、デザイン、カフェ巡り
に分けたらわかりやすい!!
・一つのチャンクに入れる項目は4つ
・人は記憶に頼らなくても済むように、するためメモやリスト、カレンダー、手帳、など脳以外の「外付けの手段」に頼ることが多い
情報を覚えて欲しければ、繰り返す
・ユーザーに何かを覚えて欲しければ、何度も繰り返す必要がある。
スキーマ
・スキーマとは 似た記憶同士が紐づけられ、ネットワーク構造を形成したもの
(頭とはどんなもの)→脳 頭髪 目 鼻 耳 皮膚など、頭を構成する様々な部位を思い浮かべる。
(消防車)→「救急車」や「火」「家」といったキーワードが紐づいたスキーマとして記憶。
・ユーザーや顧客に対してリサーチを行う大きな目的は、「対象としている集団の持っているスキーマを見つけ出し理解すること」
・提供する情報に関連するスキーマをユーザーがすでに持っているのならば、スキーマを忘れずに提示するべき。既存のスキーマに情報を結びつけることができれば、ユーザーの理解が進む
思い出させるより 認知させる
・利用者が何かを想起しなければならないインターフェースではなく、実際にみてわかりやすいものを使う
(具体的なアイコンなど)
記憶は疲れる
・情報を覚えて欲しければ、相手を休ませる(寝させる)
・人が何かを覚えようとする邪魔をしない
・発表の中間で示された情報は記憶されている可能性が低い
証言は当てにならない
・ユーザーインタビューをする場合は、インタビューの仕方によってユーザーの記憶を変える可能性がある
・過去の行動の自己申告を信用してはいけない
人は当たり前に忘れる
・何を忘れるかは、無意識に決定される
・ユーザーが忘れることを前提にデザインしてみるべき。
本当に必要な情報ならば、ユーザーが覚えれていることを当てにしてはならない。デザインの中に含める形で提供するか、すぐ見つけられるようにする。
劇的な瞬間も人は忘れる。
・ドラマチックな経験や、心的外傷を負うような体験をしても
人はその記憶が正確だと思っていても、客観的な事実として真実ではない可能性が大いにある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
