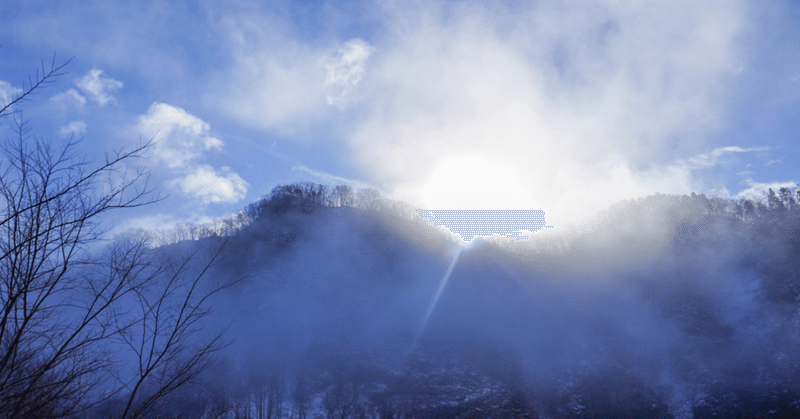
【小説】太陽のヴェーダ 先生が私に教えてくれたこと(12)
着替えを終えて、二人で食卓を囲む。
泣いた後だから味がわからない。
「先生、どうしたら先生のようになれますか?」
唐突に美咲は問いかけた。
あんなふうに癇癪を起こしても、結局何もいいことはない。自己嫌悪だけが残る。そんなのは、もう疲れた。
「私も先生みたいに、穏やかに笑って、見守っている側の人間になりたいです。先生みたいに『特技・平常心』って履歴書に書きたいです」
「そんなこと書いたことありませんよ」
雪洋が声を上げて笑う。
笑いがやむと、雪洋は美咲を見つめて嬉しそうに目を細めた。
「な、なんですか?」
「ん?」
「先生なんで笑ってんですか?」
「笑ってますか?」
「笑ってます! 私が失敗したとき先生はいっつも笑ってます!」
雪洋の微笑みは、子供の成長を見守る母親のようだ。
「……先生って、どうして怒らないんですか?」
「おや質問が増えましたね。まあ根本的なところは一緒でしょうけど」
一ヶ月以上一緒にいるが、怒った顔を見たことがない。
「どうして怒らないか、ですか。そうですね……」
雪洋が考えながら、食べかけのおかずを箸で口へ運ぶ。茶碗に残ったごはんも食べ、味噌汁を飲み干す。――なかなか答えを言ってくれない。
完食した雪洋は箸を置き、「ごちそうさまでした」と合掌している。よもや質問されたことを忘れたわけではあるまい。
美咲が辛抱強く待っていると、ようやく思いついたように雪洋がうなずいた。
「疲れるからじゃないですか?」
「……じゃないですかって、他人事ですね」
「言われてみれば、しばらく怒ったことがなかったなと思って」
これは本物だ。美咲は目をみはった。
「エネルギー使うでしょ? 怒るのって」
「……たしかに」
さっき実感したばかりだ。
「それに怒れば上手くいくかと言えば、そうでもない。往々にして上手く回らないものです。だから事後の処理にもエネルギーを使う。謝ったり、謝る機会を与えたり」
許さない、という選択肢はないのだなあと感心する。改めて雪洋を大人だと思い、その器の大きさを感じる。
「そういうことが面倒だから、怒るのをやめたのかも知れませんね。最初から穏やかに進めた方が、結果うまくいきますし」
ふと、童話の『北風と太陽』を思い出した。
雪洋は今まで何度も、美咲の心の壁をあたたかく溶かしてくれた。
先生は、太陽だな――
「怒らないようにするのは簡単ですよ。嫌なことがあっても平常心でいることです」
「簡単じゃないですよ」
「怒らずにいれば、言い過ぎたと謝ってくるのは相手です。こちらに非があった場合でも引っ込みがつかないほどの状況にはなりません。謝ることも抵抗なくできます。あとで面倒な思いをするのは意地を張った方です。こちらは忘れるくらいの気持ちでいればよろしい」
すでに無理だとあきらめ顔の美咲に、雪洋が「いいですか」と人差し指を立てる。
「何を言われても、何があっても大丈夫。無力化できるかどうかは、受け取り方次第なんですよ」
「うーん、理屈はわかるんだけど……」
「あと体のことでいら立ちを覚えるのなら、コントロールの仕方を覚えることです。たとえ不調になっても回復までの道筋が見えていれば、気持ちもそう乱れないでしょう」
「そっか……。私も心が乱れないように修行します。白い道を歩んでいきたいから」
ふと気がつくと、雪洋がまた嬉しそうに笑みを浮かべて見ていた。
「……何ですか?」
いいえ、と言う雪洋の顔は笑ったままだ
「さ、食事も済んだことですし、ソファーへ移動しましょう。足、辛いでしょう?」
少しの時間でも足を高くしておこうと雪洋がソファーのフットレストを出し、美咲の足の下にクッションを敷いてくれる。
「一つ予言をしておきましょうか」
ソファーテーブルにお茶を置きながら、雪洋が言った。
「美咲はね、今にとても素晴らしい女性になりますよ」
「え? 私が? なんでですか?」
「思慮深く、丁寧な立ち居振る舞いをするようになるからです」
「……なんでそうなるって思えるんですか?」
自信に満ちた声でそんな風に断言されると、悪い気はしないが、少し照れくさい。
雪洋はゆったりとした動作で、美咲の隣へ腰を下ろした。
「持病が暴れないような行動を取っていくと、自ずとそうなるからです。体調が悪くなるのはどういう時ですか?」
「えっ? えーと、疲れたり、足に負荷がかかったり、冷え、過度なストレス……」
自分の症状に関連する原因を、思いつく限り列挙する。
「ああ、いいですね。よく自分のことがわかっている。じゃあ症状をコントロールする方法も、わかりますよね?」
「逆をやればいいってことですか?」
にっこり笑って「そうです」と雪洋はうなずいた。
「無理が利かないから、優先順位を決めて物事を合理的に進めるようになる。衝撃や傷を嫌うから、動作が丁寧になる。朝晩の気温の変化や睡眠に気を使えば、規則正しい生活になる。自ずと精神面も安定する。人間関係でも、互いに傷つかない言葉を選ぶようになるでしょう」
美咲の目が輝き始めた。
「何より苦痛の経験があるから、美咲は人の痛みが誰よりもわかります。たとえ敵がいても、慈愛で相手を満たせば、いつの間にか味方になっているかも知れません」
気付けば美咲は、姿勢を正して聞いていた。
あまりにも輝かしい自分の未来像に、感嘆の吐息を漏らす。病と付き合ってゆくことに楽しみが見えてくる。
「……なれるかな」
「なれますよ。美咲は白い道をめざしたいと言ってくれました。そのための努力をしていけば、今話した未来像は、美咲に与えられる当然の結果です」
とんでもない。今の状態からそんな高みへ行けるなら、それはむしろご褒美だ。
「ああそれと。手足が弱い分、力仕事にも向かない。だから上手に人に頼む所作も身につけるでしょう。今までより男性にかわいがられるかも知れませんね」
その言葉で美咲の顔は急に曇った。雪洋も気付いて、不思議そうに見ている。
「……私、もう恋愛できないですよね」
「どうして? どんどん恋愛したらいいじゃないですか」
「どうせ私の紫斑を見たら誰だって、『何それ気持ちわりぃ』って言いますよ」
「――それは別れた彼に言われたんですか?」
微笑んでいたはずの雪洋の目から、笑みが消えた。
「先生だって医者じゃなく一人の男だったら、きっと彼と同じことを思うはずです」
そうですか、と言う表情と声音からは、雪洋の感情が読み取れない。
「もったいないですねえ、男性を一緒くたに彼と同じに括って。それじゃいい人がいても、そのよさに気付けないじゃないですか」
「誰だって嫌がるに決まってます。恋愛も結婚もこの先できるかどうか……」
自分は普通に結婚して、普通に出産して、普通の家庭を築いていけるものだと、当たり前に思っていた。
それを今、とても疑わしく思う。
友人たちは着々と女性としてのステップを駆け上がってゆくというのに。
「たとえいい人がいたとしても、こんな痛がってるばかりの女じゃ、一緒にいて楽しむこともできない。だから――」
「それは違いますね」
ぴしゃりと雪洋の声が響く。
いつもと雰囲気が違う。
「愛し合うことの解釈が私とは少し違うようだ。何も一般的な形にとらわれる必要はない。みんなそれぞれ、自分たちに合った形と努力の仕方があるはずです。そういうふうに互いを思い合うことが、愛し合っているようには見えませんか?」
雪洋が言う「愛の形」は、美咲が思っていたそれとは根の部分で違っていた。
「まあ私が言っているのは、恋人ではなく夫婦かも知れませんが」
「恋人と夫婦って、愛の形が違うんですか?」
「恋人の場合はどちらかというと、オシャレな関係というか、良い面ばかりを見せ合う付き合い方ですよね」
「じゃあ夫婦は?」
「病めるときも健やかなるときも――ですよ」
結婚式でよく聞く言葉。よくよく考えればあれは、苦労もともに、という宣言だ。
別れた彼は、健やかなときだけよくしてくれた。――苦労をともにする相手ではなかったのだ。
「結婚は、しなきゃしないでもいいんじゃないですか?」
雪洋は簡単に言ってくれるが、美咲にとってはそうではない。
「先生は周りから『まだ結婚しないのか』って言われても平気なんですか」
「平気ですね。美咲は周りが言うから結婚するんですか?」
「……先生は結婚願望ないんですか?」
「お互いの気持ちとタイミングが合えば一緒になりたいですけど、結婚というイベントそのものに執着はありません。大事なのは誰と一生添い遂げたいかでしょう?」
「……先生って意外と愛を語るんですね」
意外ですか?と雪洋が笑う。
「美咲も見つけたらいい。体を理解してくれる、とことん優しい、器の大きい人」
「だからそんな人いるわけないじゃないですか。誰だって私の体を見たら気持ち悪いって言うに決まって――」
言葉を遮るように、雪洋の両手が美咲に向かって伸びてきた。
「ねえ美咲?」
その手に美咲の顔が捕まり、左右からがっちりと押さえ込まれて雪洋の方へ向けられる。
美咲の表情が、全身の筋肉が、一瞬で硬直した。
――目の前に、雪洋の顔がある。
「白衣を着ていない私を拒むのは、私を男として見ているからでしょう? 医者ではなく普通の男に面倒みてもらっている、申し訳ない、迷惑かけてる、いつかきっと嫌がられる――そう思っているんじゃないですか?」
雪洋の言うとおりだ。
寸分の狂いもなく、そう思っている。
だが――
「は……放して……」
今の美咲にまともに話をする余裕はない。
血の気が引き、歯が上手く噛み合わない。
「男として見るのは構いませんが、美咲は悪い方に意識しすぎです。男は皆彼と同じように自分を嫌がると思っている。それではいけません」
「放してください……っ」
息がかかるほどの近さから、まっすぐに美咲の内部を焼き焦がすように見つめてくる。
「ここに住みなさいと言ったのは私です。勤務中でも勤務外でも関係ありません。白衣を着ていなくても私は医者です。私は美咲を今より良くしたいんです」
「先生お願いだからもう放して!」
嫌がるに決まってる。
先生も、他の男も。
だから近付きたくない。
親しくなって好意を抱いてしまったら、そのあと傷つくのは目に見えている。
紫斑を見せたら、難病だと打ち明けたら、私は絶対に捨てられる。絶対にだ。
だから誰かを好きになってはいけない。
なりたくない。
誰もが気味悪い目で私を見ていた。
誰もが、誰もが……!
「ねえ美咲?」
逃げるように目を強くつむる美咲に雪洋が問いかける。
「たしかに私は医者ですが、一人の男でもありますよ。その私が、今まであなたの体を気味悪がったことがありますか?」
――ない。
一度たりとも、なかった。
目を開けると、雪洋に視線を絡めとられた。
もう、目をそらせない。
「少なくともここに一人、美咲の体を理解した、とことん優しい、器の大きい男がいるでしょう?」
誰もが……では、ない……。
「ねえ美咲?」
雪洋がまた問う。
「もうそろそろ、別れた彼と私を重ねるのは、やめにしませんか?」
感情が読めなかった雪洋の表情に、声音に、あたたかさが戻っていた。
誰もが、では、ない。
強張っていた体から力が抜ける。
目の前にいるのは、別れた彼ではない。
高坂雪洋。私の、先生――
白衣を着ていない雪洋は彼と同じだと決めつけていた。でもそうじゃない。そうではなかったことを、誰よりも美咲が一番知っている。
「ごめん……なさ……、先生、ごめ……」
泣きじゃくりながら必死に謝る。
失礼なことをした。とても失礼なことを今までしていたと、ようやく自覚する。
雪洋が、互いの額をこつんと合わせた。
「わかればいいんですよ」
囁くように言って微笑む。
美咲の心の壁がまた一枚、溶け落ちていった。
「とことん優しい男がここに一人いるってことは、あと三十人はいますから」
「先生、それゴキブリですって」
美咲も顔がほころぶ。
「それに優しくて器が大きいなんて、普通自分で言いませんよ」
美咲の笑った目から涙がこぼれる。
そこに愛想笑いはもうない。
自然に湧き出た、心からの笑顔だった。
雪洋も満足そうに微笑んで額を少しだけ離し――
そのまま頭突きした。
もちろん手加減はされているが、ゴツッという低い音と、「い……っ」という美咲のこらえる声が漏れる。
「あなたを捨てた心の狭い輩を、私に重ねていた非礼への罰です」
「だからって頭突きはないでしょー!?」
雪洋の胸を叩く――が、叩いた拍子に手の腫れやコブに痛みが走って悲鳴が上がる。
「ほら平常心ですよ、美咲」
雪洋が手を取ってなでる。
白衣を着ていない雪洋にそんなことをされても、美咲にはもう何の抵抗も生まれなかった。むしろ雪洋と触れたところのぬくもりが心地よい。
「今のは先生が悪いです!」
「はは、ごめんごめん」
謝っている雪洋の顔は、なんだかとても嬉しそうだった。
翌日、朝食を食べながら雪洋が言った。
「今日は送別会でしょう? 送りますよ。帰りは電話ください」
美咲は持っていた茶碗と箸を置いた。
「いえ、私行かないことにしました」
「……いいんですか?」
「先生の言うとおり、体が不調になるのは目に見えてますから」
「ほう」
「それだったら早く帰って、先生とおいしい物食べた方がいいかなあって」
「ほう?」
雪洋の片眉が上がった。
「……案外かわいがられる素質あるじゃないですか」
「え? なんですか?」
よく聞こえない。
「なんでもありません。そういうことならなおさら、今日は私が送り迎えしますよ」
「いいんですか?」
「迎えに行くんですから、間違っても残業なんかするんじゃありませんよ」
「はい、わかってます。――あ、そうだ。あの、先生……」
「何ですか?」
「こういうこと、いつ言っていいのかわからないから、今言います」
前を向くことを教えてくれた。
道が続いていることを教えてくれた。
白い道を歩けることを教えてくれた。
一番近くで寄り添っていることを、気付かせてくれた。
「とても、感謝しています。先生本当に、ありがとうございます」
感謝の気持ちを表わしたとき、雪洋はいつも何も言わずに、少し困った顔をする。きっと照れているのだろう、と思う。
今も雪洋は、少し困ったような顔をしている。
でもどこか辛そうな表情にも、見えた気がした。
「――じゃあ私からも一言」
雪洋がその表情のまま、語りだした。
「美咲、いいですか。これから先、今よりもっと辛く、耐えられないことがあるかも知れません」
「……はい」
「美咲一人でなんとかしなければならないことも、あるかも知れません」
そういうことの方が、きっと多いだろう。
「どうしても辛いときは、うずくまって泣いてもいいんです。でも気が済むまで泣いたら、顔を上げて、少しずつでも歩いていくんですよ。そうすればきっと、見える景色は違ってくるはず。心が感じることも、きっと変わってくるはずですよ」
そうなるだろうか。
いや、雪洋が言うのなら、信じることができる。
「美咲」
「はい」
「いつか、『こんな体』と思わない日がきますよ」
信じることができるから、希望が持てる。
希望が持てるから――
「はい、先生」
笑って応えることが、できる。
ここから先は

【小説】太陽のヴェーダ
どう見ても異常があるのに「異常なし」しか言わない医者たちに失望した美咲。悪化した美咲に手を差し伸べたのは、こうさか医院の若き院長、高坂雪洋…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
