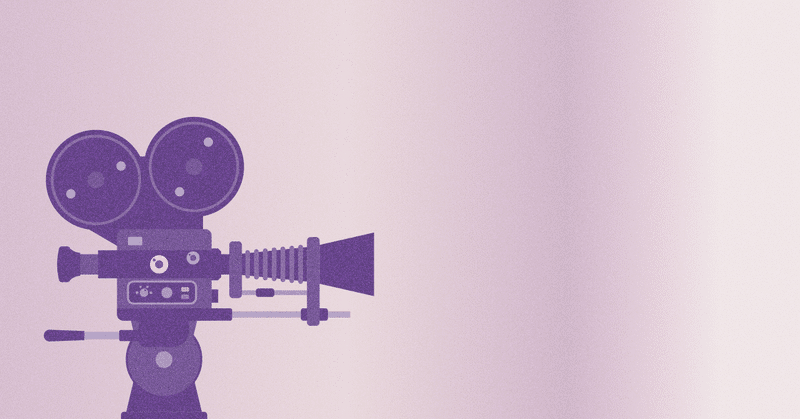
《十四. 雷次プロの始動とストーカー 》
1971年2月、独立プロの「雷次プロダクション」が設立された。雷次が社長、そして副社長には竜子が就任した。
当初、雷次は竜子を会社の仕事に参加させるつもりは無かった。しかし、竜子の方から経営への参加を希望してきたのだ。
雷次が独立する意志を打ち明けた時、竜子は何の反対もしなかった。
「貴方が独立したいのなら、私は応援するだけよ」
と後押しした。
「だけど、フリーでやっていくんじゃなくて、独立プロダクションを作るのなら、経営の手腕も必要になってくるわね」
「そうなんだ。それについては、俺は何の能力も無い。だから経営面で手伝ってくれる人を探して、参加してもらおうと思ってる」
「だったら、探す必要は無いわ。私がやるわよ」
「お前が?」
眉をひそめる雷次に、竜子は
「私が社長の娘だってことを忘れたの。父の仕事を近くで見てきて、それなりに経営の知識は持ってるわ。それに、貴方と結婚するまでは、父の会社で働いていたんだから」
「だけど見てきただけで、実際に経営に携わったわけじゃないんだろう?」
雷次が不安そうに言うと、
「大丈夫よ。私、何となく自信があるの。それに、誰かを雇ったら、それだけ給料の支払いが増えるのよ。独立プロなんだから、無駄な出費は避けた方がいいでしょ」
「うーん、それはそうだが」
「だったら決まりね」
そんなやり取りがあり、根拠の無い自信を見せる竜子に丸め込まれる形で、雷次は彼女を副社長に据えたのだった。
雷次プロ設立時のメンバーは、この夫婦に百田と大神を加えた四名だった。
会社の名前については、雷次は「雷次プロダクション」ではなく、別の候補を考えていた。「EMC」という名称だ。これはエンターテインメント・ムービー・カンパニーの略で、映画会社「ATG」への対抗心が強く込められていた。
「あっちがATGなら、こっちもアルファベット三文字でいこうぜ」
会社名について百田たちと話し合いを持った時、雷次はそう口にしている。
ATGはアート・シアター・ギルドの略称で、1961年に発足した映画会社だ。設立当初は外国映画の配給を行っていたが、1971年の時点では、日本の独立プロと提携して芸術映画や実験映画を専門に製作するようになっていた。
前述したように、雷次は芸術映画が大嫌いだった。だから、それを専門に製作する会社への不快感を抱くのは、当然のことだった。
「観客を嫌な気持ちにさせてどうするんだよ。不愉快な気持ち、モヤモヤした気持ちになるのは、現実だけで充分だ。わざわざ映画で体感させなくても、世の中を生き抜いていく上で、嫌なことなんて幾らだってあるんだよ。だったら映画を見た後ぐらい、スッキリした気分になってもらいたいじゃねえか。
別に喜劇だけを作れって言ってるわけじゃねえぜ。悲劇だって構わない。ただし、悲劇なら悲劇で、そこにカタルシスが無くちゃいけない。何の救いも無くて、ただ観客を重苦しくさせるだけの映画じゃダメだ」
雷次は、そんなコメントを残している。
ちなみに、ATGは1973年に、中島貞夫の『鉄砲玉の美学』を公開している。この時、雷次は
「ATGのくせに、生意気にも面白い娯楽映画を作りやがって。だけど、さすが中島貞夫だ。ATGには勿体無い人材だよ」
と、感想を語っている。
結局、個人的な対抗心が強すぎるEMCというネーミングは他の三名の賛同を得られず、雷次プロダクションという社名に決まった。
―――――――――
雷次プロの事務所は、東京に設けられた。大映を辞めたことや、時代劇の製作が難しい時代であることを考えて、京都に事務所を構えるよりは東京に出た方が何かと便利だろうと考えたのだ。
事務所の物件は竜子が見つけてきた。早速、仕事をしたわけだ。
引っ越し作業が済むと、第一回作品についての会議が始まった。
「とりあえず、ジャンルとして、アクションをやることは決定でいいんですよね?」
大神が訊く。大映時代の雷次は、チャンバラ映画から始まり、アクションを売りとする作品を主に手掛けてきた。大神の中では、雷次は「アクション映画を得意とする監督」という印象だった。
ところが雷次は、
「いや、一発目は恐怖映画をやる」
と宣言した。
「恐怖映画?アクションじゃないのか」
百田が確認した。彼も大神と同様、アクション映画を撮るものだと思い込んでいたのだ。
「いずれはアクションもやるが、まずは恐怖映画だ。前から、アクションを抜きにした純然たる恐怖映画を撮ってみたいと思っていたんだ。日本で恐怖物というと怪談話ばかりだが、海外だと、もっと色んなタイプの恐怖映画がある。俺は、怪談じゃない恐怖映画を撮ってみたいんだ」
竜子だけは、雷次が恐怖映画を選択することは想定の範囲だったらしく、
「そうね、いいかもしれない。『妖民の島』や『奴らに死の制裁を』は恐怖映画の味付けがあったし、『血まみれの仁義』の残酷描写にも、そういう方向性を感じた。雷次さんには、そっちのセンスもあると思うわ」
と、冷静な口調で述べた。
「だけど、今回は残酷描写をやる気は無いぜ。それどころか、血も流さないし、殺しの場面も無い。そういう映画にするつもりだ」
雷次が言うので、百田が
「サスペンス映画ってことか」
と尋ねる。
「俺としてはホラー映画のつもりだが、その辺りは、どっちでもいい。とにかく、主人公を心理的にジワジワと追い詰め、恐怖がどんどん高まっていく。そういう映画だ。実は、アイデアは大神が与えてくれたんだ」
「えっ、僕ですか?」
「ああ。実は、俺も最初はアクション映画をやるつもりだった。だけど、この事務所の引っ越し作業をしている時に、恐怖映画のアイデアを思い付いたんだ」
「僕、何かやりましたっけ?」
大神が首をかしげる。
「正確に言うと、お前の彼女がアイデアをくれたんだ」
「春子ですか」
事務所の引っ越し作業をした時、大神の恋人である春子も手伝いに来ていた。
「あの時、お前は『いやあ、僕はいいって言ったんですけど、こいつが勝手に付いて来たんですよ。こいつ、僕の行く所は、どこへでも付いて来たがるんです』などと、オノロケを聞かせただろう」
「いやあ、ノロケてなんか」
「何を照れてるんだよ。お前がノロケたかどうかは、どうでもいいんだ。それより、どこへでも彼女が付いて来るっていう話だ」
「それが、どうかしましたか」
「お前たちが恋人同士だから、それはノロケになる。だけど、もしもお前が彼女のことを好きじゃなかったら?それどころか、彼女とは何の面識も無い、赤の他人なんだ」
「そりゃあ、そんな奴が付いて来たら、薄気味悪い女ってことになるな」
大神ではなく、百田が答えた。
「ちょっと、僕の彼女なんですから」
「そこはひとまず忘れろよ」
百田がたしなめるように言う。
「だったら、別の例えを出そう。竜子、お前にずっと付きまとう男がいるんだ。相手とは何の面識も無い。名前も素性も全く知らない。そんな男が、お前がどこに行っても付いて来るんだ。これって、怖いと思わないか」
「もちろん怖いわよ。怖いに決まってるじゃない」
「お前なら、どうする?」
「とりあえず、相手を捕まえて、何者か問い質すわ。それから、もう付きまとわないでほしいと要求する」
「それでも、相手がやめなかったら?」
「警察を呼ぶわ」
「しかし、相手は何も危害を加えていない。ただ付きまとっているだけだ。これだと、何の罪も犯していないから、警察は彼を捕まえられないんだ」
「あっ、そうか」
「そこが重要で、男は何も手出しして来ない。お前を傷付けようとか、誘拐しようとか、そういうことじゃないんだ。ただ、ひたすら付きまとう。だが、それが逆に不気味で、お前はどんどん精神的に追い詰められていくことになる」
「ちょっと、まるで実際の話みたいに喋らないで。本気で怖くなってきたから」
竜子は寒気を感じ、体を震わせた。
「すまん、つい調子にのってしまった。だが、アイデアは分かってもらえただろう。どうだ、一発目の企画として」
「ああ、面白そうだ。いや、怖そうだ。それで行こう」
百田も乗り気になった。
こうして、独立第一作はホラー映画『薔薇を抱えた男』に決定した。
これは、まだストーカーという言葉が一般的に使われる以前に、ストーカーの恐怖を描いた作品だった。
―――――――――
『薔薇を抱えた男』では、出演者に有名俳優を使わず、オーディションで選んだ面々を起用することになった。これは雷次の意向だった。
最初は、ヒロインに付きまとう男役に、無名の役者を起用するプランだけが決まっていた。薄気味悪い謎の男なので、知名度が無い方が望ましいと考えたからだ。そこで、その役を決めるオーディションを開こうとなった時、
「ついでだから、全員をオーディションで選んだら面白いんじゃないか」
と雷次が言い出したのだ。
これには、百田、大神、そして今回ばかりは竜子も声を揃えて反対した。知名度の無い役者ばかりを揃えることは、観客動員を考えると、あまりにもリスクが大きいからだ。
しかし雷次は飄々とした態度で、
「でも考えてみろよ。どうせ俺たちは、人気のあるトップスターを呼べるわけじゃないんだぜ。吉永小百合や酒井和歌子みたいに、その女優が出ているってだけで客が集まりそうな役者は使えない。だったら、いっそのこと、全員をオーディションで選ぶってのも面白いんじゃないか。それが話題になって、会社や映画の宣伝になるかもしれないぞ」
その説明を聞いても難色を示していた百田たちだが、
「世の中には、埋もれている優秀な人材も多くいるはずだ。そういう人材を発掘するのも、プロの映画人の役目だ」
と雷次が説得し、最終的には渋々という形で承諾した。
オーディションは「プロ・アマを問わず」という形で開催された。既に何本も映画に出演していた役者から、一度も演技経験が無い素人まで、様々な人がオーディションに参加した。 その結果、ヒロイン役には舞台女優の五輪涼子が選ばれた。
一方、彼女に付きまとう男役に選ばれた福井至恩は、全く演技経験の無い素人だった。 それどころか、彼は映画への出演さえ希望していなかった。
彼は何を勘違いしたのか、雷次プロのスタッフになりたいと言ってオーディション会場に現れたのである。
しかし雷次は彼の風貌がイメージにピッタリだったため、出演者として採用することを決めた。
「でも、僕は監督の下で働きたいんです。役者になりたいわけじゃないんです」
そんな風に福井は慌てたが、
「役者として出演するのも、俺の下で働くことになるじゃないか」
と、雷次は真面目な顔で告げた。
「だけど、役者なんて一度もやったことが無いですし」
「誰だって最初は素人なんだよ。それに心配するな。お前がやる役は、何の演技力も要らないから」
それでも尻込みしていた福井だが、
「この映画に出た後は、ウチの会社でちゃんとスタッフとして使ってやるよ」
と雷次が持ち掛けたので、出演を承諾した。
===================
『薔薇を抱えた男』
〈 あらすじ 〉
理容室で働く片桐麻美(五輪涼子)が仕事に行くと、店の近くに薔薇の花束を抱えた男(福井至恩)が立っていた。男は薔薇を一本抜き取り、それを彼女に差し出した。麻美は何かのキャンペーンだろうと思いつつ、それを受け取った。
翌日も、同じ場所に男が立っていて、薔薇を差し出した。麻美は薔薇を受け取るが、周囲の人間に尋ねると、誰も薔薇を受け取っていなかった。それどころか、そんな男が立っていたことさえ知らなかった。
次の日、また男がいたので、麻美は
「これって何かの宣伝なんですか?他の人にも渡しているんですか」
と尋ねた。すると男は何も言わず、無表情のままで立ち去った。
翌日も男は現れたが、もう麻美は薔薇を受け取らなかった。すると男は、別の場所に現れて彼女を待ち受けた。麻美の生活圏を全て把握しているかのように、男は彼女が買い物に行く商店街や、行き付けの喫茶店の前に姿を現した。目的を尋ねても、男は何も言おうとせず、ただ薔薇を差し出すだけだ。麻美が一緒にいた友人や店員に助けを求めると、いつの間にか男は姿を消していた。
男が現われる場所は、麻美のアパートへと次第に近付いていた。ある日、ついに男はアパートの前に現れた。怖くなった麻美は、警察に助けを求めた。だが、男が何も危害を加えていないため、警察としては動きようが無いと言われてしまう。
麻美はアパートの前にいた男を怒鳴り付け、追い払った。すると男は現れなくなるが、今度は麻美の部屋や行く先々で、いつの間にか薔薇が置かれているという出来事が起きるようになった。麻美は男に襲われる悪夢にうなされたり、別人を男と見間違えたりと、精神的に追い詰められていく……。
===================
『薔薇を抱えた男』はオール・ロケーションで撮影が行われ、1971年8月に公開された。この時から、雷次は監督だけでなく、原案者としても名前が表記されるようになった。これは竜子が決めたことである。
また、この映画で雷次は警官として出演しているが、役者としての表記も「山田頼児」から「佐野雷次」に変更した。これも竜子の進言によるものだ。
『薔薇を抱えた男』は無名俳優ばかりの出演作にも関わらず、上々の興行成績を収めた。雷次プロは第一回作品から、順調な滑り出しを見せた。
だが、ダイニチ映配から配給された雷次プロの作品は、この一本だけである。同じ8月には日活がダイニチ映配を離脱し、11月29日に大映が倒産したのだ。
「いよいよ、ここからが正念場だな」
大映の倒産を受けて、雷次は気を引き締め、次回作の構想に取り掛かることにした。
なお、福井至恩は『薔薇を抱えた男』だけで役者業から足を洗い、雷次は約束通りに彼を雇い入れた。具体的に何がやりたいのか尋ねると、
「何でもいいから、とにかく監督のお手伝いがしたいんです」
というアバウトな答えだったため、とりあえず雷次は、自分のマネージャーという形で雇用することにした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
