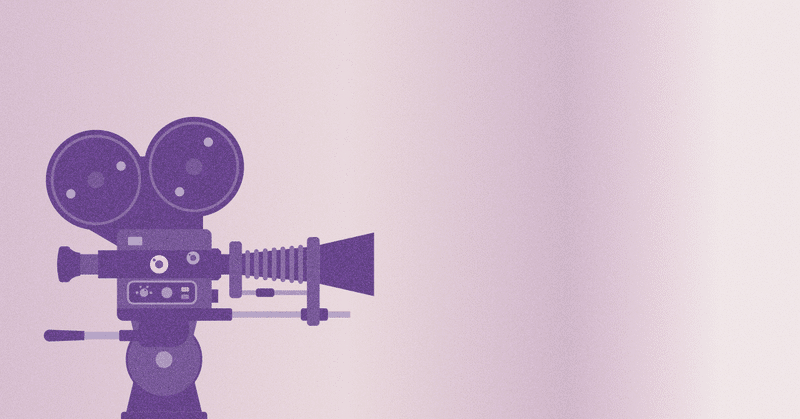
《七. 田宮二郎が二人いる 》
大映では「時代劇は京都撮影所、現代劇は東京撮影所で製作する」という住み分けがあり、雷次は京都撮影所で活動していた。
『血まみれの仁義』は昭和初期が舞台の作品だったが、任侠物は例外的に京都撮影所で撮影されていた(『悪名』シリーズも京都撮影所の製作だ)。
そんな雷次が初めて東京撮影所で手掛けた作品が、1967年6月に公開された『奴らに死の制裁を』だ。
前述したように、『血まみれの仁義』の一般受けは芳しくなかったが、中には絶賛した人物もいた。
それは、大映の専属俳優だった田宮二郎である。
田宮は『悪名』シリーズで勝新太郎の相棒として人気が高まり、その後、『黒の試走車(テストカー)』から始まった「黒」シリーズや、『宿無し犬』から始まった「犬」シリーズによって、大映の看板俳優になっていた。
田宮は『血まみれの仁義』だけでなく、それ以前の雷次の監督作も高く評価していた。彼は雷次と組んでみたいと考え、オファーを出した。
名指しを受けた雷次は田宮に呼ばれ、最初の話し合いを持った。
開口一番、田宮は
「雷坊には、今までに俺が演じたことの無いような役柄を考えてほしいんや」
と告げた。田宮は大阪生まれで京都育ちなので、関西弁だ。
「今までに無い、ですか」
「そうや。俺は喜劇もやったし、重厚な芝居もやってきた。かなり幅広くやってきたけど、まだ他にも掘れる場所は色々とあるはずや。そういう斬新な役を、雷坊やったら生み出せると、俺は期待してる」
「田宮さんほどの人にそこまで言われると、プレッシャーですね。でも、斬新と感じてもらえるかどうかはともかく、現代劇のアイデアなら、実は一つあるんですけど」
田宮の主演を想定していたわけではなかったが、その時に雷次が溜め込んでいたアイデアの中には、現代劇の作品もあった。そして、いずれは形にしたいと考え、機会を窺っていたのだ。
「どういう話なんや?」
「田宮さん、冒頭で死んでもらえますか」
「死ぬって、俺は主役と違うんか?」
田宮が困惑する。
「もちろん主役ですよ。でも、いきなり死ぬんです」
「ワケが分からんなあ。俺は幽霊にでもなるんか」
「まあ、近いですかね」
「すると、やろうとしてるのは怪談話か」
「いえ、違います。ハードボイルドなアクションです」
「どういうことや?」
田宮の困惑は、ますます深まった。
「まだ大枠しか考えてませんけど、こういう話なんですよ」
雷次は、大まかな筋書きを説明した。
「なるほど」
田宮は腕組みをした。
「それは、なかなか風変わりな話やな」
「もし気に入ってもらえたんでしたら、社長に企画を通して、百田と脚本に仕上げますけど」
「うん、それで行こう。よろしく頼むわ」
こうして、『奴らに死の制裁を』の企画は、いとも簡単に立ち上がった。
===================
『奴らに死の制裁を』
〈 あらすじ 〉
非番の警察官・鎌田義男(田宮二郎)は、吉永弥太郎(小池朝雄)がボスを務める「吉永興行」の組員たちによる殺人現場を目撃し、始末された。組織は鎌田の死体を山奥に埋め、失踪したように偽装した。
数日後、吉永興行が縄張りとする街に、一人の男が現れた。男は鎌田に瓜二つだった。しかし動揺した吉永興行の組員たちが接触すると、男は門倉卓也という名前で、身分証にもそう書かれていた。
門倉は吉永興行の事務所に現れ、用心棒として雇ってくれと持ち掛けた。
「用心棒など必要が無い」
と吉永が断ると、門倉は
「アンタたちを狙ってる奴がいる。気を付けた方がいいぜ」
と告げて立ち去った。
その夜、組員の田所(橋本力)が殺された。幹部の川上(五味龍太郎)は門倉と会い、狙っている人物に関して教えるよう要求する。すると門倉は冷たい笑みを浮かべ、
「死んだ男だ」
と意味深な言葉を口にした。
組員の米山と牧口が立て続けに命を奪われ、吉永は門倉が犯人だと確信する。彼は川上を差し向け、門倉を始末しようとした。しかし門倉は煙のように姿を消すと、吉永興行の事務所に出現した。彼が吉永と話している最中、組員の多田が死体で発見されたという知らせが入った。門倉にはアリバイがあり、その殺しは不可能だ。一方で現場の近くでは、鎌田に似た男が目撃されていた。
謎が深まる中、吉永は恐怖から精神的に不安定な状態となった。川上は門倉を狙撃しようとするが、背後から襲われて死んだ。吉永は鎌田の死体を確認するため、山へ向かった。彼が土を掘り返しているところへ、門倉が現れた……。
===================
『奴らに死の制裁を』は、シンプルな復讐劇ではなく、ホラーの要素を取り入れた異色のハードボイルド映画として作られた。鎌田と門倉が同一人物なのかどうか、それは最後まで明確にされない。謎を残したままで、映画は終幕を迎える。
1967年6月に公開された『奴らに死の制裁を』は、映画評論家から高く評価された。観客動員の方も、『白い巨塔』のようなビッグ・ヒットではなかったが、それなりの結果を出した。なお、雷次は警官役で出演している。
雷次と田宮は、翌年にも再びコンビを組んで映画を作ろうとしていた。しかし、それは不可能となってしまった。
1968年6月に公開された今井正監督の作品『不信のとき』を巡るトラブルが原因で、田宮が大映を解雇されてしまったからである。
『不信のとき』の主役は田宮だったが、宣伝ポスターでは序列が4番手扱いとなっていた。彼より前の序列には女優陣が並んでおり、それは女性映画として売るための戦略だった。しかし田宮は納得できず、永田社長に直訴した。
結果的に、ポスターの序列は田宮がトップになった。しかし田宮の抗議に激怒した永田は、彼を解雇した。
この当時、映画界には「五社協定」というルールが存在した。大映、東映、松竹、東宝、日活の五社が、専属の監督と俳優を引き抜かず、スターの貸し出しを行わないという協定である。
役者が他社の映画に出演するケースは、全く無いわけではなかったが、制限があった。希望すれば自由に出演できるというものではなかった。雷次も『お坊主天狗』の際に東映の俳優だった剣劇スター、近衛十四郎の起用を望んだが、叶えられなかった。
永田は、この五社協定を持ち出し、他の会社にも田宮を映画やテレビドラマで起用しないよう通達した。このため、田宮は大映との契約期間が終わる1969年6月まで、映画界から追放される形となった。
田宮の解雇を知った時、雷次は永田に会って翻意を求めた。しかし永田の怒りが強いと見て、説得を諦めた。永田が激怒すると、もう何を言っても聞く耳を貸さないことを、雷次は知っていた。
「あのバカ社長、自分で自分の首を絞めやがって」
雷次は永田と面会した後、そう吐き捨てた。
田宮は大映の看板俳優であり、その彼を解雇することは、会社にとって大きなダメージだった。実際、田宮の解雇によって、ただでさえ経営の苦しかった大映は、さらに追い込まれていくことになるのだ。
しかし永田にとって、そんなことは二の次だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
