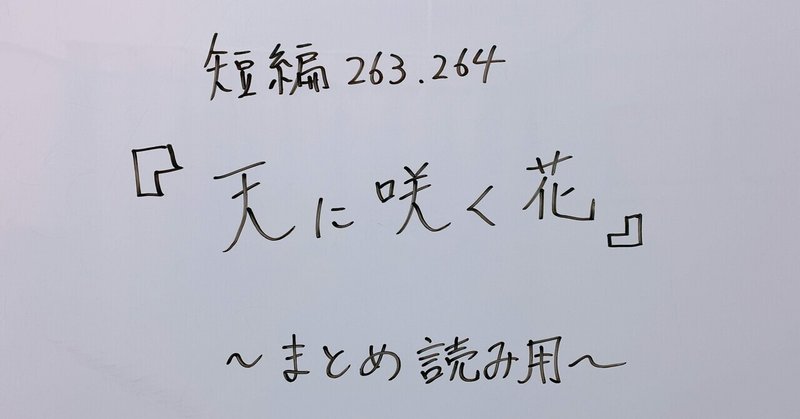
短編263.264『天に咲く花』(まとめ読み用)
独りで酒を飲んだところで何も変わらない。それは分かっている。世界がそんなに単純じゃないことは知っているし、酒が解決策をもたらすことはないことも理解しているつもりだ。
しかし、私は今こうしてバーにいる。暗い間接照明に背中を照らされて。もしこの世にバーというものが無ければ、悩みを抱えた人々は一体何処に行くのだろう。マクドナルド?そんなことはないだろう。蛍光灯による明るい照明と女子高生の奇声嬌声の中で”もの”を考えられる奴なんていない。腹か、竿をおっ立てるのがオチだ。
のしかかるストレスは相撲レスラー並みの最重量級、胃に空いた穴は宇宙みたいに広大無辺。そんなことが一つの身体に起きているのだ。この先に待つのが幸福とは考えづらい。私の来訪を楽しみに待っていてくれるのは死くらいのものだ。もし、私がハードボイルドでなければ颯爽とそこに向かって飛んでいることだろう。
私はブコウスキーの『The History of One Tough Motherfucker』という詩を頭の中で諳(そら)んじた。それは、ブコウスキーが痩せ細って尻尾も切り落とされた野良猫を拾うところから始まる(そしてそのすぐ後には、友達の車がその猫を轢く)。そんな状態でも猫は生き延び、動かぬ後ろ足と寄り目と無い歯、身体に残る散弾銃の弾を抱えて、しかしリラックスした余生を過ごす、そんな詩だ。
その詩は私にとっての御守り、この世界の最果てに設けられた防波堤のようなものだ。防波堤の先にある暗闇を覗き込み、手を伸ばして触れてみることもあったが、気が付けば乗り出した身は引き戻されている。その波止場にはいつだってこの詩がBGM代わりに流されている。
*
ジン、ウォッカ、ウィスキーと杯を重ね、思考に磨きをかけていくうち、私の目の前に小人が現れた。ウィスキーグラスよりもやや小ぶりなサイズ感のそれは一枚板のカウンターテーブルの端からやってきた。
*
私がそいつを見た時はちょうどテーブルによじ登るところだった。小さな手を角に引っ掛け、自分の身体を引き上げる。そんなシーン。ーーーよいしょ、よいしょ。そんな声も聴こえた。私は首を振った。
ーーー酔い過ぎだな。
私はバーテンダーに水を頼んだ。
小人は優雅にテーブルの真ん中を歩き、私の前までやってくるとウィスキーグラスに背中を預けた。先っぽにボンボンの付いた三角帽子を被り、お伽噺の世界御用達といった風情の上下セットアップ。可愛らしいルックスとは裏腹に顔は老人のそれだった。トータルで見ればその姿は私に、雪山のヒュッテに常備されたトランプのジョーカーの絵柄を思い起こさせた。
「別に酒のせいばかりではあるまいよ」と小人は言った。
私は水をさらに二杯頼んだ。
「悩み事があるんだろう。どれ、一つ私に話してみなさいよ」
目の前に並べられた三つのグラスを順番に煽っていく。水、の味がした。
ーーー口に出した方が良いのだろうか、それとも思うだけで良いのか。
「なに、思うだけで構わんよ。君と私の間に一つ、思考のチャンネルを開いたからな。それにバーで独り言を言い始めたら、それは終わりの合図に他ならない。つまみ出されるのがオチだよ」
ーーーオーケー。分かった。乗りかかった船にはしがみついてでも乗るタチだからね、おれは。ところで、なんて呼べば良い?
「そうだな。ワンタフマザファカ、とでも呼んでもらおうか」
ーーーだったら、猫の姿で出てきて貰いたかったね。
*
これはそんな酒の神との束の間の対話の物語である。
*
バーテンダーの目に、今の自分はどう映っているのだろう。水を立て続けに三杯飲み干した挙句、一点見つめて静止した男は。クールガイ、という認識だと良いのだが。
「別になんとも思っちゃいないよ、バーテンダーは。綺麗な女以外には全て盲目」とワンタフマザファカは言った。…ワンタフマザファカ?なんだそれ。
私は私を見回した。全てが違っていた。
「そう。君は綺麗でもなければ女でもない。だから視界の端にも入っていないよ」
ーーーおれはバーテンダーだけじゃなく、誰の視界にも入っていない。
「ふむ。それが悩みか」
根本にあるのは、それだろう。いつだって孤独の旅路を歩いている。砂塵に目を潰され、寒風に身を切られながら。実体としての姿形を持ちながら、誰にも見えてない存在。そんな奴が何をやろうが、どんな努力をしようが、世間には届かない。現に私のSNSアカウントは”フォロー中”にしか数字がない。名言を引いた短文の意識高い文章投稿数は一万を超えたところだが。
「冬に種を蒔く馬鹿はいないし、春蒔いた種が春のうちに花を咲かすことはない」とワンタフマザファカは言った。
ーーー長い冬だ。
「夏に咲く花は夏にしか咲かないもんだよ。違うかい?」とワンタフマザファカは言った。
ーーー長い春だ。
「秋に実る実を夏のうちに刈り取れば、その収穫は少ない」とワンタフマザファカは言った。
青光りするシワのよったスーツからはみ出す三千円の時計。無駄にゴールドに輝いている。アメ横で買った中国製。プロフィール写真用に必要だった。実際に金を持っていることよりも金を持っていそうに見えることが大切なこの時代、分かりやすさこそが正義だ。ツーブロックに刈り上げ、グリスでオールバックに固める。外資系保険会社の末端か情報商材屋の出来上がりだ。
「まずは畑を耕すところから始めた方が良さそうだな、ボーイ」
ーーーそうだね。お疲れ様とだけ言ってもらいたい、かな。
いつの間にか小人は消えていた。ずっと注視していたはずなのだが、そこにはもうウィスキーのグラスしか無かった。私は財布から壱万円札を抜き取ってグラスの底に挟み、その場を離れた。
出口の扉につけられた鈴の音は確と鳴った。しかし、バーテンダーの耳には聞こえなかったようだ。
*
あの出来事を今こうしてシラフの頭で振り返ってみれば、実に異様なひとときであったと思う。
ーーーあれは酒が見せた幻覚だったのだろうか。
でも、あの場では全てが手触りのあるリアルだった。ワンタフマザファカと名乗る小人の声は確実に鼓膜を揺らし、グラスについた水滴は小人の形にくり抜かれて乾いていた。
何にせよ、もう何でも良かった。幻覚だろうが、妄想だろうが、脳の器質的な異常であろうが。
腕に時計は既になく、グリスもスーツもゴミ箱に放り込んである。
#ブコウスキー #バー #酒 #猫 #神 #詩 #春夏秋冬 #易 #小説 #短編小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
