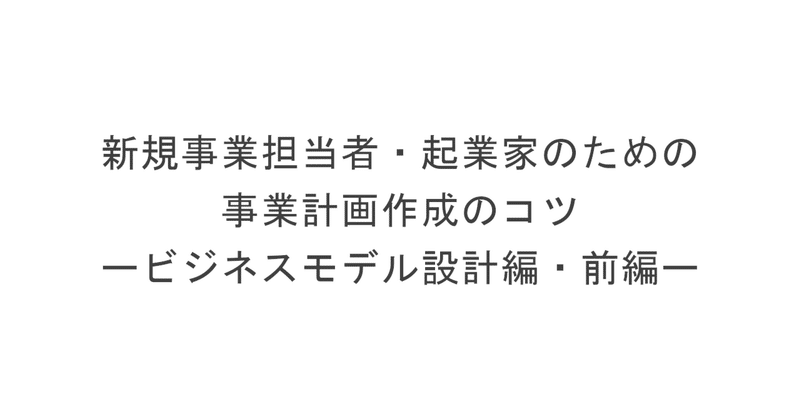
新規事業担当者・起業家のための事業計画作成のコツービジネスモデル設計編・前編ー
西田 泰典さん著『事業計画に落とせるビジネスモデルキャンバスの書き方』では、資金獲得をめざす新規事業担当者・起業家のために、紙一枚から作る穴のない事業シナリオ「ビジネスモデル・キャンバス」の書き方をご紹介しています。
新規事業想像プロセスの全体像
新規事業を立ち上げるまでのプロセスは、
1.新規事業構想
2.ビジネスモデル設計
3.事業計画書の作成
4.投資の意思決定
の4つのフェーズで構成されます。
ー2.ビジネスモデル設計編・前編ー
ビジネスモデルとは
新規事業で何をするかが決まったら、次はビジネスモデルの設計をします。
ビジネスモデルという言葉の定義には、多くの研究者がそれぞれ違った見解があるのでいくつかご紹介します。
ビジネスモデルは、ビジネス機会の活用を通じて、価値を創造するための取引内容や構造、ガバナンスに関する設計
経営資源を一定の仕組みでシステム化したものであり、その活動を自社で担当するか、社外の様々な取引相手との間にどのようなkン系を築くか、を選択し、分業の構造、インセンティブのシステム、情報、モノ、カネの流れの設計の結果として生み出されるシステム
ビジネスモデルは、ビジネスが顧客と企業の双方にとっての価値をどようにして創造・提供するかを表現したもの
ビジネスモデル・キャンバスとは
2010年にアレックス・オスターワルダーとイヴ・ピニュールがビジネスモデルの設計・実現、既存のビジネスモデルを分析・変革するための方法として提唱したフレームワークです。
ビジネスモデル・キャンバスはビジネスモデルを9つのブロックに分類して、それぞれが相互にどのように関連しているか図示したものです。9つのブロックを記入していくとビジネスモデルを設計することができます。

ビジネスモデルキャンバス導入のメリット
メリットは主に3つあります。
①ビジネスモデルを容易に設計できる
②組織内でのコミュニケーションツールとなる
③ビジネスモデルを検証するのに相性がいい
①ビジネスモデルを容易に設計できる
ビジネスモデル・キャンバスを活用すれば、一枚でビジネスモデルを図示でき、シンプルでわかりやすく、かつ9つのブロックを書き入れることでビジネスモデルに欠かせない構成要素を抜けもれなく設計することができます。
②組織内でのコミュニケーションツールとなる
ビジネスモデル・キャンバスは組織内の共通言語として活用することができます。
ビジネスモデルを議論する際、社内の様々な立場の人たちが、それぞれの立場から意見を主張します。
ビジネスモデル・キャンバスは構造化されたビジネスを俯瞰することができるため、異なる立場を理解した上で議論することができるようになります。
③ビジネスモデルを検証するのに相性がいい
ブロックに書かれている内容の仮説を立て、検証を繰り返しながら議論を重ね、追加したり、削除したりすることでビジネスモデルの完成度を徐々に高めていくことができます。
ビジネスモデルの完成度を高めるポイント2つ
①3つ目のを意識する
鳥の目、虫の目、魚の目
②マーケティングの基本を理解しておく
マーケティングの基本として「STPP」を理解しておきましょう。
STPPはマーケティングの世界的権威であるフィリップ・コトラーが提唱したもので、マーケティング戦略を策定のためのステップを示しています。
S・・・セグメンテーション(Segmentation)。標的とする市場を絞り込む、分けること
T・・・ターゲティング(Targeting)。顧客を特定すること。
P・・・ポジショニング(Positioning)。どこにポジションを取りながら価値提供をするのかを考える
P・・・マーケティング・ミックスと呼ばれ、「4P」の「P」を表しています。4Pとは、製品(Product)、価格(Price)、チャネル(Place)、プロモーション(Promotion)の4つの頭文字です。
STPPに沿って検討を進めると誰に、何をどのように販売するか、というのが明確になることでマーケティング戦略の策定ができます。
ビジネスモデル・キャンバスの右側5つのブロックはこのマーケティングのSTPPと深いかかわりがあります。この記事では右側5つのブロックの書き方についてご紹介します。
ビジネスモデル・キャンバスの書き方
<顧客セグメント>
このブロックでは主に以下の3つを検討します。
①誰に
②JOB
②顧客が抱える切実な問題

①誰に
誰のための価値を創造するのか?
もっとも重要な顧客は誰なのか?
を明確にします。
マーケティング戦略施策STPPの「S(Segmantaition)」、「T(Targeting)」をより明確に絞り込むプロセスです。
①-1.toC/toB それぞれの切り口で絞り込む
まず、BtoCか、BtoBかで分けて考える必要があります。
そのうえで、それぞれの切り口で絞り込みましょう。
BtoCの場合の切り口

BtoBの場合の切り口

BtoBは少なくとも2つ以上の切り口で絞り込むとよいでしょう。
ただ、上記の切り口は他社も同様に絞り込んでいるので差別化をはかるためには独自の切り口で絞り込むことがベストです。
①-2.標的とする市場を絞り込む
次に、以下の3つの視点から標的とする市場を絞り込みます。
・市場の魅力度
・競合他社の参入状況
・自社の資源の適合度(自社の強み、技術力、顧客基盤、生産能力など)
ここで注意したいのは、既存の顧客だけを見るのではなく、未開拓の新しい顧客まで視野を広げることです。
また、この段階では、ターゲット顧客を決め打ちするのではなく、候補となる顧客をいくつかあげておくにとどめます。
②JOB
JOBとは顧客が自社の製品・サービスを使って、やりたいこと、成し遂げたいことです。
※②、③は本来ビジネスモデル・キャンバスには記入しませんが、真に顧客が求める価値を提供するために追加検討します。
顧客が抱える問題やニーズを的確にと捉えるためには、まずJOBを明確にする必要があります。
かつてマーケティングの権威であるセオドア・レビットはこのようにいいました。
顧客はドリルが欲しいのではなく、穴が欲しいのである
これはJOBを的確に表現しています。
JOBを理解できていないと、どうしてもドリルの方にフォーカスしてしまい、ドリルの性能や、品質を向上させることに注力するでしょう。
しかし、穴をあけられるのであれば、ドリルではなく桐でもいいのです。
「JOB」こそが顧客が、製品・サービスを購入する決定要因となります。
③顧客が抱える切実な問題
ここでいう「問題」とは、②JOBを阻害している問題のことを指します。
顧客が求める本質的な価値を提供するためには、顧客が切実に困っている問題を解決する必要があります。
顧客が抱える切実な問題を解決する4つの視点
③-1.現状対策
③-2.現状対策における問題点
③-3.その問題のインパクト
③-4.同じ問題を抱えている人の多さ
③-1.現状対策
顧客が切実に困っている問題であれば、必ず何か対策を打っています。逆に、対策を打っていないのであれば、切実に困っている問題ではないということです。
顧客が現状どのような対策を打っているかを調査します。
③-2.現状対策における問題点
現状対策が明確になったら、その対策で何が問題なのかを明らかにします。ここで明らかになった問題は、ビジネスモデル・キャンバスに書き入れましょう。
③-3.その問題のインパクト
どれくらい問題が深刻か、影響度はどれくらいあるかを確認します。
このインパクトを定量化しておくとより説得力が生まれます。
例えば、工数が○○時間かかっていて無駄が多い
コストが○○億円かかっていて大きな負担になっている など
③-4.同じ問題を抱えている人の多さ
この点については次の「顧客が抱える切実な問題を捉える上でのポイント」について具体的に述べますが、顧客はこのような問題を抱えているのではないか、と仮説を立て、インタビューや現場の観察をすることによって裏付ける必要があります。
顧客が抱える切実な問題を捉える上でのポイント
③顧客が抱える切実な問題を検討したら、次の3つの条件を満たしているかを確認します。
③-5.顧客が対価を支払ってまでも 解決したい問題か?
③-6.潜在化している問題を捉えているか?
③-7.共通している切実な問題か?
③-5.顧客が対価を支払ってまでも 解決したい問題か?
「顧客が抱える切実な問題」の仮説を検証するためにインタビューをしてみると、顧客からは「確かに問題を抱えているが、お金は支払えない」といわれることがよくあります。
この場合9割近くが最初に検討した「顧客が抱える切実な問題(仮説)」が外れてしまっています。
つまり、思い込みが多いということです。そのために顧客へのインタビューは欠かせません。
③-6.潜在化している問題を捉えているか?
潜在化している問題とは、顧客は問題があることをなんとなく感じているが、何が要因なのかはっきりとわかっていないような問題です。
反対に顕在化している問題は、顧客自身がきちんと認識している問題で、同時に、競合他社も認識している問題といえます。
潜在化している問題を捉えることで優れたビジネスモデルに近づけます。
③-7.共通している切実な問題か?
1つの企業だけに当てはまる問題ではなく、ターゲティングした顧客層が抱える共通の問題になっているかを見極めます。
ビジネスモデル・キャンバスの書き方
<価値提案>
このブロックでは以下の2つを検討します。
①製品・サービス名
②価値

①製品・サービス名
価値の提供を実現するための手段を記述します。
先述した「顧客が欲しいのはドリルではなく穴である」に当はめると、ドリルに該当します。
提供する価値とそれを実現するための手段を混同してしまうひとが多いので注意しましょう。
②価値
「価値」という言葉の解釈は様々あるので、ドトールとスターバックスを例に認識を合わせておきましょう。
目の前にスターバックスコーヒーとドトールがあったらどんな理由で、どちらに入りますか?
スターバックスを選ぶ人は「ゆっくりできる」「考えごとをするときに最適」「落ち着く」という理由が多く、ドトールを選ぶひとからは「安い」「待たされない」「喫煙できる」という理由があがります。
両社の提供する価値は全く異なることがわかりますね。
また、両社は同じコーヒーを販売していますが「コーヒーがおいしいから」と回答をするひとはほとんどいません。
つまり、コーヒー自体は価値を提供する手段であって、顧客にとっては価値になりにくいということです。
上記のように、価値というのは、簡単にいえば「購入理由」と言い換えることができます。
さらにここで検討する「価値」は、以下の3要素を満たしたものを検討します。
②-1.顧客の問題を解決できる
②-2.他社が提供していない
②-3.自社の強みが反映されている
②-1.顧客の問題を解決できる
価値は顧客の問題を解決できるものでなければなりません。
そのためには<顧客セグメント>で検討した「③顧客が抱える切実な問題」を解決できる価値を明らかにしなければいけません。
②-2.他社が提供していない
加えて、価値は他社が提供していないものでなければなりません。
例えば、高い品質を提供していることは価値にはなりません。
②-3.自社の強みが反映されている
さらに価値は自社の強みが反映されていなければなりません。優位性を持続する必要があるからです。強いが反映できなければ他社と連携して価値を生み出すこともひとつの手です。
価値を検討する際の2つの切り口
②-4.必需的価値 or 魅力的価値 の切り口で検討する
価値を検討する切り口として、必需的価値が提供できているかどうかを意識しましょう。
魅力的価値はあると満足度向上、他社との差別化につながります。

②-5.機能的価値、経済的価値 ot 情緒的価値の切り口
日本の製造業は、上記の価値のうち「機能的価値」に偏る傾向にあるので注意が必要です。
価値は機能だけではありません。経済的価値、情緒的価値の観点を含め、広い視野で検討する必要があります。3つの価値をバランスよく反映できるといいでしょう。

②-6.競合を意識した価値か
ビジネスモデル・キャンバスには競合他社について記述するところがありません。
競合を意識しすぎると革新的なビジネスモデルが生まれにくくなる、という懸念もありますが、競合他社を全く意識しないといわけにはいきません。
参入が想定される競合他社がどんな価値を提供するのかは少なからず考えておく必要があります。
ビジネスモデル・キャンバスの書き方
<チャネル>
チャネルはマーケティング戦略策定「STPP」でいうところの最後の「P」の中の一つ「Place」に該当します。顧客と企業の接点となる場所です。

チャネルがもつ5つの機能
チャネルは大きく5つの機能に分けられます。
5つの機能のうち、自社の製品・サービスを提供するにあたって最も適したチャネルを選択します。
①認知
②評価
③購入
④提供
⑤アフターサービス
①認知
企業の製品・サービスを顧客に知ってもらうことを指します。
トヨタのレクサスが初めて市場に投入された際、全国に多くの販売店が展開されました。高級感あふれる販売店を設計することで「高級ブランド」ということを全国に認知させました。
②評価
顧客に企業の製品・サービスを評価してもらうことを狙いとしています。
電子ペン大手のワコムは、店舗を出店していますが、店頭ではペンを試してもらうのみで、インターネットで購入してもらう方法をとっています。
これは顧客からの評価を促すことを目的とした販売方法です。
③購入
実際に購入してもらう接点です。
BtoC企業の例
・コカ・コーラの場合 のどが渇いて飲みたい時に飲める➡自動販売機
・ルイヴィトンの場合 ステイタスを感じられる場所➡直営店、百貨店
・セブンイレブンの場合 近くで手軽➡効率よく店舗が展開できるフランチャイズ制
BtoB企業の場合は、まず以下の3つをのうちのいずれかを検討します。
・営業担当者を自社で抱える 直接販売
・販売店や代理店などを利用して他社に販売してもらう 間接販売
・直接販売と間接販売のミックス
さらに直接販売であれば、直営店を持つ、WEBで販売するのか。
間接販売であれば卸売業者に卸すのか、販売店に卸すのかという分岐があります。
一般に直接販売の場合は、顧客の声を収集しやすく、製品・サービスを自社でコントロールしやすいというメリットがある反面、人件費という莫大なコストを抱える必要があります。
間接販売は一気に製品・サービスを全国展開するときには適しています。
④提供
製品・サービスを顧客に届ける機能です。
⑤アフターサービス
販売後に顧客が求めるサービスを提供する機能です。
家電やブランド品など、保守・修理が必要な製品ではアフターサービスを重視すると提供する製品・サービスの価値が高まります。
ビジネスモデル・キャンバスの書き方
<顧客との関係性>
このブロックはマーケティング戦略策定「STPP」でいうところの最後の「P」の中の一つ「Promotion」に該当します。顧客との関係を構築あるいは維持するための活動や仕組みを記述します。

顧客との関係を構築・維持のための2つの視点
①顧客獲得
②顧客維持
①顧客獲得
新しい顧客を獲得する際にどんなプロモーションをするのかを検討します。
自社が検討する価値に合わせてバランスよく組み合わせる必要があります。
a. 広告(プル戦略)
b. パブリシティ(プル戦略)
c. 人的販売(プッシュ戦略)
d. 販売促進(プッシュ戦略)
②顧客維持
次に、顧客を獲得した後、関係性を維持するための活動や仕組みについて検討します。
②-1.ロイヤリティを高める
業種にもよりますが、顧客が年間に離反する比率は約2割といわれています。
また一般的に、新規顧客を獲得することと、既存顧客に販売するときのコストを比較すると、約5倍新規獲得の方が高くなると考えてられています。
その点で顧客生涯価値(LifeTime Value)を意識したビジネスモデルが重要です。
LifeTime Valueとは、ある顧客から生涯に渡って得られる利益のことです。
ビジネスモデル・キャンバスの書き方
<収益の流れ>
このブロックはマーケティング戦略策定「STPP」でいうところの最後の「P」の「Price」に該当します。
収益は「顧客単価 × 顧客数」で表すことができます。

このブロックで明確にすべき点は以下の3点です。
①主な収益項目
②収益の獲得方法
③収益の流れ
①主な収益項目
設計するビジネスモデルで獲得できる主な収益項目を記述します。
ここでは詳細に記述する必要はありません。
箇条書きで表現してみましょう。
例)ICT企業がソリューションを提供する場合
・コンサルティング料
・ハード機器料
・ソフトウェア料
・保守サービス料
・オプション料
頻繁にリピート購入してくれそうな収益項目があるかどうかについても確認しましょう。
①-1.価格設定:ペネトレーション・プライス
最初に低価格で設定し、早期のシェア獲得を目指す手法です。
シェアを獲得しておくことで、その後の競争が有利になったり、量産できるようになるので1つあたりのコストを下げられるようになります。
①-2.価格設定:スキミング・プライス
最初に高価格で設定し、開発費の早期回収をする手法です。
市場投入当初から確実な利益が見込める可能性が高まりますが、競合が同じサービスを低価格で展開し始めたときにそのままの価格帯でいるとあっという間にシェアを奪われてしまいます。
②収益の獲得方法を検討する
顧客が喜んでお金を支払ってくれる収益の獲得方法を検討しましょう。
代表的なものとして以下5点があります。
②-1.継続
②-2.囲い込み
②-3.高い利ざや
②-4.メリハリ
②-5.他の収益源
②-1.継続
最近では安定した収益が見込める、という理由で、継続して収益を獲得する継続型ビジネスが増えています。
例)キャノン、エプソンのプリンター業界
ハード機器は品質がよいにもかかわらず、1万円を切るような価格設定ですが、純正インク、トナーは5000円以上します。
例)動画配信サービス
サブスクリプション(定額課金モデル)
例)あべのハルカス入退場システム
成果に応じて支払額を決めるレベニューシェアを採用。
入退場者数が少ない頃は費用を抑えることができ、入退場数が増えたときに支払額が上がる。
②-2.囲い込み
新しいビジネスモデルは既存の顧客が存在しません。顧客を囲い込むための手段として一定期間の無料、あるいは低価格で提供することが有効です。
②-3.高い利ざや
価格とコストの差を作って利益を得る考え方です。
かつて日本の製造業は「良いものを作って安く売る」という考えがシュル夕でしたが、利ざやで儲ける場合は「安く作って高く売る」という考えになります。
キーエンスは粗利益率80%以上でなけれ商品を開発しません。コストを最小にして価値を最大化する努力を徹底しています。
②-4.メリハリ
一律に製品・サービスに利益をのせて販売するのではなく、儲ける製品・サービスと儲けなくてもいい製品・サービスを分け、総合的に儲けを生み出す考え方です。
例)マクドナルド
メインの商品であるハンバーガーでは儲けをとらず、ポテトなどのサイドメニューで利益を生み出しています。
②-5.他の収益源
メリハリと考えて方は似ています。別のサービスで儲けを出す考え方です。
例)ミュゼ・プラチナム
脱毛サービスを展開する企業ですが、数百円でサービスを提供しています。
機材は高額で出店にも多額の費用がかかりますが、数百円のサービスで獲得した膨大な顧客データをヘルスケアや化粧品会社に販売し利益を獲得しています。
③収益の流れ
収益の流れはピクト図での表現をおすすめします。
収益の流れを設計するときは、すべての利害関係者がWIN-WINになるように意識します。自社だけが儲かればよい、というモデルでは継続していくのは難しいでしょう。
ここまで、ビジネスモデル・キャンバスの右側の5つのブロックをご紹介してきました。
残り4つのブロックは後編にてご紹介します。
書籍購入にあてさせていただきます🍃
