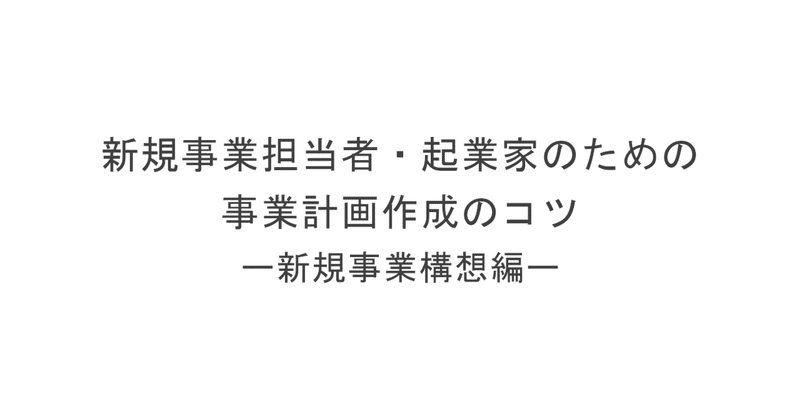
新規事業担当者・起業家のための事業計画作成のコツー新規事業構想編ー
西田 泰典さん著『事業計画に落とせるビジネスモデルキャンバスの書き方』では、資金獲得をめざす新規事業担当者・起業家のために、紙一枚から作る穴のない事業シナリオ「ビジネスモデル・キャンバス」の書き方をご紹介しています。
はじめに
新規事業を生み出す際、最も重要なのは「ビジネスモデル」です。
ビジネスモデルとは、2010年にオスターワルダーとピニュールが「どのように価値を想像し、顧客に届けるか論理的に記述したもの」と定義しています。
そして、視覚的にビジネスモデルの構造を紙にまとめたフレームワーク「ビジネスモデル・キャンバス」を提唱しました。
この記事では『事業計画に落とせるビジネスモデルキャンバスの書き方』をもとにビジネスモデル・キャンバスを活用して新規事業を成功させたいと考えいている人へポイントを解説していきます。
新規事業想像プロセスの全体像
新規事業を立ち上げるまでのプロセスは、
1.新規事業構想
2.ビジネスモデル設計 前編/後編
3.事業計画書の作成
4.投資の意思決定
の4つのフェーズで構成されます。
本書では1~3のプロセスについてご紹介します。
1.新規事業構想
新規事業は3つに分けられる
新規事業は主に次の3つに分けられます。
・周辺事業を拡大したい新規事業
・エリアを拡大した新規事業
・多角化を狙った新規事業
周辺事業を拡大したい新規事業
既存の市場・顧客に対して、新規の製品・サービスを展開するものをいいます。
例)建機メーカーのコマツが建設機械にGPS機能を付けた「KOMTRAX」という事業。機械の盗難防止や、事故を未然に防ぐという価値を創出。
エリアを拡大した新規事業
新規の市場・顧客に対して、既存の製品・サービスを展開するもの。
例)輸送機器メーカーのホンダが、スーパーカブをASEANの新興国などの新たな市場に展開。
多角化を狙った新規事業
新規の市場・顧客に足して、新規の製品・サービスを展開するもの。
この象限はさらに2種類の分かれます。
①すでに他社が取り組んでいて世の中に事業として存在するが自社にとっては初めての事業となるもの
例)富士フイルムが医療機器事業や化粧品事業に参入
②まだ世の中に存在しないゼロから生み出す事業
例)Uberタクシーの配車アプリ事業、Airbnbの民泊仲介事業
筋のいいテーマを見つける
事業テーマの検討にあたっては、市場性や他社の動向を調査する等、十分なインプットを行い、ヒアリングによって裏付けとなる情報を収集するなどして、慎重に選定することが必要です。
とはいえ、あまり時間をかけすぎると事業環境や市場、顧客の状況がかわってしまいますので注意しましょう。
新規事業を実現する時間軸を決める
チームメンバー間で時間軸を共有することはとても重要です。
3年後に実現したいのか、5年後か、10年後か、それによって新規事業の内容は大きく変わります。
例えば3年後であれば既存の自社のコア技術を活用しながら今の事業の半歩先を行くような提案になるでしょう。実現性は高いですが、すぐに他社に追いつかれる可能性もあります。
10年後、あるいはもっと先の実現であれば空飛ぶ車や宇宙エレベーターといった夢のような事業テーマ案になるかもしれません。
アイデアを生み出す6つのインプット
アイデア出し、といえばブレーンストーミングを思い浮かべるかもしれませんが、新規事業のテーマ選定には向きません。
「筋のいいテーマ」を導くためには、市場や顧客にたいする深い洞察や技術に関する理解が必要です。そのためにはまず個人で、市場や顧客、技術に対して十分なインプットをしておく必要があります。
インプットの6視点
①取り組む意義
②マクロ環境
③市場・顧客
④自社
⑤競合
⑥他社の成功事例
①取り組む意義
取り組む意義とは、新規事業の「背景」を確認することです。
なぜ自社が新規事業に取り組むのか、なぜその事業テーマを選定したのかの理由です。
②マクロ環境
自社だけではコントロールできない、受け入れざるを得ない環境を指します。マクロ環境を捉える手法としてPEST分析があります。
PEST分析とは、政治・法律(Political)、経済(Economic)、社会(Social)、技術(Technological)、の4つの切り口から事業の変化を捉える分析手法です。
4つの視点からマクロの変化を洗い出し、新しい事業を立ち上げる上で、プラスになるか、マイナスになるかを判断し、その影響度を評価することが重要です。
③市場・顧客
市場については、まず対象市場を決め、その市場規模がどれくらいなのかを検討します。また、どれくらいの割合を自社がとるのか、新規事業の規模を予想します。
すでに市場が存在するのであれば、各省庁や各業界団体、民間調査会社が発表しているデータや調査会社のレポートなどからおおよその市場規模を把握することができます。
全く新しい市場の場合は予測値を作る必要があります・
代表的な方法としては「顧客数×顧客単価×頻度」で概算値を導き出すことができます。概算値から将来どうなりそうかの動向についてもある程度イメージしておくことが重要です。
次に、市場だけでなく、顧客の情報について着目することも重要です。顧客の困りごとの中でも、潜在化している問題を少し掘り下げてみましょう。
④自社
自社の強みと弱みを理解し、特に自社の優位性について理解しましょう。
「コア技術」や「有望技術」を特定するためには、その技術の水準が競合他社の技術と比較して優位にあるか、同レベルか、あるいは弱いのかに分け、さらに技術の成熟度を、揺籃期(ようらんき)、成長期、成熟期、衰退期に分けて判断します。
⑤競合
まず、すでに他社が取り組んでいないか、を確認します。
これらを調べることは困難ですが、公開されている情報だけでも十分情報を得ることができます。
他社がすでに取り組んでいたら自社が提案するものとの差別化を検討しましょう。
また、思いついた事業テーマの代替となる商品・サービスが存在するかどうかも確認しましょう。
⑥他社の成功事例
業界が同じ他社の事例を取り入れれば「模倣」になりますが、異なる業界の事例を取り入れると「イノベーション」につながります。
他社の事例をインプットし、ブラッシュアップして取り入れましょう。
事業テーマ案を決める
6つの視点で情報をインプットした後、事業テーマ案を検討します。中心となるのは、「市場・顧客」に関する情報と「自社」に関する情報です。これらを中心に組み合わせることで事業テーマを考えます。
事業が決まらない場合の3つの対処方法
①事業テーマを検討する前のインプットをもう一度やり直す
②組み合わせて考える
③発想力を高めるフレームワークを活用する
発想力を高めるフレームワークワーク
<強制組み合わせ法>
軸を2つ決めてそれぞれに含まれる各要素を組み合わせていき、新しいアイデアに繋がるかどうか検討する
例)外部環境トレンドと内部資源の強みの2軸
<チェックリスト法>
テーマ・対象を決め、あらかじめ準備したチェックリストに答える
例)オズボーンのチェックリスト
「転用」、「応用」、「変更」、「拡大」、「縮小」、「代用」、「再利用」、「逆点」、「結合」
<連想法>
テーマ・対象について連想を広げる
例)「近接」、「類似」、「対象」、「因果」等
事業アイデアを定量的に評価する
テーマを発想した後は、最終的にどのテーマに取り組むのかを決めるべく、発散したアイデアを収束させる必要があります。
マトリクスを活用して定量的に判断する方法を使います。選定する際に重視する評価項目を数値化することでチーム内でも納得度が高まり、合意形成が進みます。
8つの評価基準
①取り組む意義
②市場の魅力度
③自社の優位性
④競合状況
⑤収益性
⑥新規性
⑦実現度
⑧熱意
熱意はなによりも重視すべき項目です。精神論だけで新規事業がうまくいくわけではないですが、困難な壁にぶち当たったとき、熱意がなくては切り抜けることが難しいからです。
事業テーマの妥当性を確認する
いくつかテーマを絞り込んだら、優先度の高いものからその妥当性を確認します。十分なインプットをし選んだアイデアですが、市場に受け入れられるか、魅力があるか、可能性があるかなどを検証する必要があります。
検証はヒアリングを中心に行います。顧客や、技術者、専門家、社内の人間など、できるだけ様々な関係者に検証しましょう。
周囲へ意思表示をすることで重要なキーパーソンに出会うことがあります。とても重要なプロセスです。
まとめ
新規事業テーマを検討するための手順
①十分なインプットを行う(6つの視点)。
②市場、顧客、自社に関することを中心に組み合わせてテーマを検討する。
③決まらない場合は3つのフレームワークを試す。
④決まったアイデアをマトリクスを利用して評価する(8つの評価基準)。熱意は何よりも大切。
⑤妥当性を確認、キーパーソンへ出会うためにヒアリングを行う。
書籍購入にあてさせていただきます🍃
