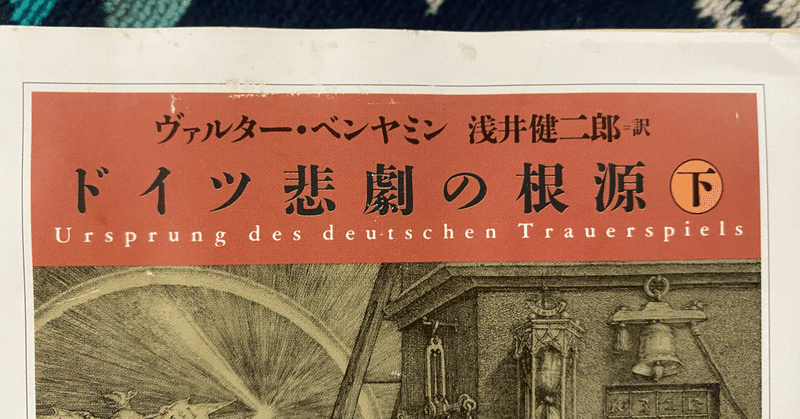
ドイツ悲劇の根源(下)/ヴァルター・ベンヤミン
システム化された象徴はあっても、無定形で断片化しがちなアレゴリーはない。
それが現代の特徴ではあるのだが、そのことが随分と人類のバイタリティを弱めているのではないだろうか?と感じている。
上巻を紹介してから少し間が空いたが、ヴァルター・ベンヤミンの『ドイツ悲劇の根源』の下巻はそんなアレゴリーがテーマだ。
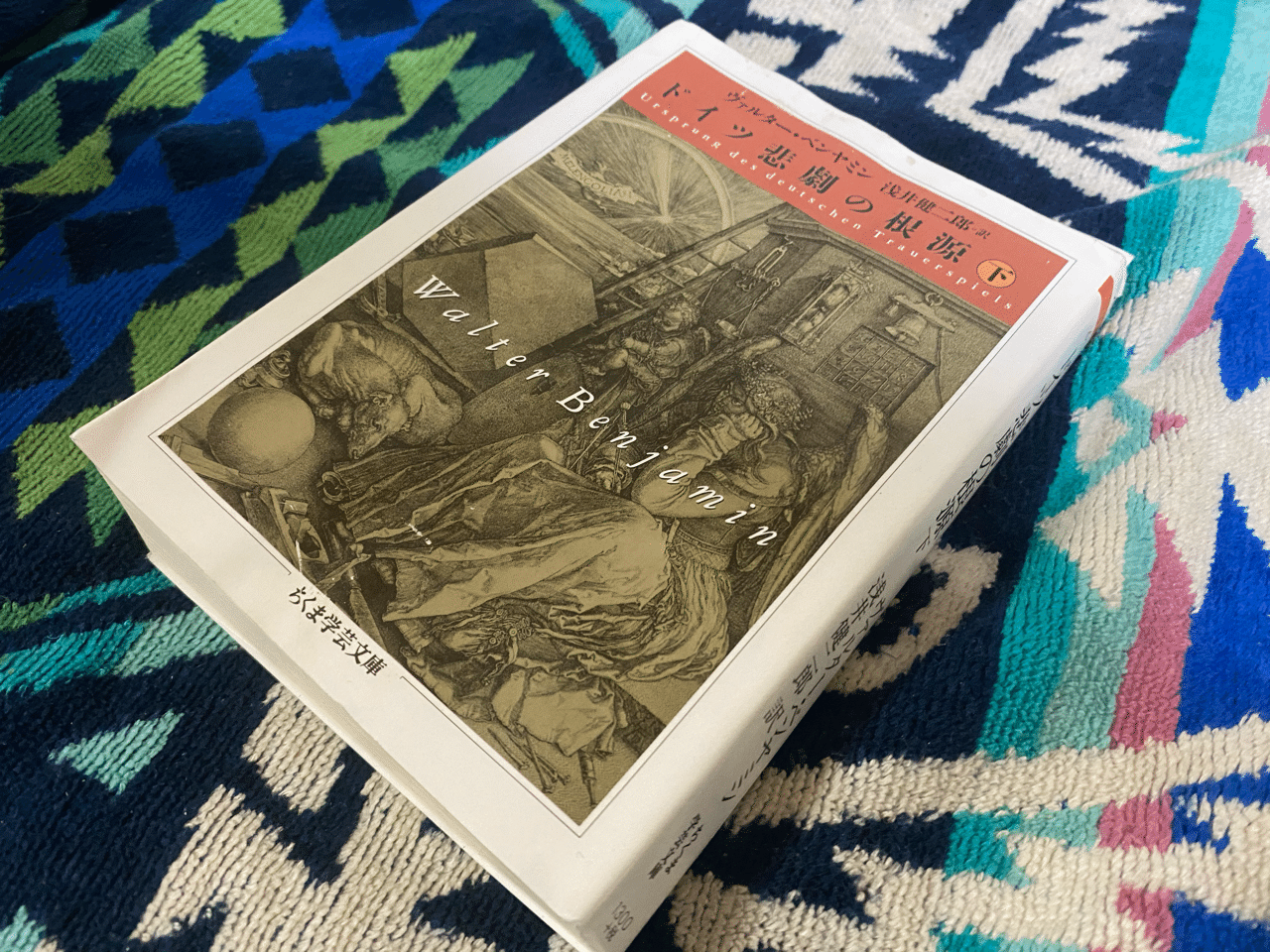
下巻は「アレゴリーとバロック悲劇」と題された第2部にあたる。
第1部の「バロック悲劇とギリシア悲劇」とはずいぶんと内容が異なっている印象を受けた。
古典古代の象徴、バロックのアレゴリーという比較が行われているという面ではもちろん重なる部分はあるが、演劇そのものを直接比較対象とした上巻と異なり、下巻では象徴とアレゴリーの比較に重点があるため、ギリシア悲劇とバロック悲劇の直接的な比較はさほど行われない。
下巻の半分は、付録的に『ドイツ悲劇の根源』と関連のある長短さまざまな論文が掲載されている。
なかでも「暴力批判論」と「カルデロンの『げに恐ろしき怪物、嫉妬』とヘッベルの『ヘロデとマリアムネ』――歴史劇についての覚書」は読み応えのある論文だ。
こちらの方が上巻で展開された論と重なる部分が大きい。
とはいえ、やはりなんといっても興味深かったのは「アレゴリー」だ。
その話をしないとはじまらない。
アレゴリーと象徴
アレゴリーは、日本語では比喩や寓意という言葉に訳されることが多いだろう。
絵画などでも「美」や「真理」などの抽象的な概念が女性などの姿で描かれてきた(表紙のデューラーによる「メランコリー」も寓意画のひとつだ)。それらをまとめたものとして17世紀のチェザーレ・リーパによる『イコノロジア』などが知られる。まさにバロックの時代に書かれたものだ。
そんなアレゴリーに対して、ベンヤミンが比較して並べるのが象徴である。抽象的な概念を表象しているという意味では、僕ら日本人にとっては、この象徴とアレゴリーの違いはわかりにくい。
しかし、ここがわからないということが、日本人がどうしてもモノを重視しがちで、デザインに関しても「デザインする」という思考作業より「デザインされたモノ」のほうに意識がいってしまうこととも深く関係しているのだと思う。
たとえば、象徴とアレゴリーの違いをベンヤミンはこんな形で示している。
ゲレスとクロイツァーがアレゴリー的志向に認める、あの現世的な広がり、歴史的な広がりは、自然史として、意味作用のあるいは志向の原史として、弁証法的な性質のものである。時間というカテゴリーを記号論の領域にもちこんだことは、右の2人の思想家の偉大なロマン主義的洞察であったが、この時間という決定的なカテゴリーのもとでこそ、象徴とアレゴリーの関係を鮮明かつ定式的に言い表わすことができるのだ。つまり、象徴においては、没落の変容とともに、自然の変容して神々しくなった顔貌が、救済の光のなかに一瞬みずからを啓示するのに対して、アレゴリーにおいては、歴史の死相が、硬直した原風景として、見る者の目の前に横たわっているのである。
古典古代の神話的時間に対して、バロックの歴史的かつ現実的な硬直した時間。これは上巻でもバロック悲劇に対して指摘されていたことでもある。
その違いはまさにここでは、古典古代の象徴とバロックのアレゴリーの違いとしても指摘される。
被造物を暗号としてみる
すでに神話的な時空間としての古典古代からは切り離された世界としての17世紀のバロック期。それは神話からの隔たりであると同時に、ルネサンスが復興しようとした古典古代からの隔たりだ。
歴史に死相をみるところからも古典古代にあった神話の生に溢れた躍動感はそこにはなく、もはやルネサンスが意図した古典古代の復興への断念のようなものがそれに続くバロック期においては主調をなしているようにも見える。
ゆえに古典古代の象徴にあった「没落の変容とともに、自然の変容して神々しくなった顔貌が、救済の光のなかに一瞬みずからを啓示する」奇跡が生じることはもはや諦められ、「歴史の死相が、硬直した原風景として、見る者の目の前に横たわっている」ように感じられたのであり、
歴史にはそもそもの初めから、時宜を得ないこと、痛ましいこと、失敗したことが付きまとっており、それらのこのすべてに潜む歴史は、ひとつの顔貌――いや髑髏の相貌のなかに、その姿を現わすのだ。
ということになる。
そして、この髑髏もまた古典古代の象徴としてではなく、歴史解釈として読み解かれるのを待つ暗号のように機能するものとなるのだ。
暗号の読み解きとデザインすること
被造物だけが暗号として捉えられたわけではない。
何より歴史そのものも暗号のように読み解く必要があるものとして、バロック期の関心の中心に置かれていた。
このような髑髏には、たとえ表現の、〈象徴に特有の〉一切の自由さが、形姿の一切の古典的調和が、一切の人間的なものが、たしかにまったく欠けていようとも、この最も深く自然の手に堕ちた姿のなかには、人間存在そのものの自然のみならず、ひとつの個的人間存在の伝記的な歴史性が、意味深長に、謎の問いとして現われてもいる。これがアレゴリー的な見方の核心、歴史を世界の受難史として見るバロックの現世的な歴史解釈の核心である。
歴史を、受難としての神秘的な自然の顕現として解釈しようとするバロック的思考。このことを理解するためにも、ヨーロッパ的における神的なもの、理性的なものに関する思考の変遷を簡単にでも振り返ってみないといけない。
プラトンのイデア論に代表されるように、古典古代においては、被造物そのものや人間の生み出す芸術的創作物よりも、真理としての神のイデアそのものに価値が置かれた。神話的な出来事も、そうした神的なものの顕現として捉えられたのであり、被造物や創作物的なモノそのものは重視されなかった。
ここがモノ重視の日本人の見方との大きな違いだろう。
自然の被造物にも人工物にも、あらゆるモノそのものに八百万の神をみた日本と、神という存在を人間や被造物の世界を超越したものとして捉えたヨーロッパの違いだ。
ゆえに、日本人にはヨーロッパ的な象徴もアレゴリーもすこし捉えにくいのだと思う。
だが、ヨーロッパにおいてもバロック期にはすでに、そうした神的なものから人間は切り離されてしまっていた。
しかも、世界は宗教戦争、そこから派生した絶対王権へと向かう世俗権力同士の覇権争いによる戦禍がヨーロッパ全土を覆っていた時代でもある。「歴史を世界の受難史として見る」バロック精神がそこに生じるのも当然であり、歴史はどこまでも現実そのものでありつつ、悲しみの歴史においてこそ見え隠れする自然という謎を読み解く必要が感じられたのだ。
そう。こうした意味において、あらゆる自然の被造物を、その背後に隠された謎を解かれるものを待つ暗号的なものとして扱うことがバロック期の特徴なのだといえる。
そして、これこそがやはり「デザインの誕生」で書いたとおり17世紀初頭に、ディゼーニョ・インテルノ(内的構図)というキーワードとともに、隠された謎を読み解き、それを表現するのが芸術家の役割という考えられるようになったきっかけだったともいえる。
ここから、内面にある理念的なものをディゼーニョ=デッサン=構図という形で視覚的に変換or表現してみせるという意味での「デザインする」という思考が登場しているのだ。
だから、このイデア論的なものからの転換の経験をもたない日本にとってデザインがいまひとつ「制作物重視」の姿勢から脱却できない大きな要因となりえるのは自然である。
であればこそ、制作物の美的、機能的な価値のみを問う以上のことを、デザインの可能性として問うためには、このあたりの知識はどうしたって欠かせないはずだ。
なのに、その知識の獲得なしに済ませようと横着をして、欧米的な意味でのデザイン同様の価値を問おうとしたところで、話が袋小路に陥るのは当然だ。
横着せずにちゃんと根底となる知識を学ばなくてはならない。急がば回れ、だ。
エンブレムとアレゴリー
さて、被造物の裡に隠された神秘を読み解くこと、被造物を暗号的に捉えること、これがバロック悲劇とは別の形で結実したのが、同時期のエンブレムの流行である。
エンブレムの流行の背後にある思考も同じく、被造物の背後にある神秘的な文字を読み解くことからきており、エジプトのヒエログリフの解読の流行をその前身として持っている。
ベンヤミンはこう書いている。
バロックの目的論は、被造物の現世的至福にも倫理的至福にも捧げられるものではなく、それはもっぱら、被造物に対する神秘的な教示を目指している。というのも、バロックにとって自然は、それが意味しようとするものの表現にとって、それがもつ意味のエムブレム的表現にとって、合目的にできているのだ。この表現は、アレゴリー的表現として、自然がもつ意味の歴史上の実現とはどうしようもなく異なるものであり続ける。歴史は、道徳的な見せしめ話や悲劇の大詰において、ただエムブレム的表現の素材上の契機と見なされたにすぎなかった。意味作用をもった自然の硬直した顔貌が勝利をおさめる。そして、歴史はあくまで小道具のなかに閉じこめられたままであれ、というのである。
「被造物に対する神秘的な教示」を目的とするバロックの精神。その教示の獲得=自然のもつ意味の獲得を通して、それとは別の形で表現されている歴史――しかも悲しい歴史――の示す意味の超克を目指したのだといえる。
その具体的な精神のありようとして、アレゴリー的な意味合いをもったバロック悲劇やエンブレムというものに結実しているのだといえる。
そして、間違いなく、これは歴史という現実を自然=神秘の力の発展としての自然科学を用いて超克しようとする近代以降のデザイン的な思考を用意しているものだといえるだろう。
この自然という謎を解釈するバロック的な姿勢は、すこし前に「綺想の表象学―エンブレムへの招待/伊藤博明」でも紹介したことと同じことだろう。『綺想の表象学』からも引いてみよう。
シュンボルムは長い間、古代人たちの秘儀において用いられてきた。(中略)これと同じ種類に属しているのが、ピュタゴラス派のシュンボルム、いわゆる「アレゴリー」であり、アルチャーティの「エンブレム」がそう呼ばれているような「謎」であり、また「慣習的な徴」である。これらは秘儀に満ちており、人生であれ特徴であれ、万象の適切で秀逸な例を含んでおり、見識のある人々には明らかにされるが、無知な人々には知られないままである。
ここでいう「シュンボルム」は言うまでもなくシンボル=象徴である。やはり、象徴はアレゴリーと関係づけられ、さらにエンブレムとも関係づけられる。
ただし、これはエンブレムが流行したバロック的な見方におけるシンボルの見方であって、その精神はそれを「謎」や「慣習的な徴(=sign)」とみる。その暗号をデコードすること、signを理解しde•signとすることがバロック精神における課題であったのだ。
アレゴリーの文字性と近代の萌芽
だからこそ、ベンヤミンは、こんな風に書くのだ。
芸術象徴、つまり有機的な総体性をもった像である彫塑的な象徴に対して、アレゴリー的文字像のこの無定形な断片ほど鋭く対立するものはない。従来、人びとはロマン主義を古典主義の最高の敵対者として認めたがったものだが、右の対立において、バロックこそ古典主義の最高の敵対者であることが明らかになる。
被造物として表現されたものの背後に自然の謎を読み解こうとするバロックのアレゴリー精神は、自ずと文字志向となる。
バロックにおいて、言葉〔音声言語を指している〕と文字の緊張は測りがたく大きい。言葉は――こう言っていいだろうが――被造物の法悦なのであり、神の前での露呈、不遜、無力である。他方、文字は被造物の蒐集室なのであり、地上世界の事物に対する威厳、優越、全能である。少なくともバロック悲劇においてはそう言える。
声としての言葉として向こうから現れる知というより、こちら側から積極的に読み問わなくてはならない知を隠した文字。
この知のありようの変更がバロックである。
ゆえに読み解く力をもった人に読み解かれない限り、自然は完璧な姿を顕にしていないことになる。
感性的な美しい自然に、不自由さ、未完成さ、そして断片性を認めることは、古典主義にはその本質からして当然拒まれていた。だが、まさにそうした点こそを、バロックのアレゴリーは、その途方もない華美にくるんで隠しながら、以前には予感さえされなかったほどに強調しつつ呈示するのである。
この文字の優位性のうえでアレゴリーは象徴とは区別されるものとなるし、この隠された自然の意味の解釈というところから、近代的な自然科学も、近代的な意味でのデザインによる革新も生じていることを理解する必要がある。
アレゴリー的な知と悪
その意味で、このバロック的なアレゴリーは近代的なものの萌芽に欠かせないものであったのだが、同時に、このアレゴリーが忘れられたところに近代的な思考が成立したのだともいえる。
そして、アレゴリーとともに近代が忘れたことがもうひとつある。
それは、この自然の謎を読み解くという行為が同時に悪を創出するものでもあるということだ。
悪の存在根拠はむしろ、絶対的な――つまり神を認めない――精神性の国という蜃気楼とともに開示される。このような絶対的な精神性の国が、精神の対極をなす物質的なものと結びついたときに、悪ははじめて、具体的に経験されるものとなる。悪のうちに支配している感情の状態とは悲しみであり、それはまた同時に、アレゴリーの母にしてアレゴリーの内実なのである。
知るということは善いことと悪いことを分けることである。しかし、「知と善悪」で先に紹介しておいたように、人間的な知以前には神の善しかないことをベンヤミンは指摘している。
聖書は、悪を、知見という概念のもとに導入している。最初の人間たちに蛇が与えた約束とは、「善と悪を認識するもの」になる、ということだった。しかし、創造を終えたときの神については、こう言われている。「神が、造ったすべてのものを見られたところ、それは、はなはだ善かった」。したがって、悪についての知見は、まったくいかなる対象ももってはいないのである。悪の知見の対象となるものは、この世界には存在しない。それは知ることの喜び、いやむしろ判断の喜びとともにはじめて、人間自身のうちに生じきたる。
悪を認めるところに、現実世界の現状の問題を改善しようという意思が芽生え、世界や社会をリデザインしようとする行動につながる。
ソーシャル・グッドというが、それはバッド、悪と、グッドや善を切り分けられてはじめて可能になる。
しかし、その区分けは神の創造のなかにはなく、人間のアレゴリカルな思考によって生じる、きわめて人間中心的な区分けでしかない。
その人間的な善の追求によって、多くの非人間的なものがバッドな状況に追い込まれていることは言うまでもない。
知見というこの衝動は悪の空虚な深淵へと下降し、そこで無限性を自身に確保しようとする。それは、しかしまた、底なしの沈思の深淵でもある。
こうしたアレゴリー分析が、ベンヤミンの「暴力批判」や、それがナチスの台頭の時代に書かれたことの意味にもつながっている。
それは善いものと悪いものを暴力的に分け、一方を徹底して排除するような理屈を正当化しえてしまうのだから。それはいま問題になっている自粛警察や誹謗中傷の問題とも根本を同じくするものなのだから。
そうした観点において、バロック以降の近代的思考を批評的に思考することではじめて、本当の意味でのポストヒューマンなものも視野に入れた持続可能性を問うことが可能になるのではないだろうか?
僕らはそのような意味において、あらためて政治的にならなくてはいけない。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
