
知らないというのは、とても無責任なことだ。
いまのように平常が壊れると、よりいっそう知に対する姿勢が問われてしまう。
なにかについて知らなければ、その対象に対して配慮することはできない。
相手のことをわかってあげなければ、相手を慮ることはできない。
今みたいに普段どおり振る舞うことができず、自分自身も含めて、つねに普段どおりじゃない状態にある他人や社会を慮りながら行動しなければさまざまな不具合や衝突が起こってしまうような状況では、知るということは、他人や社会との適切な関係を維持し協調しあって、日々を幸福に生きていくために何よりも必要なことだということにあらためて気づかされる。
知ろうとすること、理解しようとすること。
それが人間が幸せに生きるために欠いてはならない態度であるということをあらためて思い知らされる。
ソクラテスの「気づく」
知るということは、その時々の状況に応じて、適切な言動をとることができるようにするために必要なものだ。
悪い状態をつくらないという意味だけではなく、より良い状態を目指すという意味でも。
八木雄二さんの『神の三位一体が人権を生んだ』にもこんな記述がある。
ソクラテスは、「気づく」という理性のはたらきは、「気づかう」とか「配慮する」とか「留意する」といった理性のはたらきと同類のはたらきであるとみていた。じっさい他人の弱さに気づくことは、他人を気づかうことである。気づかうことは、心を配ること、配慮することである。それはまたソクラテスによれば精神的愛であった。ソクラテスは自分の理性を自覚して、それを善美なものにするために、自分の心を気づかい、さまざまなことに対応していたが、同時に、その気づかいが他者においてもなされるように、他者に対して同じことをするように、懸命に促していた。
無知の知によって知られるソクラテス。
そして、「知を愛する」という意味のフィロソフィー(哲学)の源流として位置づけられるソクラテス。
そのソクラテスにとっての「気づく」という知のあり方がまさに「気づかう」こと、「配慮する」ことのためであることを、僕らはちゃんと理解した方が良い。知というものが何のために必要なのかを、ソクラテスな視点で、他者との関わりのため、社会において正しく生きるためであるということだと認識しなおした方が良いと思う。
そして、ここで「気づく」という表現があるとおり、「知」を「知ってる」という意味で捉えることよりも、「気づく」や「知った/わかった」という無知から既知への状態変化の意味で捉えることが大事なんだと思う。
『神の三位一体が人権を生んだ』には、ソクラテスについて、こんなことも書かれている。
知らないのに知っていると(間違って)思っている者に何らかの問いを投げかけることによって、ソクラテスは、その人が自分が知らないということを認めざるをえない地点にまで追いつめる。つまり知らないことを知らないと自覚させる。
と。
これこそがソクラテスが「無知の知」ということをいった理由だろう。
知っていることが良いのではない。
つねに現実にあわせて、みずからの知を新しく更新し続けられるかが大事なのだ。
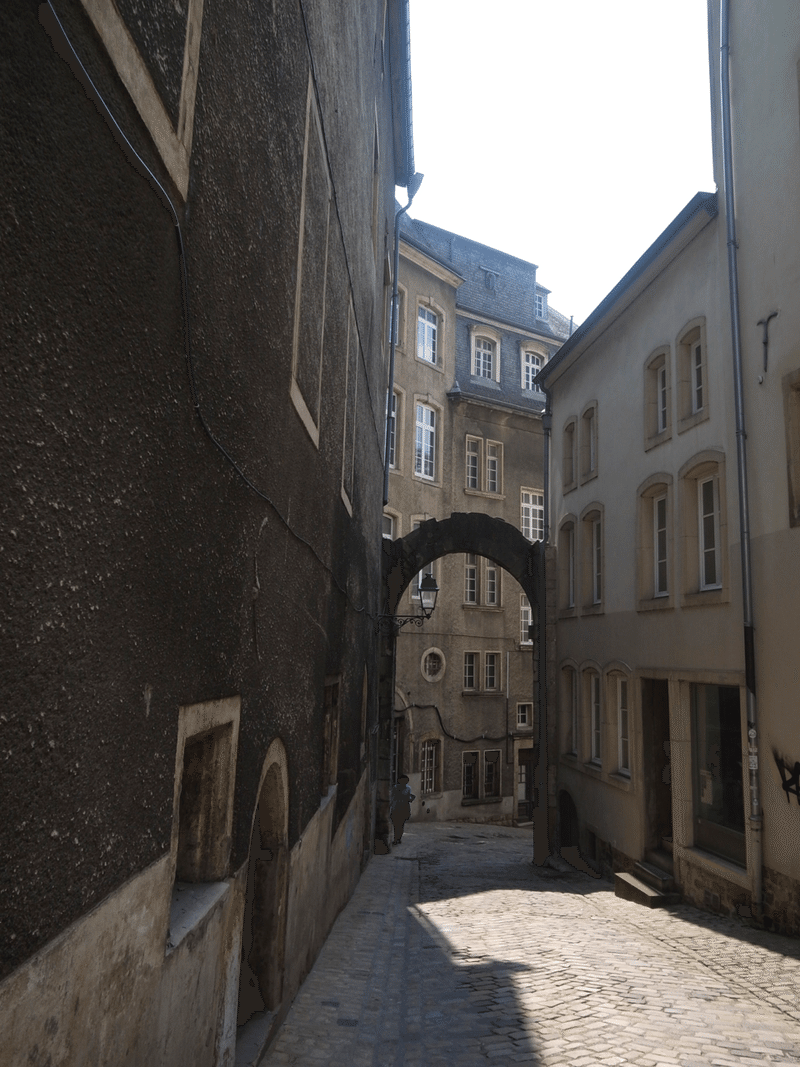
知らない=他人や社会との断絶
いまのこの新たな日常を生きるのに、コロナ禍前までの常識、知識に基づいて行動しても仕方がない。
何が悪いか、何が良いかをつねに見直さないといけないのだと思う。
上の引用のあとにこう続いているように。
それは相手に、無知を暴かれた怒りを引き起こすが、同時に、自分が何を知っているかについて無自覚な者に、それを自覚させる力をもっている。知らないと言っていながら内心悪いとわかっているのとについては、悪いと知っていると言わざるをえないと告白する結果(悪を暴かれた怒りの沈黙)を引き起こす。
したがって「疑わしい知」とは、知っていると思い込んでいるが、本当に知っていると言えるかどうかを「吟味していない状態の知」であり、他方「確信できる知」とは、十分な吟味がなされ、当人が「知っているとしか言えない状態の知」を言うのである。
知ることを邪魔するのも知である。
知っているつもりになることが、知を新たにする機会を奪う。
しかし、何かがうまくいっていなかったり、もっと状況をよくしようと思えば、知るべきこと、気づくべきことはたくさんあるということだ。
自分がすでにもっている知を疑って、新たな知の獲得のために「吟味」が必要だ。
どうしたら悪くならないか、どうしたらより良くなるかということを考えるためには、その状況をつくりだす構成要素としての他人や環境、そして、自分自身の価値基準やそのときの状態などについてできるだけ知っておくことが不可欠である。
自分がこれから行う言動に影響を与えるものに対する理解がなければ、どんな行動をし何をどう話すかを選択する基準が定まらないのだから。
逆に言えば、相手のことを知らないし知ろうとしないこと、社会について理解してないし理解しようともしないということは、相手との良い関係や社会への責任ある参加を拒んでいるというのと変わらない。
少なくとも、他人や社会とともにより良く過ごすことに対してきわめて無責任だということだ。
なんらかの仕事をはじめるときにリサーチからはじめるのだって、そういう理由だし、日々世の中のことを知っておくことが仕事をうまくやるためには必要な理由だって、そういうことである。

政治をする
ようするに、政治だ。
小さな範囲での民主主義だ。
他人を知る、他人と話ができる、相手のことを理解してあげる、慮ってあげられる。そうすることで相手とのあいだに良好な関係をつくること。
そのためには互いの利害も調整しながら互いの行動を選択していく必要がある。
それは小さな政治だ。
また、それは直接的には交流のない人々が同じ地域や同じこと日常を共有する小さな社会において、それぞれが幸せな生活を送り続ける場合でも変わらない。
その小さな社会を構成する人々やいろんな事物などの資源のことを理解し、それについて話をし、どうしたら構成員それぞれにとってより良い状態になるか、それを保ち続けられるかを考えて、それぞれが行動できるようにする。
やはり政治だ。
利害の食い違う人たちのあいだで、限られた資源を配分することができる、相手の利害を理解したうえで、こちらの利害と最適な調整を行うことができるということを目指すには、それぞれが相手のこと、相手とのあいだで共有してすべき資源について知っておかなくては何も慮れない。
もうひとつ先の本からソクラテスの哲学について引用しておこう。
哲学は本来、専門性を超えたものでなければならない。だから専門性をもつ哲学などというものは矛盾なのである。専門性をこえたところにあるのはむしろ市民の日常的一般性である。哲学の問いはすべての市民の心に起こる問いであり、市民がそれを忘れているなら、ソクラテスがしたように誰かがあえて問いかけなければならない。だからソクラテスはひとりひとりが「幸福に生きる」ことを一番に問題にした。(中略)それゆえソクラテスは「善美な精神」=「美徳」の理解に努めたのである。そしてその理解にもとづいて人々に精神の善美に配慮するように親切に求めたのである。
そして、その答えをだれもがもたなければならない。だれかに任せていてよいことではない。他人にそれを任せることは、善悪の判断を他者に任せることであり、それは結局は、その人にあらゆることで指導を仰ぐ羽目に陥るからである。
自分で善悪の判断ができないことは自律的自己を失うことであり、ヨーロッパ社会では奴隷に成りさがることである。
美徳のための哲学。
それは哲学者のものではなく、市民の日常的一般性において問われるものであり、「自分で善悪の判断ができないことは自律的自己を失う」という意味において万人にとって必要なものなのだ。
他人と社会とどう向き合うかということは、誰かに任せて決めてもらうことではない。
政治という意味では、自分の肉体という資源をどう扱うかもある意味政治だ。
それを悪に用いるか善に用いるかを決めるのを誰かに任せてよいのか。
自分の肉体が何か悪いことに加担してしまったとき、その責任を誰か他人のせいにしてしまうのか。
そして、善悪の判断はじめ、自分の行動の判断基準を他人や社会のしくみに委ねてしまうということは、そもそも人が「自分」だと思っている意識そのものを受け渡してしまっていることにほかならないのだから、そのとき、いったい、あなたは誰なんだろう?
社会的な視点に立っていうなら、誰かに任せれば、それは「善悪の判断を他者に任せること」になり、「結局は、その人にあらゆることで指導を仰ぐ羽目に陥る」ことになって、全体主義の罠に入り込んでしまう。
たとえば、こんなことのように。
だからこそ、民主主義を新たな視点で捉え直すべきで、そのためにも個々人が「知」というもののあり方を見つめなおすべきなのだろう。

神が、造ったすべてのものを見られたところ、それは、はなはだ善かった
さて、ここで話をややこしくしてみよう。
ベンヤミンの『ドイツ悲劇の根源』から、こんな一文を引用することで。
ソクラテスの教えは、善を知ることが善行に導く、とする点で考え違いをしているかもしれぬが、それを、悪を知ることは悪行に導く、と言いかえるなら、こちらの方はむしろ正鵠を射ているといえる。悲しみの夜のなかに悪についての知見として現われるのは、内なら光、自然の光ではなく、地下的な燐光が大地の体内から仄光るのである。悪魔の反逆的な鋭いまなざしが、沈思黙考する者のなかで、この燐光に光るのだ。バロックの博識ぶりが近代悲劇文学に対してもつ意味が、新たに確認される。というのも、なにかがアレゴリー的なものとして立ち現われるのは、ただ知見のある者にとってだけだからである。
ベンヤミンはここで真っ向からソクラテス的な「知」に疑問を投げかける。
知ることは善行につながるのではなく、悪行につながるのでないか、と。
知と善悪の関係について、ベンヤミンはこんな風に、聖書を参照しながら補足する。
聖書は、悪を、知見という概念のもとに導入している。最初の人間たちに蛇が与えた約束とは、「善と悪を認識するもの」になる、ということだった。しかし、創造を終えたときの神については、こう言われている。「神が、造ったすべてのものを見られたところ、それは、はなはだ善かった」。したがって、悪についての知見は、まったくいかなる対象ももってはいないのである。悪の知見の対象となるものは、この世界には存在しない。それは知ることの喜び、いやむしろ判断の喜びとともにはじめて、人間自身のうちに生じきたる。
ベンヤミンの言ってることは一見ソクラテスと正反対のことを言っているようにも思えるが、基本的には同じことだ。知は善悪を分けるものなのだ、と。
ただし、その知の機能の善の側に着目するか、悪の側に着目するかの違いである。
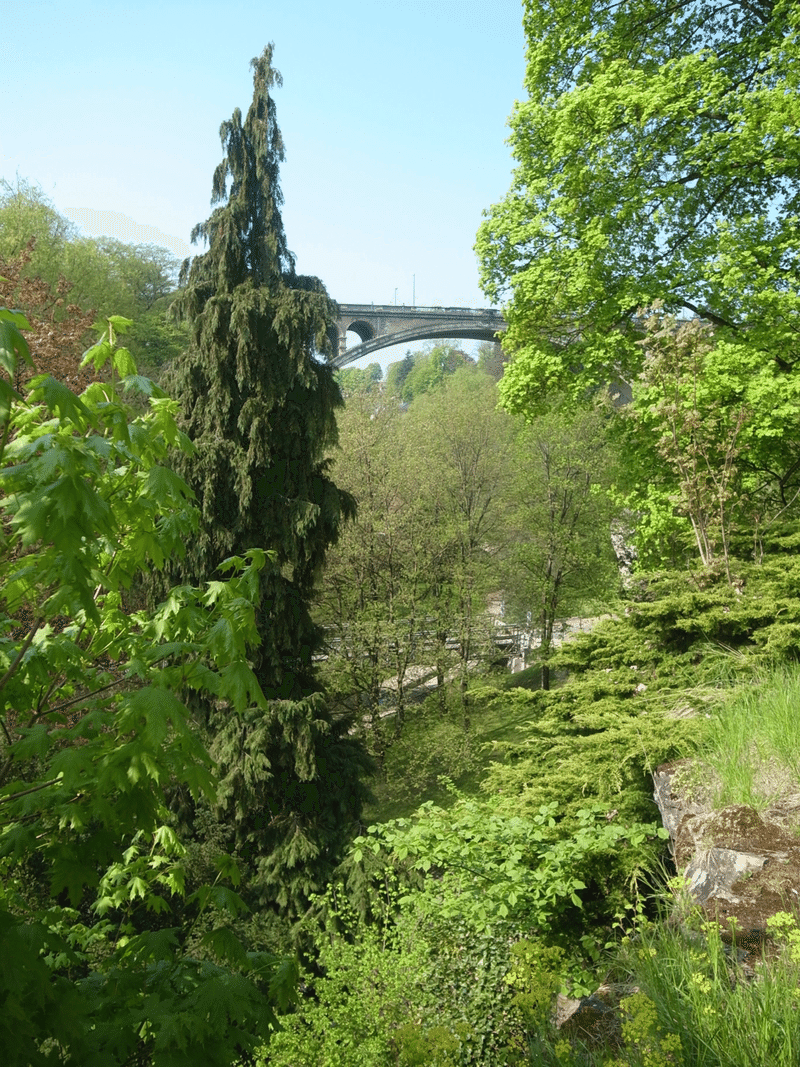
アダムの知
ベンヤミンが悪の側に着目するのは、やはり、それが書かれた時代背景を無視することはできない。「非常事態と原状回復」でも書いたとおり、ベンヤミンがこの『ドイツ悲劇の根源』を書いた1923-25年というのは、ドイツ国内においてナチが台頭してきた時期でもあるからだ。
そして、この『ドイツ悲劇の根源』において、ベンヤミンが扱っているのも絶対王政的に専制政治に移行していく萌芽のみられる17世紀という時代なのだ。
いずれも、人びとがみずから知り、みずから考え、みずからの意思で行動することを制限された時代だ。
善悪を自分で判断することが許されず、専制君主や独裁者に判断する自由を奪われた時代だ。
「他人にそれを任せることは、善悪の判断を他者に任せることであり、それは結局は、その人にあらゆることで指導を仰ぐ羽目に陥るからである」。
そんな視点に立って、ベンヤミンが楽園追放前のアダムについて語るのを読むとき、僕らは「知る」と動物としての人間のあり方について学ぶことができる。
楽園の認識はこの〈名―言語〉において事物を名づけたのだったが、かの問い〔何が善で何が悪か、という問い〕の深淵のなかで、この〈名―言語〉を見棄てる。名こそ、言語にとって、具象的な要素が根づいているただひとつの基盤にほかならない。これに対して、言語の抽象的な要素は、裁く言葉のうちに、すなわち判決のうちに根差している。
ここでいう名とは、存在そのものとしっかりと結びついた知のあり方なのだと思う。
それを忘れて、存在そのものから切り離された知をもって、自分以外の人や物事を批判し裁くようになったとき、世の中を悪が埋め尽くすようになるのではないだろうか。
それはソクラテスがいった「吟味していない状態の知」であって、存在するものと結びついた知こそ「確信できる知」なのだと思う。
そこにおいてはじめて政治的な行動は善のためのものとなる。
逆に、存在と結びつかない知見を振りかざして、他人を、世の中を、その知見にもとづく判断でどうにかしようとしたとき、ベンヤミンが次のように語る悪の主観に自分自身も社会も飲み込まれてしまうのだろう。
専制君主や陰謀家によって代表されるような絶対的な悪徳は、アレゴリーである。それら、絶対的な悪徳は、実在するものではなく、それらが絶対的な悪徳としてあるのは、ただ、メランコリーの主観的なまなざしの前においてだけなのである。
知ることは大事だ。
知ろうとしないことは社会生活をおくるうえで、とてつもなく無責任なことだ。
だが、一方で現実と結びつかない知を振りかざすことで、新たな悪を招いてしまうリスクについてもちゃんと理解しておかなくてはならない。
知は人を欺くからだ。
意識している自分が自分であるかのように肉体を置き去りにしがちなくらいなのだから、自分の外の他者や社会に対しては、知っているつもりのことと実際に知るべき対象を容易に見誤らせる。
けれど、僕らは知らなくてはいけない。
知らなければ、僕ら自身が社会や世界を破壊する怪物になってしまうのだから。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
