
絶望を希望に変える経済学/アビジット・V・バナジー & エステル・デュフロ
滅多に読まない経済学の本を読んだ。
2019年のノーベル経済学賞を受賞したアビジット・V・バナジー & エステル・デュフロという男女2人の経済学者による『絶望を希望に変える経済学』という本だ。
経済学の本は滅多に読まないどころか、これまでの人生でたぶん5冊も読んでいない。
そのくらい狭い意味での経済学にはあまり興味がない。
でも、経済学って、ほんとはすごいし、優しいなとも、この本を読んで感じた。
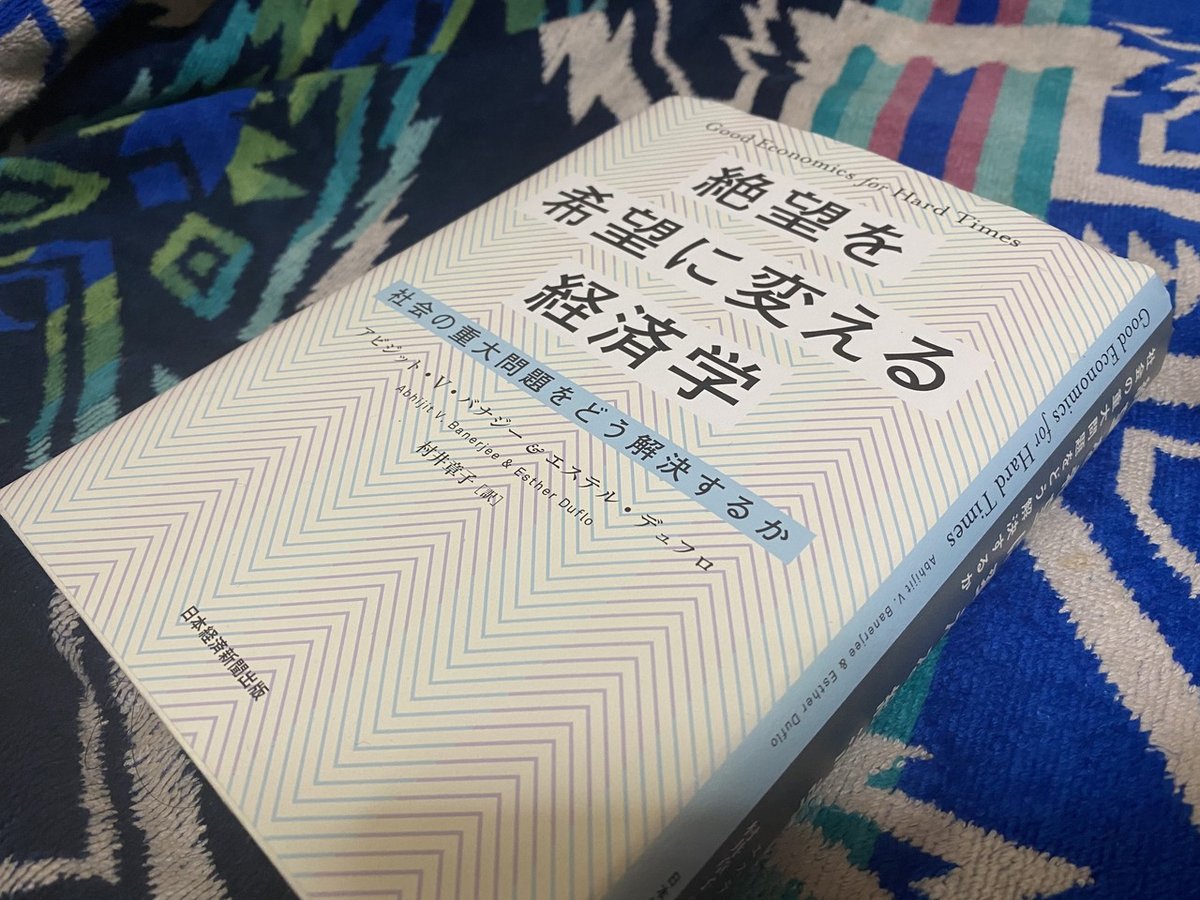
経済学とはそもそも人間学
そもそも近代経済学の父と言われるアダム・スミスからして、ほんとは人間学を研究したかったのだ。最初からいわゆる経済学という言葉から想像されるものを研究しようとしたわけではない。
時は18世紀のなかば、1759年にスミスが出版したのは『道徳感情論』という本だった。
ちょうど資本主義社会が芽生えてきた頃である。
株主に企業へと投資させる株式会社のシステムはオランダから始まった。1602年にはオランダ東インド会社がアムステルダム証券取引所で最初の有価証券を発行した最初の会社だ。これはインドへの航海に必要な船舶や乗組員たちを用意する資金を集めるためのものだ。
すぐにイギリスも同じように株式会社として東インド会社を設立。こちらははじめてオフィスをもった会社として知られる。いまリモートワークでその必要性を疑われはじめたオフィスの起源だ。
そして、ロンドン・シティのまわりには証券取引所ができ、そこに集まる人々に投資に関する情報を提供する場として機能したのが、17世紀の半ばから流行しはじめたコーヒーハウスだった。コーヒーハウスと聞いて侮ってはいけない。そこでは、いまでいう新聞や雑誌、広告や政党などが生まれている。
1720年に南海泡沫事件が起き、ロンドンの証券市場が崩壊した際に登場した保険という商品もコーヒーハウスから生まれたものの1つだ。
予期せぬ損害に対するリスクを軽減するための保険をはじめて商品として提供したロイズ保険会社もまた、そもそもはロイズ・コーヒーハウスだった。
そんな時代にアダム・スミスが研究しようと思ったのは、台頭する資本主義社会のなかで大きく変化し始めるかのように見えた道徳だったわけである。
人は何によって動かされ、何によって考えが変化させられる。産業革命環境下の新しい社会を生きはじめた人間に影響を与えるものについて、スミスは研究した。
その結果、生まれたのが経済学である。
経済学者も間違う
「経済学者は幸福な福祉という概念をひどく狭く定義する傾向がある」と著者らは言う。
そして、続けて、次のように書くのを読むとき、そのアダム・スミスの経済学に通じるものを感じる。
たとえば所得だとか、物質的な消費、といった具合に。だが、豊かな人生を送るために私たちが必要とするのはそれだけではない。周囲や社会に認められ、重んじられること。家族や友人が幸せに暮らしていること。そして、人間としての尊厳。楽しみやよろこび。所得だけを問題にするのは、単に便利で手っ取り早いからにすぎない。このように歪んだレンズで世界を見ていると、いかに頭脳明晰な経済学者であってもまちがった道に迷い込むことになりかねないし、政治家であれば国家を誤らせる決定を下すことになりかねない。そして多くの人々が根拠のない強迫観念に駆り立てられることになる。
まさに、そうだ。
所得や物質的豊かさだけでは、僕らは幸福を得られない。逆に、人としての尊厳が与えられるしくみがあるなら、それが幸福のための福祉となりうる。
何が人を動かすのか?と問うとき、それはお金でもなければ、物質的報酬ばかりではないだろう。もちろん、お金のため、何か物理的な報酬を得るため、人は働くが、そこで人としての尊厳や楽しさやよろこびが得られなかったら長続きしないか、ストレスをためながら嫌々続けるはめになるかのどちらだろう。
そこを間違えてはいけない。
そこを間違えば経済学者も、政治家も、誤った政策を行うことになる。
まちがいを犯すのは経済学者に限らない。誰にだってまちがうことはある。危険なのは、まちがいを犯すことではなくて、自分の見方に固執して事実を無視することだ。前へ進むには、つねに事実に立ち戻り、まちがいを認めなければならない。前を向くのはそれからだ。
間違いが悪いわけではない。誰もが間違うのだから。
問題は間違いに気づいたとき、立ち止まって、事実に戻れるか?だ。
そのためにこそ、経済学はあるのだ。
この本を読んで僕はそう思った。
労働者は簡単に移動しない
たとえば、間違いのひとつの例として著者らが挙げるのが移民の脅威という話だ。
移民が自国の低所得層の仕事を奪うとか、富を外に持ち出してしまうという話だ。
しかし、著者らが数字をもって指摘するのは、そもそも移民として、土地を移ってくる者はそんなに多くないということだ。
いや、むしろ、人は、ほかの土地や国によりよい条件の仕事や幸福に暮らす可能性があっても移動したがらないものだと著者らは示す。
たとえば、中国製品が安く輸入された影響を受けて、産業が縮小して、雇用が減ったアメリカの街の例でも次のような点を指摘する。
チャイナ・ショックの影響をもろに受けた通勤圏では、他の通勤圏に比べ、製造業の雇用が大幅に減っていることがわかった。これは予想されたことだが、意外だったのは、労働者の移動がまったく見られないことである。つまり、新しい仕事に移る人がいない。(中略)非製造業が雇用を増やして製造業の雇用減を埋め合わせる、というふうにもならない。もしそうした現象が起きているなら、打撃を受けた通勤圏で非製造業の雇用が増えているはずだが、実際には影響を受けた通勤圏における非製造業の雇用の伸びは、他の通勤圏より低かった。これらの通勤圏では他より賃金水準も低下し、とくに低賃金労働者にその傾向が顕著だった。
近隣の通勤圏はさほどチャイナ・ショックの影響を受けていないのに、労働者は移動しなかった。
街の産業が輸入品との競争に敗れて、職を失ったり、賃金が少なくなったりした人でも、すぐ隣町によりよい仕事があっても移動しないというのだ。
ヨーロッパではたびたび移民が問題とされるが、実際には移民が増えることで、元からいた市民の職が奪われることが起きることはなく、むしろ、移民によって需要が増えることで仕事も増え、元からいた市民はより良い仕事に就くことができる可能性が高いのだという。
この事実を見ずに、移民を無闇に締め出そうとすると、市民がより良い仕事に移る機会や街での需要が高まる可能性も潰してしまうのだ。
コロナ禍で経済格差も浮き彫りに
この本を読んで、あらためて考えさせられるのは経済格差の問題だ。
ウルトラ・リッチ層などが何人もいるアメリカなどに比べると、日本はまだマシとはいえ、それでも格差はどんどん上下に広がっていて、低所得層の暮らしはかなり厳しいものとなっている。
それがより明らかになったこのコロナ禍ではあるが、一方で、以下のnoteでも紹介されているように、その株式資産が合計1.5兆ドルで世界の富の約6%を占めると言われている世界のトップ25人は、3月後半からの2か月間の乱高下した株式市場で株式資産を2250億ドルも増やしたと言われている。
それでも自由な国、アメリカンドリームという幻想の残るアメリカでは、それでも市場はフェアなしくみで運営されてるがゆえに、その怒りの捌け口はウルトラリッチ層にでなく、他に向かうのだという。
アメリカでは、怒りが別の形で現れている。多くの人がアメリカの市場システムは基本的にフェアだと認めているため、何かほかに捌け口を求めざるを得ない。そこで仕事に就けないと、エリートどもが共謀して本来自分に来るはずだった仕事を黒人かヒスパニックか、でなければ中国の労働者に回してしまったのだろうと恨む。(中略)経済成長が止まってしまうとか、成長しても平均的な人気には利益が回ってこないという状況では、スケープゴートが必要になる。これはアメリカにとくに顕著な現象だが、ヨーロッパでも起きている。標的にされるのは、いつも決まって移民と貿易だ。
捌け口として利用されるのはまたしても幻想でしかない「われわれの仕事を奪う移民どもや輸入品」だ。この幻想を利用しているのがいうまでもなくトランプである。
そのアメリカ社会では、コロナの感染者や死亡者の割合が人種によって大きく異なり、低所得層の多い黒人やヒスパニックの感染率や死亡率が高くなっているという現象まで起きてしまっている。
金融商品と累進税率
この忌まわしい経済格差を生んだ理由はいくつもあり、たがいに絡み合っているが、その理由のひとつは、ハイエンドな金融商品だ。
一因は金融にあると言えるだろう。アメリカとイギリスは「ハイエンド」な金融、平たく言えば金持ち向けの金融で他国の追随を許さない。投資銀行、ジャンク債、ヘッジファンド、モーゲージ担保証券、プライベート/エクイティ、クォンツの類いは英米の独壇場だ。そしてこの方面では近年天文学的な報酬が支払われている。ある資産によると、金融仲介業者を使う投資家は、投資総額の1.3%を毎年ファンドマネージャーに払うという。つまり退職に備えて30年にわたって資産運用を行うとすると、細書の投資額の約3分の1がファンドマネージャーに入る計算だ。(中略)投資額が年々増えるとすれば、この手のファンドマネージャーたちが途方もなく立地になるのも不思議ではない。(中略)アメリカでは、最上位所得層に占める金融従事者の割合が1979年から2005年にかけて2倍になった。
ハイエンドな金融商品の提供がアメリカやイギリスほど行われていない各国では、この2国に比べるとウルトラリッチ層などが現れる率は低いという。
もうひとつスーパーリッチ層が生まれやすくしているのは、富裕層ほど税率が高く設定される累進税率が年々低くされたせいということもある。
1970年から現在までの最高税率の引き下げ幅と所得格差の拡大との間には、国レベルで強い相関関係が認められるのである。ドイツ、スウェーデン、スペイン、デンマーク、スイスでは最高税率が高いままだが、これらの国では最高所得層が国民総所得に占める割合が急増するという現象は見受けられない。対照的に、最高税率が大幅に引き下げられたアメリカ、アイルランド、カナダ、イギリス、ノルウェー、ポルトガルでは、この割合が急増している。
日本にウルトラリッチ層がいないのは、アメリカが戦後戦略中に設けた富裕層向けの最高税率が高かった(80%)せいとも言われる。
しかし、いまではその累進税率も所得税にかかる分こそ、富裕層向けには高い税率になっているが、所得税には含まれない証券取引による収入に関しては一律であるため、所得の95%を証券取引から得ているスーパーリッチ層にとってはむしろ税率が優遇されているような現状だ。
経済格差が埋まらないと
しかし、リッチ層が低所得層の生活の困窮を見ぬふりしてこのままのほほんと暮らしていけるかというとそうでもなさそうだ。
BLMのデモや闘争、あるいはそれに続いて各地で見られる英雄の銅像が次々に倒されている状況などを見ると、低所得層の不満の爆発はエスカレートして世界を危険に晒しかねないからだ。
富裕層は、繁栄の共有へと舵を切るほうが自分たちの利益に適うといずれ気づくかもしれない。さもないと、そのうち手痛い方法でしっぺ返しを喰らうことになるだろう。というのも、不平等が行き過ぎれば社会には不安と不満が蔓延することになるからだ。
と、著者らも警告している。
持続可能性を考えるとき、この経済格差の問題は、気候変動とはまた異なる意味で人類を危険に晒す要因であり、解決が求められる課題だ。
著者らがいう次のような2つの方向性について、僕らは考えてみないといけない。
2つの結論を引き出すことができる。1つ目は、取り憑かれたように成長をめざすのはやめるべきだということだ。レーガン=サッチャー次代の成長信仰以来、その後の大統領も成長の必要性をつゆ疑わなかった。成長優先の姿勢が経済に残した傷跡は大きい。成長の収穫を一握りのエリートが刈り取ってしまうとすれば、成長はむしろ社会の災厄を招くだけである。(中略)2つ目は、この不平等な世界で人々が単に生き延びるだけでなく尊厳を持って生きて行けるような政策をいますぐ設計しない限り、社会に対する市民の信頼は永久に失われてしまう、ということだ。そのような効果的な社会政策を設計し、必要な予算を確保することこそ、現在の喫緊の課題である。
もちろん、こうした変更は政治に求められるものではある。
けれど、この社会は民主主義社会であるはずで、そうであればこそ、こうした方向転換には市民ひとりひとりとしての僕らの意志こそが必要なはずだ。
この社会を平和で幸福に過ごせる社会にしていくためには、僕ら自身が希望を叶えようと行動し続けるしかない。
というわけで、とても良い本なので、いろんな人に読んでもらいたい。
この記事が参加している募集
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
