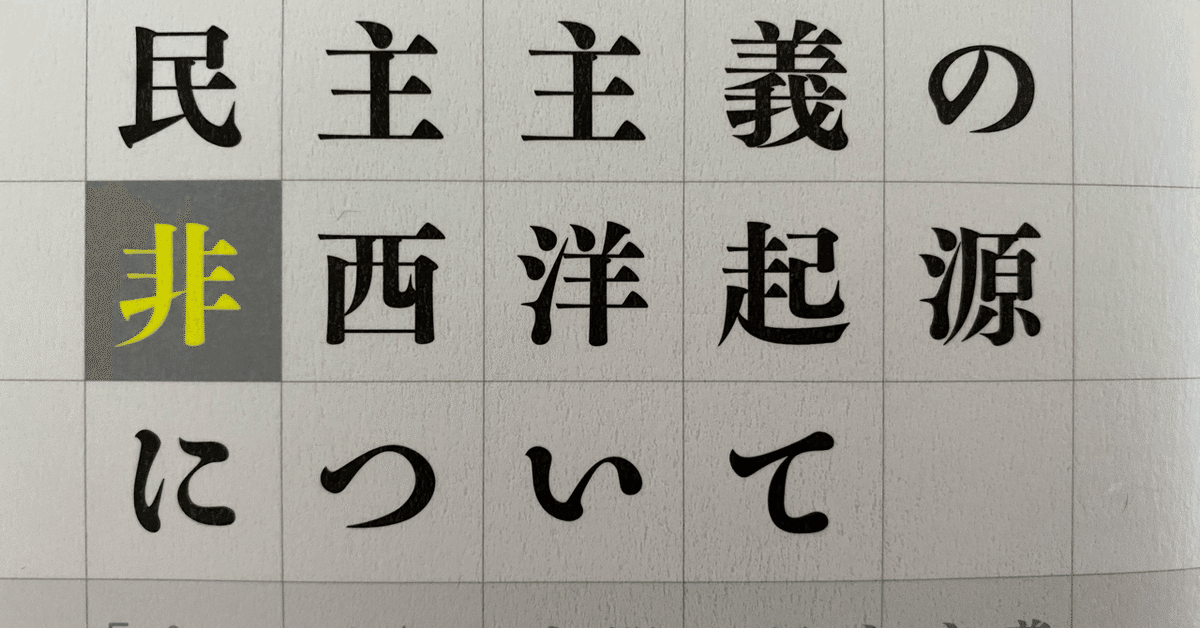
民主主義の非西洋起源について/デヴィッド・グレーバー
民主主義ってなんだろう?
そう思わずにはいられない状況ではないだろうか。
このコロナ禍にどう対処していくかを一向に示すことができない政府に、それに対して文句や諦めの言葉を口にしつつもそうした政治を変える力も気持ちもない人びと。誰もがこの状況にまともな政治を求めているのに、その政治を担う役割を誰もつかもうとしていないかのように見える。もちろん、他人事だけでなく、他ならぬ自分自身も含めて。
批判する側/される側、どっちもどっちで、主権とはなんだろうな?と考えてるのがここ最近。
だから、これまでほとんど読んだことのなかった政治を扱う本を何冊か続けて読んでいるというのは「アルス・ロンガ/ペーター・シュプリンガー」でも書いたとおり。
そんな折、このデヴィッド・グレーバーの『民主主義の非西洋起源について』という本が出版されたのを知って、タイトルだけに惹かれて、どんな本かもよく調べずに買ったわけだ。
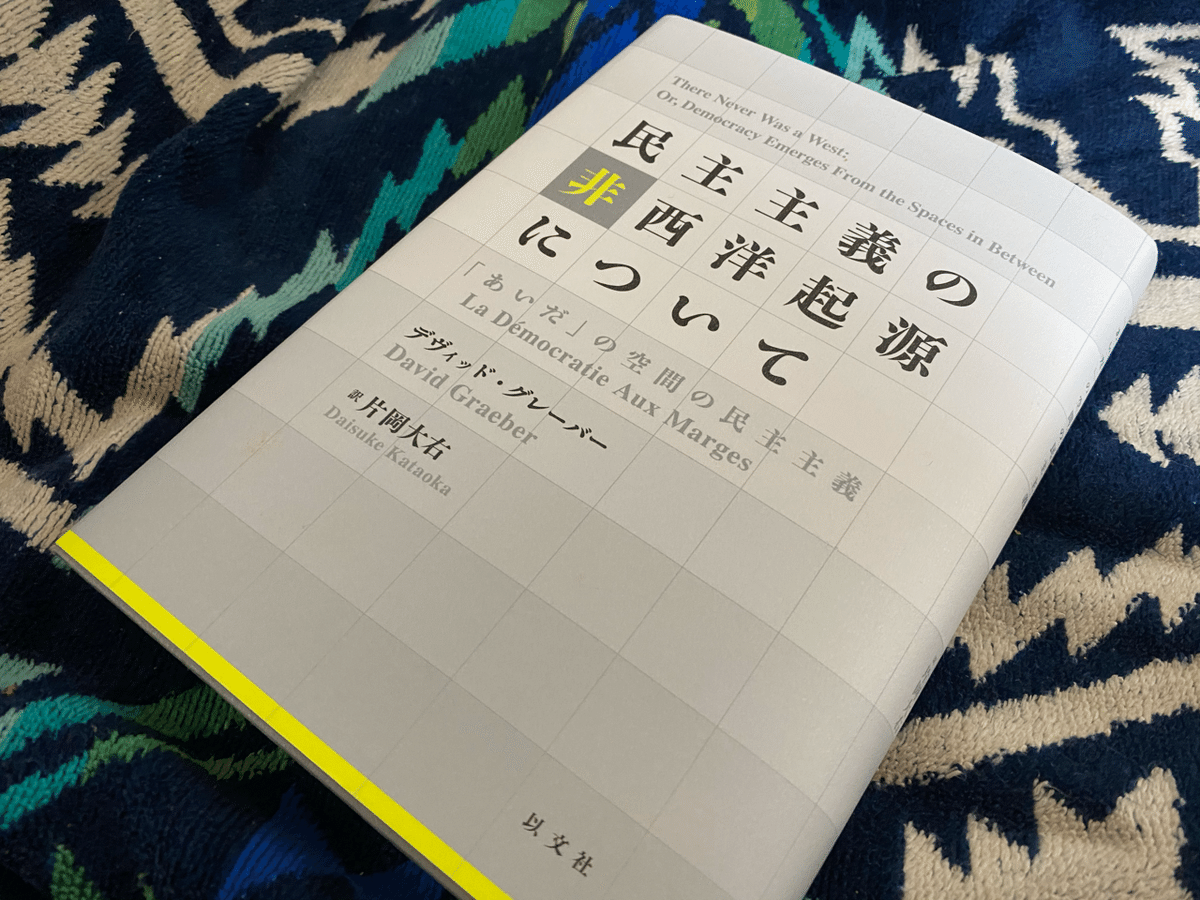
その何気なく買った本に、僕は心を掴まれた。
民主主義はアナーキーなものだ
僕がこの本に心を掴まれたのは、人類学者である著者が西洋に限らない世界あちこちの歴史を紐解きながら提出する「民主主義」というものに対する見解がこのようなものだったからだ。
歴史の大部分のあいだ、それは政治的無秩序、暴動、リンチ、党派的暴力について用いられた(じっさい、それは今日における「アナーキー」と同じ連想をかきたてる言葉だった)。
19世紀以前のヨーロッパでは民主主義はアナーキーと同様の意味で捉えられており、当然、政権を握る側からは嫌われていたというのだ。
この動きの主要原理の多く(自己組織化、自発的結社、相互扶助、国家権力の拒絶)は、アナキズムの伝統に由来する。ところが、今日これらの発想を受け入れている人びとの多くは、自分たちを「アナキスト」と呼ぶことに乗り気ではないか、必死で拒絶している。実は民主主義という言葉もかつてはそうだったのだ。
僕は、これを読んで驚いたというより、ものすごく納得がいったのだ。
なぜなら、このコロナ禍の分断された社会で感じるのは、人間というのは、つくづく利己的で、かつ自分と違う考えや行動をする者を批判し排斥したりする生き物だということだからだ。
自粛警察的な振る舞いをする人がいたり、自粛など知らないといった風に利己的な行動を続ける人がいたり、先行きを示すことない政府に憤っている人たちがいたり。これらの行動はどれも利己的であるだけでなく、どれも本人自身にとっても解決につながらない行動だったりもする。他人に悪影響を与え、かつ自分も満たされないのだから残念だ。本当はすこしでも解決に向かう道を探れたらよい。
だからアナーキーとは言うほど、そこに信念も主義もないのだけれど、利己的な姿勢で、自分と異なる方向性を示す他者とぶつかろうとする姿勢は、実はきわめて政治的なものだ。
水平構造の重要性
ただ、そこに足りないのは、直接、対立する他者と向き合い議論を交わそうとせずに、オンラインの空間が分断されていることをいいことに、一方的に言い逃げして去っていくということをお互いにしていることからみても、対話の姿勢であることは明らかだ。
対立するもの同士が同じ社会で生きていかなくてはいけない以上、その対立をどのように解決して社会を回していくかを決める政治的姿勢は欠かせないのだけれど、いま欠けているのはまさにそれだ。
このコロナ禍に世界が包まれる以前から、社会は格差の拡大による分断や、環境問題に基づくさまざまな資源の奪い合いなどの問題によって、立場の異なる人びと同士の対立が表面化していたはずである。
そんななか、さまざまな形で社会課題の解決を目指す活動家たちは草の根的な活動も含めて、中央政権的な政府を頼ることを前提としない活動を展開してきた。その活動はある観点でみればアナーキーなものだということに先の一文を読んで気づいた。
そうした彼らの活動が、いまのコロナ禍で噴出している利己的な人びとによる他者への非難と異なるのは、そこに対話の姿勢があるからだ。
それは著者が次のように羅列する機能に重なる。
垂直構造ではなく水平構造の重要性。発議は相対的に小規模で、自己組織化を行う自律的な諸集団から上がってくるべきものであって、指揮系統を通しての上意下達をよしとしない発想。常任の特定個人による指導構造の拒絶。そして最後に、伝統的な参加方式のもとでは普通なら周縁化されるか排除されるような人びとの声が聞き入れられることを保証するために、何らかの仕組みを――北米式の「ファシリテーション」であれ、サパティスタ式の女性と若者の会議であれ、無限に存在しうるほかの何かであれ――確保することの必要性。
ここに羅列されたような形で政治的な調整を対立するもの同士のあいだで行う必要なのは、そもそもが、さまざまな意味で限られた資源(物理的なものも精神的なものも含めて)をいかに分配するかの調整を行うことが政治の機能といって良いからだろう。それはブルーノ・ラトゥールが『地球に降り立つ: 新気候体制を生き抜くための政治』で明らかにしているとおりだ。
小規模な集団によるコンセンサス
その調整の権利を誰が持つかというのが、主権という意味で、ベンヤミンやアガンベンが指摘するように普段は人民に主権があるようなふりをしていながら非常事態下においては暴力装置としての政権が顔をもたげるのが近代以降の政治(フーコーやアガンベンが生政治と呼ぶ)ものだろう。
それに対して、現在起こっている(起こっていた? どうもコロナ禍でそれすら小休止状態に追い込まれてしまっているようだ)のが、よりミクロなコミュニティによる運動であるように思う。
著者はそれを称して「何かが起こっている」と表現している。
多数決の支持者とコンセンサス・プロセスの支持者のあいだの対立のような、過去の苦い対立の一部は、おおむね解決されてしまった。いやおそらくより正確に言うなら、次第に意味のないものとなってきたように思われる。というのは、ますます多くの社会運動が、小規模の集団内部においてのみ完全なコンセンサスを用いつつ、大規模な連合に際しては様々なかたちの「修正コンセンサス」を採用するようになってきているからだ。
「小規模な集団内部」で直接民主主義できない対話のなかでコンセンサスがつくられ、それをベースにより大きな規模でのコンセンサスが得られるよう、修正していく。
コロナ禍の社会分断に至る前、世界が作ろうとしていたのは、そうした新しい民主主義のコンセンサスプロセスではなかっただろうか。
多数派民主主義の成立する条件
コンセンサスをいかにしてつくるかが問題だ。
限られた資源をどのように使うか、何のために使うのか、ということにいかに合意形成を行うかである。
人間がある程度、利己的なのは仕方ない。ただ、利己的なら利己的で、それでもいかに他者との共存により全体的な利益の最大化に向かうにはどうすれば良いか?を考えるのが本当の意味で利口なのではないか。
その際、資源に限りがあるのを知らないというのは論外だ。知らなかったらちゃんと知ろうとするべきでもある。利己的な人びとに欠けているのは、この知ろうとする姿勢だろう。
話をコンセンサスの形成の話に戻すと、現在の代表制による政治においては、それは選挙を通じて選ばれた代表者による多数派による決定によるものとなっている。
これが「民主主義」と呼べるものか?とは著者も否定的に問いかけているが、その「多数派民主主義」が成立する条件として挙げているものも、非常に示唆的である。
多数派民主主義が発生しうるのは以下の2つの条件が同時に満たされた場合にはのみなのだ。
1.人びとが集団的意思決定に際して平等な発言権を持つべきだという感覚の存在、そして
2.決定事項を実行に移すことができる強制力を持った装置の存在。
著者は、古代アテネやローマで民主主義が成立していたのは、「決定事項を実行を移すことができる強制力」として武力があったからだとしている。
特にローマにおいてはそれが顕著で、ローマの社会においてはすべてが競争によるもので決定が行われていた。討論にしろ、肉体的な競技にせよ。なぜ円形競技場が必要だったかがその観点からわかるというものだ。

ローマの軍団もまた、民主主義の担い手たりえたであろう。彼らがローマ市内に入ることを決して許されなかったのは、主としてそのためだ。まただからこそマキァヴェッリは、「近代」の幕開けにあって民主主義主義的共和国の観念を再生させた時、武装した観念に立ち返ったのである。
この武力による強制力があるから、多数決という敗者にとってはなんら納得感のないコンセンサスの形成の方法が成り立つわけだ。
ベンヤミンやアガンベンが指摘してるような、そうした体制が非常事態において専制的な形に変わりうるかという龍もそれでわかるだろう。
海賊船の民主主義
であれば、そうした暴力装置を隠しもった政権に対するには、それに相対する民衆の側も自然と力や暴力を必要とすることになる。
暴動、一揆、反乱、謀反、革命、海賊行為、テロなどなど、民衆が自分たちの力の行使により権利の奪取を目論む、そうしたアナーキーな行為は、現政権側からすれば、暴力以外の何ものでもないが、民衆の側からすれば民主主義的な行為だとも言える。
こうしたことを考えるのは、「民主主義(デモクラシー)」という言葉それ自体を説明するのにも役立つだろう。この言葉は、それに敵対するエリート主義者たちが、中傷の意図をもって考案したもののように思われるのだ。それが文字通りに意味するのは、人民の「力」、さらには「暴力」でさえある。つまり、kratosであって、archosではないのだ(注より「前者は単なる強さや力、後者は正当な支配者を含意」)。この言葉を考案したエリート主義者たちは、民主主義というものをつねに、単なる暴動や暴徒支配とそう変わらないものとみなしていた。
実際、民主主義とは19世紀になるまで、そうしたアナーキーなものと同じ意味で捉えられていたから、フランス革命やアメリカ独立戦争を担った人びとにせよ、自分たちが民主主義と呼ばれることを断固として拒否したのだという。
一方で、いまの民主主義のしくみにつながるものを培っていたのは、「非西洋的なもの」と考えられるアメリカ先住民たちや、多国籍な乗組員たちのコミュニティであった海賊船であったという指摘は、とても興味深かった。
18世紀の海賊船の典型的な組織は――マーカス・レディカーのような歴史家の復元するところでは――際立って民主主義的なものだったように思われる。船長は選挙で選ばれるのみならず、一般に、アメリカ先住民の戦頭(いくさがしら)とかなり似た役割を果たしていた。追跡や戦闘のあいだは全権を与えられていながら、平時においては一般の乗組員と同格の扱いだったのである。(中略)とにかくどんな場合でも、究極の権力は総会が持つものとされ、大抵はこの全員参加の会議が、きわめて些細な問題に至るまで裁定していた。裁定の手段はつねに、挙手による多数決だったようだ。
この本のサブタイトルは、"「あいだ」の空間の民主主義"だが、著者が民主主義の起源を「非西洋」にみるが、かといって、それは他の別の地域に起源が求められるものではないということをそれは示している。
著者がみる民主主義の起源は、特定の一地域に限定されたり、コンセンサスが比較的容易に得られるような一体感のある集団を想定されたりはしない。
むしろ、著者が考えるのは、複数の文化や民族、階級や身分が交差する「あいだ」にこそ、民主主義の起源はあるというものだ。
これは考えてみれば、当然だろう。
複数の立場が異なる人びとが交わるからこそ、限られた資源を分けあうために、民主主義できないコンセンサスが必要とされるからだ。
その典型がコスモポリタンな乗組員からなる海賊船だったというわけである。
「1717年にブラック・サム・ベラミーが率いた乗組員は「あらゆる国の人びとの混交」からなっていた。イギリス人、フランス人、オランダ人、スペイン人、スウェーデン人、アメリカ先住民、アフリカ系アメリカ人、さらにはある奴隷船から解放された2ダースほどのアフリカ人までいた」。
このなかで平時は民主主義的に取り決めがなされ、非常時のリーダーシップをとる船長が誰かということも選挙によって決められた。
だから、船長は獲物の追跡や戦いにおいて結果を出せばその身は安泰だったが、失敗すればその責任を負わされお払い箱になったのだ。
それが民主主義のしくみである。
異文化間の実験空間で
こうした海賊船にせよ、アメリカの連邦制の元になったとされるアメリカ先住民の〈六部族同盟〉にせよ、ひとつの方向を向いた人びとのあいだからではなく、多様な方向性をもった人びとのあいだの利害調整のコンセンサスのためにこそ、民主主義は萌芽したのだと著者は指摘する。
言い換えればこういうことになる。ここにはスウェーデンの「ディング〔自由民が集う会議〕」からアフリカの村会、そして、〈六部族同盟〉の成立基盤となったアメリカ先住民の評議会に至るまで、直接民主主義の多様な諸制度について、少なくともある程度直接の知識を持っている人びとが含まれている。(中略)これこそは完全な、異文化間の実験空間だった。事実、新たな民主主義的制度の発展を導くのにこれほど好都合な基盤は、当時の大西洋世界のどこにも見出せなかっただろう……。
こうした実験空間で生まれた民主主義は、19世紀、20世紀と国家に回収されて、政権運営の仕組みであるかのように用いられてきた。
しかし、いま、それは機能不全を起こしている。
ただし、機能不全を起こしているのは民主主義という仕組みではなく、国家のほうだ。「今日私たちが経験しつつあるのは民主主義の危機ではなく、むしろ国家の危機である」と著者は書いている。
その理由はこういうことだろう。
民主主義者たちは過去200年にわたり、民衆の自己統治に関わる諸理想を、国家という強制的装置に接ぎ木しようと試みてきた。しかし結局のところ、このような企てはまったくうまくいくものではない。国家とは、その本性からして、真に民主化されることなどありえないものなのだ。要するに、国家とは基本的に、暴力を組織化する手段にほかならない。
海賊船の乗組員たちやアメリカ先住民たちの「異文化間の実験空間」で培われた民主主義は、国家により回収されてうまく働かなくなっていたが、それはいままたインターネットを介したコスモポリタンなネットワークによって、新たな実験の段階に入っているといって良い。
その一例として、メキシコのマヤ先住民族によるサパティスタ民族解放軍の活動を著者は取り上げている。サパティスタにはコミュニティのコンセンサス形成のための集会(アセンブリ)があり、また、男性支配とのバランスをとるため、女性と若者の会議(コーカス)がそれを補佐する。
この長い歴史をもつコミュニティを基盤として、1996年には惑星全域に広がる国際的ネットワーク、ピープルズ・グローバル・アクションの形成をもたらし、〈土地なし農村労働者運動〉、〈カルナータカ州農民連合〉、〈カナダ郵便労働者連合〉をはじめとするヨーロッパや南北アメリカの多数のアナキスト団体や先住民組織とのコミュニティを形成するに至っている。
著者は、このサパティスタの例を参照しつつ、次のように新しい民主主義の実験の可能性に賭ける。
グローバル化は惑星規模の意思決定構造の必要性を生じさせることになったけれども、惑星規模で人民主権の見せかけを維持し続けようという企てなど――ましてや人民参加の実現など――、馬鹿げているとしか言いようがない。(中略)こうした背景のもとで、サパティスタの出した答え――革命とは国家の強制的装置を奪い取ることだと考えるのをやめて、自律的コミュニティの自己組織化を通して民主主義を基礎づけなおそうという提案――は、完璧に有効である。
このコミュニティの自己組織化による民主主義の基礎づけなおしという実験の姿勢は、この分断されたポストCOVIDの社会、非常事態下における暴力装置が発動されそうな危機的な状況でこそ、求められるものだろう。
かといって何も無理して革命的なことをしようというのではない。
いかにしてごくごく日常的な生活、仕事のなかで、自分たちや他の誰かと共存するための手段を構築していくことを進めていけばよいのだと思う。
あとは仕事も生活もそうした政治とは無関係なものではないということをひとりひとりがどれだけ自覚して生きることができるかということだろう。
この記事が参加している募集
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
