
ホモ・サケル/ジョルジョ・アガンベン
その者を殺しても、殺害した者が殺人罪に問われることのない生をもつ者、ホモ・サケル。
なんとも法秩序から見放されたような存在である。
しかし、古代ローマの時代においては、そうした生をもつ者が存在したというのだ。
聖なる人間(ホモ・サケル)とは、邪であると人民が判定した者のことである。その者を生け贄にすることは合法ではない。だが、この者を殺害するものが殺人罪に問われることはない。
殺しても殺人罪には問われないが、生贄として犠牲にすることは許されないという、不可解な位置を占める存在。
本書『ホモ・サケル』の著者ジョルジョ・アガンベンは、ポンペイウス・フェストゥス(?-前35年)の『言葉の意味について』中の上の引用で語られる「聖なる人間(ホモ・サケル)」を、「主権権力と剥き出しの生」というサブタイトルがつけられた、この本の主タイトルに採用している。
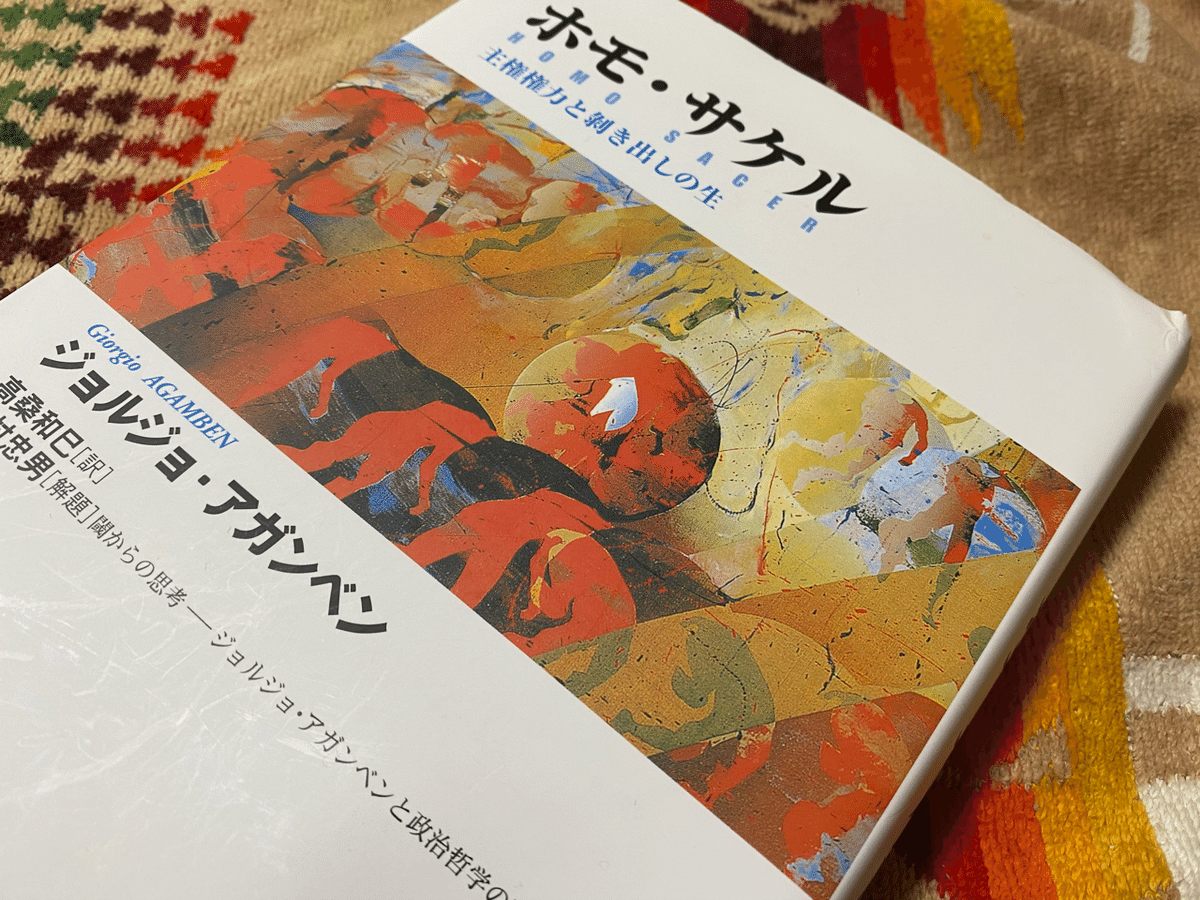
アガンベンの本を読むのは、これで6冊目となるが、後に「ホモ・サケル・プロジェクト」とも呼ばれることになる政治の場がテーマとなった、このシリーズを読むのははじめてだ。
昨年の終わり頃、アガンベンの自叙伝的な一冊『書斎の自画像』を読んでいて、彼自身によってすこしだけ語られる「ホモ・サケル・プロジェクト」に興味をもった。そのとき、第1作の『ホモ・サケル』と、プロジェクト最終巻とされる『身体の使用』を購入しておいた。
その『ホモ・サケル』を、政治とそれが社会に働きかける力が普段以上に身近なこと――そう、まさに自分を含めて、いろんな人の身体や生命に近接した身近なこと――として感じられる状況にある今の状況で読んでみたわけだ。
収容所とは、例外状態が規則になりはじめるときに開かれる空間のことである。
と、言及される本書を。
例外状態が規則となる
まさに、いまこの例外的な状況は、ある意味、世界中の人類を閉じこめる収容所のようなものだ。
この状況をもたらしたのは、新型コロナの世界中のあらゆる国や地域への流行であるが、それにともない、人間自身が「ステイホーム」のかけ声のもと、みずからを閉じこめているともいえる。
だから、いまや、この世界は二重に収容所的な状況となっている。人を危険に晒す脅威としての収容所と、それらから身を守るシェルターとしての収容所として。
後者のかけ声を発したのは各国、各地域の政治的なリーダーたちである。
そのリーダーたちの声には国や地域によって大きな違いがあった。あえて新型コロナの蔓延を防げたかどうかではなく、どの程度、人間の行動を制約したかという観点でみても、罰則を含めた強制力のあるものもあれば、自粛要請レベルのものもあるように違いがある。
その中には、ハンガリーのようにコロナ対策の無期限延長を可能にする非常事態法を可決して、他のEU諸国に懸念を表明されている国もある。まさに例外状態が規則化されたわけである。して、他のEU諸国に懸念を表明されている国もある。まさに例外状態が規則化されたわけである。
その逆に、日本では、国の強制的な非常事態宣言がないことに不満をいう声もある。「例外状態を規則になりはじめるときに開かれる」のが収容所なのだとしたら、日本においては、まだ政治的には収容所的な規則は発行されていないのだといえるのだろうか。
自由が脅かされて
しかし、こんなタイミングでこんな話を読むと、そもそもにおいて、政治というものは、この例外状態をみずからに内包しつつ排除することがデフォルトなのだとあらためて気づかされる。
ナチが権力を掌握して、1933年2月28日に「人民と国家の保護のための政令」を布告し、個人の自由、表現と結社の自由、住居の不可侵性、文通と電話通信の秘密に関する憲法の条文を無期限で宙吊りにしたとき、この意味では、ナチを、すでに先行する政府が強化済みの実験を継続したにすぎない。
自由が脅かされる。
いや、自由だけではなく生そのものが脅かされた。
しかし、それは別の脅威への怯えに対する対応でもあったことは忘れないほうがよい。
もちろん、そうだからといってナチの行ったことを肯定する要素など何1つないとしても、僕らが学ぶためにそれが怯えに対する対応であったことは忘れてはならない。
20世期の終わり(1995年)に出版された、この本でアガンベンはこう書いている。
難民(今世紀においてその数は増え続け、今日では人類のなかでも無視できない部分を占めるようになった)が近代の国民国家の秩序においてこれほど不安を与える要素になっているのは、とりもなおさず難民が、人間と市民、出世と国籍のあいだの連続性を断つことで近代の主権の原初的虚構を危機にさらすからである。難民は、生まれと国民のあいだの隔たりを明るみに出すことで、政治の舞台に、その舞台の密かな前提となっているこの剥き出しの生を一瞬出現させる。
別のところからやってくる者が自分たちの平穏な日常を奪う。あるいは奪った。
だから、そうされないようにしようとして、逃げてくる民(難民)に対してヘイト的行為を仕掛けてしまう愚かさはいまこの状況でも変わらない。
各国は鎖国的に外から来るものを拒み、人々はすでに内にいる異国の民をヘイトする。外から入ってくるものを許さないよう、国に対して要求する。
現在の新型コロナに自由を脅かされる状況に対して、それに対応するために、政治的には人間みずからがみずからの自由をあきらめる選択を国家単位で行っている。しかし、それ以上に自分以外の人たちに自由をあきらめさせようと、国家が強制力ある行動に出ることを要求したりする。
例外と規範の共犯関係
アガンベンの本書での指摘が鋭いと感じるのは、その強制力ある規律の実現自体、実は例外状態そのものをもともと排除しつつ内包するという宙吊り状態により、主権が得ているものだいうことを見抜くからだ。
例外化とは一種の排除である。例外は、一般的な基盤から排除された単独な事例である。しかし、例外をまさしく例外として特徴づけるのは、排除されるものが、排除されるからといって規範とまったく関連をもたないわけではない、ということである。それどころか、規範は、宙吊りという形で例外との関係を維持する。規範は、例外に対して自らの適用を外し、例外から身を退くことによって自らを適用する。
例外は排除されることで、規範の適用を可能にする。例外を排除したものは規範を手に入れると同時に、例外をその内に排除されたものとして内包する。
例外的な対応(非常事態宣言など)が可能なのは、もともと超法規的なもののして排除されることで内包されていたものが例外状態において規則として採用されるからである。
例外とは、自らが所属している全体に包含されることのできないもの、自らがすでに包含されてある当の集合に所属できないもののことである。所属と包含、外にあるものと内にあるもの、例外と規範、これらをはっきりと区別するあらゆる可能性の根源的な危機が、この限界形象において姿を現す。
つまり、政治において、あるいは、法において、元よりその中には、例外と規範の境界の不分明な領域が存在している。日常においては、姿を見せない、その不分明な領域がなんらかの脅威に晒された例外状態において、姿を見せるのだ。
例外状態における暴力の対象
同じことをアガンベンは、ヴァルター・ベンヤミンのなかに見出す。そう。法の中には暴力があるといったベンヤミンのなかに。
アガンベンは、ベンヤミンの「法権利を措定する暴力と法権利を保存する暴力の関係」から次のような一文を引いている。
「法制度の内には潜在的に暴力があるということを自覚することが少なければ、法制度は衰退する。最近の議会がこの過程の一例である。議会が知ってのとおりの悲しいスペクタクルの姿を呈しているのは、議会が自分の存在を負っている革命的な諸力を自覚し続けることをやめたからである。〔……〕議会には、議会において表象される法権利を創造する暴力に対する関係が欠けている。議会がこの暴力にふさわしい決定に脱することがなく、政治問題に対して暴力なしで事を済ませようとする妥協的姿勢を取るのも、驚くにはあたらない」。
この暴力は通常排除されている。
しかし、完全に排除されているというよりも宙吊りにされている。
排除されると同時に、法に内包された二重の状態にある暴力だ。
そして、アガンベンが明らかにしたのは、この暴力の対象こそが、ホモ・サケルであるということである。ゆえにホモ・サケルも二重の状態にあるのだ。
ホモ・サケルの条件を定義づけるのは、ホモ・サケルに内属した聖性がもつとされる原初的両価性などではなく、むしろ、ホモ・サケルが捉えられている二重の排除のもつ特有の性格、この者が露出されてある暴力のもつ特有の性格である。この暴力――誰もが罪を犯さずにおこなうことのできる殺害――は、供犠の執行としても殺人罪としても定義づけることができない。それは、処刑とも冒瀆とも定義づけることができない。それは、人間の法や神の法といった裁可された形式を離れて、聖事の圏域でも世俗的な活動の圏域でもない人間の活動の圏域を開く。この圏域をこそ、理解しようと努めねばならない。
供犠という通常の儀礼において殺すことはできない。しかし、殺害しても罪に問われない。法の例外にあるホモ・サケルはまさに法の外で暴力の対象となる。
それはナチ支配下の収容所でユダヤ人たちに対して行われた暴力そのものだ。
我々の観点からそれより興味深いのは、生きている人間が自分自身の生に対して行使する主権に対して、ある境界線がただちに固定されるということである。その境界線を超えると生は法的価値を失い、殺人罪を構成せずに殺害されるようになる。「価値のない生」(ないし「生きられるに値しない」生)という新たな法的範疇は、少なくとも外見上は異なる方向を向いてはいるが、ホモ・サケルの剥き出しの生にちょうど対応するものである。この範疇は、ビンディングの想像した限界のはるか彼方にまで拡張されうる。
それはまるで、生の評価や「政治化」(つまるところ個人が自分の実存に対してもつ主権のうちに暗に含まれているもの)はすべて、境界線に関するある新たな決定を必然的に含意しているというかのようだ。その境界線を越えると、生は政治的な重要性を失い、ただの「聖なる生」になってしまう。その生は聖なるものである以上、これを抹消しても罰せられることがない。
境界線を引くということは、そうした暴力性を常にともなっている。境界線を引くことで脅威に怯えることなく、自分たちを守ろうとすれば、その境界の外にホモ・サケルを用意する必要がある。法規制とはそういうものであることを僕らは忘れてはいけないのだろう。
剥き出しの生
アガンベンはこの本の冒頭で、「ギリシア人は、我々が生という語で了解しているものを表現するのに、単一の語をもっていたわけではない」といい、「ゾーエーとビオス」の2つの語が使い分けられていたことを指摘している。
この内、アガンベンが問題にするのは、ゾーエーのほうで、それは「生きているすべての存在(動物であれ人間であれ神であれ)に共通の、生きている、という単なる事実を表現していた」ものであったという。
それ故に、ギリシアの時代の政治においては、ゾーエーはその対象とは考えられず、個体や集団の生き方や生きる形式を意味したビオスの方を対象にしていた。生き方や生きる形式に関わる、つまり精神的な生に関することが政治であって、肉体的な生は政治の対象とはされなかった。
それが明確に変化した地点を、アガンベンはフランス革命の時代に置く。
人権宣言は、神的な起源をもつ王の主権から国民主権へという移行が実現される場と見なされなければならない。人権宣言は、アンシアン・レジームの崩壊に引き続くべき国家の新秩序における生の例外化を確実なものにする。すでに指摘したとおり、「臣民」は人権宣言を通じて「市民」へと変容するが、このことが意味するのは、生まれ――自然的な剥き出しの生そのもの――がここにおいてはじめて、(我々が生政治的な帰結を今日ようやく計り知ることのできるようになったあの変容によって)主権の直接の保有者になるということである。
ゾーエーが政治の対象となり、自然なままの生まれ、そして、肉体的な生が政治的な監視の対象、法規制の対象となる。
自由・平等・博愛の人権を可能にするのは、自然なままの生=剥き出しの生が政治的な対象物となったからで、それ故に、生まれやネイションが政治的な監視や規制の対象になったのだ。
身体を対象にした制御
実は、これには、近代、特に18世紀の啓蒙の時代になって以降の医学の進歩が深く関係している。
バーバラ・スタフォードが「啓蒙された批評家の仕事は今や数学者のそれと似ていた。この木立ちに剪定の鋏を入れて、永遠の原理に従って構想された秩序立ち、客観的で機械的な自然にと刈り込むのである。身体が概念へ、蓋然が公式に変わるこの複雑な変化が完成するには丸一世紀を要した」と『ボディ・クリティシズム』などで論じているとおり、18世紀を通じて身体はイメージを介して制御の対象となる(数値を用いてより科学的に制御が行われるようになるには、もうすこし待たなくてはならない)。
スタフォードが身体のイメージとその制御の例としてあげるのが、当時有名だった観相学者のラファーターが人の人相をコード化していく例だ。
ラファーターの『観相学断片』は幾何学的グリッドの罠の中に容赦なく閉じ込められた簡略な身体イメージを広めていった。ラファーターの仕事は、一個の全体を無機的な部分が寄せ集められたものという形で一番はっきり擬人化されるところのもっと大きな生物縮約化への動きに棹さしたものなのである。単純化が、一八世紀後半に台頭したより広汎な文化的革新運動のいかなるかをよく示していた。新古典主義を特徴づけるメンタリティは描写の濃密より要約化、コード化、図式化を助長するものだった。
身体は、要約され、コード化され、図式化されることで監視・制御の対象となっていく。医学の技術が政治的にも利用可能になる。
これが時代が降って19世期に入ると、ジョナサン・クレーリーが『観察者の系譜』で論じているように、生理学という人体制御に使える分野も成立しはじめる。
人間諸科学において賭けられているのは、むしろ、身体-労働者、学生、兵士、消費者、患者、犯罪者としての身体-やその機能の様態に関する知を通して、いかにして人間主体を権力の新しい配置=配列に適合的な存在にするかという課題なのである。視覚自体も測定可能なものにはなるだろう。だがフェヒナーの方程式のなかでおそらくもっとも重要なのは、[人間主体を]均質化していくその機能だ。それは、知覚行為を営む人々を、管理可能、予測可能で生産的な存在とし、そして何よりも他の合理化の領域と連動するような存在と化すための手段なのである。
計測できないものは管理できない。
医学がその計測能力を高めたことがアガンベンのいう生政治が可能な基盤を作ったのだといえる。
医学の分野における、こうした発展とともに、政治が身体を通じて剥き出しの生を管理・制御の対象とすることが可能になったのである。
収容所の出現を許すかどうか?
そのことは、アガンベンは本書でも指摘している。
実のところ、国民社会主義帝国は、医学と政治が、一つに統合されるという、近代の生政治の本質的特徴がその完成した形を引き受けはじめる瞬間をしるしづけている。このことが含意するのは、剥き出しの生に関する主権的決定が厳密に政治的な動機や領域から離れ、さらに両義的な領域へと移動していく、ということである。この領域では、医師と主権者が入れ替わっているように思われる。
生き方や生きる形式に対象を絞るのではなく、自然のままの生=剥き出しの生であるゾーエーを対象とした政治が可能になったからこそ、ナチによる収容所のような装置が可能になる。
冒頭引用したナチによる、さまざまな自由を奪った法が成立したのと同じ年の7月、まさに身体的な制御のための法が発布されている。
1933年7月14日、ヒトラーの権力掌握からほんの数週間後、「遺伝学の血統の予防」のための法が布告された。これは、「遺伝病に罹っている者は、医学的検査の結果、子孫が心身の重大な遺伝病に罹る高い蓋然性のある場合は、不妊手術を施されうる」と定めていた。
剥き出しの生を政治が例外状態を規則に変える形で制御下に置く。ナチの優生学的な姿勢が極端な方向に走った結果である。この先、さらに極端な例外状態に陥り、ホモ・サケルの収容所における惨劇にいたる。
しかし、それは極端な例ではあっても、孤立した例ではない。あらゆる政治がその機能を果たすためには、例外状態を必要とする。問題は、その通常は背後に隠れた例外状態を表に出してしまい、それそのものを規則にしてしまうかどうか?である。
収容所とは、例外状態が規則になりはじめるときに開かれる空間のことである。
この収容所の出現を許すかどうかは、例外を規則にしてしまうことを政治に許してしまうかどうかを担う、市民一人ひとりの自覚なのだろう。
フランス革命を機に、剥き出しの生が政治の主権者になったのであれば、その生を守ることを、政治にすべて委ねるのか、一人ひとりが自分やまわりの生に責任と行動をもって守ろうとするのか、そのいずれを選ぶかが問われているのではないだろうか。
非常事態における剥き出しの生に対する責任の在り処がいま問われている。これほどに一人ひとりに政治的な姿勢が問われる状況はそうないように思える。そんなことを考えさせられた、いま読むべき一冊であると感じた。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
