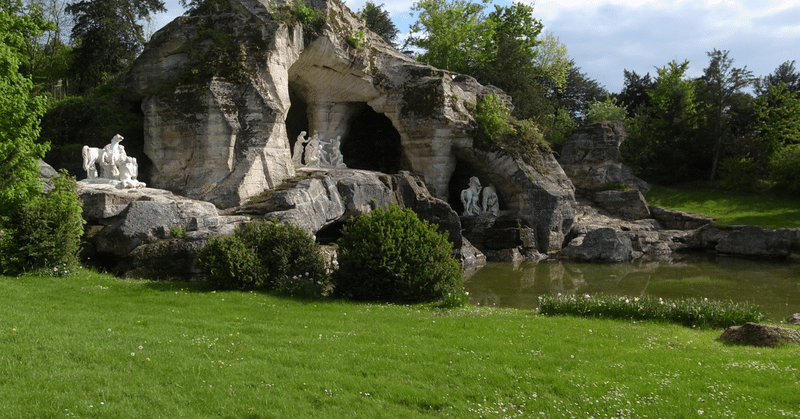
UXとユクスキュル
UXとユクスキュルは似ている。
いや、語音だけでなくて、その基本となる考え方が。
19世紀後半から20世紀前半を生きたドイツの生物学者のヤーコプ・フォン・ユクスキュルは、動物それぞれに異なる世界の見え方、認識のされ方があるということを示したことで知られる。
環世界と呼ばれる、その有名な考え方は、UXが前提としている点と重なっている。人それぞれで世界の見えかた、生きている環境の世界認識が異なるがゆえに、その違いを理解した上でデザインを行わないと、デザインする側の「良い」とデザインされたものを使う側の「良い」のあいだにギャップが生じて、使い勝手が悪くてよいユーザー体験へとつながらないという点がそうだ。
ユクスキュルの環世界
UXとの関係を明らかにするためにも、もうすこし例をあげてユクスキュルの環世界について書いてみる。
例えば、ハエとクモでは見えている世界が異なる。
ハエが蜘蛛の巣にかかるのは、ハエにはクモの巣が認識できないからだ。認識できないクモの糸にかかり、ハエは自分でまったく気づかぬうちにクモの餌食となる。僕らには避けられるクモの巣が、ハエには避けることがまるで不可能なものなのだ。ハエには自らの危険を察知する可能性がはじめから失われている。
ダニは哺乳類の血を求め、木の枝から哺乳類の背中にタイミングよく落下して、運良く背中に落ちることができたら血を吸うことができる。
しかし、ダニが哺乳類の血の匂いなどに反応して、落下のタイミングをはかっているかというとそうではない。いや、それどころか、ダニは自分が欲する哺乳類の血をそれとして認識できていないとユクスキュルはいう。
ジョルジョ・アガンベンの『開かれ』にこうある。
ダニが血の味を好んでいるとか、あるいは、すくなくとも血の味を知覚するための感覚を備えているとかといったことを期待するとしても、それは、至極当然なことだろう。だが、まるでそうではないのだ。ユクスキュルが伝えるところでは、研究室でいろいろな種類の液体を満たした人工膜を使って実験を行なった結果、ダニがまったく味覚を欠いていることがわかったという。ダニは、温度に狂いがなければ、つまり、哺乳類の血液と同じ摂氏37度でありさえすれば、どんな液体にも貪るように吸いつくのである。
なんと、ダニは自分が大好きな哺乳類の血を識別できない。彼らにできるのは、摂氏37度の液体だけだ。哺乳類の側はダニに血を吸われたと思うかもしれないが、ダニのほうは単に37度の液体ならなんでも吸ってしまうのだ。

ヒトは、ダニやクモ、ハエと同じ世界に生きているつもりでいる。
しかし、彼らと接点がもてるということは、必ずしも、同じように世界を見ていて、同じように解釈をしていることにはならない。なにしろ僕らが絶対的存在と思って疑わない時間すら、理論物理学者のカルロ・ロヴェッリが言うように、人間の環世界に特有のものでしかなく、他の生物にも同じように時間というものが存在してるかわからないくらいなのだから。
ダニやクモ、ハエなどのまったく異なる種とのあいだだけではない。同じことがヒト同士のあいだでもいえることを僕らは忘れがちだ。同じ世界に生き、同じものを見ていても、それは同じ世界認識のなかにいることにはならないのだ。
異なる文化、異なる社会環境、異なる組織に属した者同士のあいだでは、世界を同じように見て、同じ解釈のなかで生きているとは限らない。異なる世界に生きる者同士のあいだでは言葉が通じないし、同じ言葉で違う解釈をすることもある。
その違いが同じデザインを使いやすいという評価にもするし、使えないという評価にもする。よいデザインがあるというのではない。特定の用途を欲する特定の人たちに対して、その人たちの世界認識にあったよいデザインがあるというだけ。同じものが、異なる世界認識をしている人たちにとっては、使い物にならない悪いデザインだと評価されることは十分に起こり得ることだ。
ハイデガーの道具分析
そのことをうまく表現しているのが、ユクスキュルの影響を受けた哲学者のマルティン・ハイデガーの「道具分析」だと思う。
グレアム・ハーマンが『四方対象』でこう書いている。
『存在と時間』におけるハイデガーの有名な道具分析が示すところによれば、私たちは普段事物を扱うとき、それらを意識の内で、手前にあるものとして観察しているのではなく、手許にあるものとして暗黙裡に信頼している。ハンマーやドリルが私たちに対して現れるのは、大抵の場合、それらが機能しなくなったときだけである。そうなるときまで、ハンマーやドリルは、決して現れることなく宇宙におけるそれらの実在性を成立させつつ、隠された背景へと退隠している。
使える道具、よくデザインされたツールは、使っているときに意識されない。
「手許にあるもの」は自分の手と一体化して意識されない。使い方などを意識してしまうのは、それがうまく使えないときだけだ。履いてることを意識する時間が多い靴ほど、自分の足に合っていない。靴擦れという痛みがあらわれるのがその最たる例だろう。うまくいっている道具は意識の外に置かれ、「隠された背景へと退隠」する。
どういうデザインの道具が、靴擦れのような不快な意識をもたらすかは、誰がそれを使うかによって異なる。靴擦れが起こるかどうかは、足のサイズや形状によって異なるし、歩き方やどこを歩くかによっても違うだろう。使う人の生きる世界やその認識がわからないとよいデザインにはならないということだ。デザインされた道具が「隠された背景へと退隠」するほど、その人の身体の一部になるような馴染み方はしない。

ヒトも、その他のあらゆる動物も、自らの生きる世界にのみ生きており、それは他の動物種とは重ならないし、ヒト同士でも見えている世界は必ずしもいっしょではない。だから、それぞれに合ったデザインが必要になる。
ハイデガーの道具分析は、この点ではユクスキュルの思想を継いでいるといえる。
地球環境のためのよいデザイン
自分とは異なる世界認識のもとに生きる人のこと、自分にとって未知のことを知っている人のことを考えることができなければ、そうした相手のためのよいデザインはできない。つまり、「未知の知」を持つことが、よいデザインをするための前提になる。
この前提がわかっていなければ、よいUXを実現するデザインもできないどころか、デザインの領域においては喫緊の課題ともいえる、地球環境全体のことをどう考えていけばよいかもわかるはずもない。
ダボス会議でも気候変動が長期リスクの首位に位置づけられたように、これまで人間が盤石なものだと信じていた、文字通り生きる基盤としての環境が実は人間の活動次第でいとも簡単に致命的なほど変化してしまう脆いものであることに気付かされている。
この脆さの原因を理解するためにも、地球環境の物質の、そして、人間以外のすべての生物にとっての「よいデザイン」とは何か?を非人間中心主義的な視点で見直さないといけない。
最近『現代思想からの動物論: 戦争・主権・生政治』のような本などで、脱人間中心主義的な流れから動物というテーマが議論されるのも、ある意味、UXを拡張し、微生物までも含めたアニマル・エクスペリエンスのような視点が持続可能性という観点からも必要とされているからだろう。
僕がアガンベンやバタイユの本に興味を持つのも同様の理由だ。人間の外に目を向ける必要がいまこそあると思う。例えば、アガンベンが『開かれ』で書いている、
人間を、持ち前の特徴によってではなく自己認識によって定義するということは、つまり、人間とはそのようなものとして自己認識するものであり、人間とは、人間たるべくしてみずからを人間として定義しなければならない動物である、ということを意味している。
といったことなどは、まさに各人が人間としての自分をどう定義するかが自分の世界認識をもつことと同等の意味であって、動物が種で共通の環世界を持つのに対して、人間は同一種のなかでも多様な環世界を持つ=各自が定義する動物であることを示しているといえるし、バタイユが『ドキュマン』で書いている、
動物界の歴史では、唖然とするような変態がただ相次ぐだけであり、そこには人間の歴史に特徴的な決定要因、つまり哲学、科学、経済条件の変様、政治や宗教の革命、暴力と錯乱の時代……を思わせるものは、見たところなにもない。さらにそれらの歴史的変化は、まずは因習的に人間に与えられた自由に属するのであり、人間とは、行動と思考において逸脱が認められた唯一の動物なのである。
ということも同等であると同時に、そのことが哲学、科学、経済、政治や宗教に影響を与え合うものだということを示唆している。つまり、UXを考えるということは、そうした哲学、科学、経済、政治や宗教と切っても切れない影響関係にあるということでもある。なのに、なぜUXに関わるデザイナーがそうした学問領域を無視してしまえるのか?という話でもある。
ラトゥールのアクターネットワーク理論や、ハーマンのオブジェクト指向存在論というアプローチに関心を持つのも、ポストヒューマンの時代の拡張された人文学の視点が、ルネサンスの人文学がいまのデザインの基本を作ったのと同じように、ポストヒューマンの時代のデザインについて考える道筋を与えてくれると思うからだ。
ノーマンのよいデザインの4原則
さて、話をUXに戻そう。
UXという言葉を初期の段階で定義した人のうちの1人でもある、認知科学者のドナルド・A・ノーマンは、『誰のためのデザイン?―認知科学者のデザイン原論』で「よいデザインの4原則」として、以下を挙げている。
可視性:目で見ることによって、ユーザは装置の状態とそこでどんな行為をとりうるかを知ることができる。
よい概念モデル:デザイナーは、ユーザにとってのよい概念モデルを提供すること。そのモデルは操作とその結果の表現に整合性があり、一貫的かつ整合的なシステムイメージを生むものでなくてはならない
よい対応づけ:行為と結果、操作とその効果、システムの状態と目に見えるものの間の対応関係を確定することができること。
フィードバック:ユーザは、行為の結果に関する完全なフィードバックを常に受けることができる。
この4つのうち「よい概念モデル」というのが、結局、ここまで書いてきたことと重なってくる部分になる。
1960年代にアンテルナシオナル・シチュアシオニストという活動を率いて、1968年の五月革命にも影響を与えたフランスの著述家・映像作家であるギー・ドゥボールは『スペクタクルの社会』の書き出しで、
近代的生産条件が支配的な社会では、生の全体がスペクタクルの膨大な蓄積として現れる。かつて直接に生きられていたものはすべて、表象のうちに遠ざかってしまった。
と書いているが、ここで指摘されている表象をみて生きているのが、1960年代からさほど変わらない(もしくはさらにヴァーチャルなスペクタクルのなかに閉じ込められてしまった)現代人であり、そのスペクタクルの表象がノーマンのいう、人それぞれの「概念モデル」をつくる要因のひとつとなっている。
ドゥボールの60年代と比較しても、そのスペクタクルの表象は細分化し、多様化しているから、概念モデルも多様化し、それゆえ異なる概念モデルをもった人たちのあいだで、誹謗中傷合戦のような諍いばかりが起こる。異なる概念モデル、異なる環世界に生きる者への歩み寄りがないために、とにかく自分と異なる相手を否定することが自分の陣地を守る唯一の方法であるかのように振る舞ってしまう。その結果がこの地球規模の危機を引き起こしてしまっていることが明らかなのに、いまだにそのことに懲りず、自分の概念モデルの外に目を向けようとしない。そんなことではUXどころか、あらゆる生き物、非生物の体験が悪化するばかりだというのに。
「デザイナーは、ユーザにとってのよい概念モデルを提供すること。そのモデルは操作とその結果の表現に整合性があり、一貫的かつ整合的なシステムイメージを生むものでなくてはならない」というノーマンの「よい概念モデル」のデザインということを、あらためてポストヒューマン的な拡張して考える必要があるように思う。UXという場合の"U"の対象を、地球というツールを使うあらゆる存在のエクスペリエンスに拡張して考える必要性が出てきているといえるのではないだろうか、と。
それができるようになるためにも、まずは何より自分の概念モデルの外の世界へと積極的に足を踏み出せる、リサーチマインドが不可欠なのではないだろうか。つまり、自分の既知の知の外にある、他人の、そして非生物のもつであろう知、つまりは自分から見たら未知の知に対して、いかに目を向け、配慮することができるかという、「知を愛する」という語源的な意味での哲学的な姿勢だし、未知を探索するというリサーチ(研究)的な姿勢が、未来をデザインする誰しもに必要になってきているということではないだろうか。誰もが学際的な指向性をもった研究者的であり、誰もがデザイナー的である社会。そんな社会が求められているように感じている。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
