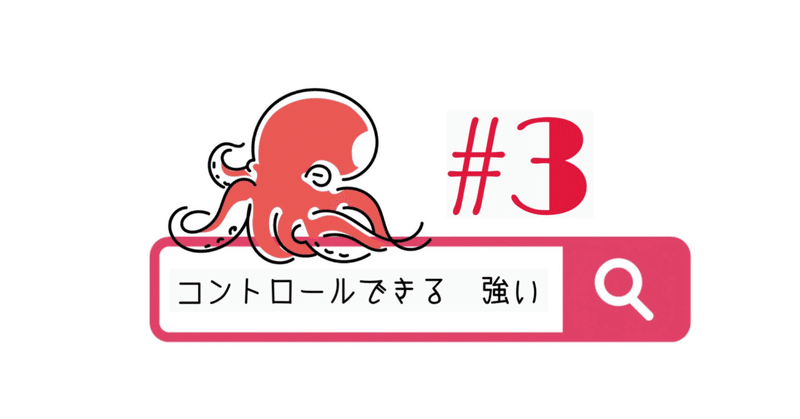
#3 コントロールできると強い!③
結論▼
何事も、コントロールできるようになれば強い!
できるようになるには、意識して経験し何回も繰り返そう!
これまで、野球の例と感情の例を用いながら、私の考える「コントロール」とはなにか、についてお話してきました。最終回では、ではどうやってできるようになるのかということについてお話したいと思います。
まずはコントロールとは何だったのかを確認しよう。これまでの例からおさらいすると、「コントロール」とは、「⑴自分が持っている技なり感情なりといった選択肢から、⑵その状況に適したものを選びとり、⑶実行できること」である。これを定義としてみる。
この定義の各要素から、どうすればできるようになるかを考えたい。
⑴自分が選択肢を持っていること
1つ目の要素を言い換えるとこういうことである。コントロールというのは日本語で「支配」や「統制」と示されることからも分かるが、コントロールするためには自分の支配下にその選択肢がなければならない。それは野球の球種のような技能なら、自分がそれを習得していなければならないということだ。そういった選択肢がないとコントロールするものがそもそも無いことになり、あっても少なければ、様々な状況下には活かせないことになる。
つまりまずやるべきことは、選択肢を増やすことなのだ。
では、選択肢を増やすには?
それには、意識してたくさん経験を積み、たくさん繰り返すことだと私は思う。色々なことを経験するのは時間がかかるし、苦労することもある。しかし、明確な意識をもって様々な経験を積むことで、選択肢として必要なことが見えてくることもある。どうにかして相手の打ちにくいボールをと考えた結果、幾度にわたる実戦の中で握り方と投げ方を試行錯誤した結果、多様な球種の発明に繋がったかもしれない。これは選択肢の創出という珍しい例だが、一般に、コーチや親に変化球の投げ方を教わる子どもの経験も、熱い意識は同じである。その後はもう、練習あるのみである。とにかく多くの場面で何度も実践し、自然と自分のものにしていく。そうすればいずれ当然のようにできることになる。つまり、「選択肢」になるのだ。
⑵と⑶はまとめてしまおう。というか、もはややるべきことは既に書いてしまったのだ。すなわち、⑵状況に最適な選択肢を選ぶ力も、実際にそれをその状況下で実行できることも、意識した経験と繰り返しを重ねることで、磨かれていくのである。
ただし注意すべきは、⑴の時点での経験と繰り返しの意義は、あくまで各選択肢を自分のものにし、増やしていくことにあるということだ。⑵と⑶ではその意義が少し変わってくる。
⑵においては、各選択肢に関してではなく、選択肢全体を把握し状況とリンクさせて考える、いわば俯瞰的な視点が求められる。それを、経験と反復が教えてくれるのだ。
⑶においては、各選択肢が、求められる状況下で実際に効果を発揮できることが求められる。ただステータスとして「できる」「やったことがある」ではなく、「活用できる」という点で⑴とは異なり、その力はやはり、経験と反復によって磨かれるのだ。
またどの時点においても、それを自分が「意識して」行うことも忘れてはならない。
いよいよ総括である。
新しい言葉や考えはもう出てこない。これまで丁寧に述べてきたことをまとめたのが、初回から示しているこちらである。
結論▼
何事も、コントロールできるようになれば強い!
できるようになるには、意識して経験し何回も繰り返そう!
ここまで読んでくれた方には、改めて説明することは必要ないと思うため、最後に私の実践例と目標を書くことにする。
いちばん大きな実践例は、「人生を楽しむこと」である。これまで様々な経験をしてきたが、その中で最も自分を誇れることは、この考えを持てることだ。#2で取り上げた菅野仁さんの「苦味を通してうま味を味わう」にも似ているが、人生に起こる色々なことを、すべて自分のためになることとして捉え、深め、学び取る。それが、楽しむということである。非難するわけでは決してないが、そのように捉えられず、腐ってしまう人も実際にいる。よってこのように生きられることは、感情や行動をある程度「コントロールできること」のおかげだと感じるのだ。
目標は、「人に伝えること」である。私はもともと文章を書くことが好きで、読書感想文やレポート課題などのような、自分の頭の中を表現することには積極的に取り組んできた。今も、このnoteを書くことを選んだ。要するに、これにはある程度の自信があるのである。しかし、その表現したものを誰かに「伝える」となると、まったく難しいものである。今回それを痛感したのは、なんとも初歩的な、常体か敬体か、すなわち「だ・である調」か「です・ます調」かという問題だ。読者を意識すれば敬体になっていくが、そうすれば思考だけでなく、読んでほしいという欲求が乗っかってしまうのだ。結果私は、序文は読者を意識し敬体を用い、本文はこのように常体を用いるという戦略をとった。今後私の言葉遣いがいかに変化していくのかは、たまに私の記事を見に来て確認して頂きたい。というのはあまりに強引な宣伝か。
ここまでお読みいただきありがとうございました。分かりにくい箇所もあったとは思いますが、いかかだったでしょうか。ここは思いを伝える敬体ゾーンですが、本当にこちらの方が感情が伝わりやすいのでしょうか(笑)。
ぜひ、次のテーマも楽しんで頂ければ嬉しいです。🐙
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
