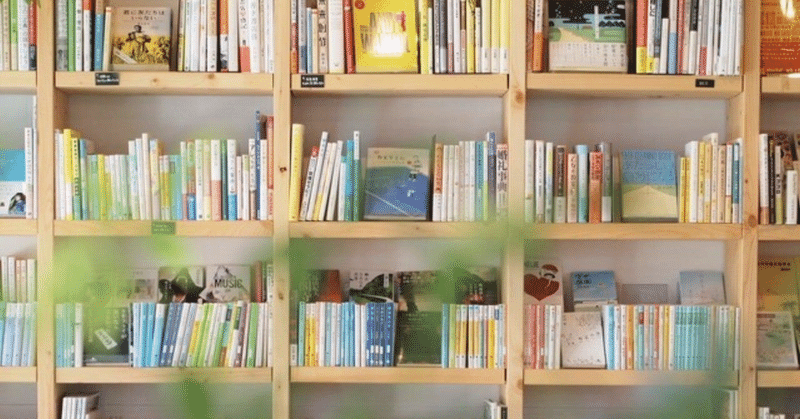
いろんな本を読むということ
先日、「新潮文庫の100冊 2020」の未読本を読み終えました。
一昨年から、いろんな本を読もう、と思い立って始めてみた「新潮文庫の100冊」。
今回、未読本はそんなに多くなかったので、興味のある本も時折入れながら読んでみました。
立て続けにいろんな本を読むと頭の中がごちゃごちゃになるんじゃないか?と心配もありましたが、案外大丈夫なものですね。
かえって相乗効果で、より深い読書が楽しめたように感じます。
面白い読書体験だったので、noteに残したいと思います。
・「新潮文庫の100冊 」の魅力
「新潮文庫の100冊」の魅力は、名作からラノベまで、小説からノンフィクションまで、幅広く揃っていることだと思います。
昔から本を読むのは好きでしたが、どうしても自分の好みに偏ってしまうもの。
私の場合、時代小説やノンフィクションは、あまり読むことはありませんでした。
しかし、司馬遼太郎の「人斬り以蔵」。
面白かった。
もともと歴史に詳しくないので、「さて、読みますか!」と気合を入れて本を開いたのですが。
短編集だからでしょうか。登場人物がそんなに多くなく、物語もギュッと凝縮されていて集中して読める。
それぞれの主人公は、歴史上の表舞台でキラキラ輝く人物ではなく、その陰で妖しい光を放つ曲者揃い。近くにいたら、まず近寄らないタイプ(笑)
でも、そこが人間臭く、魅力的で、面白い!
淡々としたハードボイルドの文体もカッコいい〜。
司馬遼太郎が面白いのは分かっているんです。
「燃えよ剣」は読んだ。面白かった。時間かかったけど…。
長編で登場人物が多いイメージがあり、時代小説をあまり読まないこともあって、なかなか他の本も読もうとは思いませんでした。
だけど、はー。
こういう本もあったんだ。
読むことができて良かったよ。
ノンフィクションも、嫌いじゃないですが、自分からあまり読まない分野です。
寮美千子編「空が青いから白をえらんだのです-奈良少年刑務所詩集-」は、「詩集だからサラッと読めそうだな〜」と軽い気持ちで読み始めましたが、想像以上にガツンと心を揺さぶられました。
罪を犯した少年たちが、詩人・寮美千子に導かれて、内面から浮かんできた言葉を詩にします。
そのまっすぐで不器用な言葉は、私の中にあるさまざまな弱さや脆さと繋がって、心を揺さぶりました。
もし彼らが、罪を犯す前に、自分の気持ちを言葉にし、誰かに伝えられたなら。
それをきちんと受け止める人が、もし身近にいたなら。
気持ちを表現すること、それをまわりの大人が受け止めようとすること。
それがいかに大切なことか。
「どんな凶悪な犯罪者も、はじめは心に傷ひとつない赤ちゃんだったはずです」
教官の言葉が、ズンと胸に響きました。
罪を犯すことは、決して許されるものではありません。
それを防ぐために、まわりの大人は何ができるのだろう、と考えさせられました。
自分では選ばないだろう本で、こんなふうに心を揺さぶられると、自分の世界の狭さにハッとします。
自分の好きなものを読んで楽しむのもいい。
でも、それだけでは出会えない感情や感動が、本当はもっとたくさんある。
もちろん、感じ方は人それぞれで、100冊すべてが私的大当たりだったわけではありません。
「面白かった!」と思わずガッツポーズする本もあれば、「ん?」と首を傾げる本もある。
でも、そんなことも含めて「新潮文庫の100冊」は、私の世界を広げ、いろんな感情や感動を与えてくれました。
・本を読むことは、土壌を作ること。
「新潮文庫の100冊」の中には、私の嫌いな数学に関する本もあります。
2020に選ばれた本の中で「あちゃー」と思ったのは、森田真生の「数学する身体」。
つい後回しにしてしまい、未読本読破のゴールが見えた頃にやっと読み始めました。
ところが、けっこう読めた。それどころか、なかなか楽しめた。(失礼!)
「はじめに」で「全編を読み通すために、数学的な予備知識は必要ない」と書かれているように、数学が分からない私にも読めるように書いてあります。
とは言っても、数年前の私だったら、たとえ読んでも楽しめなかったのでは、とも思います。
「数学する身体」の中に、アラン・チューリングと岡潔という2人の数学者が出てきます。
アラン・チューリングはサイモン・シン「フェルマーの最終定理」で、岡潔は「人間の建設」という小林秀雄と岡潔の対談集で、それぞれ読んだことがありました。どちらも「新潮文庫の100冊 2019」に選ばれていたので。
(「フェルマーの最終定理」は2020でも選ばれています)
なかなか読むのに苦労しましたが、そのぶん、思い出深い本です。
そして、青柳碧人の「浜村渚の計算ノート」。
こちらは新潮文庫ではなく、講談社文庫。
私の遺伝子を引き継いで数学嫌いになってしまった娘たちが、「これを読んだらなんとかなるかも」と読むようになった数学ミステリーのシリーズです。
可愛い表紙に騙されてはいけません。数学はかなり本格的。
毎回、ほほぅ…と思いながら、じつは分からないところもけっこう多い。
でもイラストの可愛さと奇想天外なストーリーで、数学の部分を飛ばしても楽しく読める。娘たちはそうしている。(オイッ!)
この本のおかげで、数学ってよく分からないけど、なんか面白そうだなぁと感じるようになりました。
「数学する身体」の中に、岡潔のこんな言葉が載っています。
「職業にたとえれば、数学に最も近いものは百姓だといえる。種子をまいて育てるのが仕事で、そのオリジナリティーは「ないもの」から「あるもの」を作ることにある。数学者は種子を選べば、あとは大きくなるのを見ているだけのことで、大きくなる力はむしろ種子のほうにある」
この言葉について、著者の森田真生はこう書いています。
しかし、なぜ「ないもの」から「あるもの」ができるのか。それは種子の中に、あるいは種子を包み込む土壌の中に、「ないもの」から「あるもの」を生み出す力が備わっているからだ。
ここを読んだとき、「あ、これは私にとっての読書だ」と感じました。
「数学する身体」という種子だけだったら、きっと「読んだ」で終わっただろう。
でも、「フェルマーの最終定理」や「人間の建設」や「浜村渚の計算ノートシリーズ」という土壌があったから、楽しむことができた。
そうか、いろんな本を読む面白さは、こういうことなのか、と心が震えました。
私にとって、本を読むことは、土壌を作ること。
一冊の本が、ほかの本と結びつき、より深い感動や気付きを与えてくれる。
苦手な数学の本がそれを気付かせてくれたというのも、深いものを感じます。
・「誰かの靴を履いてみる」のは難しい。
だから本を読もうと思う。
「新潮文庫の100冊」以外で読みたかった本に、ブレイディみかこの「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」がありました。
感想をひとことで言うと、「間違いなく面白い!」。
人種差別、ジェンダー、貧富の差、アイデンティティなどヘビーな問題に、著者のブレイディみかこと英国の元・底辺中学校に通う息子が正面から向き合います。その姿勢はとても真摯で、読みながら共に考えさせられます。
印象的な場面がありました。
ブレイディみかこが、公立だけど評判の良いカトリック校を見学したときのこと。
授業中、教室の前方に座る生徒は熱心に授業を受けているのに対し、後方に座る生徒は雑誌を読んだり携帯をいじっていたそうです。
それを見た感想を、次のように書いています。
前方と後方では、まるで違う教室のようだった。こういうのを、教室内の前後格差、とでも言うのだろうか。
英国のブライトンという街での出来事ですが、これは日本の私の世界と同じだと感じました。
私のまわりには、あからさまな差別を口にする人や、多様性を否定する人はいません。
また、差別に悩む人や、生活に苦しむ人もいないように見えます。
だけど、それは本当だろうか。
私が、自分と近い価値観や環境の人たちと一緒にいるからではないだろうか。
同じ空間にさまざまな人がいても、教室内の前後格差のように、お互い関心を持たず過ごしているのではないだろうか。
生活していく上で、ある程度それは仕方ないことかもしれません。
ただ、そのことで誰かを差別したり、傷付けたりしてはいけない。
それは多くの人が理解していること。
でも、本当に出来ているだろうか?
無意識に、差別したり、傷付けたり、無関心だったり、そんなことはないだろうか。
本の中に「エンパシー」という言葉があり、「自分で誰かの靴を履いてみること」という意味のようですが、簡単そうでなかなか難しいと感じます。
ケンブリッジ英英辞典のサイトによると「エンパシー」の意味は、
「自分がその人の立場だったらどうだろうと想像することによって誰かの感情や経験を分かち合う能力」
と書かれているそうです。
それなら、本を読んだり、映画を観たり、音楽を聞いたりすることで、自分と違う誰かの感情を体感できないだろうか。
元・底辺中学校のクリスマスコンサートで、皆から怖がられている少年が歌うラップに、歓声が鳴り止まなかったように。
差別的な言動が著しいダニエルが、映画「ボヘミアン・ラプソディ」を観てクィーンを歌ったように。
私がこの本を読んで、元・底辺中学校に通う子供たちに思いを馳せたように。
音楽や、映画や、本には、自分のいる場所を軽々と超えて別の世界を体感させる、そんな力があるように感じます。
本を読むということは、「誰かの靴を履いてみること」と近いように思います。
いろんな本を読みながら、自分と違う世界を体感する。関心を寄せる。
それなら私にも出来そうです。
映画の好きな人は映画で。
音楽が好きな人は音楽で。
自分のできる「誰かの靴を履いてみる」で、少しでも差別や無関心が無くなれば、と願います。
「新潮文庫の100冊 2021」では、どんな本に出会えるでしょう。
そして、ほかにはどんな本を読もう。
楽しみです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
