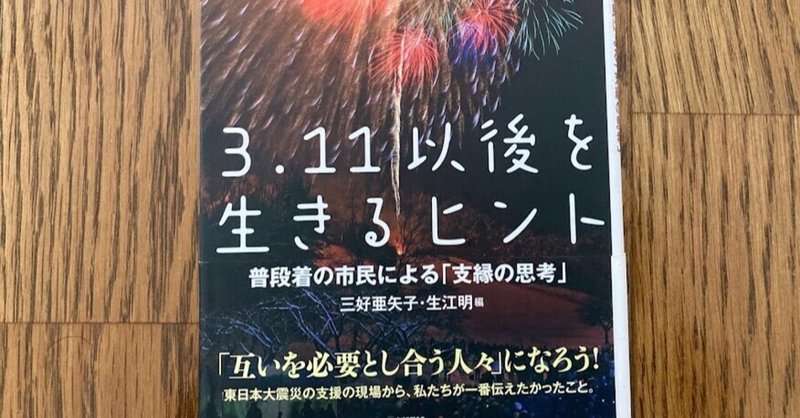
生活者目線の支援策探る――三好亜矢子・生江明編『3.11以後を生きるヒント:普段着の市民による「支縁の思考」』(新評論、2012年)評
東日本大震災から約二年。被災した人々に対し、さまざまなアクターによる多彩な支援が行われてきた。それらのうち、特に「普段着の市民」――行政職や専門家など「支援」のプロではない、普通の生活者たち――によって行われた支援をとりあげ、それがもつ可能性や有効性について論じたのが本書だ。
本書では、被災地支援に活躍したNPOやボランティア・グループ、協同組合など、一五ほどの実践事例が詳細に紹介され、それぞれ丁寧な検討や考察が施されている。本県からは、米沢市の生活クラブやまがた生協を母体とする支援団体「ボランティア山形」(13章、14章)や同市内に開設された避難者支援センター「おいで」(15章)、最上町の曹洞宗松林寺による災害ボランティア(3章)の活動などが取り上げられている。
では、こうした「普段着の市民」による支援のメリットとは何か。本書はそれを、①小さいこと、②多様であること、③現場密着で丁寧であること、④対話があること、⑤夢があること、の五原則として定式化する。これらはどれも、行政職や専門家などプロが行う制度的な「支援業務」の対極にあるものだ。
例えば、制度的な「支援」では、すべての対象者に公平かつ迅速にサービスを提供せねばならないため、①~⑤のようなありかたは許されない。しかし、被災地では制度の「想定外」の事態が常態化していた――例えば、個数の不足ゆえに分配できず避難所の隅に積まれたままの物資の山――ことは震災後の私たちにはもはや常識。「想定外」の環境下で被災者と資源とをつなぐための最適解が、小さく多様な市民たちのイニシアチヴにより、そしてまたそうした人びとのヨコの連携(本書はこれを「支縁」と呼ぶ)により、各地で豊かに紡ぎだされていたのだった。
あのとき、そしてあの後、いったいどんな支援が行われていたのか。これは、私たちの社会が非常時にどう機能したかをめぐる問いでもある。本書が浮かび上がらせるのは、そうした私たちの社会の自画像である。(了)
※『山形新聞』2013年03月10日 掲載
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
