
なぜ世界の海を支配したシーパワーは衰退したのか?『イギリス海上覇権の盛衰』の紹介
海洋戦略の研究に取り組みたいのであれば、イギリスの歴史学者ポール・ケネディの著作『イギリス海上覇権の盛衰(The Rise and Fall of British Naval Mastery)』(1976)を読むべきです。これはアメリカの戦略思想家アルフレッド・セイヤー・マハンが『海上権力史論』(1890)で取り組んだ研究を引き継ぎ、新しい視点で海洋戦略を歴史的アプローチで研究した業績です。17世紀から20世紀までの3世紀にわたるイギリスの政治、外交、戦争の歴史に興味がある方にもおすすめします。
ポール・ケネディ『イギリス海上覇権の盛衰:シーパワーの形成と発展』上下巻、山本文史役、中央公論新社、2020年
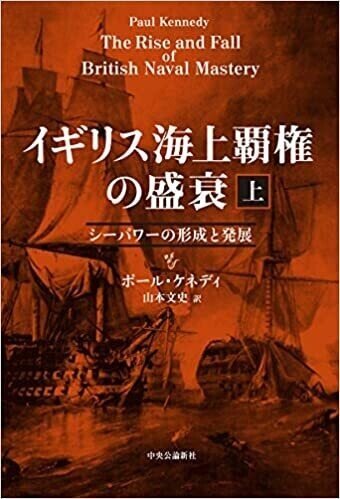
序章 シーパワーの要素
第一部 興隆
第一章 イギリスのシーパワーの黎明期(一六〇三年まで)
第二章 スチュアート朝時代の海軍と英蘭戦争(一六〇三―八八年)
第三章 フランスとスペインに対する戦い(一六八九―一七五六年)
第二部 絶頂
第四章 勝利と躓き(一七五六―九三年)
第五章 フランスとの闘争、ふたたび(一七九三―一八一五年)
第六章 パクス・ブリタニカ(一八一五―五九年)
第七章 マハン対マッキンダー(一八五九―九七年)
第三部 凋落
第八章 パクス・ブリタニカの終焉(一八九七―一四年)
第九章 膠着、そして試練(一九一四―一八年)
第一〇章 凋落の日々(一九一九―三九年)
第一一章 幻想の勝利(一九三九―四五年)
第一二章 道の終わり:戦後世界におけるイギリスのシーパワー
著者は本書の目的をイギリスの台頭を可能にしたシーパワーの発達を歴史的に再検討することである、と説明しています。海軍史の著作として読むこともできますが、戦闘や戦術に関する記述はないので、あくまでも海洋戦略に焦点を合わせた歴史書です。
著者自身の要約によれば、本書の要点は以下の3点です。第一に、イギリスの海軍力と経済力は常に密接な関係を持っていました。17世紀以来、イギリスは商業革命、海上貿易、産業革命がもたらした富によって大規模な艦隊を建設することができました。したがって、イギリスの海洋戦略を研究するためには、軍事史の視点だけでなく、経済史の視点が必要であると考えられています。
第二に、イギリスがシーパワーによって世界各地の情勢に大きな影響を及ぼすことができた時期は、外洋を安定的に航行可能な帆船が普及した一六世紀の初めから、第二次産業革命の影響でヨーロッパやアメリカで工業化が進んだ一九世紀末までのことでした。20世紀以降に起きた産業構造の劇的な転換についていけなかったイギリスは大国の地位を保持できなくなり、第一次世界大戦で決定的な打撃を受けました。
第三に、シーパワーの有効性が高かった時期でも、その効果には一定の限界もありました。イギリスの海洋戦略が成功したのは、あらゆる機能を海軍に頼っていたわけではなく、陸軍と海軍を巧みに組み合わせて運用することができたためです。ヨーロッパ大陸での陸上戦に巻き込まれることは避け、同盟国に財政的援助を行う程度の限定的な関与に限定する孤立主義は戦略として上手くいきませんでした。
著者自身は以上のように本書の要点をまとめてはいますが、実際に読んでみると、この要点だけでは捉えきれない内容が数多く盛り込まれていることが分かります。海洋戦略の特徴の一つは、その戦域が地政学的な広がりを持っていることです。陸上戦略を研究する場合は、戦域が交戦国の領土の範囲に限定されることがほとんどですが、海洋戦略の研究ではそのような狭い範囲に戦域を限定することができません。著者はそのことをよく理解しており、本書の随所で世界地図を示しながら、イギリス海軍が世界のどこで活動していたのかを示しています。
歴史的にイギリスのシーパワーが及ぶ海域は近海から出発して大西洋へ広がり、そして大西洋から地中海、インド洋、東南アジアへと拡大していきました。ナポレオン戦争(1804~1815)が終結してから、イギリス海軍は列強でも最大規模の艦隊を世界中に配備し、1848年の時点で本国に35隻、地中海に31隻、西インド諸島に10隻、太平洋に12隻、西アフリカに27隻、南アフリカに14隻、東インドと中国に25隻の主力艦を活動させていました(上巻、326頁)。
もちろん、これほどの規模の艦隊の戦闘力を適切に維持するためには、多額の資金が必要であることは言うまでもありません。国家がシーパワーを造成し、運用する上で戦略家が懸念すべき深刻な問題は、その財政的負担の大きさです。マハンもこの問題に対する認識は持っていましたが、本書の著者の方がより専門的な見識を持っています。著者は19世紀の後半に入ってイギリス経済は衰退の局面に入っていたことを指摘しています。
1860年に世界の貿易でイギリスが占める割合は25.2%で、フランスは11.2%、アメリカは9.1%、ドイツは8.8%でした(下巻、31頁)。しかし、20年後の1880年にはイギリスが世界の貿易で占める割合は18.1%まで減少し、フランスも9.3%まで減少しています。それに代わって台頭したのがドイツとアメリカであり、それぞれの貿易は世界全体の10.4%と9.0%を占めるようになっていました(同上)。
イギリスが大規模な海軍を維持する上で貿易と投資がもたらす利益は非常に重要な財源でした。しかし、貿易の中心地が1870年以降にイギリスから遠ざかるにつれて、次第に貿易赤字が拡大するようになっていきました。
歳入の減少に直面したイギリスの財政に追い打ちをかけたのが19世紀の後半に起きた技術革新による軍艦の開発費、建造費、維持費の上昇です。安上がりな帆船の時代は終わり、内燃機関で推進し、装甲で防護され、大口径の火砲を搭載した軍艦が当たり前に各国で配備される時代が始まりました。それに伴って海軍の予算は飛躍的に増大するようになりました。
1893年にイギリスで建造が始まったマジェスティック級戦艦の1隻あたりの平均費用は100万ポンドでしたが、1904年に建造が始まったネルソン級戦艦は平均で150万ポンド、1910年に建造が始まったキングジョージ級戦艦は195万ポンドもかかりました(同上、36頁)。イギリスは1883年に1100万ポンドだった海軍予算を1903年には3450万ポンドに引き上げて対応しましたが、国際競争に敗れた製造業、造船業の衰退は食い止めることができず、輸入に頼らなければならなくなり始めました(同上、37頁)。
1914年に勃発した第一次世界大戦では航空機が登場しました。19世紀の後半にはすでに潜水艦が戦艦にとって重大な脅威になっていましたが、この航空機は海上戦の様相をさらに大きく変化させる画期的な装備でした。しかし、海上戦における戦艦の価値は本質的に変わっておらず、航空機は無用の長物と考える保守派が海軍で根強く残っていました(同上、174頁)。何よりも第一次世界大戦で赤字を大きくため込んだ結果、イギリスはますますアメリカに経済的に依存するようになり、海軍としても新装備の研究開発のために十分な予算を確保することができず、装備の更新が滞りました。
イギリス海軍の予算が削減された影響は1939年に第二次世界大戦が勃発した時点におけるイギリス海軍の態勢に現れています。当時、イギリス海軍が保有していたのは戦艦・巡洋戦艦12隻、航空母艦6隻、巡洋艦58隻、駆逐艦100隻、小型護衛艦101隻、潜水艦38隻でした(同上、192頁)。同時期にドイツ海軍が保有していた巡洋戦艦2隻、ポケット戦艦3隻、重巡洋艦1隻、軽巡洋艦5隻、駆逐艦17隻などの戦力に比べれば、数字の上では優勢であるように見えましたが、その内訳はほとんど老朽艦でした(同上)。
1939年の時点では参戦していませんが、ドイツと同盟を結ぶ日本には戦艦10隻、航空母艦10隻、重巡洋艦18隻、軽巡洋艦18隻、駆逐艦113隻、駆逐艦63隻があったことも考慮に入れると、もはやイギリスが世界の海を支配するとは言い難い状況であったことが分かります(同上)。少なくとも、イギリスが東アジアから東南アジアの正面にわたって日本の脅威に対処することは戦略的に不可能な状態でした。
著者はイギリス海軍の予算を削減した大蔵省の緊縮財政が歴史家によって繰り返し批判されていることも紹介していますが、問題は財政だけではありませんでした。ゴム、錫、サイザル麻、タングステン、硬材などの供給源であるアジアの生産拠点は日本の脅威を受けていました(同上、222頁)。ドイツの潜水艦による通商破壊でイギリスは数多くの船舶を失っており、第二次世界大戦を通じて1145万5906トン分の商船を沈められました(同上、229頁)。イギリスの造船業には需要の増加に対応できる供給能力がなく、戦争で商船隊の規模は1939年の70%に減少し、海上輸送力の不足が深刻な状況に陥りました(同上、229-230頁)。
アメリカが1941年に第二次世界大戦に参戦しなければ、イギリスが最後まで戦い抜くことは困難だったはずです。第二次世界大戦が終結した時点で著者はイギリスがもはや世界強国としての地位を維持することができないことは明らかになり、世界各地に広がる自国の領土や植民地から部隊を撤退させることを余儀なくされたことも詳細に記述しています。
著者は世界の歴史で大国がその圧倒的な勢力を永遠に保持できた例は一度もなく、イギリスもその例外ではなかったと述べています。しかし、その歴史には数多くの興味深い要素があり、海洋戦略を研究する人々に貴重な教訓を与えてくれるでしょう。また、現代の日本、アメリカ、中国などの戦略を研究する際にも参照するべき文献だと思います。
見出し画像:U.S. Department of Defense
関連記事
調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。
