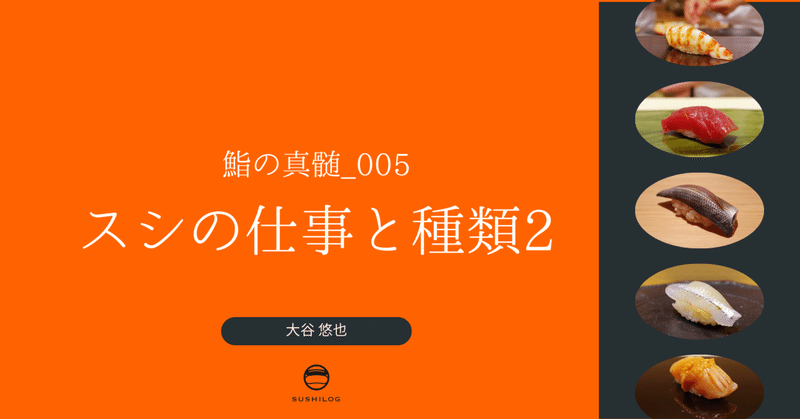
鮨の真髄No.005 スシの仕事と種類2
本記事は「鮨の真髄」の連載5回目です。筆者が2023年12月末に始めた、アメリカのSubstackで連載している"Spirits of Sushi"の完全日本向けバージョンです。筆者は本が大好きなので、書籍をイメージした構成でお届けします(最下部に目次を記載しています)。
本連載を読み終えたときには、必ず鮨通になっています!
ググってもSNSを開いても得られないような情報を盛り込んでいきます。
「スシの仕事と種類」のチャプターでは、江戸前鮨の仕事=調理法を深掘りするとともに、色々な種類のスシを見て行きます。江戸前鮨に詳しくなるだけでなく様々なスシを知る事で、鮨の食べ歩きがさらに楽しくなるのは間違いありません!
本記事では、江戸前鮨の仕事の「包丁」と「締める」について解説します。
切る:魚介類を適切な形状、厚みに切る
締める(塩締め、酢締め、昆布締めなど):魚介類の水分を抜き、魚自体の味わいを深め、塩味を含ませる
下記が前号の記事となります。
「江戸前鮨」の仕事の詳細
それでは、江戸前鮨が誇る「仕事」の詳しい説明を行う。
切る

鮨において握る技術よりも重要なのが包丁の切り付けである。鮨のみならず日本料理において最も重要なスキルが包丁だ。食材の味は間違いなく包丁の技術で変わる。言わずとも明瞭なことであるが、素人が切った魚と熟練の職人が切った魚では味が全く違う。両者が同じ魚を用い、仮に見た目の面では素人の方が綺麗であったとしても、味わいの面では熟練の職人が凌駕する点は興味深いところだ。かつては欧米人の中に「刺身は魚を切っただけなので料理ではない」と軽んじる不届き者も散見されたようだが、昨今は日本料理・和食の人気が高まり、包丁の仕事も大切な調理法であることが認識されている。東京で有名な「かっぱ橋道具街」に行くと、包丁を真剣に吟味する外国人の姿が目立つ。食を愛する日本人として嬉しい光景だ。
上質な江戸前鮨においては、食材を切る際に教科書どおりに切るのではなく、魚介類の味を計算して切られる。魚介類の時期、サイズ、脂の乗りや、自身の調理法、自身の酢飯の味わいを考慮して切り付けるのだ。包丁のスペックや切れ味だけでなく、この見極めの点において玄人と素人に大差が表れる。また、刺身で食べるための切り付けと鮨で食べるための切り付けは異なる。よって、同じ魚を用いていても、酒肴で頂く時と鮨で頂く時では印象が異なる。このような意味において、鮨に限らず日本料理店でも居酒屋でも、切り付けが下手なお店は訪問リストから外した方が賢明である。懐が寂しくなるだけでなく、魚が可哀想になる。二重苦だ。
なお、鮨を食べて「味が薄い」と感じることはないだろうか?私は、たまにある。「味が薄い」と言う表現には、味覚に加えて比喩的な意味合いも含まれている。「味の存在感が無い」と言っても良い。その原因については、魚のクオリティよりも、むしろ施す仕事が理由であることが実に多い。教科書どおりに仕事をしていても魚の魅力を引き出せないのだ。使用する魚の特性を見極めて、自身のシャリとのバランスを考えて仕事をしなければ、味の存在感を失う。ここに鮨の難しさと楽しさが存在する。このプロセスを楽しめる方のお店は、訪問する度に美味しくなる。楽しみながら王道を探求している職人さんを見つけてお店に通うのが鮨通になるための近道である(もちろん初回の訪問が好印象であることは大前提である)。
締める(〆る)
締める仕事は鮨で多用される極めて重要な仕事だ。そのため、塩締め、酢締め、昆布締め、砂糖締めについて、個別に説明する。なお、締めは漢字表記以外に「〆」と記載されることもある。漢字よりも視覚的に認識し易いので、以降は「〆」と記載する。
塩で〆る

「〆」の仕事の中で最もポピュラーな仕事だ。江戸時代には保存性を高める目的で使用されていたが、現在は味覚を重視して使用される。塩〆の主な目的は魚介類の味を向上させるためだ。まず、魚介類に塩を振ることで悪臭の原因となるトリメチルアミンなどのネガティブな要素を除去することが出来る。そして、魚介から水分を抜くことで味を引き締めることも可能だ。魚に塩を振りかける手法が最も一般的だが、塩味が染み込まないように塩分濃度が低い塩水で〆る「立て塩」という方法もある。「立て塩」の場合、液体ゆえに脱水効果は穏やかで、魚の身が凝縮する事は少ない。柔らかいテクスチャーを活かしたいときや、小魚を用いるとき、味を上品に仕上げたいときなどに使われる。
さらに、最近のセンスがある鮨職人は使用する塩を選び抜いている。どこの産地の塩を使うか?は重要な要素である。一昔前(1997年)までは日本では塩が専売制だったので、含有量の99.9%がナトリウムの精製塩が使われていた。しかし、自由化の後は各地で伝統的な製塩が復活したため、ミネラルが豊富な塩も作られるようになった。何分、何時間〆るか?は鮨職人のセンスを表すポイントだ。塩を駆使して魚介類の味を引き出す技術に鮨職人の技量とセンスが表れる。
酢で〆る

塩〆と併用されることが多い仕事が酢〆だ。お酢で〆ることで食材の食感が更に引き締まり、お酢の酸味も身に浸透する。要は爽やかな味になるわけだ。そして、酢で〆た後に冷蔵庫で数日寝かせると魚の味は劇的に変わる。お酢の酸味がまろやかになりつつ、魚介類の旨味が引き出されるのだ。小魚の場合にはお酢の酸味で小骨が溶け、テクスチャーも良くなる。江戸前鮨で主役級の鮨種であるコハダについては、塩〆と酢〆の芸術と言える。コハダは鮨で食べるのが最も美味しい不思議な魚で、鮨専用のような存在だ。江戸前鮨で最も重要な〆の技術を駆使して持ち味を引き出す魚なので、古来より「鮨はコハダにとどめさす」と言われてきた。コハダは仕事が用いる魚なので、生でも美味しい鮪や海胆よりも「江戸前鮨の主役」だと断言できる次第だ。最近は日本人の嗜好が変わり、「柔らかくて甘いもの」が好まれがちだ。大トロや海胆に留まらず、アオリイカやアカムツ(ノドグロ)など。しかし、「柔らかくて甘いもの」の礼賛は味覚の幼児退行であると言わざるを得ない。鮪や海胆はインスタグラムで映えるので人気を博しているが、鮨の魅力としては間違いなくコハダが上を行く。自身が「美味しい」と感じる要素が旨味ではなく脂や糖分であるとすれば、それは危険信号なので注意した方が良い。脂や糖が過剰な食材ばかり食べていては味覚は向上しない。
また、酢〆の変形パターンも存在する。黄身オボロ〆や雪花菜〆だ。これらは黄身オボロ(卵を細かい粒子になるまで低温で炒ったもの)や雪花菜にお酢を浸透させ、その中に魚や海老を漬け込む〆方だ。お酢がダイレクトに触れないので、まろやかな〆加減が可能となる。このような〆方は実践する鮨職人が少ないため、試みている方のお店には優先度を上げて訪問して良い。なお、【車海老の黄身酢オボロ漬け】は「すし匠」の中澤親方が考案者と考えている人が多いが、正しくは「奈可久」の鈴木親方である。中澤親方は「奈可久」で実食して自身の仕事に応用された次第だ。「間接的に酢〆を行う調理法」については、今後も生み出されていくだろう(筆者はポテンシャルを感じている)。
なお、酢〆においても使用するお酢の質は極めて重要である。塩と同じく良いものを選ばないと美味しくならない。不味いお酢で〆た青魚ほど、人にトラウマを植え付ける存在は無い。日本人には幼年期に〆鯖に苦手意識を持つ人が多い。この理由は、廉価で低質な穀物酢を用いて下手に〆た鯖を食べて拒否反応を覚える為だ。旨味が無く、酸っぱいだけのお酢で魚を長時間〆ると、魚を見事なまでにダメにする。家庭においても、低質なお酢は決して健康に良くないので、真面目に造っているお酢に変えることを推奨する。
昆布で〆る

昆布は鮨や和食において無くてはならない食材だ。日本料理から昆布を取り上げると料理の生命線である出汁や旨味を使えなくなるので破綻する。鮨における昆布〆は、昆布の主要な遊離アミノ酸であるグルタミン酸を食材に移し、旨味が少ない魚介類の旨味を増やすとともに、脱水する効果がある。基本的には魚介類を美味しくする仕事だが、やり過ぎると魚介類の持ち味を壊してしまうため要注意である。特に、白身魚や淡い味わいの光物に昆布〆を用いる場合には、「昆布の味と香りしか感じない状態」にしてしまうと失敗なので繊細な見極めが必須だ。冗談のような本当の話になるが、ミシュランの星を取っていて日本では誰もが知るお店でも昆布〆が過剰なケースは時折ある。素人目に見ても「なぜこのレベルの味で出せるのか?」と感じる。食べ手としては、昆布〆において昆布の香りと旨味が行き過ぎていないか吟味して頂くのが良い。最も分かりやすいタネは春子で、最初に昆布の香りと旨味を感じるものは出来損ないである。
砂糖〆
最後にユニークな〆方を紹介しよう。砂糖〆だ。魚に砂糖!?と驚く方も多いかもしれない。ただ、これは理に適っている手法だ。砂糖で〆ると魚介類の水分を脱水するどころか、甘味が浸透してしまうのではないかと不安になるものだが、甘味は浸透しない。砂糖の粒子が大きいために甘味が浸透する前に脱水出来るのだ。よって、味を凝縮させるために塩〆の前に砂糖〆を行う職人は割といる。もちろん粒子が細かい和三盆糖などを用いると甘味が浸透してしまうが、精製された上白糖であれば砂糖〆が可能である。江戸時代には存在しなかった〆方が生まれ、さらに進歩しているのが面白い。
次の記事では、残る7つの仕事について解説する。また会うのを楽しみにしている。
今後の目次構成
今後については、以下のとおり執筆していく予定です。
スシの歴史
スシの仕事と種類:江戸前寿司(握り鮓)、関西鮓などなど
スシの用語: 鮨店を100%楽しむための重要用語集
鮨の生命線:シャリ、酢飯、鮨飯について
鮨種(タネ、ネタ)についてのマニアックすぎるガイド
鮨職人の技:包丁や鮨職人の道具について
日本が誇る魚文化: 築地から豊洲市場、そして各地へ
必訪の鮨レストラン: 東京から札幌、福岡、その他の地域まで
郷土寿司の世界: 日本の多様な寿司文化を探る
鮨と日本酒のペアリング
鮨の作法とテーブルマナー
家庭で美味しいスシを作るための必需品
ポップカルチャーの中のスシ: マンガと映画
スシの健康と持続可能性
まとめ:スシの未来
なお、こちらがサブスタックの英語版記事になります。
それでは、今後ともよろしくお願いします!
次の記事
ご支援頂いた分は取材や執筆活動に投資します。より良い情報提供を目指します!
