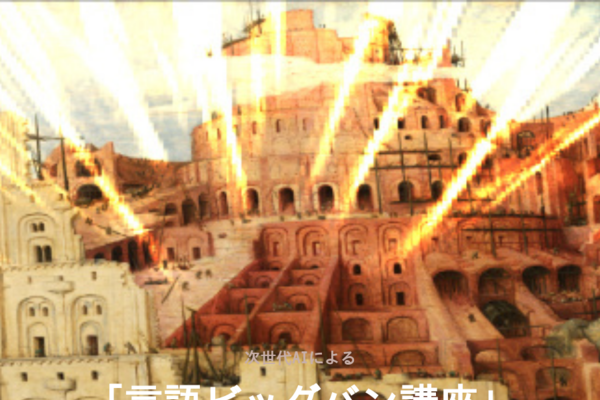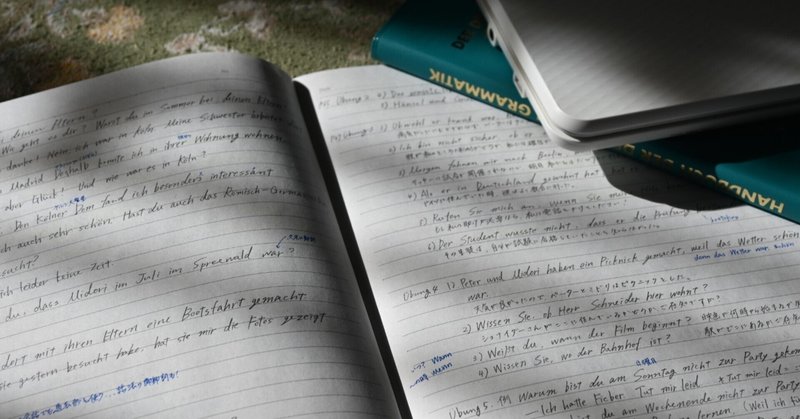
AI 翻訳を外国語学習にどう使いますか?
自作の落語「おなら指南」を言語ビッグバン講座のフォーラムに投稿した時に添えた一言。
KTさんに触発されて落語の台本を創作しました。古典落語の翻案(ぱくり)ですが。
KTさんは趣味で落語をやっている方で、ビジネスマンとしての豊かな見識から講座の zoom 交流会でもいつも面白くて鋭いコメントをしていた。
「野ばら」の Papago訳の「おなら」にまっさきに反応してくださったNTさんが、同じグループの分かち合いの時に、「こどもはおならとかうんこが大好きで、そういう言葉をいろいろ AI翻訳で調べて遊んでいる」というお話をしてくださったのもヒントになっています。
NTさんは看護師で、小児病棟で赤鼻のホスピタルクラウンの経験がある。
日本語のできない外国人の患者さんとのコミュニケーションの話題を提供してくださったり、ヒューマンライブラリーについてリサーチした結果を紹介してくださったり、医療従事者というバックグラウンドからさまざまな貢献をしてくれたメンバーだった。
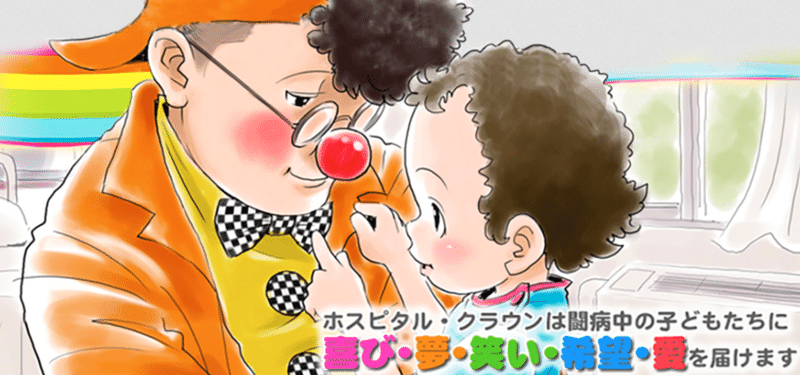
実は、言語ビッグバン講座の第2講のテーマは「 AI 翻訳と語学学習」だった。
私の落語「おなら指南」も主人公が英語を習うために DeepL を使うという設定にして一応(いや、ムリヤリ)テーマに沿わせたのだが、この落語を投稿する前に、「自分自身の語学学習にAI 翻訳を使うとしたらどのように使うか」という問いに対して私は次のような投稿をしていた。
2021年 08月 20日(Friday) 08:25 -
自分自身の外国語学習に AI 翻訳は基本的に使わない。現時点での AI 翻訳のレベルであれば「怖くて使えない」というのが本音です。
でも、この後すぐに言い訳のような投稿もした。
2021年 08月 20日(Friday) 10:15 -
自分個人の「外国語学習」に使うつもりは今のところありませんが、仕事や研究の場で、自分ができない外国語による情報を理解したい時には、 AI 翻訳を使っています。とても助けられています。決して、AI 翻訳否定派というわけではないので、念のため補足しました。
そして、同じ日の夕方に次のような投稿をした。
2021年 08月 20日(Friday) 17:36 -
ふと思ったので、忘れないうちに書いておきます。課題の質問は「語学学習」だったのですが、私があえて「外国語学習」と書き換えたのは何かそうしたいという気持ちが働いたのだろうなあ、と。
日本語の「語学」ってどこか「お勉強する」ニュアンスがありますが、英語の language learning ってコミュニケーションのツールとしての言語を使えるスキルを身につけるという意味で使っていると思います。
もちろん、専門的にたとえば「英語学」というように1つの言語の歴史や文法の成り立ちなどを含めて極める(深める)「学」もありますが、世界中の英語学習者の大半はそのようなことは関係無く英語を「道具」として使っています。
日本人は「英語のお勉強」というセンスからなかなか抜けられないのでは?
すると、フランス在住の日本語教師のゆーばんさんから返信があった。
確かに!
「外国語学習」というのと「語学学習」というのでは、ニュアンスが違いますね。別に「◯◯学」じゃなくていいんですよね。コニュニケーションツールの習得が目的なら。
また、同じ「◯◯学」でも、日本語は対象は同じなのに、「国語学」と「日本語学」という二つの表現があります。
学校の授業の「国語」の科目名もそうですね。「日本語」でもいいのに。
日本の社会の多様化が進んで、日本語が母語ではない人が増えてくると、この辺りの感覚も変わってくるのでしょうか。
そう言えば、フランスやアイルランドでは、学校の科目も「外国語 foreign languages」ではなく、「現代語 modern languages」を使っています。
「古代ギリシア語やラテン語ではなく」という文脈があるからでしょうが、いろんなルーツをもった人たちがいて、人によって何が母語で何が外国語なのか線引きが難しい、線引きをする意味がない、からでしょうか。
語学学習、外国語学習、現代語学習、名称やそこから感じるイメージ、込められている思いって、小さいようで大きいなあと感じました。
私はゆーばんさんに次のように返信した。
日本の中学生や高校生が「英語が好き」とか「英語がきらい」っていうの、どういうことなんだろう?って。
「英語が大好きだから英文科に行く」って私の世代の日本の高校生には普通のことだったみたいですが私は違和感がありました。
イギリスやアメリカの文学はたしかに英語が嫌いでは原書で読めませんが。
また、日本の大学の英米学科の指導教授で伝統的に尊敬されてきた先生方は英米文学の専門家でしたが、英語は読めてもしゃべれない。
20年前は「学生に通訳とか教えるのって大学でやることではないと思います」と面と向かって会議で英文学ご専門の教授から言われました。
今はかなり変わりましたが。
コミュニケーション・ツールとしての外国語。ツールの使い方を効率よく身につけて、そこから広い世界へ飛んでいってほしい。
英語教室を運営し、オンライン講座も開催している運営チームのAさんから、次のような返信がきた。
子どもの頃、教科によっての好き嫌いは、先生が好きかどうかによる場合が多かったです。先生は嫌いだけど、その教科は好きというのは聞いたことありません。
今は、学校の他にも先生以外の大人から学べるチャンスがあるので、先生が嫌いでも大丈夫な世の中になっているかもと思いました。YouTubeやオンライン講座など、学べる環境が整っています。
私からAさんへの返信。
コメントをありがとうございます。
小中学生の頃に「科目」としての英語が好き、という感覚は理解できます。先生が好きで、先生に褒めてほしくて英語で高得点を取れるよう頑張れば英語が「得意科目」になって自分は「英語が好き」なんだと認識するのでしょうが、はっきり言ってそれは大きな勘違いではないかと。
高校生になって、大学の進学先を考える段階でまだこの勘違いを引きずっていると、コミュニケーションのツールとしての「英語」という理解が歪んだままになるのではないかと思います。
そして、この週の課題の2番目の問いだった「AI翻訳を語学教育に使うとしたらどのように使うか」に答えた私の投稿。
2021年 08月 20日(Friday) 09:05 -
2. AI翻訳を外国語教育に使うとしたら、現時点での AI翻訳に全面的に依存することがいかに危険かという視点で、 AI 翻訳による誤訳の実例を示しながら活用します。
実際に大学で外国語教育に携わっている立場として、学生たちが外国語の基礎力を身につける前に AI 翻訳にかなり依存している現状をみて危機感を抱いています。
私の投稿に、英文科出身で今は情報関連の授業を担当している大学教員のKKさんから返信がきた。
これは切実な嘆きですよね。
10年くらい以上前のことですが、英語の先生が、Itから始まる文が多くて何故だろうと不思議に思っていたと。Yahoo翻訳を使っていることがわかったと。日本人は主語を言わないので、AI 翻訳さんも主語に困ったのですね。
私からKKさんへの返信。
KKさん、コメントありがとうございます。
私は学生たちに AI 翻訳の使用を禁じてはいません。実際に使ってみて、自分で修正するように促しています。つまり、AI の限界がわかるほどの言語能力を身につけてほしいと思っています。
AI 翻訳の間違い探しは、数年前から演習に取り入れています。特に、構文とは何かを理解するために重要だと思っています。
私たちのやりとりを読んで、ゆーばんさんからコメントが来た。
AI翻訳を実際に使ってみて、かつ限界を知りながら、自分で修正する力をつけていくというのが、これから求められる言語能力の一つだと、KKさん、すみさんのやりとりを見てますます意識しました。
それから、同じ母語話者でも使っている表現は一人として同じではないことを考えると、「より自分らしい表現・言い方」をAl翻訳の助けを借りながら、探求できるからなとも感じています。
言い間違い、誤解、メッセージの読み違いは、AIに限ったことではなく、日常に溢れているので。
AIを信用しつつ、疑うスタンスかな、と今描きながら、自分自身のことを振り返りました。
ゆーばんさんの「AI を信用しつつ疑うスタンス」というフレーズにすべてが込められているような気がする。外国語学習に活かす時は特に大切なスタンスだと思う。
ちなみに、言語ビッグバン講座の1期はただ今(2022年3月)開講中で運営チームの山中さんがこんな記事を書いている。