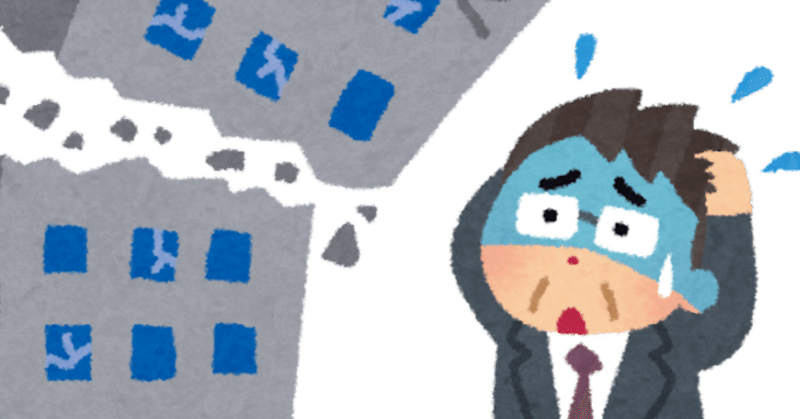
敗者だから伝えたい こうして会社は倒産しました 19
~メーカ再建でも頑張ります~
体験した実話の倒産劇。何かの参考になれば幸いです。
前回までのあらすじ。いい人材が入社しても、解雇してしまいました。
問屋業の社内が騒いでいる中で、メーカー業も赤字なので、考え方を変えて挑戦しなければなりません。
販路拡大は重要な再建の手段
売上が足りないさつま揚げ屋さんで、単価の安い地元スーパーで販路拡大しても、採算分岐点に届くのはいつの日か。
単価が高くて利益率が高いのは、ギフト・土産・直販・県外なので、元々の強みでない部門で売上を上げていかないと、再建につながりにくいことになります。
そこでまずギフトの拡大です。大手量販店のギフトに採用されれば、中元歳暮時期だけですが、一定の売上を見込めます。大手量販店は直接取引口座を作ることが非常にむつかしいため、現在取引している仲介ベンダーを頼ったり、展示会に出品することで露出を増やしていきました。ギフトについては、仲介ベンダーの多大な助力もあって、複数の大手量販店のギフトとして採用されました。
商談は主に東京と大阪で、要求される資料やコンプライアンスも厳しい面がありましたが、何とかクリア。しかし今ならもっと厳しくなっていると思います。
話題性ある新商品開発
次に必要なのは直販の強化です。直販も当時は直売店が2店舗、インターネットは楽天市場店のみでした。過去には先代社長から継続的にスーパー向けの新商品を多数出してきたのですが、どうしても商品寿命が短く、資材ロスも大きいことから、私に引き継いだ後はスーパー向けの新商品開発は減らしていました。
さつま揚げの新商品としては、新たな具材を入れるとか、個包装するとかのアイデアがよく出てきます。しかしロングランでヒットするような新たな具材はなかなか厳しい状態です。
個包装は、手が汚れないから売れそうという、100人が考えたら90人が思いつくような凡庸なアイデアで、私が社長になる数十年前から当社も多数の同業者も挑戦しましたが、さつま揚げの場合は、どんな素晴らしいパッケージに仕上げようとも、どんな手法でどこの販売チャネルを使っても、単に手間とコストが上がるだけで、絶対に売れないという結果になります。(私も専務時代に一度やってます)
そこでさつま揚げが最も売れない2月に売れる商品として、史上初のハート型のさつま揚げを開発しました。大きさや厚みも様々なパターンを模索し、パッケージとネーミングに代理店の協力を得て、販路は2月限定で直販とネット、そしてスポット対応で披露宴用の引き出物用の限定商品としました。
型を使って製造するので、小ロットは採算が取れないので作れません。数量がまとまる時期と、市場のみで販売したところ、かなりの好評で、メディアも取材に来て頂けました。取材だと広告料が要らないので、再建企業ではありがたい。
最も強い販路として持っているスーパーからも一部の得意先から売りたいとご希望を頂きましたが、単価も高く設定してますし、バレンタイン商戦用なので、かまぼこ・さつまあげ売り場にバレンタイン商品を探しにくる人などいません。
また、要冷蔵なので、チョコの隣に置くこともできないので、ほぼ間違いなく売れ残って見切り品コーナー行になることが目に見えていたからです。そういう扱いが一度あると、直販でも売れなくなります。
特産品展示会では少し珍しいので、一緒に展示してみました。会った同業の社長から価格を聞かれて、「高っ、売れんの?」と言われました。まあ形が違うだけの商品で、2倍の設定なので無理もないです。毎年そこそこ売れました。今では同業者も真似してます。
同様の商品で、コンビニ向け商品と、別の直販用商品も考案していたのですが、事業がそれどころじゃなくなったので、頭の中だけで封印されてます。たぶんそこそこ売れます。倒産から15年以上経ちますが、まだ誰も思い付いて無いみたいです。
県外から新たな要望がくる
更に県外市場狙いでBtoBサイトに登録して、鹿児島産のさつま揚げとして差別化できる県外に販路を求めました。
すると真空パックの商品が欲しいと連絡が来ました。真空パックの商品は、パックした後で熱湯殺菌をしているため、3週間の賞味期限が保証できる程度に保存性が高く、生産効率もいいです。
サンプルを送ると、販売先で採用が決まったとの事で、思わずガッツポーズをとります。もしかして死語かな?
早速注文が来て、初回1ケース、2回目5ケースと順調です。3回目でさらに大量の注文が来たので、何と無く怖くなって、営業方に会社訪問してもらいました。
すると、
「行ってみましたが、とても普通の会社では無いので、商談できません。」
と、連絡が来ました。詳しく聞くと、扉を開けて中をパッと見て帰ったそうなのですが、どう見てもいわゆる反社勢力の事務所にしか見えない感じだったそうです。
電話で送付済みの商品について支払いを求めたら、それっきり連絡が取れなくなりました。いわゆる取り込み詐欺に引っかかったのです。
少しの売上が欲しいために、更に損を重ねてしまいました。
ちなみにこれだけやっても、まだメーカー業も赤字です。
倒産社長が伝えたい経営の教訓
「事業不振の時ほど怪しい人が寄ってくる」
不振になると、仕入先もほとんど気付いていないはずなのに、どこから聞きつけたのか、闇金融なのか消費者金融なのか不明な、知名度の無い会社から融資の話はたくさん来ます。
また、こうした取り込み詐欺の会社も多数の連絡が来たりします。一度貸し倒れしてからは、信用情報を先に取るようになりましたが、苦しい時に更に苦しくなる状況を自ら作る罠がやってくるのは今も同じだと思います。
面白いとか、役に立ったとか、つまらないとか思って頂けたら、ハートをお願いします。ツイートやFBで拡散して頂けると、とってもうれしいです。
シリーズ1回目はこちらからです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

