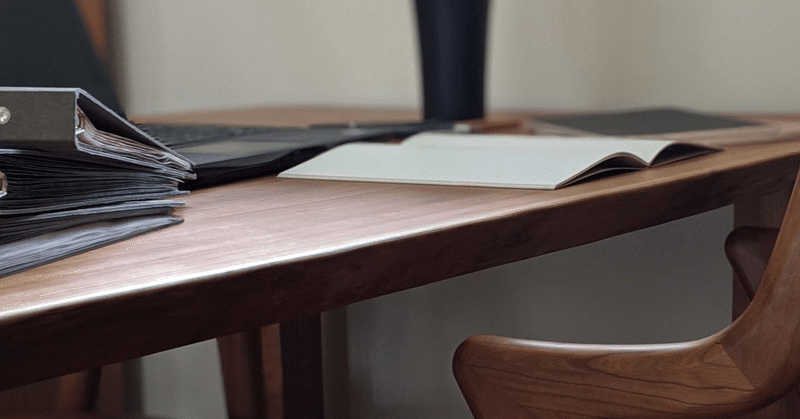
大学改革の顔
「ソーシャルインパクトが期待できない研究は無駄です!本学では、そういった無駄な研究は許されない!」
改革担当理事が言った。
「無駄な研究を排除してスリム化を図り、大学全体としてソーシャルインパクトの高い研究にフォーカスします」
教職員はざわついている、ように思えた。実際のところはわからない。この教職員研修はリモートで行われているからだ。
改革担当理事の言葉にAは驚き、自分の研究が無駄と見做されるか否かを少し考えた。
提示されているスライドには、「スリム」「フォーカス」「ソーシャルインパクトが期待できない研究はしない!」「無駄な研究はなし」「専門技術が必要ない作業は機械化・自動化!」「先進性と機動性をキーワードに!」といった言葉が並ぶ。
「そもそも改革担当理事っていう名称はどうなんだ?」
AはPCを前にして呟く。もちろんマイクはミュートにしてある。
改革を掲げる所作が古臭く映る時代になった、Aはそう感じていた。改革は、一つ前の元号を象徴する言葉だ。
改革担当理事の話は続いている。
「Withコロナで問われたのは、ソーシャル・トリアージです。社会全体で本当に優先すべきものは何か?無駄は何か?そういったことを突き詰めていかなければいけない」
理事が持論を展開する中、モニターの下方でチャットの通知バッチが点灯した。リモートで行われている今回の教職員研修では、参加者がチャット機能を用いて随時コメントや質問を投じることが可能になっている。
[コメント]
研究テーマについて選択集中するのではなく、大学全体として多様なテーマを遂行すること、研究環境としての「遊び」を確保することが、学問の自由という観点からも健全ではないでしょうか?
紋切り型の反論だな、とAは思った。
今となっては、「学問の自由」は学者や研究者の言葉というより、左派の言葉になってしまったような気がする。こういった言説への反動を養分に育ってきた改革派は、「学問の自由」を既得権益、自らを勇気ある対抗者と定義するのであろう。抵抗勢力をラベリングすることが改革のTIPSの一つだ。
[コメント]
方針に全く同意できません。金の取れる研究だけやれ、といった研究のスリム化は、大学院生や教員・研究者の自由な発想を持った研究を困難にすると思います。
[コメント]
無駄な研究の削減について、誰が何をもって必要・不要と判断するのでしょうか?多様性を潰していく、主流以外を切り捨てていく危険さを感じます。
「多様性」という言葉は誰のものになるだろうか。改革派がこれを簒奪する日が来るかもしれない。多様性を破壊する者が多様性を語る倒錯が起こることも、ありえなくはない。
[コメント]
“突出した研究”を推進するにあたって、専門ですらない理事の先生方に判断することが可能とは思えません。本学全ての研究の評価を外部に委託することも現実的ではありません。
選択と集中は、評価の過大評価を前提とする。評価対象の持つ価値や将来性を正確に評価することが可能だと信ずるからこそ、選択と集中という手法が可能になる。
改革担当理事にとって、コロナ禍は未来の不確実性を教えてくれたわけではなさそうだ。
「緊急事態宣言発令に伴い、大学からは研究の自粛の依頼があったと思います」
改革担当理事が言った。
緊急事態宣言下、国民は移動を7割、できれば8割削減することを求められた。附属病院を有する本学は、臨床で働くスタッフは出勤せざるをえないため、基礎研究に従事する教職員に9割の出勤削減・在宅勤務を求め、全学として7割の出勤削減を目指したのである。
Aは、チャット画面から理事の顔に目線を移した。
「私は、自分のいた分野の大学院生たちにメールをしたんです。自分の研究が不要不急の9割に入るか、本当に必要な1割に入るのか考えて、1割に入ると思ったら大学に来なさい、と。そうしたら半分の大学院生は大学に来て研究を続けましたが、残りの半分は来なくなりました。そういうのが無駄な研究、ソーシャルインパクトの無い研究なんです」
Aは思わず苦笑いした。
感染拡大防止のため、社会の要請に応えるため、泣く泣く研究を中断している教職員は多いだろう。自分もデータ採取を中断し、在宅で手持ちのデータをまとめたり論文を書いたりしているが、出来ることなら大学に行き科研費申請のためのパイロットデータを取りたいというのが正直なところだ。
コメント欄には批判的な意見が並ぶ。
[コメント]
COVID-19によって研究を1割に制限するよう大学から要請されている中、自身の分野の研究者に対しては必要ならば研究を継続することを容認するような発言をし、約半数の研究者が研究を続けたというような内容は、研究継続を理事のお墨付きで容認したように受け取りました。大学としての使命のために研究活動を制限した研究者に対して失礼ではないでしょうか?
[コメント]
社会のために研究を我慢した多くの研究者に対して失礼です。
[コメント]
COVID-19に全学で対応する上で、基礎系の出勤自粛は重要なミッションだったはずです。特にCOVID-19で研究自粛した人々に対して「自粛できるということは本来必要ではない研究だった。そのような不必要な研究はするべきではない」との発言は、全学でCOVID-19にうまく対応したことに水を差しかねません。
[コメント]
役に立つ研究だったら在宅勤務にする必要が無いというご意見に衝撃を受けました。第二波がもし来たときには、今度は私も研究を積極的に継続するようにします。
[コメント]
研究レベルを9割下げてと頼んだら5割の人が来なくなり、そういうのが要らない研究、という単純な評価がされるなら、在宅勤務や働き方改革など進まないのではないでしょうか?
緊急事態宣言下の研究制限は、改革担当理事にとっては無駄な研究を選別するイベントとして機能したようだ。
この論理はどこかで聞いたことがあるな、とAは思った。
緊急事態宣言下で病院の受診控えが起きた。受診を控えたということは、そもそも不要な受診であり、無駄な医療である。緊急事態宣言下で受診が減った病院は、不要な受診で診療報酬を稼いできたということだ。無駄な病院を潰して医療費を削減すべきだ。
先日見たテレビ番組で評論家がそう熱弁をふるっていた。
同じだ、Aは確信した。
緊急事態宣言下の外出自粛は、この評論家にとっては無駄な医療を選別するイベントだったのである。
改革担当理事の話は診療部門の話に移っていた。
「必要性が低い診療科を縮小します。具体的には、コロナ禍で患者が減った科、Postコロナで患者が戻らない科を縮小します。Society 5.0への転換加速は前提条件であり、リモート診療や5G、大規模データの活用は必須です。医療ビジネスへの進出を目指し、大型産学連携や大学発ベンチャー起業を推進します」
不採算部門の削減という発想は、財政難を前提とする。
国立大学はどこも財政難である。多額の赤字を抱える本学が10年後には財政的に立ち行かなくなるのではないかという噂は、学生にまで届いているようだ。かねてから医学部を欲しがっている超有名私立大学に合併吸収してもらうのが良いか、という案も上層部の会議で出たという話だ。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
