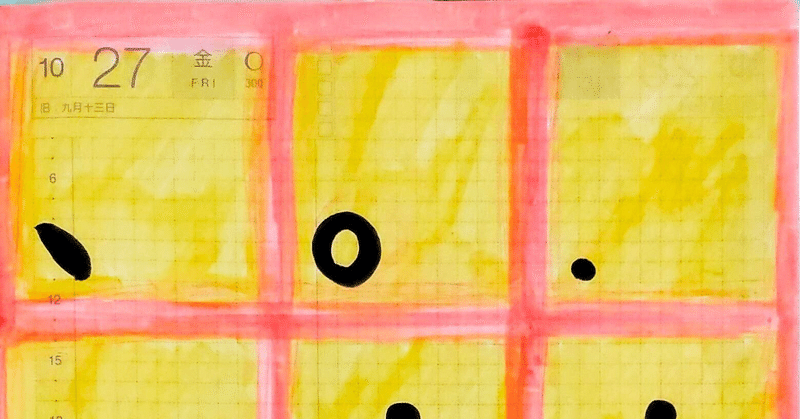
【文章作成の基本】読点の打ちどころ
先日、このような記事を上げました。
「一文をなるべく短くする」のは、どんな文章術の本や講座でも言われる、文章作成上の基本です。だから、そのためにどうしたらよいかについて、述べました。
ただし、これは、文章を書き慣れない中高生が一文を長く書きがちで、それによって(十分な「文章力」がないために)文構成が乱れ、結果文意が通らなくなるということが往々にしてあるため、それを防ぐ「予防線」として言っていることです。
「実際の文章」、「自然な文章」ということで言えば、「基本単文によって文章展開するも時に重文や複文(長い文)が入る」ことで、文章の自然な「メリハリ」、「リズム」が生まれ、冗長、単調ではない、いわゆる「うまい文章」となります。そのため、「絶対に一文を短くしろ!」ということではなく「なるべく短くした方がよい」という「ゆるいルール」として、(特に大人の方には)理解していただきたいと考えています。
つまり、文章展開の実際においては「長い一文をあえて書く」場面もある、ということなのです。
しかし、ここで問題になるのが「読点の打ちどころ」です。単文(短い文)の中ではとりたてて問題にならなかったことですが、ここでは大きな問題としてクローズアップされてきます。
英語のように分かち書きをしないにも関わらず、古来日本語には「、」も「。」もありませんでした。当然、文章が読みにくい、わかりにくいという支障が生じます。そこで中国の公文書における記号が転用され、それが日本語の表記法として明治から昭和前期にかけて整理され、今に至ります。長い文のなかで、どこからどこまでが主語なのか、その修飾語がどこにかかるのか、といったように、文構成(文の構造)を読み手にわかりやすく可視化するために、読点は生まれたのです。明治39年に文部大臣官房図書課が示した句読点法案の「テンの項」にある二十一か条の法則を下敷きに、昭和21年に文部省国語調査室によって句読点法案の十三のテンの項目が作成され、それが今の公文書における句読点の使い方の基本となっています。
とまあ、こうした細かい歴史的経緯はともかくとして、「長い文」を書くためには「読点をうまく使う」ことに意識的にならないといけない、ことは間違いはないです。
しかし、読点の使い方に意識的である人は少ないでしょう。特に中高生の文章の中では、(私の経験では)「感覚的に読点が打たれている」感じがします。その結果「やたらと文節ごとに打って、打ち過ぎて読みにくい文」や逆に「打たな過ぎで、文構成が見えにくく読みにくい文」が多々見られます。
そこで、読点はどこに打つのが適切なのか、ここで示します。ただし前述の二十一か条や十三項目を一つひとつ取り上げて紹介してもよいですが、さすがに難解な内容となるので、ここでは優先的に注目した方がよい「読点の打ちどころ」のみを単純化して示します。これによって、恣意的ではなく、読点の打ち方に自覚的になることができ、わかりやすい文章を書くことができるはずです。
1 従属する修飾節の後に打つ。
以前の記事で複文について述べましたが、複文を用いる場合は、読点の打ち方にある程度意識的になった方がよいでしょう。複雑な文構成を読点によって可視化して整理して読み手に示すことで、読み手の誤読を避けることができます。
例1:彼がけんか腰でそう話したとき、相手の態度が変わった。
例2:午後に雨が降るので、練習は中止です。
例1は「~とき」までが、「変わった」を修飾する節なので、ここで読点を打ちます。同じく例2も「~ので」までが、「中止です」を修飾する節なので、ここで読点を打ちます。
2 主語‐述語が離れるときに打つ。
例2‐1:練習は、午後に雨が降るので中止です。
複文では、(あまり望ましくないですが)主語と述語が離れ、「入れ子構造」になる場合があります。この場合は、主語「練習は」が中の「午後は~ので」を飛び越えて述語「中止です」に係るため、このように読点を打つとよいです。一方、「午後は~ので」という修飾語は直後の述語の「中止です」に係る(被修飾語)ため、この間にはあえて読点を打たず、「午後は~中止です」までをひとかたまりの「述部」としてまとめます。(なお、「わかりやすい文章」ということで言えば、主語と述語はなるべく離さない方がよいです。)
つまり1も2も、主述関係や修飾関係が離れて生じる場合、「対応する述語や被修飾語が直後にはなく、より後ろ(遠く)にある」ことを読み手に注意喚起するために読点を打つ、と言えます。
また、ここで注目したいのは、「必ず主語の後に読点を打つ」ということではない、ということです。
例2‐2:午後に雨が降るので、練習は、中止です。
このように読点を打っても間違いではないですが、この場合、主語「練習は」の後の読点は不要と言えます。ここでは主述は近接しているため、あえてここに読点を打って分ける必要はありません。むしろ「練習は中止です」をひとかたまりにして、ひとまとまりの主述であることを読み手に伝えた方が親切です。
主語の後に読点を打つのは、次のような場合です。
3 長い主語の後に打つ。
例:お客の側からお店のスタッフが不当に暴言を吐かれたり暴力を振るわれたりするカスタマーハラスメントが、近年社会問題化している。
「ここからここまでが主語(主部)のひとかたまりですよ」ということを、読点を打つことで可視化します。(ただし、ここでも言えますが、「わかりやすい文章」ということで言えば、主語が長くなることは避けるべきです。)
要するに、「読点を打つとは読み手が誤読しないように『かたまり』を作ること」と言い換えることもできますね。こう考えると、読点の打ちどころには、次のようなものもあります。
4 重文の前後の節を分ける。
例1:太郎は長男で、二郎は次男だ。
例2:今日は寒かったが、明日は日中暑いらしい。
主述のかたまりごとに前後を分けるために、読点を打ちます。ここも…
例1-1:太郎は、長男で、二郎は、次男だ。
…と主述の間にまで読点を打ってしまうと、逆にかたまりがわかりにくくなり読みにくい文になってしまうので適切ではありません。
これが全てではありませんが、主だった「読点の打ちどころ」をここでは紹介しました。「かたまり」を意識して、読点を打つとわかりやすい文章になります。参考にしてみてください。
参考図書:『句読点活用辞典』第1版第2刷(1981年2月1日発行) 栄光出版社 刊 大類 雅敏 編著
なお、今回は「、」の話でしたが、「。」の話はこちらでしています。
「記事が参考になった!」と思われる方がいましたら、サポートしていただけると幸いです。いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
