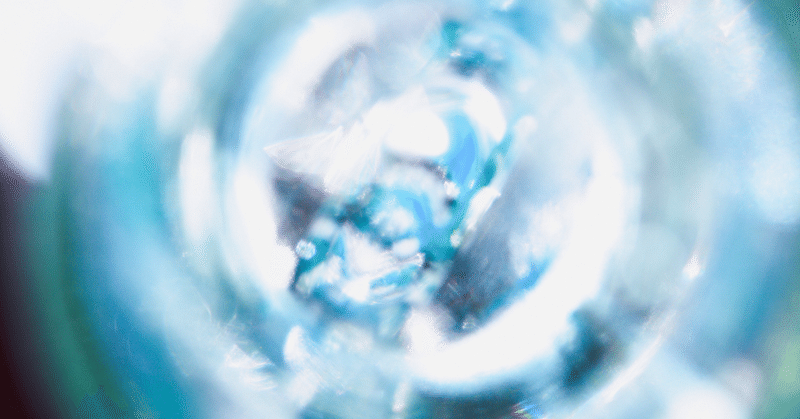
短編幻想小説『ねじれの報酬』5
Ⅴ
「ねえねえ、これなあに?」
ベッドで上腕運動をしているじいさんが、邪魔くさそうに少年を一瞥した。
「おじいちゃん、これ、なあに?」
一度目は聞こえなかったと解釈したのか、ルシアスはじいさんの顔を覗き込みながら、ご丁寧に大きな声を出した。
「うるさい、聞こえとる。お前の耄碌ジジイと一緒にするな」
「モウロクってどういう意味?」
「うるさい、バカ者。懐くな。そして触るな」
少年はじいさんの言葉に一切構わず、犬の首輪の真ん中にぶらさがった見慣れぬ透明の物体に見入った。それは下方向の矢印もしくはスペードのような形で、縁取りは少しもこもこと葉っぱに似ている。表面は8面のカットが施されており、揺れる度にきらきらと光を反射させている。ルシアスは裏面も見てみたかったが、ジャックがどうしても触れさせないため、今は眺めるだけにした。後で絶対触ってやる、と彼は神に強く誓った。
「それはね、クリスタル・ガラスっていうんだよ」とじいさんの孫娘が言った。
「クリスタル・ガラス」とルシアスが繰り返した。なんだか雪の妖精の名前みたいだな。
「きっれいーだね。きらっきらしてるね。クリスタルー」と即興の節を甲高く口ずさみながら、ルシアスは指をもぞもぞとその物体に近づけた。しかしジャックは長い鼻を突き出し、少年の動きを完全に封じ込めてしまう。正に、カンゼンに。前足を動かすまでもないという風に、悠然とした態度が憎らしい。犬のくせに……。
「それにしても、じいちゃんにも友達いたんだね。その人にお礼しなくていいの?」とMがじいさんに訊ねた。「いらん。そいつに会ったら、わしから礼をしておく。余計な心配するな」腹筋運動をしながら、じいさんががなった。
「はいはい、分かりました。良かったね、ジャック。じいちゃんのお世話してるご褒美もらえて。見ている人は見てるもんだね」
一応褒められたことを感じたのか、ジャック・ロンドンはクンと鼻を鳴らした。そしてジャックは警告をこめた眼差しで、じろりとルシアスを見た。やれやれ、ママみたいだ、と巻き毛の美少年はため息をついた。確かに「見ている人は見ている」のだと、彼が5年の長い人生で初めて悟った瞬間だった。
じいさんは腹筋運動を50回行うと、額にうっすらかいた汗を首に巻いていたコットンタオルで拭った。組立て式の簡易テーブルの上には、ルシアスが持参したホットミルクのマグカップが湯気を立て、その甘い香りがじいさんの微かな汗の匂いと混じりあった。窓の外には広大な庭が広がり、患者や見舞い客たちの談笑の余韻が、風に乗って病室の窓の隙間から入りこむ。じいさんはMに窓を閉めるように指示し、少年には「ミルクを飲んだら帰れ」と命令した。絶対君主制の暴君ばりに、不条理をつま先ギリギリに乗せてスキップをするような人間なのだ、じいさんは。
「それにしても、お前のママはまだ帰ってこんのか」とじいさんが付け足した。
「あと1時間ぐらいで、帰ってくるみたい」と、Mが少年の代わりに答えた。「それまで一緒にここにいれば良いよ。じいちゃんもルシアスのパパにはお世話になってるんだから」
「医者として当然だ。わしは患者の権利で世話になってやってるだけだ」とじいさんはふて腐れた態度で、腹筋運動を再開し始めた。じいさんのふて腐れはいつものことなので、誰も気にしなかった。じいさんは、今度は15回で運動をやめた。そして混ぜ物なしの水かどうか確認するため、孫娘が差し出したガラスコップの口に鼻を近づけてから、水をゴクゴクと飲み干した。
「さて」とじいさんが突然言葉を発した。どうやら張り切って運動をしたおかげで、少し鬱々としていた気持ちが晴れたのであろう。「ここで愚かなお前たちに、ひとつ話しをしてやろう。これはある国のある時代を生きた男の話じゃ。その男には妻子がいた。子供は双子で、男と女ひとりずつ。彼ら4人はとても幸せに暮らしておった。だがよくあることに、その男の国も、戦争をしよった。ちょうど双子が10歳の時、何回目かの戦争が始まり、働き盛りのその男は戦場に行ってしもうた。本当は誰も行きたくなかったし、行ってもらいたくもなかったんじゃが、それは我儘というもんじゃった。男は暑い日も寒い日も、同じように集められた男たちと一緒に、銃剣を抱えて歩き、眠り、歩き、眠りを繰り返した。そんなこんなで5年ばかりが過ぎよった。最初の2年は、故郷の家族からの手紙が、定期的に戦場に届けられた。戦場にいる男も、定期的に手紙を書き送っておった。しかし3年目からは国の財政事情も悪くなり、郵便も滞るようになってしもうた。それに加えて、何年も銃剣を抱えて歩き、眠り、歩き、眠りを繰り返す男には、もはや遠い国に暮らす家族の存在は幻想の産物になってきた。こんなことを言うと、その男を薄情者と思うかもしれん。だがな、年々錆つく銃剣を抱えて眠る男の周りもまた、錆つく銃剣を抱えて眠る男たちなんじゃよ。そうして5年経ち、ついに男の国とその敵の国は、戦争を止めてみることにした。詳しい理由は誰も知らなかったが、取りあえず帰れるということだけが、男たちに伝達された。男は船に乗り、電車に乗り、元の町に帰ってきた。だがそこは男の知っている町ではなかった。見たことのない人間が、見たことのない服を着て、見たことのない家に住んでいた。見たことのない料理を食べ、見たことのない飲み物を飲んでいた。男は怖くなった。男は自分の家だったはずの場所に急いで行ったが、やはりそこも見たことのない家だった。男は見たことのないその家の住人に事情を話し(幸い言葉は通じた)、一晩その家に泊めてもらうことになった。その日の真夜中、男は一睡も出来ずにいた。見たことのない町全体が寝静まり、人の気配は一切しない。男は自分ひとりが眠っていないことに不安を感じた。そしてなぜ眠れないのか考えた。そしてふと、あの錆びついた銃剣のことを思い出した。男は5年間、毎晩そいつを抱えながら眠っていたんじゃよ。男は帰郷前に若い係によってシステマティックに回収された、あの銃剣のことを想った。銃剣は毎晩、男の体温で温まり、ぐっすりと眠っておった。しかし今晩は男と同様、見知らぬ場所で、見知らぬ銃剣たちと一緒にひとりで眠っていることだろう。男はそう思うと、悲しくて仕方なかった。結局男は一睡も出来ぬまま、朝を迎えた。そして男は町を去った。見たことのない町は、見たことのない男をすぐに忘れてしまった。それ以降、男の行方は誰も知らないし、知ろうともしなかった」
じいさんがここまで話し終えると、カツカツという高い靴音が徐々に大きくなり、病室の扉がノックされた。Mが扉を開けると、頬を上気させた少年ルシアスの母親だった。
母親はMとじいさんにお礼を言い、少年に自室のベッドに戻るように即した。ルシアスは名残惜しそうにじいさんを見たが、じいさんは「ミルクを忘れるなよ」とがなっただけだった。ルシアスは仔ウサギのマグカップを掴むと、ちょびっとそれを前歯で啜りながら、母親と一緒に部屋を出ていった。話の続きが気になったが、これ以上長居は無理というものだった。
「ようやくうるさいチビが消えたわい」とじいさんが大仰に伸びをした。Mはじいさんが話を続ける気がないことを感じ、帰る用意を始めた。じいさんこそ、夕食前の睡眠の時間なのだ。Mは鞄を掛け、えび茶色の編み上げブーツの紐がしっかりと結ばれているか確認し、じいさんとジャックにお暇を告げ、扉を開けて出て行った。
じいさんがひとり(厳密には一匹もいるが)になると、隙を狙った睡魔が襲ってきた。じいさんは布団を頭まですっぽり被り、睡魔の攻撃に身を任せ、そのまま闇の世界へと旅立っていった。
ジャック・ロンドンはその様子を見守ると、そろそろと自分の小屋に戻った。彼の首もとで揺れるクリスタルは、きらきらとその輝きを誰かに主張していた。
《続く》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
