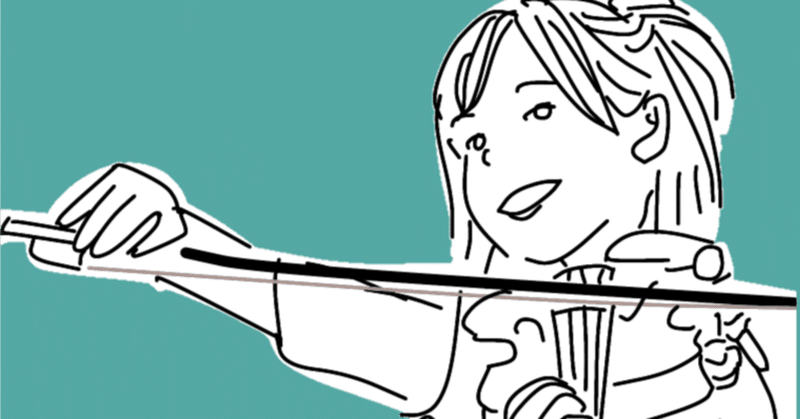
コーチの社会分析 Note【人生を輝かせる「目的」とは?・間違いだらけのキャリア教育を解説するシリーズ③】
「これからの時代を生きていく子供たちに必要とされる学びは何か?」
ということが可視化、言語化され、具体化される。ここにきちんと落とし込まれていない。説明できる人が極小数なので、今のキャリア教育ではそれぞれが、それぞれの理解で、エビデンスのない好き勝手な自己流を主張しているような状況が発生してしまっています。
という前回でした。特に子育てという経験を通じた親という存在は、その中から得た個人の「正解」やそれに類する手法、方法をついつい語りたくなります。しかし、その「正解」が普遍的な正解であるかといえば、大概はそうではない。「その親子だけに限った正解」であるということが、むしろ多いわけです。
ですので、こと「教育」というカテゴリーではよりEBPMが必要になります。【Evidence Based Policy Making(エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング)の略。エビデンス(データ・合理的根拠)に基づいた対策、企画立案を行うこと】
欧米では1990年代くらいから当たり前になっていますが、日本政府では約20年遅れた2010年頃からの導入。「その場限りのエピソード(経験や勘)に頼ってきた政策企画のあり方を改め、まずは政策目的を明確化したうえで、政策効果の測定に重要な関連を持つ情報やデータ(エビデンス)に基づいて政策形成を行う」とされていて、この基本は、これからの学びでもとても大切です。下図でわかるように、個別事例を並べて横展開とか専門家の意見を聞いてといった考え方、やり方は、EBPMでは最弱根拠に過ぎません。そんなものに命運を預けるわけにはいきませんし、ある意味で昭和の負の遺産とすら言えるでしょう。
実際、日本のどこかの地域で成功した事例や専門家の意見が日本中の他の地域やエリアで通用しなかった。必要とされる効果をあげなかった。だから、今の日本の状態があります。教育のカテゴリーでも同じように、日本のどこか、誰かの家庭で成功した方法が日本中の他の家庭で成功するはずがない・という前提をまず共有していきましょう。

☆本当の「目的」あってこその
「齋藤さん、ようやく得心しました。いままでも会社で招いてくれたキャリアコンサルの方とかいましたが、キャリアを計画したら将来がどうこうなるのではなく、私自身のライフプラン。そこからキャリアが生まれるんですね!」
先日のセッションである大手企業の方からこんなフィードバックを頂きました。50代の方で定年もカウントダウン。それこそ、これから、このあとのキャリアに直面している現在地でした。
ダン・ボンテクラフトはハーバード・ビジネス・レビューの中で「パーパス(Purpose・目的)は人生を輝かせる」とも書いていますが、輝く人生を歩むためにどんな目的を見出し、その為にどんなキャリアを歩むか。その論文でダンは3つのマインドセットに触れていて
・ジョブ・マインドセット⇒収入(お金)を意識
・キャリア・マインドセット⇒支配力、社会的地位を意識
の二つが仕事時間の意識において半分以上を占めているのであれば、人生と仕事の目的を考え直すべきだとしています。つまり3つ目の
・パーパス・マインドセット⇒職業と人生の目的意識が一致している
状態を言語化し、確認することが不可欠ということです。先のフィードバックは、僕がクライアントの「人生の目的」に対して向き合い、丁寧に言語化していったことで起こった事象と言えるでしょう。
先のキャリアコンサルの方も大企業が招いた著名な方であったでしょうが、こうした各個人の人生とは向き合えなかったのではないでしょうか。ジョブとキャリアのリソースからでも改善やベターな選択肢を示すことは出来ます。しかし、クライアントが心の奥底で望んでいることを達成する為に制限を取り払い、組織の外、より幅広い関係性といったものに目を向け、イノベーティヴかつ挑戦可能と判断しうるワクワクな「目的」。これを現実に描くことは出来なかった・ということ。
これ、最近のセッションでは本当によく起こるな・とも感じているところです。
☆パーパス(Purpose・目的)の勘違い
前記のダンと同じくジョン・コールマンはハーバード・ビジネス・レビューの中で
①パーパスは見つけるものである
②パーパスは一つしかない
③パーパスは時間がたっても変わらない
という三つのよくある誤解を指摘しています。この三つは、日本でも「意味付け(meaning)」という言葉で一時期流行しました。仕事や行動にどんな意味を見出すのか?ということですが、主体性のない会社都合、学校都合の押し付けが多く、本質からずれてしまって廃れた(当たり前ですけど、それでは結果が出ません)という最近でしょうか。
同じ仕事をしていても一人一人の動機は違いますし、違っていて良い。まあ当然です。僕は東京時代には「休日の為に」働く人だったし、それが「家族の為」である人もいるだろうし、顧客や自身の成長であっても良い。ところが、この国ではそれを変に揃えようとする人が少なからずいるので、会社や学校ではおかしなことが起こり、心を病む人がわんさか現れる結果になってしまいます。
例えば、高校という「場」が受験を唯一絶対の目的とするような圧力を持つならば、それ以外の勉強や活動に情熱を注ぐ生徒を否定し、テストで成績の取れない生徒を切り捨てていくメッセージにもなります。そんな「場」があってよいわけがないのですが、テストによる教師の絶対評価という実際においては、これに近い状態が通常モード。それもまた今の一面です。
☆パーパス(Purpose・目的)を与える力
ジョンはこれらの誤解の生じる理由として、正解となる目的がどこかに隠れていて、探すことで見つかるように考えているとし、その考え方(マインドセット)そのものが誤りと明確に触れています。
そして、私達はやること全てに「目的」を与えることが出来る・としていて、僕はこの箇所を「目的を言語化することが出来る」とも読み替えています。それは、私達の脳中枢が「なんとなく」感じたことを行動に移し、やっているうちに前頭葉が理解し、可視化、言語化できるというプロセスがあるからでもあります。
この「なんとなく」の行動をやっていて「あ!」と気づいたときに脳機能(VTA)の働きでドーパミンが出ます。そして、この神経回路構造をコツコツと発達させてきた人は、心の底からやりたいことをワクワクとやり抜く習慣を得ます。理論や理屈で無理やり信じ込ませた本当はやりたくないことを人がやり抜くのはとても難しいのですけれど、こちらの機能を使っている人はやれるし、やっている本人も幸せになりやすいわけです。
*というあたり長さも考慮し次回に。キャリア教育においては、こうしたその人自身の奥深い部分にタッチすること。それが不可欠なことだということが見えてきたのではないかと思います。
ありがとうございます。頂きましたサポートは、この地域の10代、20代への未来投資をしていく一助として使わせて頂きます。良かったら、この街にもいつか遊びに来てください。
