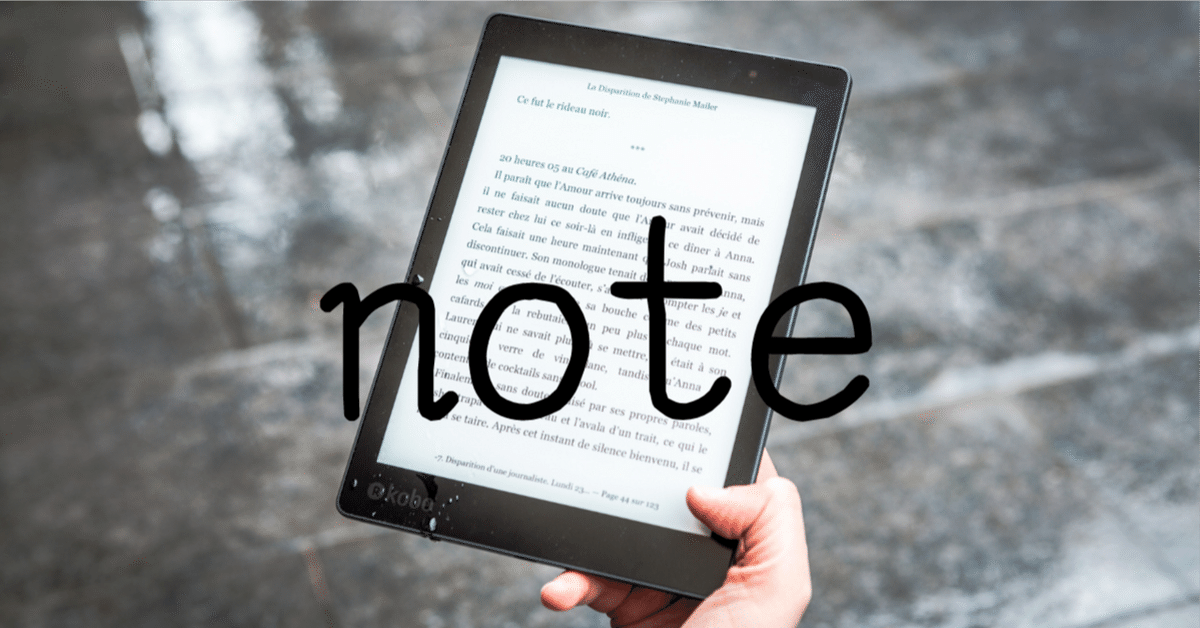
ついつい買ってしまうkindleのキャンペーン。
一言一句、暗記するようにじっくりと読み進めるようなスタイルを止めてから、目を通せる本の数が増えてきました。読んでいる内容を自分の言葉で表現し、分かりやすく伝えることで、はじめて確かなインプットになると言いますよね。noteでそこを出来るのがベターだと思っていますが、まずは普段の仕事で抱いている疑問や不明を解決する手段、ヒント探しとして読んでいます。
8月はお盆休みもありましたので、何冊か読みました。
(※以下に挙げている本は僕の手元にあったものを読んだということで、タイトルにあるkindleのキャンペーンに該当する本とは限りません)
500ページ以上ある、ぶ厚めの本です。阪急グループや宝塚歌劇団、東宝の創設者である小林一三という人物について、詳しく書かれています。
僕がこの本を手に取ったのは随分と前でして、新1万円札に渋沢栄一が選ばれたというニュースからしばらく経ったくらいの時だったかと思います。「関西にも渋沢栄一のような人物がいたのかな?」とニュースを見て疑問に思い、調べてみた中で出てきたのが、小林一三でした。
阪急電車は僕も関西人としてよく乗っているので、こんな人が関西の発展に尽力したんだな~と思いながら読みました。
仕事柄、提案のコンセプトを考える機会が多々あります。ただこんなことが僕たちは出来ますと主張しても、自分のとこ以外にも対応できる会社さんはたくさんいますし、そうなると価格勝負で安価な会社さんが選ばれる確率が高くなります。
勝率を少しでも上げるためには、コンセプトを明確にして相手とイメージを共有すること。そのイメージが相手に具体的なアフターとして映り、僕たちのところに投資する価値があると思ってもらえることが大事では?と思い、この本を手に取りました。
コンセプトは言葉の存在感が大きいですが、自分だけが気持ちよくなるような言葉の選び方や向き合い方をしないよう気を付けないとなと思いました。
自分の説明を振り返ると、「これまだ抽象的だなあ・・・」と感じることがあります。自分の中で明快になっていないと、説明って長くあやふやで断言で終わらないですよね。
この本を読んで感じたことは、「手段は既に知っているけど、身に着いてない」ということでした。精進します。
落合陽一の本はこれまで読んだことがありませんでした。この本が初めてになります。本人が紹介されている読む本の順番に沿ってはいませんが、ここ最近感じていることに「やっぱそうだよね」という同調を得たいという欲求が、購入のきっかけでした。世間に対して文句があるなら、SNSで愚痴る・批判する時間を減らし、それを解消するためのイノベーションを起こすための発明や制度の開発とかに時間を割いた方が、有意義だなと感じました。
この本も仕事柄、情報を得たくて購入しました。記載されている内容は結局Webで検索したら出てくるものに留まりますが、こうした情報が少しずつ浸透し、各企業が手段だけでなく本質(自分たちの会社は社会に何が提供できるのか。何を社会へ提供するために会社として存在しているのか)とも向き合うことの重要さに気付くこと。本質から目を背けず利己的な稼ぎ方ばかり考えず、一攫千金を狙わず中長期視点で着実にビジネスを育てていく意志と思考を持たないと、デジタルを活用した施策は大半が実を結ばず失敗に終わるよね。と感じました。
こんな感じで、普段の業務知識を補完するような形で本を読み進めています。
9/7(木)までAmazonのkindle本 ビジネス書が最大50%OFFのキャンペーンをしているので、また新たに数冊買ってしまいました。どれも面白そうなので、早く読んで自分の知識として身に着けていきたいです。
