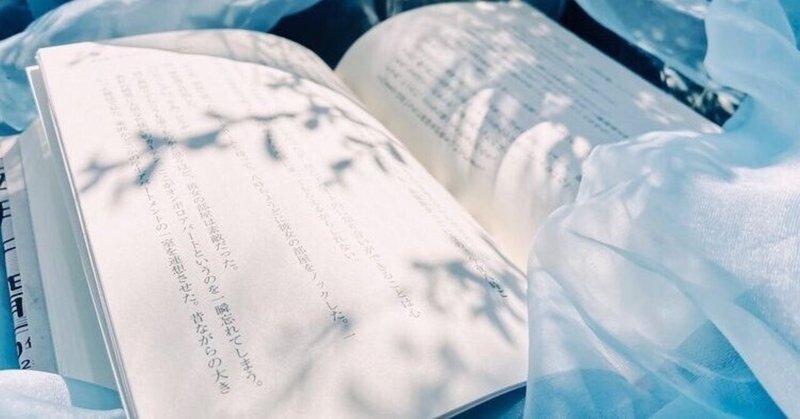
32歳の男が今まで読んだ本から100冊を選別してみる。
なにかを選ぶ作業をしたかった。
「1万時間の法則」というものがある。「1つの分野でプロレベルになるためにはおよそ1万時間の練習を必要とする」とのこと。
学生の頃、小説家は「1万冊の本を読めばプロレベル」になると聞いた。
僕はまだ1万冊の本を読めていない。
ただ、1万冊を読み切るための途上にはいる。長い山頂への道を歩いている中で、ふと立ち止まって後ろを振り返って自分が進んできた道を見る。
そういう作業を今回してみたいと思い、今まで読んできた本の中で特に印象に残った100冊を選んだ。
最近の僕は小説やエッセイをコンスタントに書けていない。
生活の変化もあるし、読む時期だと色んな文章を読んでいるというのもある。
けれど、僕は何かを書く人でありたい。
今回の100冊を選ぶ作業はスランプに陥った人が、今までの自分を振り返る作業にも近いものがあるかも知れない。
僕がこの先、あらゆる文章を書いていく中で「あいつ、こんな本読んでいれば、そりゃあこういうの書くよな」と思ってもらえるようなリストになれば嬉しい。
同時に、これは僕自身も見返しては、自分でそりゃあこうなるか、と納得するためのリストでもある。
これはとても個人的な作業ではあるのだけれど、32歳の小説好きの男(一般的とは言い難いかも知れないけれど)はこんな小説や評論に触れて影響を受けて生きてきたんだな、と受け止めていただければと思う。
それが、どれだけの人の参考になるのかは分からないけれど。
ちなみに順番にはとくに理由はありませんので、悪しからず。
1~10
・「ノルウェイの森」村上春樹
・「ダンス・ダンス・ダンス」村上春樹
・「ねじまき鳥クロニクル」村上春樹
・「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」村上春樹
本を読むようになったきっかけが村上春樹なので、外せなかった。最初に長編小説を四作。
個人的に長編小説はゆっくり日常の隙間で読んでいくのだけれど、村上春樹の長編は旅行に似ている。旅行は終わりが近づくと名残惜しくなるように、村上春樹にはそういう力がある。
個人的に一番読んだのは「ノルウェイの森」で、内容はもちろんだけれど、直子と緑という二人の女の子の対比が魅力だった。「ダンス・ダンス・ダンス」はユミヨシさん、五反田君。村上春樹に登場する人物はみんな魅力的だ。
「ねじまき鳥クロニクル」と「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」は少し込み入っていて、提示される謎との距離感が好みで選んだ。
・「象の消滅 短篇選集 1980-1991」村上春樹
・「神の子どもたちはみな踊る」村上春樹
こちらは短編集を二作。
村上春樹がインタビューで答えているのだけれど、「短編小説というのは「うまくて当たり前」の世界」と言うように、彼の短編はうまい。とくに「象の消滅 短篇選集 1980-1991」は冴えわたった何かがある。
「神の子どもたちはみな踊る」は高校生の頃に読んだ。再読する度に学校へいく電車の中を思い出す。
・「若い読者のための短編小説案内」村上春樹
・「走ることについて語るときに僕の語ること」村上春樹
・「村上春樹 雑文集」村上春樹
・「職業としての小説家」村上春樹
村上春樹の書く文章はだいたい好き。ただ、エッセイよりは何かしらの大きなテーマに沿って書かれた内容の方が好み。「若い読者のための短編小説案内」はとくに強い影響を受けた。このリストに「第三の新人」が多く入っているのは、この本のせい。
「村上春樹 雑文集」は大きなテーマが定められているわけではないけれど、単行本の後ろに「すべての細部に村上春樹は宿る。」と書かれているように、雑文の細部が好きで選んだ。
11~20
・「Carver's Dozen レイモンド・カーヴァー傑作選」レイモンド・カーヴァー
・「ティファニーで朝食を」トルーマン・カポーティ
・「キャッチャー・イン・ザ・ライ」J・D・サリンジャー
村上春樹翻訳の三冊。
翻訳文体が若いころは苦手で、あまり手に付けられずにいたのだが、村上春樹の翻訳本で読み方(というかリズム?)を身につけたような気がする。
「Carver's Dozen レイモンド・カーヴァー傑作選」は本当に、うますぎる短編が贅沢に並べられていて「傑作選」の名に偽りはない。
「サマー・スティールヘッド(夏にじます)」「足もとに流れる深い川」「ささやかだけれど、役にたつこと」の三篇はとくにいい。
・「ムーン・パレス」ポール・オースター
村上春樹の仕事を追っていると、柴田元幸の名前にいきつく。また、それとは別にポール・オースターの名前も本好きで色々読んでいくと、ぶつかる。学生の頃は、ポール・オースターを読んでいると、なんか格好いい。そんな空気があった気がする。
「ムーン・パレス」は若さ100パーセントみたいな内容で、苦い。若いってことは不完全ってことだから、そりゃあそうなんだよな、と。
・「存在の耐えられない軽さ」ミラン・クンデラ
まず、タイトルに惹かれた。
クンデラは長編小説の人だと勝手に思っているのだけれど、「存在の耐えられない軽さ」は後半で少し時系列をいじっていて、そこが長編小説ならではな感じがあって非常にいい。あと、犬のカレーニンも。
・「赤頭巾ちゃん気をつけて」庄司薫
・「白鳥の歌なんか聞えない」庄司薫
・「さよなら快傑黒頭巾」庄司薫
・「ぼくの大好きな青髭」庄司薫
庄司薫の「薫くんシリーズ」は二〇一二年に新潮社から出版されたバージョンで読んだ。当時の僕は二十歳超えたくらい。一冊読み終える度に、アルバイト先の近くにあった小さな本屋で続きを買った思い出がある。
青春のままならない色んなことを薫くんに重ねて読んでいた。あの頃に読めてよかった。
個人的に一番読んだのは「赤頭巾ちゃん気をつけて」だけど、凄みを感じるのは「ぼくの大好きな青髭」。
若いうちに読んでおいてよかったのは「白鳥の歌なんか聞えない」。好きな子に告白されても、ちゃんと警戒しようと思ったりもした(そんな警戒は僕の人生には必要なかったけれど)。
・「女の子を殺さないために 解読「濃縮還元100パーセントの恋愛小説」」川田宇一郎
ラブコメや恋愛小説のメカニズムを解き明かす一冊。
こちらも二〇一二年くらいに読んで、影響を受けた。読み返しすぎて、少し傷んでる。
川田宇一郎はもう本を書かれないのかも知れないけれど、今の「恋愛」を扱ったエンタメを彼はどう見ているのか、興味はある。
21~30
・「砂の上の植物群」吉行淳之介
・「暗室」吉行淳之介
・「夕暮まで」吉行淳之介
最近、「男流文学論」上野千鶴子 、富岡多恵子、 小倉千加子を手に取ってみたところ、吉行淳之介のディスから話題が始まり、それが作品外の著者のイメージによる内容で、著者と作品は別では? となった。
ある世代からは非常に嫌われている作家らしいけれど、個人的には好き。著者がではなく、作品が。
技巧的と本人も何かで言っていた気がするけれど、吉行文体みたいなものが確立されていると思う。真似できないかと思って、「驟雨」を模写したこともある(無理だった)。
短編も良いんだけど、今回は長編を三つ。ちょっと前にネットで見つけた「夕暮まで」の評論(三上桜という方の)は新しい発見のある良い内容だった。
・「海辺の光景」安岡章太郎
・「プールサイド小景・静物」庄野潤三
・「抱擁家族」小島信夫
・「成熟と喪失: "母"の崩壊」江藤淳
第三の新人は村上春樹も触れていたけれど、江藤淳の「成熟と喪失」が結局一番有名なのかな、と思ったりする。実際、一読の価値ある内容。
個人的に日常的なものを書くとされた第三の新人が「海辺の光景」や「抱擁家族」を書くってことに繋がっていくことに興味がある。
あと、庄野潤三の「静物」の家族が主題になっている作品には目を背けてはいけないものがあるな、と思っている。
・「幼児狩り・蟹」河野多惠子
・「秘事・半所有者」河野多惠子
河野多惠子の初期の短編が非常に上手くて好き。女性の醜い部分とか、強かな部分をごまかさずに書いている印象。
晩年になっての「秘事」は傑作すぎる。別れそうな夫婦が読むと、もう少し頑張ろうと思える一冊だと山田詠美が言っていたけれど、確かにと思う。
・「むかし女がいた」大庭みな子
大庭みな子は童話的な想像力を根底に作品を書かれていた作家というイメージなのだけれど、その童話的なものとデビュー作の「三匹の蟹」の現実的なものが上手くブレンドされたのが「むかし女がいた」だと勝手に思っている。
コオロギの話が個人的に好き。残酷で。
31~40
・「忍ぶ川」三浦哲郎
・「拳銃と十五の短篇」三浦哲郎
三浦哲郎は私小説作家であり、短編小説の名手でもあった。彼の兄妹のほとんどが失踪か自殺をしており、自分もいつかそうなるんじゃないか、という怯えから子供を作るか悩む作品(本棚を探したがなかったためタイトル不明)など書いている。
そのため、彼が自殺ではなく、病院で死去したと知った時はそれだけで泣けてしまった。彼が背負わされた運命にちゃんと勝ったんだな、と。
・「たった一人の反乱」丸谷才一
結婚は「欠けた茶碗」だと言っているシーンがあって、出版されたのが一九七二年で、当時にそう思われていた「結婚」は今どうなのかを考える。
タイトルとは反して、日常的な小説で一つの時代の移り変わりを描いている印象がある。
・「コインロッカー・ベイビーズ」村上龍
やたらに格好いい小説。村上龍の文体は美しく格好いい。
新装版で読んだ。解説は金原ひとみで、これもよかった。
・「朝の歓び」宮本輝
・「胸の香り」宮本輝
宮本輝は名作の多い作家だけれど、個人的に好きな二作を。「朝の歓び」はとくに夢中になって読んだ。兄弟が再会するシーンは仕事の休憩中に読んで泣いた。
・「泳ぐのに、安全でも適切でもありません」江國香織
・「号泣する準備はできていた」江國香織
・「献灯使」多和田葉子
江國香織の言葉選びが好みなのだけれど、この二作のタイトルはしびれるくらい好き。二作とも短編集で結局僕は短編が好きなのかも知れない。
今回入れなかったが、「いくつもの週末」という旦那さんとのエッセイは、同棲をはじめて再読し、より楽しめた。江國香織は年齢を重ねるごとに面白さが変わる作家の一人かも知れない。
「献灯使」は3.11を考えると外せなかった一冊。
こちらも年齢を重ねて読むとまた違った世界を見せてくれそう。
・「文学問答」山田詠美・河野多惠子
世代の違う人たちの対談はアンバランスになることもあるけれど、山田詠美と河野多惠子のやり取りはバランスの取れた意味ある内容になっていた。
個人的に山田詠美の対談集も好きなのだけれど、今回はリストに入れられず。
41~50
・「デクリネゾン」金原ひとみ
思考している小説が好きだ。「デクリネゾン」は常に何かについて考えていて、答えのようなものを見つけ出そうとしている。こういう小説は答えを見つけられなくても良い。そのプロセスに意味がある。
・「臣女」吉村萬壱
人間は人間の範囲を超えたことはできない。「臣女」は奥さんが巨大化していく、という突拍子もない設定だけれど、それを囲むすべてにリアリティがあるために迫ってくる緊迫感は本物だった。
島清恋愛文学賞を受賞していて、確かにこれは「恋愛文学賞」をとるべき一作だったと思う。
・「ダーティ・ワーク」絲山秋子
ローリング・ストーンズの曲名が各篇のタイトルになっていて、音楽と小説の組み合わせの中でもとくに好きな作品。
格好よくて、解説で佐々木敦が「泣ける純文学」と称するように、感動的な終わりも見せてくれる。
・「オーデュボンの祈り」伊坂幸太郎
・「魔王」伊坂幸太郎
・「砂漠」伊坂幸太郎
・「モダンタイムス」伊坂幸太郎
・「PK」伊坂幸太郎
伊坂幸太郎は選ぶのが難しかった。
現在、30代の小説好きは基本的に伊坂幸太郎を通ってきたのではないかと思う。好き嫌いはあるにせよ。
映画化された作品も素晴らしいのが多いけれど、今回は外してみた。最初に読んだのは「魔王」で、当時の僕は高校生だった。タイトルから、もっと派手な小説を想像していたのだけれど地味で、しかしそれこそが小説にできる力なんだと思った。
映像作品ではできない地味さ、それゆえに切実な物語。
そういう点で「砂漠」と「PK」を。「PK」は最後に世界を救ってしまうけれど、それもまぁ地味な方法なので。
「オーデュボンの祈り」と「モダンタイムス」はスケールの大きな話でありつつ、しっかり終わるデビュー作(オーデュボンの祈り)と、絶対に綺麗に終わらせねぇぞ、と決めた時期の総決算(モダンタイムス)を選んでみた。
・「六つの星星 対談集」川上未映子
・「春のこわいもの」川上未映子
川上未映子は文学界隈の何かを確かに引き継いでいる作家の一人だと思う。そういう重圧みたいなものをちゃんと作品に落とし込んでいる感じを「春のこわいもの」には感じた。
「あなたの鼻がもう少し高ければ」と「娘について」は息苦しいくらい辛いのに、目を離せない引力があった。
51~60
・「動物化するポストモダン――オタクから見た日本社会」東浩紀
・「ゲーム的リアリズムの誕生――動物化するポストモダン2」東浩紀
・「クォンタム・ファミリーズ」東浩紀
東浩紀は何を選べばいいのか分からず、初期の方を三つ。
「クォンタム・ファミリーズ」は一度挫折し、徳島へ旅行に行った際に再度買い直して、帰り道に読んだらすいすい読めた思い出。
東浩紀の仕事が社会に今後どこまでの影響力を持つのか。注視している。
・「シンセミア」阿部和重
・「ピストルズ」阿部和重
・「オーガ(ニ)ズム」阿部和重
阿部和重の『神町サーガ』みたいな小説を書きたい。多分、それが僕の根本のところにある。見上げた夜空で最も強く光っている星。その光に近づきたくて進んでいる。
・「キャプテンサンダーボルト」伊坂幸太郎・阿部和重
好きな作家の二人の合作。こんなの読まないわけにはいかない。
伊坂幸太郎と阿部和重がいかに映画が好きか、というのが分かる最高のエンタメ小説だった。
・「ニッポンの思想」佐々木敦
・「ニッポンの音楽」佐々木敦
佐々木敦は「未知との遭遇」を入れるかめちゃくちゃ迷ったけれど、「思想」と「音楽」の移り変わりを的確に捉えた二冊を。
「ニッポンの思想」を読んでから東浩紀を読まねばと思ったような記憶がある。
・「図書館の魔女」高田大介
メフィスト賞は「一作家一ジャンル」と言われている新人賞で、その名に恥じない大型新人として高田大介はいる。
ファンタジー小説をあまり読まないし、今回のリストは唯一ではあるけれど、これが傑作であることは分かる。
61~70
・「蘆屋家の崩壊」津原泰水
・「たまさか人形堂ものがたり」津原泰水
あらゆるジャンル小説を書きながら、「すべて広義の幻想小説である」との発言は非常に納得のいくものだった。
津原泰水にしか書けない世界。それがどの小説を読んでも分かる。個人的に「たまさか人形堂ものがたり」 の視点人物、澪のような女性の描き方が好み。
・「九十九十九」舞城王太郎
・「ディスコ探偵水曜日」舞城王太郎
・「キミトピア」舞城王太郎
・「獣の樹」舞城王太郎
・「淵の王」舞城王太郎
舞城王太郎も選ぶのが難しかった。文芸誌に彼の名前が載る度に買うほどハマっていた時期があり、まだ単行本化されていない作品も含めて基本的に全部好き。
その中で、あえてデビュー作は外して長く難解な「九十九十九」と「ディスコ探偵水曜日」を選んだ。短編も好きなのだけれど、今回は「キミトピア」のみ。収録作品として芥川賞候補になった「美味しいシャワーヘッド」も好きだが、「やさしナリン」がとくに好み。
舞城王太郎の長編は途中から精神世界にいってしまうのだが、「獣の樹」と「淵の王」は比較的終盤まで現実世界で持ちこたえている。「獣の樹」は蛇が世界に宣戦布告してしまったりするけど。
・「銃」中村文則
・「掏摸〈スリ〉」中村文則
学校の先生に勧められて「掏摸〈スリ〉」を読んだ。その頃はまだ文芸誌に載っていて単行本は出ていなかった。
それまで村上春樹は読んでいたけれど、純文学というものを全く意識していなかったので衝撃は大きかった。僕にとって純文学と聞くと、まず中村文則が浮かぶ。
ドストエフスキーにカフカに太宰治。そういう作家に影響を受けた作品群。
ハマりすぎて、おそらく僕が最もサイン本を持った作家でもある。
・「おばちゃんたちのいるところ - Where the Wild Ladies Are」松田青子
この短編集の最後から二番目に姫路が舞台の一編がある。姫路モノレールなるすでに廃止されたモノレールの橋脚の傍で雑貨店を営んでいる女性の話。
僕はその一編が好きで、その話をしたら姫路モノレールの展示がされている博物館に連れて行ってくれたのが、今の恋人。
そして、僕は今姫路に住んでいる。モノレールの橋脚の傍にある雑感店をたまに探すけれど、まだ見つかっていない。
71~80
・「敗戦後論」加藤典洋
政治と文学をつなぐ評論。
ちゃんと十全に理解できているかと言われると難しいが、加藤典洋は30代も半ばへ向かう今、読むべき評論家だよなと最近とくに思う。
・「新映画論 ポストシネマ」渡邉大輔
・「新写真論 スマホと顔」大山顕
東浩紀が作った会社ゲンロンから出版された二冊。
令和という時代を評論の言葉で語るとしたときに、ゲンロンから出版されたいくつかの本は無視できないのではないか、と思う。少なくとも僕は今後、映画について語るときに「新映画論」は念頭に置く。
大山顕の「新写真論」も非常に面白く読んだため、今群像で書いている内容が単行本化されるのを待っている。
・「渋沢栄一 I 算盤篇、II 論語篇」鹿島茂
渋沢栄一が紙幣になるということで、読んでおこうと思い手に取った。評伝という形式の本を読むこと自体、ほぼ初めてだったが、鹿島茂がフランス文学の研究者ということもあって、日本側とフランス側の事情を分かりやすく解説してくれているため、面白く読んだ。
・「哲学の門前」吉川浩満
最近の僕の指南本。
日常生活の中でいかに哲学を使ってきたか、ということが書かれている本で、この中で加藤典洋も出てくる。彼とカフカの言葉を組み合わせた「君と世界の戦いでは、世界に支援せよ。なぜなら、きみは悪から善をつくるべきだ、それ以外に方法がないのだから」は、僕の深いところに突き刺さったまま、いまだ抜けずにいる。
・「書きあぐねている人のための小説入門」保坂和志
・「ニッポンの小説: 百年の孤独」高橋源一郎
小説を書く、ということについて考える時、この二人は外せないところにいた。少なくとも平成の世で小説を書こうとした二十代の頃には。
令和の今、この二人はどのような評価になっているのかは分からない。けれど、僕自身は強い影響を受けたのは間違いない。
・「謎とき村上春樹」石原千秋
石原千秋の名前を最近、見かけない。テクスト論で小説を読む時代は終わったんだ的なことをツイッターでおっしゃっている小説家の方がいた。
終わったのだろうか。分からないけれど、「謎とき村上春樹」は面白い。それは間違いない。少々、無理筋な部分はあるにせよ。
・「「おたく」の精神史 一九八〇年代論」大塚英志
80年代って僕にとって生まれていない何も知らない時代って感じだけれど、僕の好きなサブカルチャーの芽吹きの時代と捉えると非常に興味深い時代だったんだなと思う。
・「関係する女 所有する男」斎藤環
男女論がSNSで盛んに交わされているのを見かける度に、「関係する女 所有する男」を引用して誰か何か言っていないかな、と探すけれど、誰も言っていない。みんな、私/俺の知っている、体験したことを語っている。
そういう自分の周りのことだけじゃない話をするために本を読むべきなんじゃないか、と少し思ったりする。
81~90
・「ゲームの王国」小川哲
上巻と下巻で評価が分かれていると読んだ後に知ったけれど、どっちも最高だろう、と。上巻のままいかれるとしんどいし、下巻の感じを最初からやられると現実感がなくなってしまう。
そういう点で、絶妙なバランスで立っている作品という感じがする。
・「QJKJQ」佐藤究
・「Ank: a mirroring ape」佐藤究
佐藤究はすごい一瞬を描くために、ちゃんと積み木を重ねていく。この、すごい一瞬は現実では絶対に起こらないもので、小説でしか見ることができない。
そういうものをちゃんと描写している佐藤究は優れた作家と言う他なんと言えばいいか分からない。
・「朝が来るまでそばにいる」彩瀬まる
短編集なのだけれど、全編名作。個人的に「明滅」という夫婦の話が一番好き。「真っ暗な、なんの救いもない場所に連れて行かれたら」の問いに対して妻が完璧な回答をする。
愛情とは、こいう形をしているんだ、とすとんと心に落ちてきた一編。
・「サクラダリセットシリーズ」河野裕
・「「階段島」シリーズ」河野裕
・「イリヤの空、UFOの夏」秋山瑞人
このリストの中にライトノベル作品を選んでおきたかった。
「「階段島」シリーズ」はライト文芸だけれど、涼宮ハルヒなんかのライトノベルを踏まえた内容もあって選んだ。
河野裕はゲームと物語を混ぜるのが非常に上手い作家で、シリーズを通して一つのゲームの説明と終わらせる手腕には脱帽する。
「イリヤの空、UFOの夏」は高校二年生の夏休みに読んだ。カッターナイフで自分の首筋に埋め込まれた虫を抉り出すシーンを深夜のベッドで読んだのはいまだに忘れられない。
・「『円紫さん』シリーズ」北村薫
・「さよなら妖精」米澤穂信
ミステリー小説のジャンルとして「日常の謎」というがあって、僕はそれが好きだ。代表作としての「『円紫さん』シリーズ」は熱中して読んだ。
米澤穂信の代表作は「〈古典部〉シリーズ」か「〈小市民〉シリーズ」になるかと思うけれど、「さよなら妖精」を無視できなかった。若者の自意識過剰というか、頑張れば頑張るほどドツボにハマる苦しさ。
30歳を超えた今、その苦しさは今なお迫ってくるものだと分かる。
・「パレード」吉田修一
二十一歳くらいの頃に読んで衝撃だった。小説というジャンルはこんなに怖いものを作れてしまうのか、と旋律した。
「たとえばこの世界に、もう一つ東京があったとしたら」
そんなものはない。我々は一つしかない人生を歩むしかないけれど、思わずにはいられない。「たとえばこの世界に、もう一つ東京があったとしたら」
91~100
・「幸福な食卓」瀬尾まいこ
なんて魅力的な一文から始まれるのだろうか。
「父さんは今日で父さんを辞めようと思う」
どうしてと疑問に思う。と同時に、「父」という役割は辞めていいものなのかも知れない。そんな可能性について考えはじめる。
・「路傍」東山彰良
・「奇蹟のようなこと」藤沢周
・「夕子ちゃんの近道」長嶋有
まったく共通点のない三作だけれど、すべて連作短編の形式を持っている。僕はこの形式が好きで、一編一編が緩く繋がっていくのも読んでいて気持ちいい。
書く側に回って思うことは、しかし、その繋がっていく構成は非常に難しいということ。技術があって初めて成立する構成であり、選んだ三作はとびっきり上手い。
・「ショート・サーキット」佐伯一麦
働くこと、恋愛して家族を作ること。そのすべてが背伸びすることなく描かれているのが、佐伯一麦の作品群だと思っている。
私小説という形式が僕は好きだし、この先も残ってほしいと思うけれど、令和版の佐伯一麦はちょっと想像が難しい。
・「情事の終り」グレアム・グリーン
新訳で読んだので、昔に読んだ方と印象を一致できるか分からないけれど、好きな小説だった。良きものを与えてくれたはずの神様という存在が、呪いになってしまう物語。
宗教的でもあり、十全に理解できているとも言い難いけれど、男と女の話であるために分かると思わされてしまうのが上手い。
・「悲しみよ こんにちは」フランソワーズ・サガン
このタイトルにした時点でサガンは勝ったよな、と思う。
少女が大人になる途上を、この小説は確かに書ききっているんだろう。
・「終わりの感覚」ジュリアン・バーンズ
若いころに受けた傷は老人になっても忘れられるものではない。けれど、傷つけた方はすっかり忘れてしまう。
現実ってそういうものと言えば、そうだよなと。
年を重ねていく中でテーマになっていくのは、記憶なんだろうとも思った一作。
・「紙の動物園」ケン・リュウ
SF短編集でどれも面白かった。SF作品は常に社会と接続されていて、どんなに荒唐無稽に思えても、現実の社会の写し鏡になっているような部分がある。
「愛のアルゴリズム」が個人的に好み。
・「書店主フィクリーのものがたり」ガブリエル・ゼヴィン
ラスト!
350ページ弱の作品だけれど、確かにこれは「フィクリーのものがたり」で、つまり人生だったんだと納得する作品だった。
登場人物の一人に、あるいは、一つのエピソードに固執すれば、分量は倍に伸びていただろうに、この小説は文庫本一冊にまとまるバランスで完成されている。
「書店主」とあるように、書店の話で本が好きな人は気に入ること間違いない。とくに本に興味がいない警官のランビアースを最後まで読んだら、みんな好きになる。
「本屋のない町なんて、町にあらずだぜ、イジー」
本当にその通りだよ!
サポートいただけたら、夢かな?と思うくらい嬉しいです。
