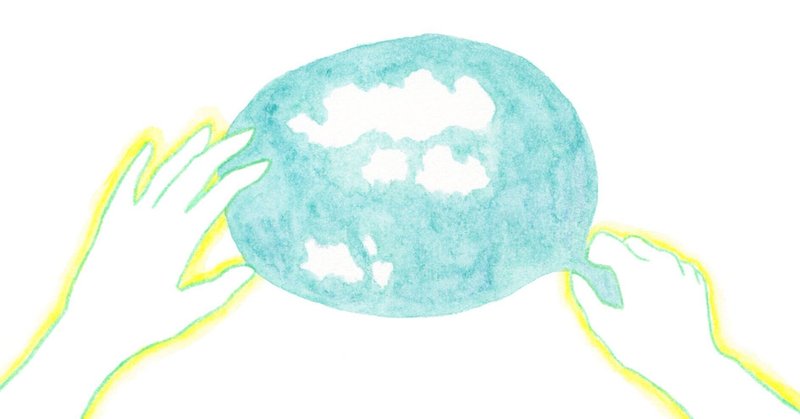
〈ファンタジー小説〉空のあたり3
3.欲求
「いらっしゃいませー」
マスターの声がする。
目を開くと、天井のベージュ色が見えた。
そうだ。昨日はここに泊まっていったんだっけ。
お店の方で、マスターとお客さんがしゃべっている。
ぼくはしばらく布団の中にじっとしていた。
お客さんが帰ったと思った頃、ぼくは、ようやく起き出した。布を畳もうとしたけれど、あまりにでかくて苦労した。手をめいっぱいのばしても、両端をつかめないから、ぼくは布を床に広げて、折りたたんだ。
カウンターへ行くと、マスターがグラスを拭いていた。
ぼくはさすがにお腹が空いていた。
「あの、マスター、ここって、飲み物以外に、メニューはないんですよね」
「モーニングなら、お作りできます」
「あ、じゃあ、お願いします」
「かしこまりました。お飲み物は、なんにいたしますか」
ぼくは、朝はコーヒーも紅茶もミルクも飲めなかったので、「お水でお願いします」と言った。
お水が、目の前に置かれた。
このお店で、お水を飲むのは初めてだった。一口飲んだだけで、おいしいと分かった。下手したら、昨日の飲み物よりも、おいしいかもしれない。
マスターが作ってくれたモーニングは、今まで食べた食事の中で、一番おいしかった。フレンチトーストだった。ふわふわで、しゅわしゅわで、口の中でとろけた。
「ごちそうさまでした」と言った瞬間、ぼくはまた、青ざめた。空のかけらを持っていないのだ。
「あ、すみません。ぼく、空のかけらを持っていないんでした」
ぼくは、モーニングをおいしく食べてしまったことを、後悔した。けれども、大丈夫だった。
「90円です」と、マスターが言ったからだった。
こっちは、普通のお金でいいんだ。それにしても、格安だ。
「まだ水は引けてないですね」
窓の外を見ながら、ぼくは言った。
ぼくは、水が引けるまで、ここにいることにした。職場に電話をかけなければならない。携帯の充電が、あと少ししか、残っていなかった。
電話はかけられたけど、休む理由を言うのに困った。部長は、まだ出勤していなかった。
「水が引けないので、もしかしたらしばらく休むかもしれません」と言うと、「そうですか。では伝えておきます」という返事が来ただけだった。
電話を切ると、マスターは、あいかわらずグラスを拭いていた。
ぼくは手持ち無沙汰になって、マスターに尋ねた。
「あの、空のかけらって、どうやったら手に入るんでしょうか?」
マスターは、ちょっと考えてから言った。
「空のかけらは、ある一定の条件を満たせば、誰でも手に入れることができます。いくらでも」
「え、そうなんですか? いくらでも手に入れられるなら、お金のかわりにならないじゃないですか」
「空のかけらは、お金ではありませんからね」
「じゃあ、空のかけらって、一体なんなんですか」
「材料です」
昨日も同じことを聞いたような気がする。
あの飲み物は、詩と空のかけらで、できているのだ。
ぼくは、空のかけらが欲しくなった。それも、たくさん。だって、たくさん持っていれば、いつでも、飲み物を飲むことができる。
「あの、空のかけらを手に入れる条件って、なんですか」
「それは、その条件にあてはまると、分かります」
「じゃあ、ぼくはまだその条件を満たしてないんですね。だって、分からないもの」
「そういうことになりますね」
「その他に、空のかけらを手に入れる方法は、ないんでしょうか?」
「そうですね……」マスターが言いかけた時、カランコロンと音がなり、お客さんが入ってきた。
「いらっしゃいませー」
「いつもの」
「はいよ」
マスターは、飲み物を作りに行ってしまった。
マスターの様子からすると、何か別の方法がありそうだった。ぼくはマスターが戻ってくるのを待った。
「はい。お待たせしました」
今まで見たお客さんの中では、一番若そうだった。マスターが、さっきの話のつづきをしてくれないだろうかと、ぼくはちょっと期待して待った。けれど、そんな様子はまったくない。もしかしたらマスターは、ぼくに教えたくないのかもしれない。
だめもとで、もう一度、聞いてみようか。
「マスター、さっきの話なんですけど、条件を満たさなくても、空のかけらを手に入れる方法って、あるんでしょうか」
「はい。ありますよ」
「あるんですか?」
「はい。裏技があります」
「それを、教えてください!」
案外簡単に教えてくれた。
「それは、現実を反対の面から見ることです」
「現実を、反対から見る……?」
あっさり教えてくれたのは良いが、意味がよく分からない。
「例えば、今まで見て来た現実が、表側から見た現実だったとします。それを、裏側から見るということですね」
「はぁ、そうなんですね」
そうなんですねと言ったけれども、具体的にどうしたら良いのか、さっぱり分からなかった。
「あのー、裏側って、どうやって行ったら良いんでしょう。遠いとこなんでしょうか」
「いえ、そのあたりにありますよ」
「それなら、行ってみたいな」
ぼくは、おもわず、つぶやいていた。
「では、この方に、連れて行ってもらってください」
マスターは、にっこりして言った。
「え?」
マスターは、さっきから飲み物を飲んでいた若者に、また突然、頼みごとをした。
「お客さん、すみませんけども、このお客さんを連れていってもらえますか」
こくんと、お客さんはうなずき、残っていた飲み物を、飲み干した。
「そんな、今すぐでなくても良いんですけど」と、ぼくは慌てたのだけれど、もうそのお客さんは、空のかけらをマスターに渡し、「こっち」と、ぼくに言っていた。
「どこに行くんですか?」と聞くと、「駐輪場に」と、若者は答えた。
このお店のどこに、そんなスペースがあったのだろう。ましてや今は、お店の周りは水で埋まっている。そんなときに、どこに自転車を停めるというのだろう。
若者は、お店を出ると、階段を下り始めた。けれど途中から、上り始めた。
あれ? と、ぼくは思った。水面に付くスレスレの所で、下りだったはずの階段が、急にクキッと曲がって、上りになっていたのだった。
「なんだこれ」と、思いながらも、ぼくはどんどん上っていった。上には、雲が見えた。その先は、見えなかった。下を見ると、どんどんお店が小さくなっていく。ぼくは怖くなって、途中から下を見るのをやめてしまった。階段だけを見つめて、ぼくは上った。
「着いたよ」と言われて顔を上げた時、そこに、メリーゴーラウンドがあった。一瞬、この間、夢に見たメリーゴーラウンドかと思ったのだけれど、よく見たら違った。普通は馬の所が、全部、自転車になっている。とてもカラフルな自転車で、タイヤも三輪車みたいに太くて、まるで、おもちゃのようだった。
「これに乗って行くんですか?」と、思わずぼくは言ってしまった。なんだか恥ずかしい。それに、そもそもぼくは、メリーゴーラウンド自体、苦手なのだ。
「そう」と、若者は言った。ぼくは、この若者が、こんなおもちゃみたいな自転車に乗るところが想像できなかった。けれど当然のように、その人は、ピンク色の自転車にまたがった。
ぼくも、白い自転車に乗った。そして自転車が動き出すのを待った。だけど、一向に動く気配がない。いつ回り出すんだろう。と思っている間に、若者の姿が自転車ごと消えているのに気づいた。
「あ、あれ」
ぼくはあちこち探した。そして上空を見た時、遠くの方に、若者が自転車をこいでいるのが見えた。
「あ、自分でこぐのか」
メリーゴーラウンド風だったから、てっきり勝手に動いてくれるのだとばかり思いこんでいた。
ぼくは急いで、ペダルを探して、足で踏み込んだ。
やわらかい感触がして、タイヤは回り始めた。どこかで、音楽が聞こえた。メリーゴーラウンドの音みたいだ。
今さら聞こえたって。と、ぼくは思った。
