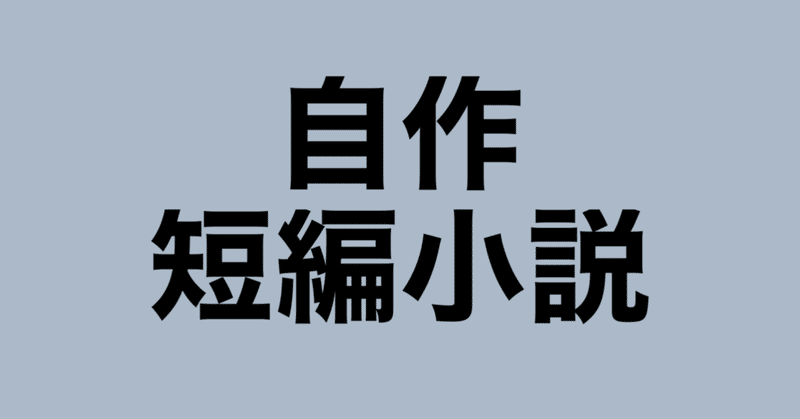
息子が強豪校に負ける日。【第三章】
届かなかった2点。
数字だけ見れば惜敗。しかし、この日球場に立っていた僕らが感じたのは圧倒的な実力差だった。
僕はプロ野球選手になるために15歳で親元を離れた。3年前、北海道の港町を出発する時、母さんだけが大泣きしていた記憶が遠い昔のことのように感じる。
「弱音を吐いてすぐ帰ってくるんじゃないよ。」
泣いていた割に厳しい言葉。
この言葉に励まされ続けた3年間だった。
小学3年生から野球を始めた僕は周りの仲間と比べても身体が大きく、上級生に混ざって試合に出場していた。5年生になった時には一つ上の子を差し置いてエースで4番を張っていた。
投げては子供らしからぬ直球で相手チームに得点を許さず、打てばほとんどが長打だった。それは中学でも同じで、僕は常にチームの中心にいた。
相手が投げる球が遅く感じ、相手が振るバットは鈍く見えて仕方がない。次元の違いを自分でも感じていた。
夢見ていた「プロ野球選手」は気づけば目標に変わっていた中3の春。
意を決して両親に思いの丈をぶつけた。
「道外の高校へ行って、プロを目指したい。」
両親は驚いていた。でもどこか嬉しそうにも見えた。実際、喜んでいたのかは分からない。
それから5日ほど経ち、父さんから話があった。
「甲子園に行きたいなら、地元から狙えばいい。でも、お前が目指しているのはそこじゃないって事だよな?」
「うん。甲子園に出てもプロにはなれない。俺は高校3年間でプロになれるくらい上手くなりたい。だから緑光。」
私立緑光学園。僕はこの時点でここに進む事を決めていた。
「父さんも調べたけど、実業も緑光もちょくちょくドラフトかかってんだな。」
もちろん実業と言う選択肢もあった。実際迷っていた期間も長かった。しかし、実業は野球部の他にもサッカー部やラグビー部、陸上部も強豪であることから、学校から離れた場所に運動場があり、練習の度に生じる移動時間を惜しく感じた。ましてや、地元を離れれば寮生活となり、時間に制限がかかることは見えていたので、出来るだけ生活圏を狭めたかった。
一方で緑光は学校の裏に球場があり、寮も道路を挟んですぐだった。甲子園に行くなら実業。プロに進むなら緑光。
より上手くなるために自分自身に時間をかけられる方を選んだ。
「甲子園に行けなくても、自分がより成長出来る方に進みたいんだ。」
「野球は詳しくないからよ。まぁ軸がそう考えるなら、緑光で頑張れや。」
加藤軸15歳。北の大地、北海道からプロを目指して緑光へ。3年間を野球にかけると誓って親元を離れた。
小学生の時に全国大会で水戸へ行った以来の飛行機に僕は少し緊張していた。いや、とても緊張していた。
凄まじい轟音と共に滑走路を走る機体、みるみる両親、いや、母さんと離れていく感覚が僕を襲った。
機内の窓からずっと向こうに見える山々、あんなに遠くに見える山よりも、僕は母さんと離れて生活するんだ。ここにきて痛むほどに感じる寂しさのあまり、すぐにLINEを送ろうとしたけど、iPhoneは機内モードだった。
置き場の無い寂しさをどうすればいいのか。喉奥の細く鈍い痛み。鼻が湿っぽくなり、目頭が熱くなる。もう一度窓の外を見る頃、生まれ育った北海道が、あんなに大きな北海道が見えなくなるほどに飛行機は高度を上げていた。
着いたらすぐにLINEを送れるよう、メモアプリに母さんへの手紙を書いた。
「こんな手紙なんて何年振りか分からんけど、めっちゃ寂しくなってさ笑 これからの3年間は自分にとって………。」
随分と長い手紙になったことを覚えている。本当に寂しく苦しい機内だった。
そして、書くと気持ちが落ち着いた事も覚えている。
「弱音を吐いてすぐ帰ってくるんじゃないよ。」
出発前の母さんの言葉。流石母親だなと思った。自分でプロを目指して決めた道とは言え、息子が寂しさで涙を流す事を見透かしていたような一言だった。
前を向かなくてはと自分を戒める着陸の滑走路。その晩から寮生活が始まった。
それまでの実家のゆとりある生活から、規則に縛られた寮生活に変わった。始まってしまえば慣れるのに時間はかからなかった。
寮は元々旅館だった建物をそのまま使っている。
3階建ての寮はお世辞にも綺麗とは言えず、いたるところで壁紙が剥がれ、天井にはシミがあった。
1階には食堂、風呂、洗濯ルームの他、おそらく宴会場だったと見られる畳の大部屋があった。この大部屋は「畳部屋」と呼ばれ、洗濯物を干す空間、風呂上がりのストレッチをする空間として使われていた。
2階と3階には共同のトイレとそれぞれ3人部屋が8部屋ずつあった。
部屋に入るとシングルベットと通路を挟んで2段ベットが置いてあり、窓際にはベタ付けで学習用の長い机と椅子が3つ置いてある。
基本シングルベットは上級生が使い、2段ベッドの上下どちらを使うか、残りの2名でジャンケンや話し合いで決めた。
僕は1年目、自ら2段ベットの上を希望してしまった。寮の部屋にはクーラーがあるわけもなく、夏は非常に寝苦しい。北海道の夏とはわけが違う暑さ、そして湿度。そうとも知らずに示してしまった自分の希望に1年間後悔しっぱなしだった。
とは言え、代々、打倒実業に燃える緑光。連日の猛練習で疲労は蓄積され、どんなに寝苦しい夜でも気絶するように眠っていた。
そして、寮生の朝は早い。朝6時に寮内至る所に付けられたスピーカーからロッキーのテーマが流れる。この曲が終わるまでの3分弱で起床し、1階の「畳部屋」に集合、点呼を行う。遅刻する者が出た場合は、連帯責任で同部屋のメンバーに罰走が命じられた。
その後は「畳部屋」から掃除用具を持って各部屋を清掃し、6時20分から食堂で朝食、7時00分から寮周りと側の公園でゴミ拾いを行う。
7時30分から8時00分までは寮前でバットを振り、8時35分のホームルームに間に合うよう支度をして学校へ向かう。
寮から学校はすぐとは言え、朝からこれだけカツカツなタイムスケジュールをこなすには、前日の準備や要領の良さが必須だった。時間の使い方はここで相当磨かれた。
練習量に対して回復量が追いつかない日々。
プロへの夢を豪語していた過去の自分に「甘くはないぞ」と囁いて眠る夜がいくつもあった。
初めての夏の大会では当然背番号は貰えず、スタンドから戦況を見守っていた。結果は県大会ベスト4。3年年が引退し、新チームが動き始めた頃、僕にもチャンスが巡ってきた。
「加藤、明日先発で行くから。5イニング。」
コーチからの突然の通達。
緑光学園。甲子園出場こそ長らくご無沙汰しているが、実業を破るなら緑光と言われているだけあって、県外の強豪校からも練習試合の声がかかっていた。
そして県外の強豪との練習試合が僕のデビュー戦となった。
しかし、散々な結果に終わる。
地元ではかすりもさせなかった自慢の直球が、打撃練習かのように打ちこまれた。アウトが取れない感覚。初めての経験だった。
コーチから通達されていた5イニングをもたず、3回途中で交代が言い渡された。
こんな不甲斐ない試合がいくつか続いた。
悔しさと改善。これを繰り返す秋となった。
結果が伴わない僕は秋の大会でも背番号は貰えず、夏と同様にスタンドからチームを応援していた。
自分ではない同級生のピッチャーが公式戦で結果を出している姿をひたすらスタンドから眺める日々。
緑光は強い。どんどん勝ち進む。それに伴って知名度が上がる同級生達。
「打たれてしまえ。」
「三振しろ。」
「負けてしまえ。」
僕が出場していない試合中の本音は憎悪に満ちた言葉だらけだった。
僕はプロになるために緑光へ来た。
スタンドから応援するために来たわけじゃない。
レギュラー陣のミスはむしろ、自分にとってプラスの要素と捉えていた。
自分の出番が欲しい。スタンドでそう思い続けた2週間。チームは秋の県大会も夏と同様にベスト4に終わった。
来年の春に向けて長い冬が始まる。
プロになるためにここへ来たんだ。
いつまでも埋もれているわけにはいかない。
練習後も同じ寮で生活するキャッチャーに球を受けてもらい、朝は点呼よりも早く起きてバットを振った。
打っても投げても一流に。
メジャーで活躍する二刀流のように。
しかし突如として監督から伝えられた言葉に僕は心を折られる。
ある日の練習前、監督室に呼び出された。
僕の他にもう1人いた。
「加藤、お前は明日からサード専念。投手メニューから外す。」
ピッチャーとしての戦力外通告だった。
「そして五十嵐は捕手メニューから外す。外野に入れ。ライト。」
それまでキャッチャーとして練習してきた同学年の五十嵐も外野に移す話だった。
「はい!」と大きな返事をしたものの、2人とも言葉を失っていた。
監督が続ける。
「2人ともバッティングを活かし、打撃に注力して欲しい。得意を磨いて、得意を磨いて、もっと尖れ。」
その後の監督が口にした事が事実なら、秋の大会はメンバー外だった僕も五十嵐も、打撃だけで見ればレギュラークラス。ただ、僕はピッチャーとしては見込みは立たない。五十嵐はキャッチャーとしては4番手。
各自がプライドを持ってやってきたポジションに見切りをつけられた瞬間だった。
しかし、僕はピッチャーとして歯が立たないと自覚していた事も事実。どこかでピッチャーとしての見切りをつけたいという考えもあったのかもしれない。そのため、残忍な通告を素直に受け入れる事が出来た。しかし、隣にいた五十嵐は涙を堪えながら、それでもキャッチャーを諦めたくないと訴えていた。
そんな食い下がらない五十嵐に対して、監督の口からは更に残酷な評価が言い渡された。
キャッチャーというポジションは他と比べて特殊。9人のうち、唯一ひとりだけバックスクリーン向きに守備を行う。仲間の8人をまとめ上げ、相手に対し常に注意を払う。そして、ピッチャーからは絶対的な信用が必要。
これらの必要な要素が他のキャッチャーと比べて圧倒的に欠けている。
ここまでキャッチャーとして努力してきた五十嵐の心をへし折るような評価の数々だった。
今にも溢れ出しそうな涙を必死にせき止めて五十嵐は続ける。
「野球が好き以前にキャッチャーが好きなんです。キャッチャーがやりたくて野球をやってます。」
厳しい表情に変えて監督が声を荒げる。
「全員色んなものを犠牲にしてここで野球をやっている。お前のプライドは伝わったが、ここを指揮する俺から言わせれば、今のお前のそういう所が完全な個人プレイ。チームのために自分を犠牲に出来ないなら、尚更捕手など務まらん。」
こんなやりとりを横で聞いている僕は五十嵐の思いに胸を熱くしていた。練習後にも僕の球を受けてくれていた五十嵐。少なくとも僕からの信用はあったが、たった今戦力外となった投手の信用など、監督にぶつけても仕方がない。助太刀をしようにも出来ない自分が不甲斐なかった。
少しの間があって監督が口を開く。
「分かった。絶対に自分の力で正捕手まで上がってこい。お前の打力は必要だ。打力を伸ばしながらも、捕手として欠けている部分を必ずどうにかしろ。ただ、次に呼び出した時には最後。その間にも別な連中だって成長する事を忘れるなよ。」
喜ぶわけでもなく真顔で返事をする五十嵐。
こんなにも熱を帯びたやり取りを聞いて「やっぱり自分も。」なんて事は言い出せるわけもなく、五十嵐が持つプライドの高さを感じると共に自分の弱さを見た気がした。
投手として戦力外通告をされてからは毎日毎日バットを振り込んだ。手の皮は常にめくれてしまい、マメになる間も無かった。
その後、有望な新入生とポジションが被ったり、不運な死球による指の骨折、熾烈なレギュラー争いや熱い思いから生まれる仲間との衝突、時間に縛られた寮生活と、満身創痍で望む授業に中間テストと期末テスト。
過酷な練習の他にこれだけの試練があって、
何度も挫けそうになった。それでも、その都度、頭に思い浮かぶのは母の言葉。
「弱音を吐いてすぐ帰ってくるんじゃないよ。」
地元では無双だった自分。プロになるために選んだ道。ここで諦めれば、全て過信だったという事を肯定してしまう気がした。だから踏ん張れた。
今思えば入学前に豪語していたプロになるという目標は何段もハードルを下げ、このチームでレギュラーを取るという事に変わっていた気がする。
とは言え、あらゆる試練を乗り越えてようやく手にしたレギュラーの座。僕は3年生になっていた。
打力を期待されて1年の秋で投手から三塁手に変わり、バットを振り続けた日々が功を奏した。
最後の夏の大会。緑光は一回戦、二回戦と、危なげなく勝利を重ね、来たる三回戦で宿敵の実業と当たった。
高校球児としては最後の勇姿となる僕の姿を見に地元の北海道からは母が応援に来ていた。
しかも一回戦から。ホテル住まいで。
実業戦には父さん、婆さんまで遥々やって来た。
写真の爺さんまで来ていたらしい。
試合前のミーティング。
あたかも実業を倒すためにここまでやってきたような内容だった。まるで勝ったその先には何も待っていない、そう捉える事も出来る程に、目の前の実業に全員の意識が集中していた。
事実上の決勝戦とはよく聞く表現だが、まさにこの三回戦に相応しい例えだった。
両校共にプロ注目の選手を擁しており、複数のスカウトが視察に駆けつけていた。
他校による偵察、高校野球ファン、吹奏楽部の大合奏、チアリーディング、全校生徒の大声援の中、灼熱の球場で両校の魂がぶつかった。
僕もスタメンに名を連ねた。
序盤は拮抗。
中盤でリードを許す。
そして最終回9回表、僕の高校野球にとって最後の打席になる打席が回ってくる。
点差は僅かに2点。
ランナーは2人。僕が3年間振り続けてきたスイングでホームランを放てば逆転の状況。
両手を合わせて戦況を見つめる父母会。
頬に粒汗を垂らしながらトランペットを鳴らす吹奏楽部。チャンスで盛り上がる緑光スタンド選手一同。ピンチで大声援を送る実業スタンド選手一同。
「守りきれ!」「いったれ!」
響く大太鼓の音。
球場は両軍入り乱れた大声援に包まれる。
3年間厳しい事を言われ続けてきた監督から出されるサインを確認し、僕は打席に入る。
実業の大エースが一球放るたびにどよめく球場。
それがストライクであれボールであれどよめく球場。試
それもそうだ最終回。球場の緊張は最高潮に達していた。
僕の中でも緊張と集中が拮抗していた。
打席で豪速球を2つ見て一呼吸置き、監督からのサインを確認。了解の合図を返す。
その3球目だった。
大エースが投じた豪速球は僕が横に構えたバットの先に当たった。
サイン通りの送りバント。これにより2人のランナーはそれぞれ進塁した。
強打者として地元を飛び出した僕の高校野球最後の打席は送りバントだった。
こうして9回表、2アウトとはなったが、ヒット一本で同点の場面を演出した。
続く打者には代打が送られ、あの時キャッチャーとして戦力外通告を受けていた五十嵐が満を持して左打席に向かう。
正捕手の座こそ掴めなかったが、控えの2番手捕手としてメンバー入りを果たしていた五十嵐。
打力も磨きをかけ、控え捕手兼代打の切り札として背番号12を背負っていた。
こだわり続けた捕手としての出場は叶わなかったが、監督との約束を果たしてここまで辿り着いた彼を心の底から尊敬する。
凡退すればあとがないこの打席でも、果敢に初球からスイングしていく五十嵐。
2球目には一塁線に鋭いファールを打ち込み、球場がどよめく。
そして3球目だった。
スピードも曲がりも一級品と称された伝家の宝刀のスライダーは左打席に立つ五十嵐の右肩に当たった。
デッドボール。
3年目にしてやっと辿り着いた2番手捕手の座。絶対的な正捕手の存在がある中で競い合ったライバル多き2番手捕手の座。
五十嵐にとって公式戦での出場はこの打席が最初で最後だったが、結果は白とも黒とも言い難い死球に終わった。
この時彼は何を思っていただろうか。
続く打者が凡退し、緑光は実業に敗れた。
球場にはよく聞く実業の校歌が流れる。
2対0。2点差の敗北。
あれだけ手の皮をむいてバットを振った3年間。
僕に限った話ではなく、部員全員で努力し続けた3年間。それでも実業からは1点も奪う事が出来なかった。
今年の実業が春の甲子園で準優勝した理由を肌で感じた。単純な話だった。点を取られなきゃ負ける事はない。超高校級の大エースとプロ顔負けの守備陣。そのままもう9イニング続いたとしても1点も取れる気がしなかった。
こうして僕の高校野球は幕を閉じた。
一目置かれた中学時代。
プロになるために選んだ緑光学園。
メジャーで活躍する二刀流に憧れ、投打に鍛錬を重ねた末にピッチャーとしては戦力外。
打撃を買われてサードにポジションを変えるも、なかなか結果が伴わない。
3年夏、やっとの思いで手にしたサードのレギュラー。打順は下位の8番固定。自信を持って地元を飛び出したが、緑光じゃ人並みとの評価に終わった。
最後の試合も2つの三振に2つのバント。
とても強打者とは言えない結果だった。
あれだけの才能を自負し、ここまで死ぬ物狂いで練習してきた3年間を思い返せば、1つも納得いかない結果に終わった。
悔しさ。虚しさ。情けなさ。儚さ。
ありとあらゆる負の感情が僕を締め付けた。
涙は出ず、むしろ、心の乾きを感じた。
上には上がいた。
身の程を知った3年間だった。
試合後、球場の外で部員は整列。
応援に駆けつけた父母会の前に立った。
監督が父母会へお礼の言葉を述べる。
「みなさんからお預かりした大切な球児たちと、、、、、」
僕はこの時もなお、歯が立たなかった自分に絶望し、監督の話も頭に入ってこなかった。
「試合は完敗です。ただ高校野球は勝敗だけで評価しきれません。そして断言します。この子らは実業よりも多くの困難を乗り越えてきました。間違いありません。なので親御さん達へのお願いです。」
親へのお願いという聞き慣れない言葉が耳に入り我に帰った僕。
「試合に出てなかった選手も含め、今日くらいは褒めてやってください。」
この言葉を耳にした時、僕は父母会の中の母さんを見た。
母さんも僕を見ていた。
その瞬間。涙が溢れた。
母さんも顔を両手で覆った。
今すぐにでも母さんの元へ帰りたくなった。
思えば色んな試練にぶつかってきたが、地元を離れる際の飛行機の中が最も辛かった。
「弱音を吐いてすぐ帰ってくるんじゃないよ。」
母さんの言葉を思い出す。
弱音を吐くことなく、地元に帰ることもなく、やり切った事を誇らしく思った。
プロになるという目標には到底届きそうにないけど、緑光で野球をやり抜いたことで身の程を知る事ができた。
血反吐を吐く思いで野球をしてきた。
その末に2つの三振と送りバント。
これが野球の儚さを感じた。
強豪校に敗北。
プロという目標が再び「夢」へと形を戻す出来事だった。
そして強豪校は2日後の4回戦へと駒を進めた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
