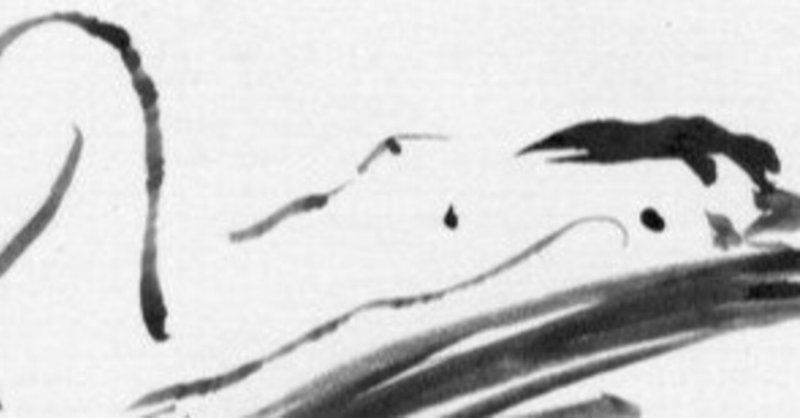
言語快楽の骨頂は「比喩の発明」にある
三島由紀夫の『仮面の告白』に「若い僧侶のような世故に長けた微笑」という表現が出て来る。ヤングアダルトの時分に小説を読み始めて最初に記憶したのがこれだ。そんな微笑など肉眼で見たことがないはずなのに「うまい、卓抜だ」と唸らされました。その後何かにつけて模倣しまくったのは言うまでもない。全ては模倣から始まるのだ。
ところで名人鬼才の手になるこんな比喩ストックを脳にたくさん詰め込んでおくと何かと重宝になる。場合によっていくらでも応用が利く。中学生高校生の分際で妙に気取ってみせた美文をものして提出すれば、「三島の再来」なんてチヤホヤされるかも知れない。されないか。実はそんなの世間に一杯いるからね。付け焼刃の文才なんか。盗作疑惑を掛けられるのがオチ。
ものを書きたがる人間はみんな他人を驚倒あるいは瞠目させるような文をいつも書きたがっている(はず)。可もなく不可も無い駄文の為にいったい誰がわざわざ時間を割きたがるというのか。どうせ人の書きものを読むからには「エクスタシー」とまでは行かなくとも、なにがしかの「背徳的な痛快さ」もしくは「悪魔的な陶酔感」くらいは欲しい。読むことは苦行ではないのだ。狂気の毒素の滲んでいない文章など私には何の魅力も感じない。
人間もそうだ。クレイジーでダーティな成分があるから面白味も出る。酒を一緒に飲んで丁々発止議論でもしたくなる。「糞真面目」であることはそれ自体がクレイジーなことと言えなくもないが、それはまったく色気を感じさせない狂い方だし、そんなやつに限って「自分の暴力性」に無頓着なんだよな。どんな不潔で邪悪な組織にも忠実になれる、そんなアイヒマン的なところがあるんだ。子孫繁栄なんていう俗悪趣味を人類の目的だと信じているのもだいたいそんなキモイ奴らだ(いや偏見であることくらい自覚してるよ)。
比喩のもたらす快楽について私は書こうとしていたのだ。
この比喩と呼ばれる修辞技法はごく大雑把に「隠喩(metaphor)」と「直喩(simile)」とに分類することが出来る。隠喩はある二つの事柄の類似性を暗示的に表現することで、直喩はある二つの事柄の類似性を明示的に表現すること。でもこんな教科書的な通り一遍の説明では分かるものも分からない。実例が大事。
「歌舞伎町の帝王」「テフロン大統領」「全身ペニス」「ハイヒールは現代の纏足である」「ネクタイはサラリーマンの首輪である」「結婚は人生の墓場である」「門松は冥土の旅の一里塚」なんてのは隠喩。暗喩ともいう。
「人生は一箱のマッチに似ている」(芥川龍之介)とか「妻子を持つことは運命に人質を取られたようなものである」(フランシス・ベーコン)は直喩に当たる。「腐った男みたいな奴ら」「晩年のエルビスのごとき運命」「司馬遼太郎を思わせる近所の白髪老人」などもそう。つまり、「何々に似ている」とか「何々のようだ」と補足的な比較語を通して表現されるものは形式上、直喩に分類される。
比喩の発案は文章作りの醍醐味といっても過言ではないだろう。だいたいこの「醍醐味」というのが既に比喩だ。醍醐とは牛乳を精製して出来た極上美味の何かのことで、いつからかその味が仏教最上の教えの比喩として定着するようになり、やがて汎用性の高い比喩に至った。
洋の東西を問わず自然言語は必ず比喩を含んでいる。とくべつ文学肌でない人々も、借り物の比喩はしじゅう口にしている(あたかも「息をするように」)。さっきの「世故に長けた微笑」と同様、私は「目を抜かれている生き馬」なんて見たことがないが、大都市の油断できない様子を日本人はとりあえず「生き馬の目を抜くような」と言い表してきた。改めて見ると、この表現、そうとうエグイし斬新だ。「新約聖書マタイ伝」に由来する「豚に真珠」にしても、はじめてこんな比喩表現を耳にした人はさぞ痛快だったに違いない。ヴォ―ドレールの『悪の華』に満ち溢れるあの奇抜な比喩群もいま読めば「ありきたり」の印象を受けるだろうが、それは彼以後の多くの凡才がそれを模倣しまくったからに他ならない。世人の度肝を抜いたどんなアバンギャルド表現もやがてすぐに陳腐化する運命にあるわけだ。
ところで私は童顔で美しい青年に対して「生まれたての子鹿のような目をした」とか「観音菩薩のように柔和で慈悲深そうな微笑み」と直喩的に表現するのが好きなのだけど、れいによって鹿がどんな面して生まれてくるのかなど全然知らないし、とうぜん観音菩薩なるものがどんな風貌をしておられるのかも知らない。それでもこの比喩は私にある鮮明で快いイメージを与える。これこそ比喩のマジックなのだ。子鹿の場合、つぶらでウルウルした真っ黒い目がありありと浮かんでくるし、観音菩薩の場合、中宮寺の『菩薩半跏像』のような中性的で気品のある顔貌がすぐに想起される。
美人の存在は人々の比喩衝動をよほど喚起させるらしい。「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」なんてのは花づくしで「前衛的」といえるけど、私にはこれがいまいちピンとこないのだ。それなら、中国古典由来の「沈魚落雁」や「羞月閉花」のほうが良い。チンギョラクガン、シュウゲツヘイカと語調に切れがある。美し過ぎる人の前では魚も恥じらいの余り沈んでしまうし、雁も落ちてしまう。月も赤面して隠れてしまうし、どんな綺麗な花も閉じてしまう。なんて大袈裟なんだろう。誇張もいい加減にしろ。まあこれが「白髪三千丈」の伝統ということか。
中国の比喩に関連してどうしても思い出されるのは、『碧巌録』『無門関』『臨済録』等に代表される禅文献のことだ。学生時代から覚えるほど精読しているのに、毎回その比喩の大胆過剰なことに舌を巻かされる。「箇ノ熱鉄丸ヲ呑了スルガ如クニ相似テ、吐ケドモ又吐キ出サズ」(『無門関』、趙州狗子)なんかはとりわけ凄絶で、一読しただけで脳裏に焼き付いてしまう。その文脈は知らなくとも、異様な迫力だけは感じられるだろう。
いったいに禅者というのは待つことが大嫌いだ。ごちょごちょした理論遊戯も大嫌い。そんなことをほざいて事を誤魔化す奴はすべて「依草附木の精霊」だというのだ。焼けた鉄のタマを呑み込んでしまったようなのっぴきならない言語的ジレンマに己を追い込まない限り「禅認識」には至れない。真剣そのものだった当時の禅者はそのことを全身で確信していた。さればこそあれだけ苛烈で真っ直ぐな比喩群が生まれたのだ。禅者の発する言葉はいつも生々躍動している。凝り固まらない。停滞しない。慣用されるなかで言葉は必ず瘡蓋化する。そんな瘡蓋を禅者は躊躇なく剥がして一喝する。「死んだ言葉に拘束されるな、今すぐここで一切を認識しろ」と。
こうした「性急な真剣さ」こそ禅者を禅者たらしめるものなのだけど、それについてはまた別の稿で詳しく書きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
