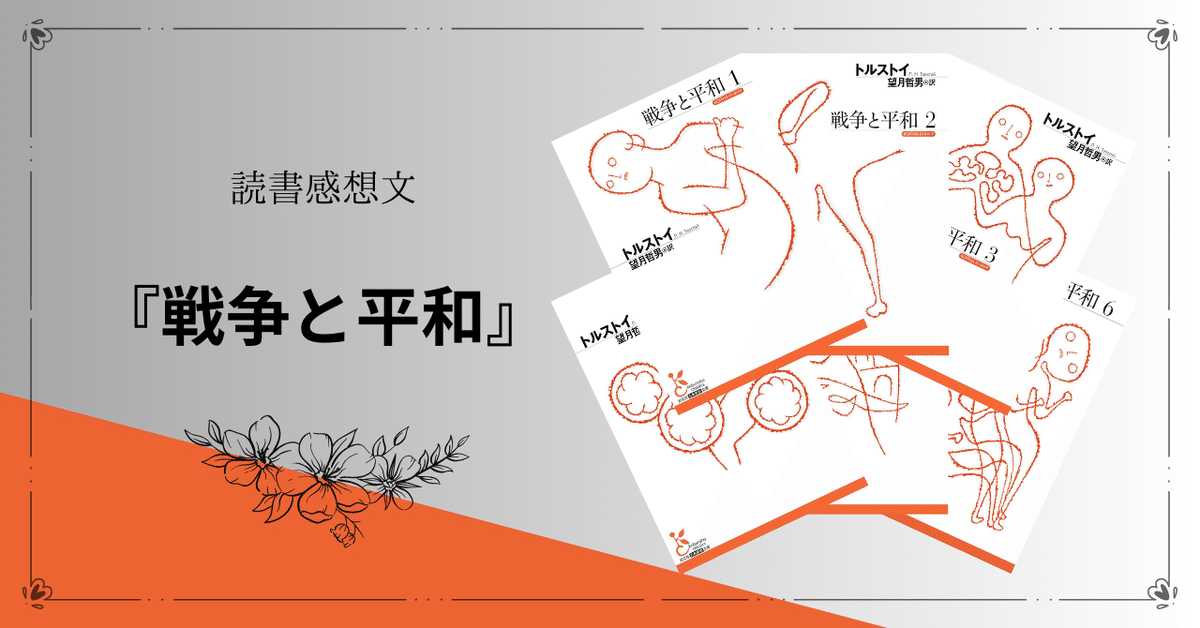
【読書感想文】トルストイ『戦争と平和』
ロシア文学の巨星トルストイの代表作『戦争と平和』。
冬の初めから読み始めて、つい最近読み終えました。
とても長い作品でありながら、現在の私自身の興味と重なって格別に面白く読むことができたと感じています。
今回は読書感想文という形をとって、この古典作品について書いてみたいと思います。
『戦争と平和』について
まずこの書物自体の紹介から。
『戦争と平和』は、ロシアの文豪レフ・トルストイによる小説で、19世紀初頭のナポレオン戦争を背景に、愛や運命、国家、そして人間の本質を描いた壮大な物語です。
1869年に完成したこの作品は、ロシア文学を代表する傑作として知られ、その圧倒的なスケールと深遠なテーマで、現在に読み継がれる名作と評価されています。
物語は、ナポレオン戦争中のロシアの貴族社会を中心に、さまざまな登場人物の人生とその変化の道を描きます。
知識と道徳の間で葛藤するピエール・ベズーホフ、理想に燃えるアンドレイ・ボルコンスキー公爵、愛に生きる美しい女性ナターシャ・ロストワ。
複数の主人公の人生が戦争と平和の中で交錯し、成長や挫折を通して深化していくという小説になっており、「あらゆる小説の中でもっとも偉大な作品」と評されることもあります。
小説のポイント
時代背景:ナポレオン戦争(1805–1812年)
主題:戦争と平和、愛、運命、人間、歴史
特徴:多くの登場人物を通して壮大なスケールで描かれる物語
読む価値:深い人間理解、歴史や自由に対する知見が得られる
邦訳はいくつか刊行されていますが、おすすめは光文社古典新訳文庫のものです。
1〜6巻に分けて刊行されています。
圧倒的な読みやすさと注の丁寧さで作品世界にぐんと引き込んでくれます。
感想
歴史の脚本
この作品は、私が現在ナポレオンについて興味をもっているという縁で手に取った本でした。
物語の背景がナポレオン戦争中のロシア社会だったからです。
歴史的な出来事を背景としている以上、主人公格の登場人物とその周辺の人たちはオリジナルのキャラクターですが、実在する人物も複数人登場します。
私にとって特に面白かったのが、そうした実在の人物たち、特にナポレオンとクトゥーゾフに対する作者の解釈でした。
彼らは、作中ではこの解釈によって性格づけられており、まさにそのような人物として振る舞います。
ナポレオンであれば、歴史という舞台におけるひとりの演者として、その行動を脚本によって強烈に規定されている一方で、そうした力に気づかずに何もかもが自分の意志で行われていると考える者として描かれています。
つまりこれまでの英雄像に反するような、ある種滑稽な人物として設定されているのです。
これに対してクトゥーゾフは、歴史の脚本の存在を感知し、みずからの意志をその通りに調和させて行動する賢者として描かれます。
この小説の個性的なところは、ときに著者自身の歴史哲学や戦争論が、物語を通して叙事詩的に語られることです。
トルストイの歴史観の核心は、歴史を動かすのは英雄や偉人ではなく、無数の人々の行動や社会の運命的な流れであるという点です。
その主張は一貫して、歴史は全ての人々のあらゆる活動によって結晶する出来事であり、王や政治家、最高司令官やジャーナリストといったいわゆる英雄によって生じるわけではないと述べるのです。
トルストイはこの具体的な様相を仏露間の「祖国戦争」に見ていますが、私たちには「本能寺の変」の例がわかりやすいかもしれません。
本能寺の変にみるトルストイの歴史論
「本能寺の変」は、織田信長が家臣の明智光秀に裏切られ、本能寺で襲撃された事件です。
一般には、この事件の原因は信長や光秀という「英雄」の個人的な動機や決断に結びつけて解釈されています。
これは、信長が光秀をいじめていたからだとか、領地替えの問題があったとか、長宗我部家の取次が台無しになったとか、光秀自身が天下を望んだとか、そうした野心や恨みという意志の理由を特定してそれを出来事の原因とみなす考えです。
しかしトルストイは、歴史的な出来事の原因を権力者の意志に帰することはできないとします。
本能寺の変は、信長自身の決断や光秀の裏切りだけではなく、戦国時代という社会的背景や無数の要因が絡み合った結果であると見るべきです。
例えば、両者に仕えた家臣団や軍勢、さらにそれを取り巻く民衆の行動や心理を考えてみると、光秀が謀反を成功させるには、家臣たちが彼に従う必要がありました。
しかし、もし重臣のひとりが光秀に従うことを拒否し、また部将のひとりが、侍大将のひとりが、足軽大将のひとりが・・・といった具合に、個々人が拒否していたら、光秀は軍勢を京に向けることはできなかったはずです。
当の光秀の意志さえも、さまざまな原因によって規定されています。
もし光秀が本能寺の変を決行する前に、たまたま信長からの感状を見て、過去に受けた恩を思い出したなら、その意志が変化することもあったでしょう。
また、出来事が生起したのは、人間の意志を超えた外的な要因も考えられます。
例えば、信長が少人数で本能寺に滞在していたことや、光秀が畿内方面軍の司令官として京付近で軍を動かす権力をもっていたこと、秀吉の援軍と称してそのタイミングで軍勢を動かせたことも原因として外すことはできません。
さらには戦国時代というムードも影響していたでしょう。
過去に原因をさかのぼるなら、戦国時代は応仁の乱のひとつの結果ですが、応仁の乱は将軍の後継問題から、将軍のシステムは鎌倉時代から、武士の台頭は平氏から・・・というように観測できる限界点までその因果関係を追うことができます。
個々人の意志、命令系統、秀吉の援軍、本能寺、畿内方面軍、下克上、このような考えられる限りあらゆる出来事によって本能寺の変は用意されつつあったのであり、出来事の因果関係のうちにがっちりと規定されていたのです。
だからトルストイ的には、そうした歴史的な出来事は偶然的に生じたのではなく、意志、時間と空間、気分といった全ての相互関係的な出来事によって生じた必然、ということになります。
こうした視点から本能寺の変をみると、信長や光秀という個人に焦点を当てるのではなく、戦国時代の社会構造、無名の家臣や民衆の行動、そして過去から現在に渡る無数の出来事が、複雑に絡み合いながら歴史を形作ったと考えることができます。
トルストイは、英雄たちの意志によって歴史が作られていくのではなく、むしろ英雄たちこそが自分の意志によってはどうすることもできない無数の規定に縛られて、出来事の名前だけの代表者のような立ち位置に置かれていると考えるのです。
このようにトルストイは、ある人物が歴史を作ったのではなく、その人物もまた歴史という巨大な流れに運ばれた存在であるとします。
自由と必然の問題
光秀が本能寺の襲撃を命じたのは、歴史の流れに規定された必然であった、というのがトルストイ的な考え方です。
トルストイは歴史において、個人の自由は制限されていると考えます。
特に、偉人や英雄と呼ばれる人物の行動は、歴史の必然的な力によって方向づけられていると論じました。
そうだとするなら、光秀には自由意志は全くなかったのでしょうか。
というのは、もし出来事が必然的に生じるのだとしたら、その出来事の主体であると思われる人物の意志など、何の関係もなくなるからです。
この問題に際して、トルストイは、人間の行動は完全に自由でも完全に必然でもないと考えました。
むしろ、自由と必然は異なる視点から同じ現象を説明するものであると考えています。
私たちの自然な感覚、つまり個人の視点(自由の視点)では、自分が自由に選択して行動していると感じますし、そうでないことなどあり得ないと感じます。
一方で、全体の視点(必然の視点)では、自分の考えや行動は世界の因果関係の外に出ることはできず、その時代の流れや環境によって決定されていることが理解できます。
トルストイはこの事態を、自由は個別の行動を捉える視点から現れるが、全体的な文脈では必然の法則に従うと主張しています。
トルストイは哲学的に、自由と必然の問題を次のように整理しています。
人間が完全に自由ならば、その行動には一切の原因がなくなり、世界から切り離されることになるが、これはありえない。
人間が完全に必然的ならば、その行動は全て機械的なものになり、個人の意志は存在しなくなるが、これは私たちの自然の感覚に反する。
実際には、自由と必然は常に相互に絡み合い、調和している。
光秀が戦国時代から完全に切り離されて存在することは不可能ですが、光秀に本能寺の変の責任が全くないというのも理解に窮します。
前者が成立するなら、それは人間界を見下ろす神のような存在ですし、後者が成立してしまうならば、人間に罪など存在しないはずです。
しかしこの矛盾においてなお、世界は調和して動いている(少なくともそう見えます)。
トルストイは、このような自由と必然の問題を通じて、次のような結論に達しています。
歴史や人生において、人間は部分的な自由を持ちながらも、全体としては必然的な力によって動かされている。
この理解によって、個人の行動の意味を過大評価することなく、全体の流れや歴史の運命的な力を認識することが重要である。
確かに人間は、出来事の必然的な因果関係のうちに組み込まれた存在です。
しかし私たちは、その因果関係の全てを認識することは明らかに不可能です。
「風が吹けば桶屋が儲かる」という言葉が示すように、人間には、本能寺の変の原因となる全ての因果関係を網羅することなどできません。
トルストイは、その不可知性に人間の自由を認めているわけです。
簡単に言えば、認識できるものは例外なく必然の法則に縛られているのですから、認識の及ばないところにのみ、自由の根拠は見出されるだろうということです。
これが人間に与えられた部分的な自由になります。
一方で、重要なのはこの必然の法則をできる限り認識することだとトルストイは考えます。
これが歴史の運命的な流れを形成するものであり、人間にはどうすることもできない必然性の根拠になります。
つまり、自由と必然は、ある現象に対する人間の認識の度合いに関わる相対的なものだとも言えるでしょう。
例えば、本能寺の変の原因についての認識が深まれば深まるほど、必然の度合いが高まって自由の度合いが低くなるという具合です。
このような理解のもと、トルストイは、歴史学というのがありうるとすれば、こうした法則の解明への努力にあると考えており、伝記のように英雄の自由意志によって歴史が成り立ってきたという考え方を排撃するのです。
運命の力と主人公たち
以上のような作者の歴史観を背景として登場人物達は動いていきますが、だからこそ物語は運命的な性格を強めているように感じました。
ナポレオンやクトゥーゾフのように、トルストイが名指してそのように描いている人物だけではなく、ピエールやナターシャ、アンドレイやマリヤといった主人公たちも、皆がこの歴史の規定性のくびきにもとに生きています。
一見すると、彼らの意志や選択がある一方で、それが歴史という巨大な力の中で制約され、あげく必然的なものとなる様子が描かれています。
ピエールは、理想を追い求める一方で、戦争や社会的変化に翻弄されます。
フリーメイソンへの参加や市民としての戦場での経験など、ピエールの行動は個人的な意志によるものですが、やはりそれらは出来事の相互作用の中で形作られた意志であり、舞台であり、彼をそのように行動させたのは、むしろ不可知の運命的な力だったと感じられます。
ナターシャは、情熱的で感受性豊か、人生や愛に対して非常に純粋で率直な人物として、場合によっては自由の体現者のように映るかもしれませんが、彼女の挫折や復活は、歴史の力のうちで描かれています。
アンドレイとの舞踏会、田舎での狩猟、アナトールと会ったオペラ、フランス軍が迫るモスクワ、家庭生活。
作中しばしば、その多感な性質からか、彼女は周囲の環境の雰囲気やちょっとした出来事にひとかたならぬ影響を受け、それに応じるように気分的直感的に動く姿が目立ちます。
これは容易に、自分の意志を超えた力の発現を想起させるものです。
例えば、フランス軍のモスクワ到着直前におけるハツラツとした態度から、疎開の道中に戦争で負傷した元婚約者を見つけた驚愕、看護を通しての和解と穏やかな喜び、そして彼の死を通しての彼女の変化は、この応答の形が顕著になっています。
また、彼の死を看取った大きな憂鬱のあと、彼女の復活のきっかけとなった出来事は家族が戦死したことでした。
このようにナターシャも、歴史の運命的な力に規定されており、ただ生来的な性格による出来事への応答の仕方が、彼女の自由奔放さの見かけを呈しているようにも思えます。
まとめ
トルストイ自身も述べていますが、小説としては最初から最後まで面白いです。
ただし長大な作品であるため、読み切るのにはそれなりの時間がかかります。
特に、第1巻と第6巻(最終巻)は全体の中では読みづらいところではないかと思います。
訳者の望月哲男さんの読者ガイドによれば、この小説の執筆にあたり途中から作者の構想に変化があったとされます。
そのためか、特にはじめの方で描かれていた人物が後の方では「こんな人だっけ?」と異なる人物ような印象を受けたりもしました。
(もちろんそれは、物語が進むにつれて登場人物に起こった深化や変化とも言えますが)
私はナターシャの従姉妹のソーニャが好きで、彼女がどうなっていくのかが楽しみだったのですが、その結末については意外でした。
準主人公的なキャラクターだったので、ピエールやナターシャほどには内的な描写もなかったので、「いつの間にそんな感じに・・・?」といった印象でした。
第6巻の読みづらさについては、その内容というよりも小説としての結構に由来すると思います。
というのは、ここでトルストイの歴史考察がエピローグの第2編をまるまるとって論じられているからです。
ただ、一度この物語世界に馴染んでしまえば、ワクワクしながらぐんぐん読み進められると思います。
私は物語の結末が近づくにつれ、ページを繰るのが惜しいような気持ちになりました。
結論としては間違いなくオススメの作品です!
